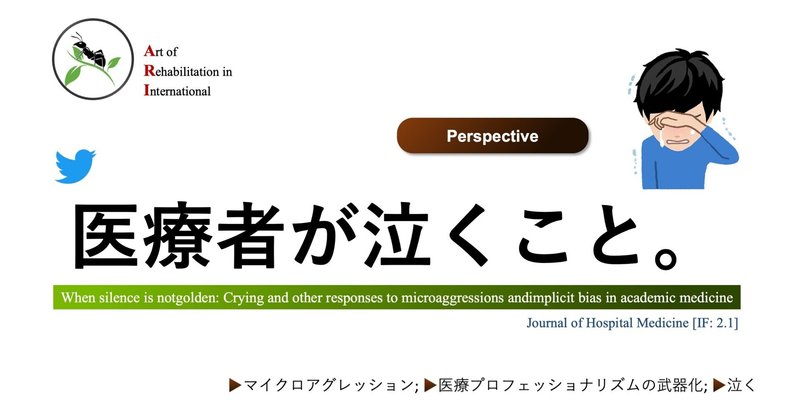
医療者が泣くこと。医療プロフェッショナリズムの武器化を防げ
📖 文献情報 と 抄録和訳
沈黙が金でないとき;学術医学におけるマイクロアグレッションと暗黙の偏見に対する泣き声とその他の反応
📕 Weerahandi H. When silence is notgolden: Crying and other responses to microaggressions andimplicit bias in academic medicine.J Hosp Med.2022;17:136‐137. https://doi.org/10.1002/jhm.2740
🔗 DOI, PubMed, Google Scholar 🌲MORE⤴ >>> Connected Papers
※ Connected Papersとは? >>> note.
✅ 前提知識①:医療プロフェッショナリズムの武器化とは・・・?
- 医療プロフェッショナリズムの概念は、裕福な白人男性という権力者によって作られ、強化されてきた
- この理想化された典型から外れた態度や性格の者は、プロフェッショナルではないと見なされ、結果として多様な声を封じ込めることになりかねない
- 例えば、医療現場で涙を流したときに「泣くんじゃない。お前はプロだろ。出ていけ。」という感じで、ある価値観や感情表現を不明瞭なプロフェッショナルという概念によって抑圧される・攻撃されることを『医療プロフェッショナリズムの武器化』と呼んでいる。
📕 Lee, James H. Academic Medicine 92.5 (2017): 579-580. >>> doi.
✅ 前提知識②:マイクロアグレッションとは?
- マイクロアグレッションは、女性やBIPOC(黒人・先住民・有色人種)、LGBT(性的少数者)に対し、言語・非言語的な方法で伝えられる日常的な侮辱や何気ない失礼な振る舞い、ネガティブな態度、偏見と定義されている。
- 「数千もの切り傷による死」と説明されるマイクロアグレッションには、意図的なものもあればそうでないものもある。マイクロアグレッションの悪影響は深刻で、長期的な心理的ストレスを生む。
🌍 参考サイト >>> site.
[レビュー概要]
- 著者の講演における、他の講師の経験した職業上のマイクロアグレッションに対する涙を流したという経験。
- 彼女が同僚にしてほしかったことを、私でも誰でもいいから、誰かがしてくれたらと思うのだ。立ち上がり、声を上げ、彼女の体験とその反応を認めてあげること。
- 学問的にも職業的にも、泣くこと、特に自分のために泣くことはプロフェッショナルではない、と言われ続けてきた。
- 学術医学の指導者たちは、偏見に対する反応(泣くなど)を「プロフェッショナリズム」という名目で取り締まらないように注意しなければならない。
- ある研究では、インターンの74%が職業に関連した理由で泣いており、その原因として燃え尽き症候群がよく挙げられていることが示されている(📕Sung, 2009 >>> doi.)。
- 泣いている同僚に対する私たちの対応は、彼らを弱者、非専門家、無能と決めつけることではなく、これほど多くの人が苦しんでいるのは私たちのシステムのどこが問題なのかを問うことであるべき。
- マイクロアグレッションに反応して泣くことがプロらしくないというのは、現在の医療におけるプロフェッショナリズムの定義が、いかに本物の感情的反応を排除しているかを示す一例である。
🌱 So What?:何が面白いと感じたか?
まず、次のTwitterを参照いただきたい。
Hi. I’m a healthcare worker crying at the hospital. It’s important to show more of this. pic.twitter.com/iw0bHBFrn4
— Adam B. Hill, M.D. (@Adamhill1212) August 17, 2021
やあ、私は病院で泣いている医療従事者です。これをもっと示すことが重要です。
医療者の方々に問う。
あなたは、臨床現場で、職場で、泣いたことあるか?
あるいは、泣きそうになったことがあるか?
もしくは、泣いている同僚の傍らにいたことがあるか?
すべて「Yes」という方、多いのではないだろうか。
1つも当てはまらないという方、少ないのではないだろうか。
医療以外を経験したことがないので他の業種のことはわからない。少なくとも医療現場には、葛藤が満ちている。
患者との葛藤、上司との葛藤、部下との葛藤、そして、怠惰な自分との葛藤。
そんな葛藤の積み重ねや、強力な一撃の葛藤が、その人を「泣かせる」。
どんな葛藤あったにせよ、その『泣く』という感情表現は、自然な感情で、真実なものだ。
そして、「泣く」という感情表現の次の瞬間が、非常に大切な局面になる。
そのときに、「泣いてんじゃねぇ。お前はプロだろ。出ていけ」と言われたら、どうだろう。
次から、泣けなくないか?
そしてそれは、「泣くという自然で、真実な感情」をねじ曲げる、抑圧することに等しいのだ。
僕が大好きな小説「三体」の中で、ウェイドという超体育会系の上司が出てくる。
彼は、落ち込んだ素振りを見せる部下に対して、以下のような言葉をぶつける。
お前も、お前も!
今後、こんな風に自分を見失うことは二度と許さん!
お前たちに許されているのは、前に進むことだけだ!
前へ、何があろうと前へ!
ウェイド、僕は大好きだが、完全に今回の問題に該当している上司だと思う。
「許さん」といわれようが、人間にとって、感情の成り立ちから考えて、自然な感情をねじ曲げたり強制しようとすることは馬鹿げたことだ、ということを以前の抄読から学んだ。
その局面で求められる行動は、「承認」なのかもしれない。
ああ、そういう葛藤があったのですね、よく分かりました。
その葛藤の根っこを、みんなでなんとかしていきたいですね。
話してくれて、ありがとう、私はそんなあなたを心から尊敬しています。
次の言葉は名言であり至言だ。だが、これに極端に心動かされる医療者は、もしかしたら「医療プロフェッショナリズムの武器化」をしてしまっているかもしれない・・・。
苦しいこともあるだろう。
云いたいこともあるだろう。
不満なこともあるだろう。
腹の立つこともあるだろう。
泣きたいこともあるだろう。
これらをじつとこらえてゆくのが男の修業である。
─山本五十六
○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥
良質なリハ医学関連・英論文抄読『アリ:ARI』
こちらから♪
↓↓↓
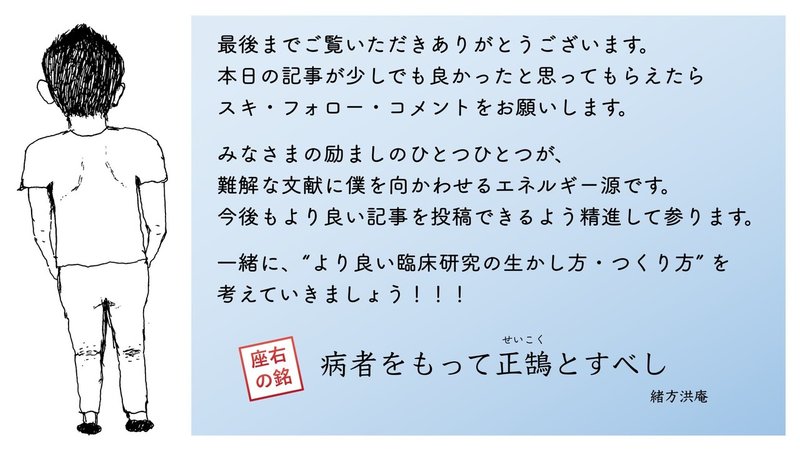
‥ ‥ ‥ ‥・・・━━━━━━━━━━━●○
#️⃣ #理学療法 #臨床研究 #研究 #リハビリテーション #英論文 #文献抄読 #英文抄読 #エビデンス #サイエンス
