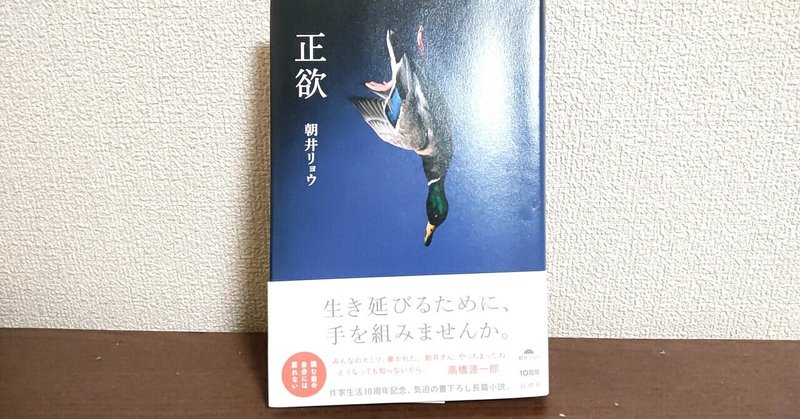
「お前らが大好きな“多様性”って、使えばそれっぽくなる魔法の言葉じゃねえんだよ」朝井リョウ『正欲』感想レビュー
僕が小説を買う最初の条件は、まずあらすじが面白いかどうかだ。それが出発点と言っていい。
僕は週に少なくとも2回は書店に立ち寄る。そこで本を手に取り、裏表紙に書かれているあらすじに強烈な興味と読書欲を掻き立てられれば、すぐにレジへと向かう。
あらゆる小説を読んできた中で各種SNSで話題になっていたのが、朝井リョウさんの『正欲』だ。これは読まなければならない。僕の直観はそう訴えかけていたものの、本書の帯にはおおよそあらすじと言えるものの表記はなく、抽象的なイメージのみだった。インターネットであらすじを検索してもヒットしない。それでも僕にとって異例と言ってもいいくらいに、まったくあらすじを把握せずにレジへと向かわせたのは、本書の何かに強烈な磁力というか、惹きつける何かがあったからだろう。
本書は3人の視点で物語が進む。
神奈川県で妻と小学生の息子と暮らす検事の寺井啓喜。岡山県のショッピングモールの寝具売り場で働く桐生夏月。神奈川県の大学で学祭の実行委員を務める神戸八重子。
お互いに顔見知りでもない3人を結びつけるのは、ある1つのキーワード。それは「多様性」だ。
ここ数年、頻繁に耳にする「多様性」という言葉。僕自身も世間一般で理解できる程度の「多様性」の感覚は持ち合わせているつもりだった。社会にはあらゆる人間が住んでいる。日本という国にもごく当たり前のように外国人が住んでいるいるし、同じ日本人でも本当に色々な人がいる。健常者と障碍者、性的マイノリティを抱えた人々。自分の頭の中では理解しているつもりだった。大学のときに初めて一人暮らしをする際に隣人に挨拶のつもりで洗剤を持って行ったとき、たまたま隣人が外国人だった。隣人は驚いた様子を見せ、片言の日本語でありがとうと言った。数日後、その隣人がお礼のためにパンを持ってきてくれた。どうやらその隣人はパン屋でアルバイトをしていて、余ったパンをくれたらしい。そのとき、僕はなぜだろうかと思ったものの、すぐに引っ越しの挨拶のときのお礼だと気がついた。日本人は引っ越しのとき「つまらまないものですが……」と挨拶するが、おそらく外国にはそういう習慣はなく、気のいい隣人は何かお礼をしなければと思ったのかもしれない。
本書を読んだとき、そのことを思い出した。僕の中では気持ちの良い思い出として残っていたのだが、本書を読んだとき、僕の理解と解釈は本当にそのままでいいのかと揺さぶられることになった。
本書はまさしく個人の頭の中で構築された「多様性」という概念が、いかに危ういものかを鋭く突き付けてくる。
本書は「多様性」というキーワードを基に物語が展開し、物語の中心人物である桐生夏月が抱えるある秘密が読者の価値観を揺さぶってくる構成になっている。
本書の最も重要な論点は、僕たちが考える「多様性」とは所詮、自らの頭の中で構築した「多様性」に過ぎず、そこからはみ出した人たちにはそもそも「多様性」という概念の俎上に載せることすら許されないということだ。性的マイノリティへの理解が進んできていたとしても、ともすればそれはマイノリティの中のマジョリティである可能性があり、さらにその枠外でひっそりと息をひそめるように生きている人たちがいるかもしれないということだ。僕はそんなことに考えすら及んでいなかった。多くの読者がそうかもしれない。
本書は、そんな人たちの叫びだと思う。
私は私がきちんと気持ち悪い。そして、そんな自分を決して覗き込まれることのないよう他者を拒みながらも、そのせいでいつまでも自分のことについて考え続けざるを得ないこの人生が、あまりにも虚しい。
P6
既に言葉にされている、誰かに名付けられている苦しみがこの世界の全てだと思っているそのおめでたい考え方が羨ましいと。あなたが抱えている苦しみが、他人に明かして共有して同情してもらえるようなもので心底羨ましいと。
P183
何かのきっかけで、これまで散々頭の中で練ってきた言葉が氾濫しそうになる。この世界の循環の中にいられるくせに不満ばかり垂れ流す人間たちに対して、人生をかけて醸成してきた思考を力の限り投げつけたくなる。
P186
彼氏彼女と言わずに大切な人と呼んでいる等という小手先の言葉選びによる多様性の尊重が礼賛される時代に、氾濫させられない叫びを噛み砕きながらどうにか割り入っていくしかないのだろうか。
P187
まとも。普通。一般的。自分はそちら側にいると思っている人はどうして、対岸にいると判断した人の生きる道を狭めようとするのだろうか。
P282
こっちはそんな、一緒に乗り越えよう、みたいな殊勝な態度でどうにかなる世界にいない。マイノリティを利用するだけ利用したドラマでこれが多様性だとか令和だとか盛り上がれるようなおめでたい人生じゃない。お前が安易に寄り添おうとしているのは、お前が想像もしていない輪郭だ。自分の想像力の及ばなさを自覚していない狭い狭い視野による公式で、誰かの苦しみを解き明かそうとするな。
P300
「自分が想像できる“多様性”だけ礼賛して、秩序整えた気になって、そりゃ気持ちいいよな」
P337
「お前らが大好きな“多様性”って、使えばそれっぽくなる魔法の言葉じゃねえんだよ」
P337
僕はそもそもこのような叫びが存在するという可能性をまったく考慮していなかった。
本書で最も胸に刺さるのは、下記だと思う。
多様性とは、都合よく使える美しい言葉ではない。自分の想像力の限界を突き付けられる言葉のはずだ。時に吐き気を催し、時に目を瞑りたくなるほど、自分にとって都合の悪いものがすぐ傍で呼吸していることを思い知らされる言葉のはずだ。
P188
僕はこの一節で「多様性」という言葉がいかに安易に使われてきたか、そして、とても危うい言葉であるということを思い知った。
本書は、令和という新時代へと移り変わっていく時間、そして、その後を時系列で追っていく。
ある登場人物は「令和になれば色んな価値観もアップデートされていくはず!」という希望を抱いているのと対照的に、静かに追い詰められていく人たちがいる。
そんな中でも本書はある2人の登場人物が交わす「いなくならないから」という対話によってささやかな「希望」を残している。
本作はささやかな「希望」と変わらないという「失望」で幕を閉じる。
この「希望」はどんな読者にも受け取りやすいメッセージだと思う。
「失望」は少し解釈が難しいと思う。これは受け手によって変わると思うけれど、僕はそう感じた。ラストでのある人物の行動は、変わらない現状を端的に表していて、それをラストに持ってくるのも本当に秀逸だと思った。
帯に「読む前の自分に戻れない」とあるとおり、本書は「多様性」という概念を揺さぶる傑作であり、快作であり、人々がこれまで考えもしなかった事実を白日の下に晒す問題作だと思う。
#日記 #雑記 #小説 #朝井リョウ #正欲 #読書 #多様性 #マイノリティ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
