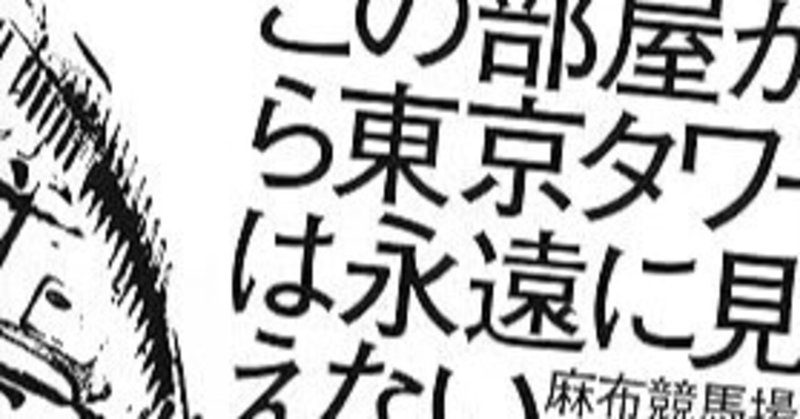
ブランドに囚われるアラサーたち:麻布競馬場『この部屋から東京タワーは永遠に見えない』
六本木、東京タワー、丸の内仲通り、麻布十番、白金高輪、清澄白河、電通、博報堂、三菱、慶應、早稲田、商社、アメフト部、クラフトビール、ビストロ、ワイン、パーソナルトレーニング、タワマン、ビームズ、イケメン、美人…
『この部屋から東京タワーは永遠に見えない』(以下『この部屋』)はブランドに溢れている。地域も、大学も、サークルも、飲むものも、食べるものも、付き合う人も、セックスする人も、自分に箔をつけるブランドとなる。アラサーの主人公たちは、さまざまなブランドを追い求めないといけないという焦燥感に支配される。なぜなら、「織田裕二、木村拓哉、松嶋菜々子が、東京タワーを背景にキラキラした恋をした。この街を出て東京に、港区に行けば、自分だってああなれる気がした」からだ。ブランドさえあれば、誰もが幸せになれるように見える。

そうしたら、港区に行けば、ブランドをすべて手に入れたら幸せになるか。
そうでもないようだ。清澄白河の良いマンションに住んでいて、夜は「京都醸造のビール」を飲み、朝は「白金高輪で買った名前の長い観葉植物」に囲まれる主人公は、過去の「ダサい」友人兼セフレが知らない女と結婚するのを見届けながら苦しむ。港区女子の主人公は美人であるものの頑張り屋さんの姉と姉の彼氏の誕生日こう想像し--「おにぎりみたいな姉の彼氏は、きっとクラシルを見ながら明治屋で買い物をして、ニトリで買った包丁で不器用に、しかし一生懸命に野菜を切ったりした」--そしてひとりで虚しく感じる。
彼らはあたかもベルの音を聞いた途端によだれを流すパブロフの犬のようだ。ベルの音はエサではないと同様に、ブランドも幸せではない。けど、ベルの音を聞くとよだれるように訓練され、自分の感性と幸せの感じ方がわからなくなってしまったのだ。
その中で、他者との関係はブランドの競い合いになってしまう。
「お前は有楽町のベニンシュラのアフターヌーンティーに行きだしたな。深夜の恵比寿のダーツバーにも行きだしたな。ビットブルを聴いてテキーラのショットを飲んだな。スナイデルなんかを着るようになったな。ボール&ジョーなんかも使い始めたな。おれはジャージにすっぴんでケン・ローチを語る君が好きだたよ。」
『この部屋』には「きみ」と「わたし」、「おまえ」と「おれ」といった二人称視点が多用される。ブランドを手に入れたきみは裏切り者。ブランドを手に入れないきみは負け組。ブランドが溢れる世界には、他人が地獄に陥るか、自分が地獄に陥る二択しかない。しかし、こうして片方が苦しむのは、幸せな関係になれない。麻布競馬場は、「ブランドなしに、他者といかに関係を築けるのか」と問っている。
その中で、幸せはどこにあるのか。馬のように走る数々の主人公たちの虚しい物語を読み、『この部屋』の終盤に私たちにはなんと幸せになれるヒントが提示される。「希望」とタイトルされた章では、世の中を斜めに構えてみる主人公がいなく、代わりに頑張って苦悩してきた「君」への愛をひたすら語る父がいる。その父はかつて会社の倒産と妻の家出を経て「惨め」で「父親失格」だった。しかし相変わらず「君」へ愛情を注ぎ、「君」が引きこもったときに憂慮し、「君」が熱中するものを見つけたときに喜ぶ。
どうやら麻布競馬場にとって、幸せはブランドではなく、他者への誠実な愛からくるもののようだ。
(ここまで読んでいただきありがとうございました。気に入ったらスキしてください!)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
