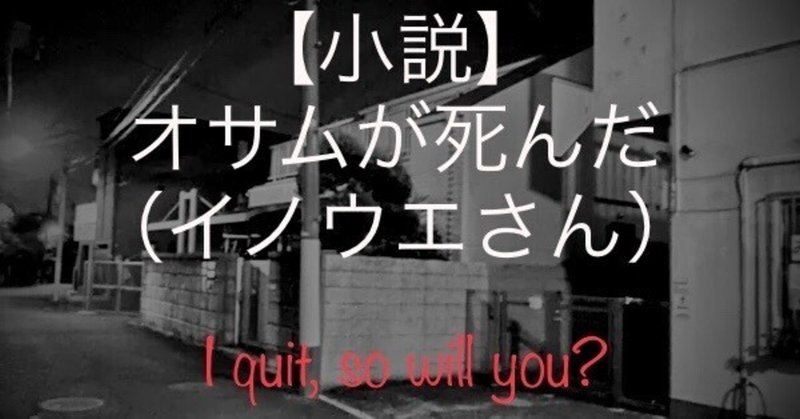
Re: 【小説】オサムが死んだ(イノウエさん)
仕事を終えて自宅最寄り駅を出たところで声をかけられた。
声をかけてきたのは見覚えのない男だった。誰か訊く前にその男はチェーン店のカフェに向かうと
「イノウエさん、はやく」
カフェの入り口に立って自動ドアを開けたままおれの名前を呼んだ。
コーヒーが白いカップの中で冷めていく。
おれはオサムが死んだと聞いて、それが誰だったか思い出すまでに少し時間が必要だった。
聞いたと言うよりは聞かされた、伝えられたと言う方が正しい。
それも今、向かい合って目の前に座る風体の怪しい男からだ。
両手をポケットに入れたまま窓の外を見ている。
おれにそれを聞かせてどうしようと言うのだ。
もう20年も会っていないような人間の死を、見も知らぬ他人から聞かされてなんと返せば良いのか。
オサム。
同い年の男だ。死んだのなら同い年の男だった、と言うべきか。
至って普通の、ノンポリで頭の鈍い──これは憶測だが私学に通っている奴などは大抵がそうだ──男だった。
近所に住んでいて同じ空手教室に通っていた時期がある、というだけの間柄だ。
別に仲良かった訳でも何でもない。
それだって中学に上がる前までの話だ。結局、お互いに黒帯を取る前に空手をやめた。
おれは辞めた事を後悔していた時期もあった。
結局のところ革命は暴力によってしか達成されないからだ。
国民の手に主権を取り戻すには選挙などと悠長な事を言っている場合ではない。だがおれひとり程度の空手や暴力でこの国が揺らぐようなことは無い。
それはおれが最強ではないからだ。
圧倒的ではないからだ。
刃物と弾丸の方が強い。ならば拳は何の役にも立たない。
「それで」
目の前の男は、外に向けていた顔をこちらに向けた。
反射するサングラスのレンズにはおれ自身が写っている。
この男の目がどこに向いているのかはわからない。
「何か思い出しましたか」
男はおれに訊いた。
何か思い出しましたか、だと。
なぜおれがお前の為に何かを思い出さねばならないのだ。
思い出してお前に伝えて、それがどうなると言うのだ。
あいつが有名人ならコメントを取って回る事も意味があるだろう。
それとも何か、おれの知らない界隈ではちょっとした有名人だったのか。
仮に何かを思い出したとしてだ。
何の仕事をしているとも取れない怪しい男にそれを伝える事などできない。
個人情報だとかいう問題ですらない。
礼儀やマナーとしてスーツのひとつでも着てくるべきじゃないのか。
名刺くらい出すべきじゃないのか。
そうだ、そもそもお前は誰なんだ。
「まぁ、久しぶりに聞いた名前でしょうから。時間、かかりますよね」
男は冷え切ったコーヒーをひとくち飲むと「すっぱい」と言って机に戻した。
「まぁ、ゆっくりでいいです」
そうじゃない。
仮に何かを思い出しても──
「それに何か思い出しても言う気になれねぇってのはありますよね」
男は再び視線をおれから背けて言った。
いや、顔を外に向けて言った。
「なんだよ」
おれの声は微かに震えていた。
「え」
男が顔をこちらに向けた。
「なんだよ、その言い草は」
「何か気に障る事いいましたか」
「気に障る、全部と言えば全部だ。お前の風体も、喋り方も、何もかもが妖しくて何もかもが癪に障る。お前はおれの知り合いなのか。誰なんだ」
おれは一気に捲し立てた。唇が乾いていた。冷めきったコーヒーを流し込む。こんなに不味いコーヒーを飲んだことがないと思った。
男はおれの勢いに全く動じなかった。
「知り合い。そうかも知れないし、違うかも知れない。オサムってのは共通のアレですけど」
ポケットから手を出してコーヒーカップをつまむと、その男もまた不味そうにコーヒーを飲んだ。
「お前はオサムのなんだ?」
「イノウエさんはオサムの何なんですか」
おれは、何なんだ。
おれとオサムは近所に住んでいたものの別々の学校に通っていた。
同じ空手教室に通ってはいたが、別に休みの日に遊ぶほど仲良くも無い。
近所なので顔を見れば挨拶くらいはするけど、だからそれがどうと言う事でもない。
中学生になってからは会った記憶が無い。
大学はどこか遠くの大学だと聞いた。
今のいままで忘れていた程度の、特に興味の無い男だ。
「特に何もないって言うなら、別にそれでいいんです」
男はそういって机の上に置かれた伝票を掴んで立ち上がろうとした。
「待てよ」
おれその手を抑えた。
男は浮かしかけた腰をスツールに下ろして「なんかあるんですか」と訊いた。
その顔は少し笑っているように見えた。
「いや」
何もない。
何もないがこのままこの男を返すのも良くないと思った。
そうだ。
オサムが死んだと言う証拠はどこにもない。誰からも聞いていないのだ。
「オサムは本当に死んだのか」
「まぁ、別に有名人じゃないので確認する方法なんてそんなにないですけど」
実家に電話して訊くべきか。
いや、実家にその情報が伝わっているかもわからない。
「いつ死んだんだ」
「さァ、自分も詳しい事は知らないのでアレですけど、最近」
「最近ってのはいつのことだ」
「最近って言ったら、ここ何か月かってところじゃないですか」
ならもう通夜だの葬式だのは終っているじゃないか。
それなら尚のこと、この男は何が目的でオサムの事を聞いて回っているのか。
週刊誌の記者にも見えない。
まして公安だとかの臭いはしない。
単に怪しいだけの男だ。
だからこそ厭な感じがする。
「何もないなら、帰りますよ」
男は再び腰を上げた。
「あいつは」
おれは咄嗟に口を開いた。
男はこちらに顔を向けてからゆっくりと腰を下ろした。
「あいつは、ネット右翼だった」
おれはカップの中で冷めきった茶色いコーヒーを見ながら言った。
「ネット右翼ですか」
男はさして関心もなさそうだった。
「あぁ。典型的なレイシストで資本主義の犬で大本営発表を喧伝する政府の犬、その犬にたかる寄生虫だった」
「凄い言い方するんですね」
「事実だよ。あいつのSNSを見ればわかる」
「見てたんですか」
「たまたまな。こっそり裏アカウントでフォローして見ていたよ」
そう、見つけたのはたまたまだった。
そしてこっそりとオサムの言動を見ていた。
オサムはネット右翼だった。
だがおれたちが望み、喧伝するようなネット右翼の姿──別に負け組の底辺と言う事は無かった。
氷河期世代にしては恵まれた職に就き、不自由なく生活していた。
だが思想は思想だった。
どこか遠くの大学にいたと聞いたが、そこで誰に何を聞いたのか教えられたのか、酷く差別的で右傾化した考えを発信していた。
そもそもマスメディアに勤めている人間がそれでいいのかと思った。
マスメディアと日本国民の習性は相性が悪いと思う。
プロパガンダを流されたレミングスがどうなるか、それは戦前から何も変わっていない。
主体性とは何なのか。
江戸幕府以前から無かったのであればこの国にそんなものがあった瞬間などないのだろう。
だから。
「それでオサムさんの家の前にカツラなんて置いてったんですか」
そうだ。
あいつは馬鹿だから写真を撮ってネットにアップして自宅がバレて悪戯されれば良いと思った。
だがあいつは写真を撮らなかった。
その程度のネットリテラシーは持ち合わせていた。
でも。
「何故それを知っている」
おれは男を見据えた。
「なんでって」
男は氷の解けたグラスの中の水を飲むと
「それ、見てましたんで」
と言った。
「まぁ手間暇時間がかかったけど、どうにかたどり着いたよ」
男は砕けた口調で言った。
「イノウエさん、卑怯じゃないかい」
サングラスを外すとオサムは黒い目でこちらを見ながらもう一度「なぁ。卑怯、じゃないかい」と言った。
その男は全て知っていた。
おれが左翼系団体やNPOから足を洗ったことも、結婚して子どもがいることも、いまの会社で業績を上げられずに立場が良くないこと。
その上に過去の活動が知られてしまい、白眼視されていることも知っていた。
「だから、どうした」
おれは絞り出すように言った。
腹に力を入れていないと声がでなかった。
「別にどうもしねぇよ」
男はつまらなさそうに言った。
「あんたがこっちをストレスの捌け口にしようと構わないけど、やるなら自分の手を汚しなよ」
卑怯だろ、その自覚くらい持てよとオサムは笑った。
「おれが誰にどうされて欲しかったのか知らないけど、自分の手でやるべきでしょ。
ポストに何を投函するにしてもベランダに生卵放り込むにしても、自分でやらなきゃ嘘じゃない?
左翼ってのはさ、そうやって自分の手を汚さないで美味しいところだけ持っていくから嫌われるんだよ。
労働者階級でもない癖に味方面だけしてさ、お前みたいにスノッブな大卒が社会問題って何言ってんだよ。
上っ面だけで、あとは税金の使い道突いてりゃ仕事した気になってるだけだろ。
生活って知ってるか、まぁお前みたいな地主の息子にはわからないだろうけどな。
一生そうやってじめじめと鬱屈してろよ。
結婚して子どもいるらしいけどお前のガキにはその思想を押し付けるんじゃねぇぞ。
お前の親父さんは若くして肺癌患って死んだんだっけ?
長生きしてたらお前も活動家から足を洗うなんてできてなかったろうな」
そう言ってオサムは立ち上がると伝票を掴んでレジに向かった。
おれは咄嗟にネクタイを解いて手に巻くと、奴の後ろから首にかけて背負う容量で締め上げていた。
サポートして頂けると食費やお風呂代などになって記事になります。特にいい事はありません。
