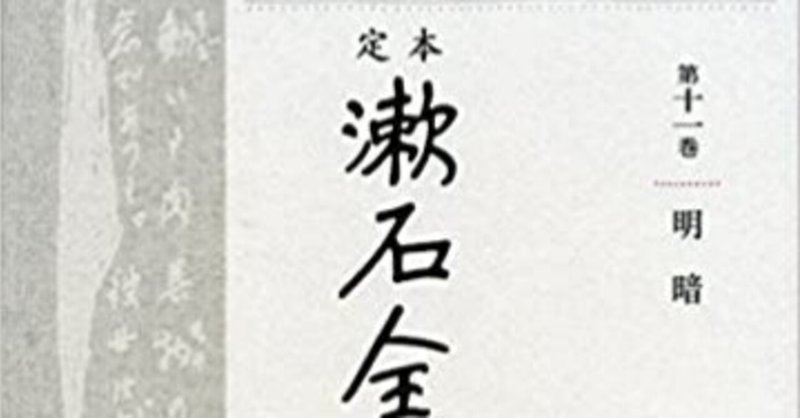
夏目漱石とAI小説 (※文学ってなんだ? 15)
「AI小説」がいかなるものなのか、この身をもって経験したことがないので、分からない。
そういう類の作品を、これまで一度も手に取って読んだこともなければ、実際に創作を手伝ってもらったという事実もない。
それゆえに、昨今、文学賞まで設立されたという、この新しきジャンルの小説について、または、AI小説生成ツールなるものについて、一家言をも持ち合わせてはいない。
だからしょせん、印象論の域を出ないものになってしまうかもしれないが、――それが肯定的か否定的かと問われたならば、むしろ肯定的である。
なぜか?
ぜひとも、読んでみたい「AI小説」が、たったひとつだけ、あるからだ。
夏目漱石の『明暗』の、”続き”である。
「大変に優れた」AI技術をもって、ぜひとも、この未完の大作の続きをば、完成させてもらいたい――そのようにして、「近代日本文学の最大の謎」にまで、迫ってもらいたいと、そう思っているからである。
「並みの小説家なんかよりもはるかに優れている」ような、素晴らしきAI小説生成ツールをもって、『明暗』の続きが書き上げられたならば――
完璧なグロッサリーやコンコーダンスが駆使された、――残され、保存された原稿についての筆跡学等による分析も踏まえた、――長年にわたって解剖・解析・研究しつくされてきた作家の生涯についての、これまで書かれたあらゆる文章をも読み込んだ――そのような完全な「定本」から紡がれた、たった数行の文章を皮切りにして、
そして、やはりそんな現存する夏目漱石の全データがインプットされたAI生成ツールによって、『明暗』の続きがついにベールを上げられたというのであれば――
ぜひとも、この手に取って読んでみたいと、思っているからである。
ただし、知りたいことは、たったひとつだけだ。
『明暗』――というタイトルが示唆している通り、漱石が迫ろうとした、”暗”の部分に、「AI小説」がどれだけ迫り得たのか、この一事である。
『明暗』を、「定本」でなく、「現代表記」なんかで読んでみても分かることだが、夏目漱石は、「どうしてあの女はあそこへ嫁に行ったのだろう」という主人公の煩悶を通して、”暗”に迫ろうとしている。
すなわち、清子という名をした一人の女が、どうして津田という名をした主人公を捨てて、違う男と結婚してしまったのか――その「どうして」という、人間が隠している”本音(暗)”のせいで、日常生活の中に表出してしまう種々の事象、現象、事件、出来事(明)……それが『明暗』という小説である。
そして、小説は、「どうして」の真相に迫るべく、津田がふたたび清子とまみえるために地方の温泉宿へ赴き……という場面で、惜しくも中断してしまっている。まさにこれから、物語の最高にして、最大の山場を迎えんとするところで…。
だから、私は、そんな「最高にして、最大の山場」を、どれだけ素晴らしくAI小説が描き得るのか――
そういう「面白さ」について、興味があるから、「肯定的」なのだろうか?
そうではない。
まったく興味が無いわけでもないが、それは言うなればエンタテイメント的面白さであって、「文学的」なものではない。
エンタテイメント性について言うならば、いずれそう遠くない日に、「AIが人間を超える」のではないだろうかと、そう予測している。
たぶんきっと、そうなるであろう。
さりながら、
いや、
だからこそ、
”暗”の部分をも、どれだけAIが描き得るものなのか、見てみたいのである。
”暗”は、ひと言でいうならば、人間の心の中身である。
AI、すなわち人工知能が、いったいどれだけ、エンタテイメント性を超えた、人間の心の中身、つまり「文学」の本質にまで迫り得るものなのか――
漱石以降の、なまくらな作家たちが、「時代」みたいなたまゆらの、水面に浮かんだあぶくみたいなものを過剰にとらえたがったあげくのはてに、アンガージュマンだの、デタッチメントだのとのたまって、海辺の砂浜でおままごとにいそしんでいた、
そんな甘えに甘ったれたような「文学ごっこ」ではなく、人間の心という大海の深みにまで、ほんとうに漕ぎ出し得るものなのか――
それをこそ、見てみたいのである。
でも、しかし、どうして、残念ですが、
そんな結論は、はじめから決まっている。
「やっぱり、無理だったね」という結果になることを、わたしは知っている。
どれだけのデータであれ、研究であれ、分析であれ、――なんであれ、「たかが人間」の始めた仕事を、「たかが人間」の造った科学的オモチャなんかが、完成させてみたところで、「やっぱり、この程度だよね」という結末にしかならないに、決まっているではないか。
くり返すが、『明暗』は近代、現代を問わず、「エンタテイメント性」において大変優れた小説なので、その側面については、AI小説が完成された日にもなお、「大変優れたもの」という評価を受けることだろう。
もし、大正5年に死んだ夏目漱石が、大正10年頃まで生き永らえていたとしたならば、間違いなく、『明暗』を完成することができたはずである。そんな生き永らえた人間・夏目漱石が完成させた『明暗』よりも、近未来のAI小説『明暗』の方が、「さらに面白い出来栄え」と、なり得るかもしれない。
しかし、どうして、残念ですが、
しょせん、「そこどまり」である。
近未来において、生身の人間の作った小説よりも面白い「AI小説」が誕生したとしても、そんな作品が逆説的にさらけ出してしまうであろう「真実」とは、「ここまで来てもよいが越えてはならない 」という、「行き止まり」である。
さながら、バベルの塔がけっして完成することのなかったように、何かが未完成な状態で残されたまま、「AI小説」は日の目を見つづけることであろう。そんな「未完成感」は、たとえば、夏目漱石の『明暗』を、「AI小説」として完成させてみれば、如実に現れてくるのではないだろうか。そう、まるで未完成感が”暗”で、面白さが”明”であるがごとく…。
それじゃあ、お前はただ、人工知能による「未完成感」を確認したいだけなのか?
――と問われれば、私の答えは「否」である。
冒頭からくり返している通り、私はAI小説に対して、あくまで「肯定的」である。
なぜか?
「偶然」に期待しているからに、ほかならない。
人間のする仕事なんか、どこまでいっても、完璧があるはずがない。それが、人間の「定め」というものである。
だからこそ、だからこそ、
必然でも、当然でも、計算通りでもなく、
まかり間違って、ミスの結果として、さかしらな人間の予想を超えた計算違いによって、
「 ”暗”の部分に、原作者よりも人工知能が迫ってしまった」
――という偶然をば、見てみたいのである。
偶然というよりも、「皮肉」と言った方が、いいかもしれない。
そしてそれは、「やさしい皮肉」である。
「辛辣な皮肉」ならば、我々はすでに、これまでの歴史上で、イヤというほど見せつけられつづけてきた。
たまには、「やさしい皮肉」があっても、いいではないか。
「やさしい皮肉」――つまり、「大いなる恵み」とか「驚くべき恵み」とかいう名のついた類のものである。
それに、これはひっきょう、「文学」の話である。
「大いなる」でなくたっていいし、「驚くべき」である必要もない。
「ちいさな」、「ささやかな」な、まるで「食卓の上からこぼれ落ちたパン屑」のような「恵み」でもいいから、
「人工知能」によって紡がれた小説が、まかり間違って、夏目漱石の『明暗』の”暗”に、だれよりも迫ってしまった、
その結果、
例えば、「希望」に満ちあふれた物語をば、読む者の心に与えてくれたのだ――
たまには、たまには、
そんな胸の温まるような「皮肉」があったって、いいじゃないか。
ねぇ、神様…?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
