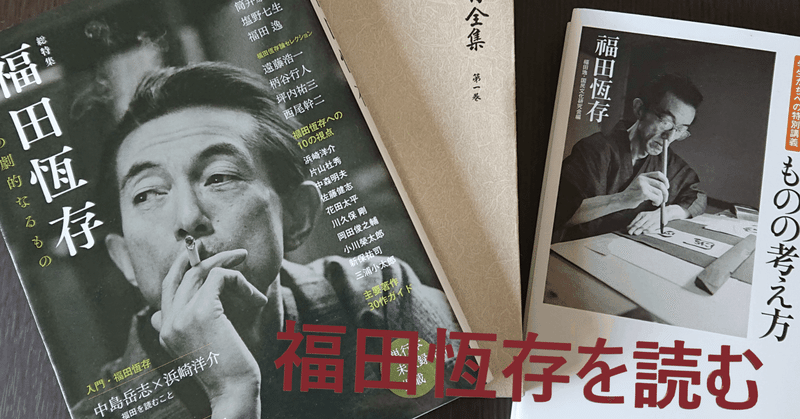
『文藝批評の態度』作品を育て、作家の意思を継ぐこと
福田恆存は、あえて「理想」を遥か遠く手の届かない場所に置き、そうすることで「現実」の相対性に処することを教えてくれる人間である。だからわたしは福田の文章を読むと不思議な心持ちになる。落ち着き、同時に高揚するのである。おそらく、その現実的な生きかたに安心を感じ、高邁な理想に気分が溌剌とするのであろう。
そういう意味では『文藝批評の態度』は、福田恆存の文藝批評家としての理想表明であると読める。福田は問う。いまだ確立されていない文藝批評が一つの独立したジャンルとして確立するために必要なものはなんであるか、と。
「創作月評はもとより、ぼくのこの文章を含めて文藝批評と呼ばれるものの多くは、厳密な意味において断じて文藝批評ではありえない。混乱の原因は、文藝批評といふジャンルのいまだ確立をみないことにある。」
では、そのジャンルとしての確立のために必要なことはなにか。
「ひとつひとつの作品を詩と称し藝術と呼びながら、その作者の生活に詩人、藝術家を発見しえぬことは、ジャンルの不幸であらう。あへて藝術とはいはない。それに従事するものの全生活を要求することなくして、あらゆるジャンルはジャンルとしての自立性を保証されないのである。あるジャンルがおのれのために、自分の生活をなげうつものをたとへひとりでも見いだしたとすれば、それは歴史がそのジャンルに時代精神の表現を委任したことを意味する。」
つまり、文藝批評というものが一つのジャンルとして確立を目指すならば、それを一つの生き方までにする人間が出てこなければならないということだろう。それも一代ではなく、系譜としてである。
「いかなる藝術のジャンルも一代にしてその完成をみることはできない。」
では、文藝批評家たるものは如何なる人間であるか。福田は言う。
「文藝批評家とは、既成のジャンルとしての近代小説の技法をもつてしては表現しえぬ精神を自己のうちに持続してゐるもののことである。」
福田は、それ以前に、ジャンルとしての近代小説の方法に疑惑の念を感じた批評家の例として、北村透谷や生田長江の名を挙げる。またその疑惑をはっきりと不信にまで意識した人間として、小林秀雄、保田與重郎の名を挙げる。
「とにかく、文藝批評家は ー その名にあたひするものである以上 ー 現代の小説をその素材として、それにたんなる価値判断を与えるのみでは、容易に表現と創造とに道を通ずることはできないのである。」
「文藝批評家たるものは、現代ではむしろ作家以上に強烈な個性と表現慾とをもつたものでなければならない。明治以来の近代小説に対する疑惑と不信とこそは批評家たるの資格の第一箇条であるが、この疑惑に応え、この不信をみづから正当化する責任を自分の生活に負ふこと ー したがつて、かれは作家以上にその生活に切実な主題をになつてゐなければならない。」
福田によれば、批評家の背後にある生活と作家や作品とが対決する場所に「批評の実感」が成立する。
「あらゆる作品はそれ自身では存在しえない。享受によつてはじめてその存在を証明される。だが、作品は存在するのみでなく、また成育するものである。作品を育て、作家の意思を継ぐこと。これはもはやたんなる享受ではない。作家と同程度の精神と精力とを必要とする。」
批評家の理想は、作品を育て、作家の意思を継ぐことである。そしてその先に、自ずと現われるものこそ、自我である。その表現を成した時、初めて文藝批評がジャンルとして確立しうる。
そういう訳で「批評家はまづなによりも名文家たらねばならない」。なぜなら、「論理はたんに証明するにすぎないが、名文は造型する」からだ。これは福田が生涯保持した理想であろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
