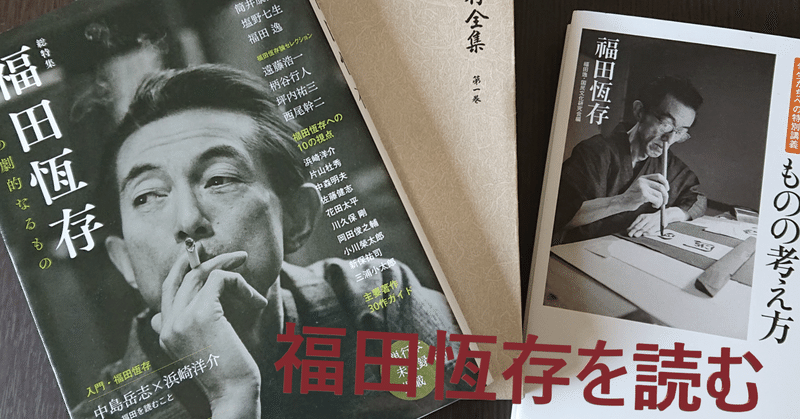
【閑話】宣長にとっての『古事記』と注釈
「宣長にとって『古事記』を読むことは、言葉を手がかりとして世界のありかたを解き明かし、それにより自己の生と心のありかたを確信する行為に他ならなかった。そうした宣長の志向を抜きにして個々の注釈を云々することはできない。」
宣長は『古事記』を読むことで、また注釈によって、「近世神話」を創造しようと試みた。それは何よりもまず、宣長自身が自らのアイデンティティーを確信させるための行為でもあった。宣長は『古事記』の言葉と向き合うことで、自己の生と心のありかたに向き合っていた。
「宣長の読んだ『古事記』は、近世の現実を生きた宣長自身のアイデンティティーを確信させる物語としてあった。それは宣長の抱えた問題として把握されねばならない。しかし一方で我々自身が、『古事記』を古典として持つことの意味と向き合いつつ、絶えず現在の読みを更新してゆく必要がある。それがいま古典を読むことの意義であり、『古事記伝』や『三大考』の「知」に教えられることなのである。」
注釈は積み重なって全体像を形づくる。
ゆえに個々の注釈の意味は、その全体像の中において読み解いていかねばならない。
だがそれは決して固定されたものではなく、絶えず更新されていくものでもあり、そこに注釈の、また古典を読むことの意義もある。
「今の学問界には、方法さへ正しければ成果はおのづから挙がる、成果が挙がらないのは、方法を知らないからだ、といふ考へが根強い。この考へに囚はれて、「うひ山ぶみ」を読むから、宣長の懐疑を見損ふ。学びやうを知るより、怠らず学ぶ事の方が、どんなに大事かわからぬ、といふところに、宣長の思想の中心がある事を見損ふ。」


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
