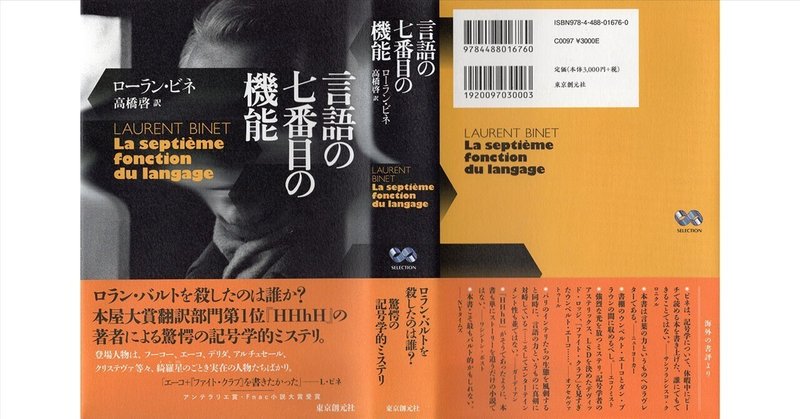
『言語の七番目の機能』訳者あとがき
これはけっして、柳の下の三匹目のドジョウではありません。
ついにローラン・ビネの第四作目『パースペクティヴ』(仮題。Perspective(s) ; Editions Grasset & Fasquelle, 2023. 東京創元社より来年刊行の予定)の翻訳に取りかかったからです。フランスの版元の触れ込みでは、ルネサンス期のフィレンツェを舞台に展開される「書簡体歴史ミステリー」とのこと。もちろん、ローラン・ビネのことですから、あっと驚く仕掛けが満載です。ちょっと早めの前宣伝を兼ねての前作紹介といったところですが、実際のところ現在進行中の『7』という変わったタイトルの長編小説(7 , romans : Tristan Garcia ; Editions Gallimard, 2015. 河出書房新社より来春刊行予定)と並行して翻訳を進めなければならないので、新たに原稿を書き起こしている余裕がまったくないのです。ご理解いただければ幸いです。なお、ヘッダーの書影は前回の投稿に使ったものが、うまくスペースに収まらず、帯の文言が読めなくなっていたから、あらためてスキャンし直しました。
*(訳者あとがき)
作家でコレージュ・ド・フランス教授のロラン・バルトは、三月二十六日、交通事故が原因でパリ市内のピティエ=サルペトリエール病院で死亡した。先月二月二十五日、エコール通りの横断歩道で自動車にはねられ、頭部に外傷を負っていた。六十四歳だった。
これは、一九八〇年三月二十七日付『ル・モンド』の記事の冒頭である。
文芸批評の世界にまったく新しい視点と方法論をもたらし、世界中の文学ファンに愛されたあのロラン・バルトが交通事故で死ぬなんて、とても信じられないという声はあったものの、事故死を疑うものは誰もいなかった。
ところが、それから三十五年の月日が経って、その事故から奇想天外な小説を思いついた作家が現れた。本書の著者ローラン・ビネである。二〇一〇年に処女作『HHhH』でゴンクール賞の新人賞を受賞して颯爽とデビューを果たした若き作家が、次に満を持して世に問うた「問題作」が、本書『言語の七番目の機能』(La septième fonction du langage; éd. Grasset, 2015)である。
出版されるや否や、「フナック小説大賞」(フランス最大の書籍販売チェーン店Fnac が二〇〇二年に創設した文学賞)と「アンテラリエ賞」(一九三〇年に創設時はジャーナリストがジャーナリストによる小説を選考する文学賞だったが、現在は作家も選考に関わり、対象もジャーナリストによる作品に限らない)を受賞し、すでに三十以上の言語に翻訳されている。
とはいえ『HHhH』のときと同じく、またもや翻訳家泣かせの小説である。そもそも『言語の七番目の機能』というタイトルそのものが、およそ小説らしくなく、事実、その出どころはロシア生まれの言語学者ロマン・ヤコブソンの『一般言語学』なのである。しかしながら、ヤコブソンがこの著作のなかで挙げている言語の機能は六つしかない。七番目の機能なるものは、分類としては存在しない。つまり「言語の七番目の機能」なるものは小説家の想像力のなかにしかなく、この作品は七番目の機能について書かれたヤコブソンの未発表原稿を追うサスペンス小説なのである。
しかし、この小説が「問題作」であるのはここからである。このヤコブソンが残した「七番目の機能」なる文書を手に入れたのがロラン・バルトだったというのである。そして、その死は偶発的な交通事故死などではなく、「七番目の機能」をバルトの手から奪い去るために入念に仕組まれた謀殺だったというのが、この小説の「仮説」なのである。
のっけからネタバレかと訝る読者もおられるかもしれないが、ここまで書いたところは、本書の冒頭十数ページを読めばすぐに見当がつくような事柄である。そして、読み出したら、作家の魔法にでもかかったかのようにページを繰る手が止まらなくなるだろう。この作家の持つ語りの力は、処女作の『HHhH』ですでに実証済みである。
ロラン・バルトが実在の人物であり、死因となった交通事故も事実であり、それを発端として小説が展開する以上、登場人物のほとんどが実在の人物なのである。二十世紀後半の世界の思想界を牽引したフランス現代思想を代表する錚々たる作家、哲学者が実名で登場する——ミシェル・フーコー、ジャック・デリダ、ソレルス、ジュリア・クリステヴァ、BHLことベルナール=アンリ・レヴィ、ドゥルーズ、ラカン、挙げていくと切りがない。のみならず政界からは、第二十一代フランス共和国大統領のフランソワ・ミッテランとのちに最初の内閣の閣僚を務める取り巻きたち、その政敵たる第二十代大統領のヴァレリー=ジスカール・デスタンも登場する。
だが、この作品は「歴史小説」でもなければ、ノンフィクションでもない。純然たる「小説」なのである。この作家がもっとも強く惹かれている領域がフィクションでも、ノンフィクションでもなく、そのあいだに広がるグレーの領域であり、じつは人間という観念的な生き物はそのグレーの領域で生きているのではないかという暗黙のメッセージがこの第二作にも流れていることは認めるにしても、ここに描かれたフランス現代思想のスターたちの、ときに目を覆いたくなるようなあられもない姿をどう考えればいいのか?
カナダのトロントを本拠に活動している文芸ジャーナリストのリディア・ペロヴィッチ(Perovic)は、著者本人に率直にこんな質問をぶつけている(http://www.partisanmagazine.com/blog/2015/12/4/an-interview-with-laurent-binet)
——〔名誉毀損で〕訴えられはしないか心配することはなかったのですか? 少なくとも英語圏の出版社はまずそれを心配したと思うのですが。
これに対して、著者はこう答えている。
——いいえ。ただ、正直言って、僕の版元は心配したかもしれませんけどね。僕が心配しなかったのは、バルトが実際は殺されていたかもしれないなどと信じる根拠がまったくなかったからです。だから僕は思い切って、誰も真実だとは思えないような奇想天外な出来事を創作したんです。
なるほど。ところが、著者は他の様々なインタビューに答えて、根も葉もない事実無根のことをでっち上げているわけではないとも釈明している。たとえば、古風な「仕込み傘」を持ったブルガリア諜報部員の活動にブルガリア出身のクリステヴァの関与が疑われたこともあったし——本人は「事実無根」と反論しているが——、精力絶倫のフーコーの姿についても、直接の目撃談に基づいて書いていると発言している。
でも、まあ、この程度のことは目くじらを立てるほどのことではないのかもしれない。見るも無残な悪役の姿に仕立て上げられたソレルスにしても、コーネル大学のキャンパスに隣接する墓地で『バスカーヴィル家の犬』に出てくるような猛犬に喰い殺されてしまうデリダにしても、親族や出版社が訴訟を起こしたという話は届いていないので。
ようするに、この作品にはローラン・ビネという才気あふれる作家のサービス精神がてんこ盛りにされていると考えればいいのだろう。フランスやアメリカで発表された書評や紹介記事の内容をおおまかにまとめると、次のようになる。
第一に、これはシャーロック・ホームズ風の探偵小説である。大学で記号学を教えている主人公のシモン・エルゾグという名が、シャーロック・ホームズ(イニシャルがS・H)に重ねられるし、フランス総合情報局の警視ジャック・バイヤールが、アメリカの人気テレビドラマ・シリーズ「24:トェンティフォー」の主人公の捜査官ジャック・バウアー(J・B)に重ねられるとは著者本人の弁。のみならず、これはじつに巧みに書かれた記号学入門の書である。著者によれば、シャーロック・ホームズの名推理はこの世の神羅万象を解読する記号学の応用篇であり、バルトの代表作『神話作用』もまた現代の資本主義社会を解析し、その本質を炙り出す記号学の名著だということになる。
あるいは、先端に毒を仕込んだ傘による暗殺劇や銃撃戦、パリ市内で繰り広げられるカーチェイスなど、アクション映画におなじみの場面が随所に出てくるところは、ジェームズ・ボンド張りのスパイ小説を思わせる。
あるいはまた、謎の文書をめぐるミステリーという意味では、中世の黙示録的文書を追い求めるウンベルト・エーコの世界的ベストセラー小説『薔薇の名前』を下敷きにしているとも考えられる。エーコ本人が小説内に登場してくるのも、この大作家へのオマージュなのだろう。
読み進めていくうちに全貌が明らかになっていく秘密結社〈ロゴス・クラブ〉主催の弁論対決の場面は、鬼才デイヴィッド・フィンチャーの『ファイト・クラブ』を念頭において書いたと本人が語っている。作品のいたるところで一九八〇年代初頭のポップミュージックがいたるところに鳴り響いているのは、著者がかつて「スターリングラード」なるロックバンドでボーカルと作曲を担当していたことと無関係ではないだろう。
作品の舞台装置として巧みに使われているポップカルチャーの要素が、かつてセーヌ左岸のサンジェルマン界隈にたむろしていた——今も?——知識人への痛烈な風刺をいっそう際立たせる効果を生み出している。
五年前に訳者がパリで著者に会ったとき、今回の作品はいくらなんでも風刺の度が過ぎるのではないかとつい本音を漏らすと、いや、これは風刺ではなく、嘲笑なんだという反応が即座に返ってきたことを思い出す。
そのとき訳者は、ああ、そうか、フランスの若い世代に属する作家たちは、そのほとんどが戦前生まれの現代思想の綺羅星たちが目の上のたん瘤のように目障りに感じているのかもしれないなと思ったものである。
(後略。続きは、実際に本書を手にとってお読みいただければ幸いです)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
