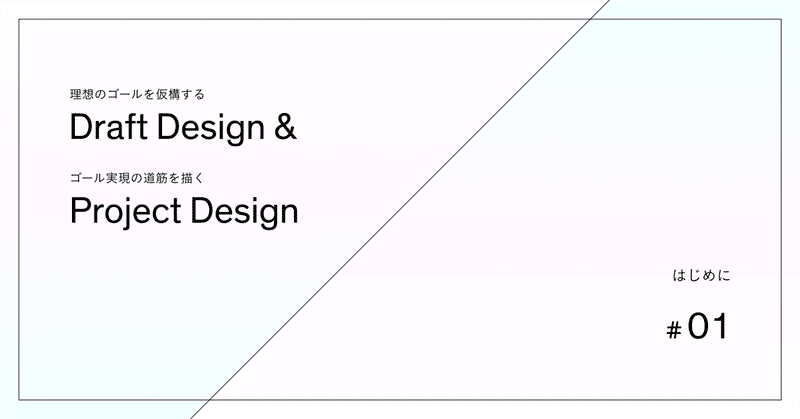
#01 はじめに
「プロジェクトデザイナー/ドラフトデザイナー」という肩書き
Takramというデザイン・イノベーション・ファームで、「プロジェクトデザイナー/ドラフトデザイナー」という肩書きで働いている。どちらも聞き慣れない職種だと思うが、それも当然だろう。
入社した当初は「ビジネスデザイナー」という肩書きで始めたのだが、Takramでは個々人がプロフェッショナルとして既存領域を越境・拡張し、新たにカテゴリメイキングすることを推奨していることもあり、自ら「プロジェクトデザイナー/ドラフトデザイナー」を名乗ることにしたからだ。
実際、胸を張って「ビジネスデザイナー」を名乗れるほど、自ら事業を興したりグロースさせた経験はないので、どこか借り物のような感じがしたということもあるが、今の世界が資本主義や価値交換を基本的なプロトコルとして駆動している以上、「ビジネス」はあらゆる物事と否応なしに関係してしまうとも言える。つまり、「ビジネスをデザインする」ということは、自身と顧客だけでなく、「社会・環境・未来との関係性までをもデザインすること」と言っても過言ではない。
さすがにそこまでのスコープを肩書きとして背負うのは荷が重いけれど、「ビジネスデザインのためのプロジェクト」であればこれまでデザインしてきたと言ってもいいかもしれない。そう思って付けた肩書きが「プロジェクトデザイナー」だ。
実際、プロジェクトマネージャーやクリエイティブディレクターなど、関わり方は時々によって変わるが、前職のロフトワーク時代を含めると、これまで10年以上「プロジェクト」に携わる仕事を続けている。
プロジェクトの内容は様々で、企業のWebサイト制作、対象者のニーズやインサイトを導出するデザインリサーチ、イベントやワークショップの企画制作、新規事業創出支援、共創空間のプロデュース、メディアの立ち上げ、芸術祭の制作など、多岐にわたる。
PMBOK®(Project Management Body of Knowledge:プロジェクトマネジメントの知識体系)において、プロジェクトは「独自のプロダクト、サービス、所産を創造するために実施される有期的な業務である」と定義されているように、プロジェクトの一つの特徴は「独自性」だ。
その通り、プロジェクトごとに転職しているに等しいくらい、毎度新しい業界やテーマに取り組み、毎度新たな学びや刺激を得られるのは飽きっぽい自分の性に合っていたのかもしれない。
しかし改めて思うが、プロジェクトをリードする方法は本当に人それぞれだ。精密にプロジェクトを設計し、丁寧にタスクやリスクをコントロールすることで確実に成功に導くタイプの人もいれば、逆に、小さなトラブルは絶えないながらも、持ち前の愛嬌や天才的なコミュニケーションスキルで関係者の誰もが最終的には笑顔になってしまうというケースも、はたまた、プロセスやロジックの飛躍に誰も付いて来れなくとも、圧倒的なアウトプットのクオリティで納得させてしまう、という人もいる。
曲がりなりにも十数年も働いていれば、さすがに自分の力量もある程度分かってくる。つまり、残念ながら僕は上記のように何かそれだけで武器になり得るような突き抜けた才能も特技も持ち合わせてはいないということだ。
では、これまでどのようにそれらのプロジェクトを推進し、実現させてきたのかを振り返った時に、一つ自分の特徴かもしれないと思い当たったのが、「叩き台(ドラフト)」を作り、提示することだった。
突き抜けた専門性がない、裏を返せばオールラウンダーだからこそ、上流と下流、戦略と実装、事業とユーザーなど、領域と領域のエッジに立ってその間を架橋することでつかめる概観・直観というものがある。
その概観・直観に基づいて、「やりたいことってつまりこんな感じだよね?」という像をドラフトとして提示できると、プロジェクトやコラボレーションを促進するドライバーとして機能するという実感があった。
これまでただの資料や中間成果物としてプロセスの中に埋没していた行為を、「ドラフトデザイン」と名付け輪郭を与えることによって、その可能性を拡張し、新たなカテゴリメイキングができるかもしれない。
そう考えて付けたもう一つの肩書が「ドラフトデザイナー」だ。
「プロジェクトデザイン」と「ドラフトデザイン」は相補的な概念
こうした経緯で「プロジェクトデザイナー」と「ドラフトデザイナー」という二つの肩書きを並べて名乗り、その視点でプロジェクトに取り組んでいくうちに、ドラフトという概念はもっと広く適用できるのかもしれない、と感じるようになった。つまり、ドラフトはプロジェクトの中間成果物としてだけでなく、プロジェクトのゴールそのものを仮構することとも捉えることができるのではないか。
そう考えると、「プロジェクトデザイン」と「ドラフトデザイン」という二つの概念がゴールという地点で接続され、互いに振り子のように行き来しながら理想を実現する相補的な概念として浮かび上がってきた。
これについてもう少し思考を深めてみたい。
プロジェクトの定義「独自のプロダクト、サービス、所産を創造するために実施される有期的な業務」から分かるプロジェクトのもう一つの特徴は「有期性」、つまり「終わりがある」ことだ。
どんなにつらいプロジェクトでもいつか終わると思えば耐えられる…というのも確かに否定できない良さの一つなのだが、長年プロジェクトに携わってきてそれ以上に気付いたのは、「終わり」が持つ前向きなエネルギーだ。
ドストエフスキーの『死の家の記録』によると、最も恐ろしい罰は「一つの桶から別の桶に水を移し、その桶からまたもとの桶に移す」「一つの場所から別の場所に土の山を移して、また元に戻す」などの不毛な反復作業だという。
この作業が有意義なものであればまだ救いになるだろうが、それでも終わりの見えない繰り返しの作業はそれだけで忍耐が求められるものであり、モメンタム(勢い、推進力)が削られてしまうことは想像に難くない。
しかし「終わり」があれば、そこまでの道のりを見通して、今が何合目あたりなのか、どのあたりが険所なのかの見当も付くし、ゴールが見えてくればラストスパートの力も湧く。
つまり、一見途方もない果てのない道に見えたとしても、ゴールを描き「終わり」を設定することで、歩を前に進める力を生み出すことができるのだ。
プロジェクトをドライブさせる具体イメージだけでなく、その理想のゴール像の仮説をドラフトとして提示する(ゴールや理想像を仮構する)ことまでを「ドラフトデザイン」と定義してみると、「プロジェクトデザイン」は、ドラフトとして描いた理想のゴール像から、現在に向かって実現の具体的な道筋をプロジェクトとして組み立てることだと言えるだろう。
そしてプロジェクトの中で、理想を中間成果物やプロトタイプなどの形で精緻化・具体化し、それをもとにまた議論を積み重ねてプロジェクトに反映していくことを繰り返して、徐々に理想を今に引き寄せていく。

考えてみると、「終わり」があるのはプロジェクトだけでなく人生だって同じだ。でもその割には僕らは「終わり」に対して無頓着ではないだろうか。終わりという言葉は寂しさや死も想起させるので、つい考えるのに後ろ向きになったり忌避したりしてしまいがちだが、プロジェクトに限らず、人生のゴールや終わり方にも向き合ってその理想像を描くことで、前向きな力を生み出し、人生をよりよく生きることもできるかもしれない。
まだ仮説の域を出ないが、これから様々な角度からこの「ドラフトデザイン」と「プロジェクトデザイン」という概念を実践する手法やその価値について考えていきたいと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
