
昨日は台風で出かけられなかったこともあり、メルヴィルの『白鯨』を読みはじめた。

その前に、チャールズ・オールソンの『わが名はイシュメイル』を読み、続けて高山宏さんの『アレハンドリア』の中の『白鯨』論を読むうちに、まだ読んだことがなかった、この古典を読みたくなり、amazonで注文したのを金曜日に受けとっていたというタイミングでもあったからだ。
上中下巻と3冊あるうちの、まだ上巻の3分の2ほどを読み終わったくらい。『白鯨』といえば、エイハブ船長が自分のこと片足を奪ったモビー・ディックへの復讐の旅を描いた物語と知られるが、すくなくとも、いまのところ、そのエイハブは登場してこない(名前やうわさだけは聞こえてくるが)。目次をみるとエイハブがようやく登場してくるのは、物語もだいぶ進んだ28章においてのようだ。
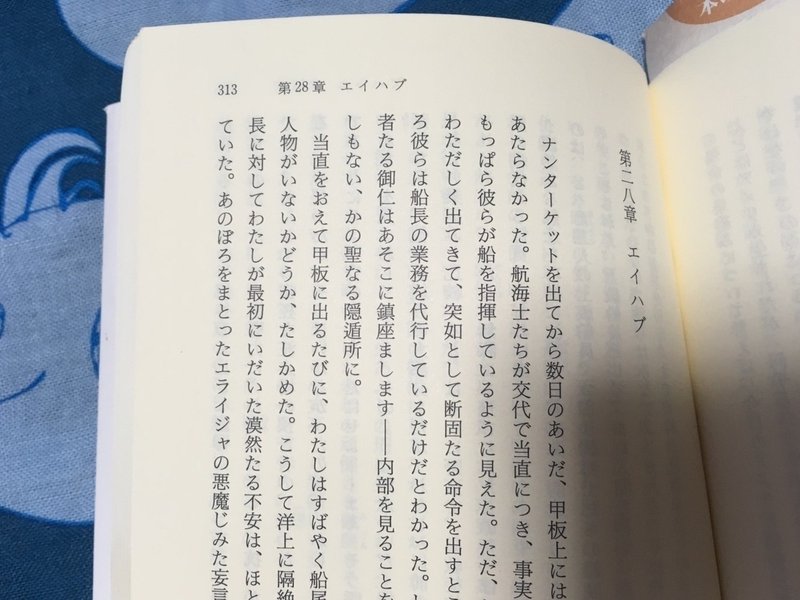
そういう思ってた展開とは異なることも含め、この作品、思ってた以上に面白い。物語が面白いというよりも、メルヴィルの作品づくりにいろんな仕掛けが感じられるから面白く感じるのだ。

Call me Ishmael.わたしを「イシュメール」と読んでもらおう。
『白鯨』の物語は、そうはじまる。
オールソンの本は、だから『白鯨』に関するものだとわかる。
その出だしに近い箇所で、オールソンはこう書いている。
メルヴィルの想像力が正常に鼓動するときには、歴史は祭祀となり、くりかえすものとなった。それは西欧人の感覚よりももっと古い感覚であり、文化よりもむしろ魔術と深い関係にあるものだった。魔術とはすべての神の信仰とは正反対のまがまがしいものである。というのも、魔術の目的はただ一つ、人間なり非人間的な力を、おのれの意志のままに動かすということだからである。エイハブどうようアメリカ的なもの、ただ一つの目的、つまり自然を支配すること。
オールソンはこう書いているが、メルヴィルのこの魔術的な力というものを、いわゆるいかがわしい魔術と思ったら大間違いだ。
その魔術は、ルルスの術やライプニッツも大いに研究したアルス・コンビナトリア(組み合わせ術)に通じるものであり、その先にはライプニッツによるいまのコンピュータ言語につながる普遍言語の試みや、百科全書派や驚異の部屋を経ての、ミュージアムやリンネを祖とする近代分類学にまで通じる、たくさんの情報、記号を用いてどう自然を制御下におくか?という大きな試みであるのだから。
先に「『白鯨』の物語は、"Call me Ishmael."からはじまる」と書いた。けれど、それは『白鯨』という本のはじまりではない。

僕の手元の本ではイシュメールの登場する物語の第1章は、本のp55からはじまっていて、物語のはじまり以前に本ははじまっているのだ。
目次を見てのとおりである。
第1章の前には「語源」と「抜粋」があるのだ。

高山宏さんは『アレハンドリア』所収の「パラドクシア・アメリカーナ」で、こう書いている。
「語源(Etymology)」で始まる小説はそう多いと思えないが、ともかく"Whale"の語源は北欧語系の'hval"にたどれるが、これは"roundness or rolling"の意味と、二種類の大辞典にある、と作者は述べる。鯨とは即ち丸ないし円、円運動そのものなのだ。
そう。メルヴィルは、物語のはじまる前の「語源」で、鯨という語の語源を提示しているのだ。
高山さんは、こう続ける。
「白」と「鯨」とはお互いに相関し合う。パラドックスそのものなのだと理解すると同時に、こうして開巻1ページを"roll"で初め、本体掉尾を"...the great shroud of the sea rolled on as it rolled five thousand years ago."で締めるこの巨大作自体が、丸く、そして循環する、早く来た『フィネガンズ・ウェイク』なのだ。
後にジョイスが書くことになる『フィネガンズ・ウェイク』に比肩されていることからもわかるように、『白鯨』はシンプルな構造、物語からなる小説ではない。鯨の物語であると同時に、鯨のような丸い形をした大きな作品である。さらに、それは鯨や捕鯨というものを通じて、当時の社会を紐解く辞書や百科事典のようなものでもある。その意味で「魔術的」なのだ。
高山さんが「二種類の大辞典」と書いたうちの1つとして、メルヴィルが『ウェブスター辞典』から引いたのが次の文章だ。
WHALE……スウェーデン語、デンマーク語ではhval。この動物の体躯がまるまるしていること、あるいはそれを輾転とさせることに由来する。デンマーク語ではhvaltは『アーチ状の』または(丸天井のような』の意

さらに、このあとの「抜粋」では、旧約聖書からはじまり、モンテーニュ、ラブレー、ベーコン、シェイクスピア、ホッブズ、ミルトンから、クック船長やジェームズ・バンクスなどの大航海をした人たちの鯨に関する記述が次々に引用される。

この引用が後の物語のなかでも、様々な形で関係するから、ここだけが独立しているわけではない。「ヨナ書」の話はイシュメールが心を動かされることになる牧師の説教で詳しく展開される、など。その構造がとにかく魔術的で面白い。
さらに物語がはじまったあとでも、鯨に関する様々な情報は物語の筋を断ち切る形で紹介される。
例えば、この古典は1851年に発表されたものだが、24章の弁護士では捕鯨業が歴史的、社会的にどのように価値があるものかが訴えられる。その文中に「もしあの二重にかんぬきをかけた国、日本が外国に門戸を開くことがあるとすれば、その功績は捕鯨船にのみ帰せられるべきだろう。事実、日本の開国は目前にせまっている」とある。ペリーの浦賀来航が1853年だから日本でいえば江戸末期に書かれたもので、まさに「日本の開国は目前にせまって」いた。世界的な歴史の中での捕鯨の位置が示される。
その意味で、この情報が発表された1851年は、ロンドンで世界最初の万国博覧会であるロンドン万博が開催され、ニューヨーク・タイムズが創刊された年でもある。万国博覧会がかつての驚異の部屋が産業と手を組んでの発展形であることが思い出されるし、小説をあらわすnovelとニューヨーク・タイムズが扱うnewsが同じく新しさを自らの特徴にしているということもここでイメージできる。その点でも紛れもなく、この『白鯨』という作品は、単なる物語というよりも、博物誌的な作品だといえる。
そもそも、この「抜粋 Extracts」というもの自体、なぜメルヴィルがここに置いたのか?ということだ。
高山さんはこう書いている。
大体が"Extracts"とは18世紀初めの第1次辞典編纂ブームの中では一般的な百科のあり方だった。ある項を既に出た説の引用の連続で構成する。ぼくなど『白鯨』の祖型に、エフレイム・チェンバーズの"Cyclopedia"(1728)といったその時代の草分け的百科の編集法を想定している。故種村季弘氏が西周に淵源する百学連環という見事な訳語で普及させたそのencyclopediasにしても、文字通り円環になる陶冶の意味で、そのことを「エンキュクリオス・パイディア」なる一文に宣することをもって、ぼくは『白鯨』プロパーから離れた。
エンサイクロペディアを百学連環と訳した西周(にしあまね)さんの凄さも感じるが、つまり、これ、鯨にも『白鯨』という作品とも重なるわけだ。百科全書としての『白鯨』、それは世界を円環でつなげる書であり、ある種の魔術書なのかもしれない。
だが、いまのいままで『白鯨』という作品がこんな作品だとは誰も紹介してくれなかったし(高山宏さんを除いて)、そういう評価になっていないのは、こうやって読み始めてみて、あらためてびっくり。解読されてない暗号みたいなものか。
そんなことを思いながら、楽しく読み進めている。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
