
新しいメディアがもたらす感覚と、古い思考のギャップの間で
「第一次世界大戦が起きた原因のひとつに外交の失敗があり、その失敗の原因のひとつが、外交官たちが電信の量と速度についていけなかったことである」とスティーブン・カーンは『空間の文化史』のなかで書いている。
マクルーハン的メディア論がベースになった僕のモノの見方的には、こういう話は大好物だ。新たなメディアが更新する拡張された人間の感覚が、その感覚を用いる人々の古い思考をあっさりと超えていく。そして、その感覚と思考のギャップが、時として悲劇的な勘違いを生じさせてしまう。
冒頭に言及された第一次世界大戦の要因をつくった1914年の状況もまさにそうしたギャップが生み出したものだ。
1914年に外交官であった貴族やその侍従たちはいろいろな意味で頭が古く、新しい技術に対して及び腰であった。一部の将軍が最新の武器や戦略に消極的な態度をとったのと同じだった。将軍たちが長距離砲弾や機銃の威力を理解できず、騎兵隊の雄々しい突撃とか「銃剣のこわさ」というレベルでものを考えていたように、外交官たちは、瞬時の伝達、つまり、遅れてもいいではないかという呑気な思いと無縁になった伝達がもつ大きな意味が理解できなかった。彼らはいまだ、じかに会って「品位のある言葉」で話すのが有効であると信じきっていたけれど、やはり、さまざま重大な懸案を導線を通じて交渉せざるをえなかった。
といった具合に。
そして、この頭で考えて志向する古いアプローチと、感覚が導く現実の新たな行動の間で悲劇的な事態が起こることもある。
無駄になった電報の山は(そののち見ることになる兵士の死体の山のように)外交の失敗の実態そのものであった。
電報の速さに見合ったコミュニケーションができなかった結果、起こった悲劇がそれだ。
情報自体は即座に伝わるのに、それを生かした判断は相変わらず、面と向かって顔を合わせる、上品すぎる遅さに終始した結果、どの国の外交官も事態を見誤り、戦争に突入していった。それが第一次世界大戦を引き起こす要因となった1914年の7月危機で起きたことだとカーンは教えてくれる。
古い思考が感覚を惑わす
これは他人事ではないはずだ。僕らも古いメディアが作った思考に縛られて、新しいメディアがもたらす感覚に忠実に動けずにいる。個人もそうだが、古い組織にいたら、さらにその古いsystem=組織にがんじがらめになり、感覚が導くのとはまるで正反対の行動に縛られたままになったりする。そのギャップが正しい感覚を惑わし、まったく無意味な不安感を生んだりもする。

1914年の危機に際して、ドイツという国が感じていたのも、そんな間違った感覚から生じた不安感ではなかっただろうか。間違った不安は間違ったアナロジーに根拠を求める。
拡大するのでなければドイツは死滅すると考える彼は、その根拠を示す自然現象をカタログのように列挙する。種子の発芽、栄養の浸透、枝を伸ばしていく過程、器官の膨張、種の生殖。生あるものすべてが、アリストテレスの言うエンテレキのあらがうことのできない際限なきプロセスにおいて自分の限界を越えてゆくことを示すべく、リーツラーは200頁にわたってアナロジーを使って議論を展開する。生命エネルギーが有機体を常により複雑な形質を獲得するように駆りたてるというベルグソンの考えが、リーツラーの「国家の生理学」に取り入れられる。これは、不可能にたち向かうひとつの共通の努力によって結び合わされた個々人の精神が有機的にまとまったひとつの統一体がドイツ国家だとみる考えだった。
拡大し続けなければ、死につながる。
先の通信技術や鉄道などがもたらした、新しい距離感、空間、時間の感覚がそうした不安をもたらした。
そして、それは国家が行う行為を生物学的なところに根拠を求めて正当化するような間違った考えを生みだす。このひとつあとの戦争で、ドイツが再び優生学を根拠にするのと同様に。
そして、誤解から生みだされた国家という偽生物は、拡大化の過程で衝突する外部に対して牙をむく。
空間としての統一が発展してゆくと必然的に外部との摩擦が生じる。「有機体とは、行動するなかで、敵意をみせる外部世界に対して対抗措置を取りつつ展開してゆかなければならないひとつのプロセスである」。リーツラーはドイツの「孤立化」の生体形而上学を用意したのであった。
けれど、現代に生きる僕らもこの時代のドイツの思考を笑えない。
押し寄せる移民、押し寄せる外国の生産物や資本に対して自国の文化や利益を守ろうとして、外に対して「閉じる」姿勢や民族的独立を目指そうとする姿勢は、1914年のヨーロッパの人々の思考や姿勢と変わらない。
それをもたらしたものが電報や電話、鉄道ではなく、インターネットやモバイルであるという違いがあるだけだ。
均質の時間
いまのインターネットやモバイルによるデジタル・ディスラプションの破壊的改革の進行同様、電報や電話、電車といった新しい技術がもたらした距離の短縮は古い世界の常識をどんどん壊していった。
それは戦争の只中においても同様だったようだ。「あの戦争は均質の時間を押しつけた」とカーンは書く。
1890年、モルトケは世界標準時の設置を働きかけ、1914年に、精確な時間にそれぞれの場所に兵力のすべてを配置させるという戦争計画を実施するのに標準時を用いた。
『鉄道旅行の歴史』という本で、ヴォルフガング・シヴェルブシュが教えてくれているのだけど、標準時という概念自体、鉄道の発展とともに生まれたものだ。「時間の統一は、英国では1840年頃個々の鉄道会社が独自に企てる。各会社が自分の路線にそれぞれ標準時間を導入する」とシヴェルブシュはいう。鉄道以前には「地方が個々に孤立しているかぎり、地方にはそれ固有の時間があった」のだというのだから、最初に知ったときはびっくりした。
その後、各鉄道会社がバラバラに設定した標準時が鉄道会社の統合とともに、標準時自体も統一される方向に進む。そして、「1880年には、鉄道の時間が英国では一般の人標準時となる」。先の引用中にあった1890年の世界標準時の設定は、その10年後のことだ。
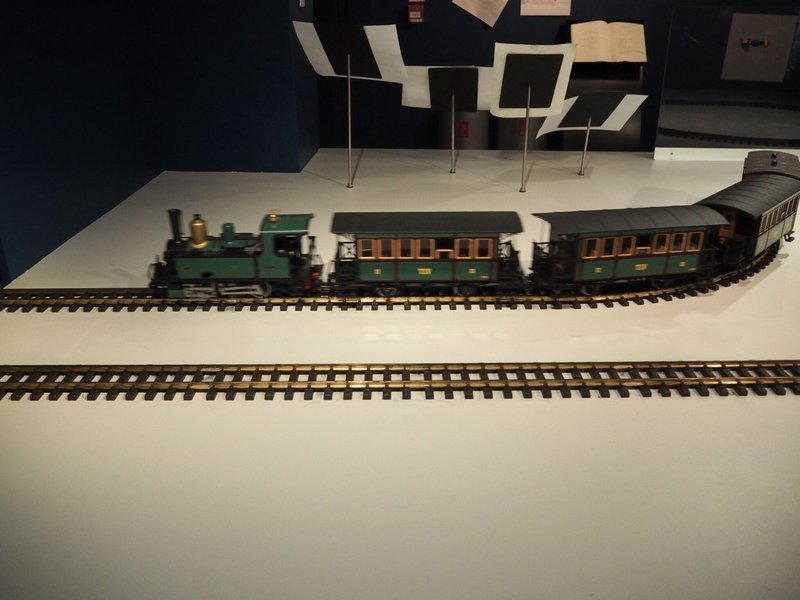
だから、1914年にはじまる「戦争前には腕時計など男のつけるものではないという雰囲気があった」というのも、そんなに不思議なことではない。標準時の設定から24年は経っているとはいえ、標準時の設定以前は時計を携行することに意味がなかったはずだから。電車で移動してしまえば、時間の根拠が変わってしまう状態がイギリス以外では続いていたのだから。
それが、戦争になると兵士が常時携行するものになった。全員がいっせいに塹壕を飛び出せるように、戦闘前に腕時計の時間を合わせた。エドマンド・ブランデンの回想によれば、突撃の前に本部で時間合わせをした時計を1兵士が配ってまわったという。1916年7月1日朝、ソンヌの戦いが始まったが、このとき何百人もの小隊長が、時間合わせしてある時計が7時半を示すといっせいに笛を吹いて、第3、第4英軍の兵士に長ばしごを登らせ、胸壁を超えて敵と味方との中間地帯に突入させた。
電報や鉄道によって時間や空間の感覚が大きく変わった新しい時代の戦争が、一気に「均一な時間」を要請した。それは戦争そのものがヨーロッパの街を破壊したのと同じくらい、それまで地域や個々人が個別に有していた時間が織り成していた文化を無残なくらいに破壊した。
ベルグソンやプルーストの、私的時間に対する繊細な感性はこの戦争には無縁であった。そんな感性は存在できるはずもなかった。砲撃や突撃を最大限に効果あらしめるべく時間合わせをした懐中時計、腕時計の普遍的時間によって、何百万人もの人員の生命を組織化した大量動員の怒涛の力の前に、そうした感性は抹消されたのである。こうして、1つの普遍的時間に合わせて動静の全体が強制的に調整されたのだが、これによって、私的時間が多数あることを作ってきた戦前の主要な文化的傾向がひっくり返ってしまった。
同じような変化の只中に僕らもいま立たされている。
そして新しいテクノロジーがもたらす変化は不可避なのだから、それに対して無意味な抵抗をするより、新しいテクノロジーがもたらす変化の意味をしっかり理解し、自ら、それがもたらす変化の良い面をより生かし、変化の悪い面の影響を極力すくなくするにはどうしたらいいかを考えていたい。
それには古い思考に囚われることなく、新しいメディアのもたらす新たな身体拡張による感覚を素直に受け止め、その変化の意味を理解できるスタンスでありたい。間違って不幸な選択をしてしまわないためにも。
#エッセイ #コラム #メディア論 #歴史 #デザイン #変化
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
