
アンドレイ・タルコフスキー『ノスタルジア』を”読む”
映画で何が成せるのか。どんな世界を、どのような手段で表現できるのか。映画の秘める可能性を強く感じた作品であった。
知覚しうる限りの全てに感服する。
純粋にそれだけの技術と完成度があるが、何より空気、気配が素晴らしい。
観るものを魅惑し陶酔させ、感覚に浸透してゆく。
タイトルを「『ノスタルジア』を”読む”」としたが、実際のところ、芸術の真の価値は読解不可能な”イメージ”にあると考えている。しかし、読解可能な意匠についてはできうる限り読解し、感覚のみが浸透可能なイメージの領域を清澄《せいちょう》させることも、芸術を堪能する上で重要な役割を担っている、とも考えている。
今回は、走り書きの稚拙な文章にはなるが、読解可能な彼の意匠を少しでも明らかにできれば嬉しい。
本作を視聴済みの読者は僕のシーン説明によって映像を思い出してほしいのだが、試聴していない読者は僕の説明が拙いが故に、映像をイメージし難いと思う。そういう方は、各セクションの後半部分を適当に流し読みするだけで構わない。そこでは僕が感じたことであったり、簡単なまとめが記載されている。
また、『ノスタルジア』においては、物語の展開をあらかじめ知ることが、映画の鑑賞体験を損なうことにはならないと感じるので、それなら読んでもいいという方がいれば是非目を通していただきたい。
なお、数日前に発刊された忍澤勉 著『終わりなきタルコフスキー』は、『ノスタルジア』の読解において非常に役立つ分析に満ちた素晴らしい著作でしたので、タルコフスキーに関心のある方は是非手に取っていただきたい。勿論、彼の作品全8作全てが網羅されている。
気がつくと
人間は自然の一部であった
というような浸水感のある作品はいい
人間のそういった
詩に満ちた佇まいに触れていると
懐かしさを覚え 憧れを抱く 郷愁に酔う
計算されたロングショット−−−−
本作は冒頭から最後のサン・ガルガノ大聖堂でのシーンまで、終始ゆったりとしたロングショットで構成されている。彼のショットにおいては、パンの速度や対象のムーブ、間《ま》、構図、視座などなど、知覚できる全てが美しい。

冒頭のシーンを例に挙げると、構図は中心に一本の木と広大な草原、そして画面全体に広がる霧のショットの右から一台の車がフレームイン、車のムーブに合わせて画面がスライドし、左奥にフレームアウトした車がしばらくして左手前からフレームインしてくる。
まず、一本の木が写されているショット、カメラは遠方高めの位置から、斜めに見下ろす形で定点している。左から右に流れる霧はなめらかで、早朝の澄んだ空気を感じさせる。その流れに逆らう向きでフレームインしてくる車も、ゆっくりと、少々燃費の悪そうな愛らしい音で唸りながら走り去る。カメラがある地点でスライドを止める。数秒間の静寂。そこには草むらと岩以外何もない。しばらくして我々は、手前に僅かながらも車の走行跡があることに気づく。そしてその頃には、左手から先ほどの車の走行音が聞こえてくる。気配の通り、車は左手前からフレームインし、正面で止まる。左手の画面外で大きく手前に弧を描き、Uターンしてきたのだろう。そこでようやくショットが完成される。その流れ,構図は想像していたよりもずっと美しい。立体的で美しいこのショットに緻密な計算がなされていることがわかる。下の画像の通りだ。

画面に空白の時が流れる10数秒の間によってか、車の走行音が聞こえた瞬間には気持ちが昂っていることが感じられる。こい、こい、来る。と思う。自然と、期待を抱いてしまうような絶妙な間《ま》なのだ。このあと、車から出たエウジェニアが画面奥に歩くのに合わせほんの少しずつズームしてゆくその速度も気持ちがいい。
草むらと車の配置、風が吹いたように再び流れてくる霧、画面奥に伸びる細い小径の奥行き、これらもまた、このショットの魅力として十分な働きをしている。ここまでで約3分半、このようなロングショットによって我々観客は、喜ばしいことに、映画の観客としてではなく、風景の傍観者として彼らを眺めているかのような没入感に支配され続けるのである。

ロングショットのあいだに人物がすれ違うという構図も、タルコフスキーは多用する。僕はこれが特に好きなのだが、特筆すると、バーニョ・ヴィニョーニでゴルチャコフとエウジェニアがドメニコについて話すシーン、彼らの向こうでは温泉の煙が白く漂う。温泉の端から端までを彼らは話しながら帰路に向かうのだが、ここで三度もすれ違いが起こる。物理的なすれ違いだ。その際の、視線の交差やカメラのパン、瞬間的に生じる奥行きなどが非常に美しい。交差する対象が、画面にゆらめきを生じさせるのである。
サン・ピエトロ教会でエウジェニアと神父がすれ違うシーンでもやはり視線の交差が独特で、カメラのフォーカス送りが気持ちよく、奥行きのあるショットが印象強い。
また、タルコフスキーは、ひとつのショットで一人の人物を複数回写す技術を使い、時間の経過を巧みに表現する。その幻想的なショットはもはやそれだけで美しく、ただ魅入ってしまうばかりである。
ワンショットの妙は他にもある。例えばゴルチャコフが幻想の中で自身の中にドメニコを発見してしまうシーンでは、鏡扉に手をかけたゴルチャコフが鏡を覗くと、そこにはドメニコが写っており、驚き、そのことが受け入れ難いというように勢いよく鏡扉を閉め、画面には再びゴルチャコフが現れる、という表現がされる。
初めて鑑賞した際には、ワンショットでなぜこのような人物のスイッチが撮れるのかと驚かされた。しかし、再見するとトリックはシンプルで、ゴルチャコフが鏡扉に触れる前、一度フレームアウトしていたのだ。そんなことにも気づかないのかと思うであろうが、これが意外と気付けない。
ワンショットで撮られているが故に、人物のスイッチを疑うことができなかった。映画においてカットとは、物語を編集する行為であるから、我々はショットとショットの行間を想定する。ここではあらゆる施しが可能であり、我々もそれを理解している。しかし、カットしない場合はそうではない。タルコフスキーは、当然ながら、ワンショットのこの特性を巧みに操り、その柔軟な表現力によって我々を魅入らせるのだ。
モチーフの選択−−−−
タルコフスキーは公言しているように、火、水、風の自然現象をモチーフとして多用する。流体としての自然現象を彼は巧みに操り、あらゆる事象を抽象的に、芸術的に、美しく表現してしまう。
「私の望むように観客に映像を見てもらうために、写っている対象のまわりには、情緒的なアウラのようなものが感じられればいい。」という言葉の通り『ノスタルジア』においても、それらモチーフとしての自然現象は、情緒的なアウラを纏っていた。
しかし、やはりそこには、単なる情緒的表現に終結しない、何か別の、理性の外側にのみ漂う”大きな存在(五感では知覚不可能な存在)”を感じさせる気配がある。彼の選びとるモチーフには、情緒的なアウラ以上に、換言不可能な、完全に感覚的な何かが胎動する余地が大いにある。
この世界の四大元素である流体としての自然現象(火、水、風)は、おそらく人間の理性には到達できない深淵なアウラを内に秘めているだろう。その深淵なアウラを纏うモチーフを使いこなすということは、”大きな存在”の気配をフィルムの中で魔術的に胎動させることを意味するのかもしれない。
何をも断定しない表現、流動的ゆえに多義的な解釈が可能な表現、深淵で情緒に満ちたこれらの表現によって、ひとつひとつのショットに思考の幅と感覚の深度が与えられているのだろう。
幻想と現実−−−−
幻想と現実という視点は、『ノスタルジア』の鑑賞においてもっとも重要であるかもしれない。本作では、終始寡黙な主人公ゴルチャコフの抱く感情が、雄弁で抽象的なイメージによって我々にも共有される。
その二つの映像が如何にして連関しているのかということは、物語を読み解く上で大きな手助けとなるだろう。しかし、この表現のもっとも重要なのはそこではなく、卓越した技術とセンスによる描き分け、そして何より幻想と現実の狭間の表現にある。
幻影として描かれるのはモノクロのシーン。通常のカラー映像の間に時折差し込まれるのだが、これは映像の抽象性が高く、イタリアに滞在している現実の展開と逸脱した映像であることから、幻影であることがわかる。
この幻影は一見不可解な瞬間に現出するため、内容を混乱しかねないのだが、基本的にはゴルチャコフの夢として再生される場合と、故郷の妻マリヤを想起する瞬間のふたつで再生されている。
前者の場合においては、イタリアの風景、出来事に対して、ゴルチャコフが”死に至る病”としてのノスタルジアを感じていることを示唆していると思われる。現実での、理性の内のゴルチャコフは感情を表にあらわすことが少なく、そのうえ自身に言い聞かせるかのような願望や思惑の混同した台詞を多く持つので、彼の真意を悟ることは非常に難しい。しかし、夢としての幻想は雄弁である。誰の言った言葉だったかは忘れてしまったが、「夢はいい。夢では、己に対する欺瞞や慢心が取り払われる。」ということは感覚的に真実だろう。

故郷の妻マリヤを想起してしまう瞬間においては、恋をしてしまっているエウジェニアに対して妻の面影を重ねてしまう、その葛藤が表現されていると考えられる。
エウジェニアがゴルチャコフを愛しているのは自明だが、その逆がなぜ成り立つのかと言えば、物語後半の廃墟と化した水の教会にて、謎の少女アンジェラに対してゴルチャコフが「大恋愛の物語を知ってるかい」と独白するシーンでわかる。彼の言う「昔風でキスは無し、何もないんだ。偉大だろ。清潔そのもの。感情も表にあらわさない。」という台詞は、エウジェニアのことを指していると考えるのが最も自然である。
ゴルチャコフはあまりにも感情を表に出さないので、何を感じ、何を考えているのか非常に解りづらい。エウジェニアがヒステリックになってしまうのも少し理解できる気はする。ただ、彼はあくまでも詩人なのだ。
現実と幻想の表現として特に秀逸だと感じた”狭間”については、”死に至る病”としてのノスタルジアと、ゴルチャコフの患っている心臓病が深く関わってくる。
常に死と隣り合わせにあり、詩人として幻想的な回路を持つゴルチャコフは、モノクロに近い色彩で世界を眺めている。モノクロで表現される幻想世界と、現実ながらも淡い世界を漂う彼は、あまりのノスタルジアに故郷の犬を幻想としてホテルに呼び込み、背を撫でる。犬が現れる瞬間に、画面の彩度が僅かに落ち、しばらくすると雨が止み始め、光線が部屋に差し込むと同時にゴルチャコフに色彩が戻る。
夢と現実の狭間にいる幻想的な状態を、偉大な小説家のプルーストは「長いことわたしは早めに休むことにした」という書き出しに始まる理性の曖昧な文体で表現したが、タルコフスキーは彩度でそれを表現した。
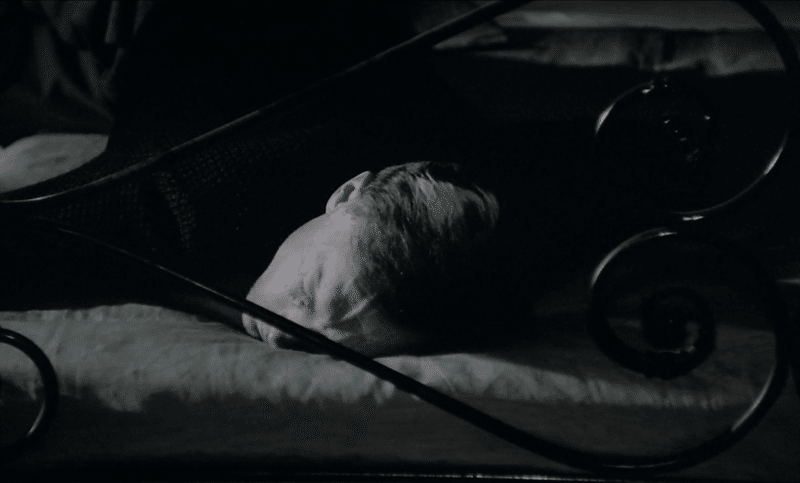
ゴルチャコフが眠りに落ちるまでの数秒では、徐々に彩度が落ちてゆく。気がつかないほど滑らかにモノクロに近づいていた映像は、突然に色彩を取り戻す。ゴルチャコフは眠りに落ち、そこにあった彼の意識、曖昧な理性が閉じたのだろう。
我々が映像として眺めているのは現実の、眠っている彼の骸である。雨水に反射したような光線が顔にゆらめき、水の滴る美しい音と共にゴルチャコフの幻想がモノクロで映し出される。
このような秀逸な表現によって、ゴルチャコフの状態を説明なく理解、直感することが可能なのである。
また、別のシーンでは、バーニョ・ヴィニョーニ(温泉)の対岸に蝋燭を立てた瞬間、持病である心臓病が悪化してしまう。その場で死に至ったゴルチャコフは、モノクロの映像の中で、幻想として故郷に帰ることができる。
彼の患っていた心臓病は、”死に至る病”としてのノスタルジアと比例し、共鳴していたように思う。
彼にとって故郷モスクワとは、死に至らなければ帰ることのできない存在だったのではないだろうか。彼の患っていた心臓病は、死への手綱、故郷への手綱だったのかもしれない。
全体として淡い色彩で映される景色は、いわばゴルチャコフの眺めている世界であり、その視界の反映が本作のノスタルジックな色彩であると取ることもできる。これは我々観客に対し、現実と幻想を浮遊する視座を与える巧みな表現である。
真に音楽的な音響−−−−
「映画的映像を真に音楽的なものにするために、音楽は捨てなければならないのかもしれない。−−−よく響く世界(映画の中の環境音等)は、映画の中に適切に組織された時、本質的に音楽的である。」
タルコフスキーは映画における音楽についてこのように考えており、本作においては然るべきシーンでのみ、強烈な音楽が使われている。MUSICとしての音楽はほとんどないが、音楽的な美しい音は常に聞こえてくる。彼の言う真に音楽的なものとは、自然の環境がつくりだす音と、その環境音を幻想的に聞こえさせる、間《ま》が生み出す響きなのではないだろうか。
ゴルチャコフが幻想に向かう際には、水の滴る音や息の漏れる音が徐々に、ゆっくりと誇張されていくことに気が付く。まるで、ぼうっとしているときの耳が覆われるような、水中に潜っている時のような、身体の中で反響する音が聞こえてくる感覚になる。
それは実に幻想的で、何故か音楽的。自然現象が稀に、人類の編み出した文法をなぞることがあるが、あの時の感覚に近い。水の滴る音などが、グルーヴに満ちているのだ。
幻想として現れる飼い犬がゴルチャコフの元に座り込むとき、空き瓶を背中で倒し転がるような哀愁漂う音が鳴ったり、電気ノコギリの音のするシーン等は何かを暗示しているのだろうが、それがなんなのかはわからない。しかし、その全てが美しい音を奏でていることは事実であり、全体としての調和もとれている。ゆえに我々は、不可解なはずなのに気にも留めない。
解らなくとも、面白い。

これもタルコフスキーの言う音楽的な音響に分類できると思うのだが、ゴルチャコフは何度かポケットに手を入れる。その時、聞こえるか聞こえないかのギリギリで僅かに鍵の音が鳴っているのだ。鍵は彼の自宅のものであるから、無自覚のうちに、ノスタルジアに襲われているのであろうことがわかるのである。ただでさえ美しいそのショットに、この繊細な音によって命が吹き込まれていることを考えると、この作品の深みの所以は細部にあると感じざるを得ない。全くもって素晴らしい表現である。
普通、手をポケットに入れているかどうかなど気づくことはないであろうし、そこに意味があるとは到底考えない。これほどまでに緻密な細部設計を前にしては、神も宿って当然だと感じてしまう。
エントランスでの会話で、持っている鍵が自宅の鍵であることがわざわざ明かされているのは、この演出のためなのだろうと振り返る。他愛もない会話だと思っていたこの台詞にも必然性が与えられていたとは、驚きである。
そう考えると、さして意識もしていなかった台詞の数々が、沸騰するように息を吹き返してくる。簡単に手のつけられるものではない。全くもって深淵なる作品である。喜ばしいことに、彼の意匠を、またその重力によって獲得された偶然の全てを紐解くことはできないだろう。
音楽は人物の心情を表現するうえで有効的に活用されるのが一般的であるが、タルコフスキーは映画における真の音楽としてそれを否定した。「私は音楽がスクリーンでの出来事の平板な図解であってはならないと願っている」という言葉がこのことを裏付ける。
自然の環境音と自然の間《ま》を音楽として美しく響かせた上で、人物の心情については別の手法を駆使し、表現する。タルコフスキーの思想と、それを叶えるための意匠、拘りに脱帽せざるを得ない。
真の象徴−−−−
20世紀初頭のロシア象徴派の代表的詩人、ヴャチェスラフ・イワーノフは「象徴はその意味が無尽蔵で限りのないとき、真の象徴といえる」と述べているが、本作を見ればこれがタルコフスキーの作品にも通ずる思想であることがわかる。また、イワーノフは「象徴は、明言されることも説明されることもあり得ない」とも述べている。
本作を一度でも鑑賞したことのある者ならきっとその存在に気がついたと思うが、ドメニコの自宅の壁に描かれている「1+1=1」という数式。これは、彼の「一滴に一滴を加えても一滴」という台詞を表していると考えられる。タルコフスキー自身、物として水が好きだと語っていることから、水には何か強い意味が与えられていることは確実だろうが、僕には何を象徴しているのかわからない。背後で唸っている電気ノコギリの音、あの音もなんなのだろうか。二人が、死への過程を歩んでいることを示唆しているのだろうか。
象徴として僕が唯一読み取れたのは電話のベルである。これはゴルチャコフの部屋で鳴っているものと思われるが、このベルは毎度エウジェニアの想いが実らないシーンに鳴っているように思う。エウジェニアのもどかしい胸懐が聞こえそうであるが、必ずしも彼女の胸懐を示しているわけではないだろう。もっと大きな意味を担っているのかも知れない。解釈は無尽蔵で、限りのない抽象だった。つまり、結局わかることはない。
他にも、ゴルチャコフの白髪や子供の口元の傷、櫛に絡まった髪の毛、ドメニコ宅の不気味な人形写真、天使の羽や捥げるタバコ等、何かを象徴するのであろう事物や現象、暗喩するイメージは作品全体に、無数に散りばめられている。「作者の意図が隠れていればいるほど、芸術作品の創造にとってよいことになる」と述べるタルコフスキーの意図は、明らかにするには中々難しい。しかし、それら抽象的な象徴によってか、作品に一層の深みが生まれていることは事実であろう。
無言、応答−−−−
タルコフスキーは、芸術において最も正当なものは”詩の論理”であると考えており、映画においても同様に、詩的連関,詩の論理に魅惑されると述べている。
ここで彼の言う詩的連関,詩の論理とは、言葉としての詩そのものではなく、詩を生み出しうる光景であり、イメージのことを指しているのだろう。
映画において、断定的な表現を避けるということは、詩的なショットを撮る上での必須条件であると思われるが、タルコフスキー作品で散見される”無言の応答”は、奥行きのある非断定的で詩的な表現である。
『ノスタルジア』では以下の三つのシーンで無言の応答が目立ったのだが、まずは冒頭でエウジェニアがゴルチャコフに話しかけるシーン。
彼女は、車から降りると、霧の流れる草原を前に、「モスクワを思い出すでしょ、光線がよく似てる」とゴルチャコフに語りかける。しかし、彼は黙すことでそれに答える。
否定はしない、だが同意もしないといったただそれだけの意味に過ぎないだろうが、応答が無言であることによってさまざまな推測が必要となり、彼が何を思い、どんな状態にあるのかを想像することが可能になる。もしこのとき彼が肯定なり否定なりを答えていたら、このシーンから詩的連関は損なわれてしまうだろう。曖昧で濁すような返答をしたとしても、それでも”無言”の詩的イメージには及ばないとも感じるから、やはり無言の応答は詩の論理を構築する上で最も適した表現だったと思う。
ちなみにこの時ゴルチャコフは同意しなかったが、後にエウジェニアに対し、「君は美しい、この光線の中でね」と伝える。物語の中盤でようやくゴルチャコフはイタリアの光線をモスクワのそれと重ね、光線の差し込む水の教会ではついに、天井を見上げ、周囲を見渡し、「ロシアみたいだ、なぜかな」と呟く。冒頭では故郷とイタリアの風景が重なることに戸惑い、動揺していたが、徐々に受け入れ、浸水されてゆく。
『ノスタルジア』は、ゴルチャコフが”死に至る病”としてのノスタルジアに抵抗し、徐々に侵され、堪え兼ね息絶えるまでの物語であると言える。
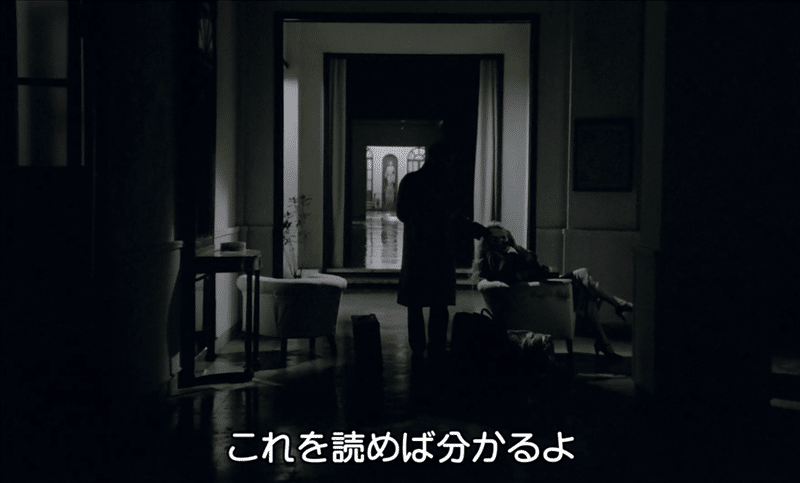
話を戻して、次はエントランスでエウジェニアとゴルチャコフが会話をするシーン。ここでエウジェニアは突然、ミラノの家政婦が郷愁のために主人の家を放火した事件をゴルチャコフに話す。彼女はこれをきっかけにふと思ったのか、音楽家サスノフスキーがなぜ危険なロシアに帰ったのかとゴルチャコフに尋ねる。彼は、この質問に答えない。怪訝《けげん》に思った彼女は、「話すほどには私を信頼していないのね」と不満を漏らす。すると、ゴルチャコフは「これを読めばわかる」と旅の道中で手に入れたサスノフスキーの故郷への手紙を渡す。
エウジェニアがゴルチャコフの無言に堪え兼ねて不満を漏らすまでの数秒、会話の途絶えた空間にはゴルチャコフの足音と、彼に足で押し避けられた荷物の擦れる音が響く。言葉で説明するには難しいが、そのシーンには詩的連関の美しさがある。発声される言葉に向かっていた我々の、客観的で平坦な意識が突然、ゴルチャコフの深淵な主観と接続され、足場を失い浮遊する感覚である。
このシーンでようやくロシアの人間に特有の、”死に至る病”としてのノスタルジアが示唆されるのだが、ゴルチャコフはこの時、”イタリア人であるエウジェニアにこの感覚を理解させるには、あまりにも自分の現状と重なり過ぎている”と感じたのだろう。自らの口で説明することなく、無言で応答し、手紙を手渡すにとどめることで、彼自身との距離を保った。
己を見つめすぎると、ノスタルジアに耐えられないと直感していたのかもしれない。無言によって生じる数秒の間《ま》、そしてゴルチャコフの僅かに揺らぐ仕草によって、我々観客も彼の心情をより深い位置で感じることができる。
最後はドメニコが聖カテリーナの苦行の再現、つまり蝋燭に火を灯したまま温泉を渡り切る儀式をゴルチャコフに託すシーン。
ゴルチャコフは「なぜ私に頼む」とドメニコに聞くが、彼は黙ったまま俯き、しばらくして(無言の間《ま》を置いて)「子供は?」と聞き返す。ゴルチャコフが二人いると答えると、ドメニコは再び若干の間《ま》を置き「ロウソクを頼む」と念を押すのみで理由には触れない。彼は、ゴルチャコフに対して自分と似た何かを感じたのだろうか。ここでゴルチャコフに訳を言わないのは、自らが過去に起こした破滅を恐れさせないためなのではないかと考えられる。ドメニコは少し前のシーンで「大きな心を持つべきだった。エゴイストだった。家族を救おうとした。世界を救うべきなのに。」と嘆いていたことから、ゴルチャコフに大きな心を持たせることはできずとも、世界を救わせようとしたのではないかと推測される。ドメニコの無言の応答によって、何かしらの躊躇いや動揺が生じていたことが感じられるシーンであった。

無言は間《ま》を生み、仕草に僅かな変化を与える。そして周囲の音に対する意識を敏感にさせる。これらがすべて、その瞬間に詩的連関を生じさせる要素であるということは、(詩性に重きを置いた)映画の脚本を考える上で重要となるだろう。それはつまり、詩的イメージの構築において台詞というものは、それほど有効な手段ではないということだからだ。
葛藤−−−−
マリヤという女性を妻に持ちながら、エウジェニアの魅力に惹かれているゴルチャコフ。彼の内心の葛藤をこれほどまでに美しく、幻想的に表現できるのかと感動した。浮気心も美しい芸術に昇華させてしまう表現力が恐ろしい。
ゴルチャコフはイタリアの風景に故郷モスクワを想起し、ノスタルジアに襲われるのだが、異国の人間にその胸懐は理解できない。だがこの状況での葛藤もまた上手く表現されており、彼のノスタルジアを悲劇的に想像することは可能である。
冒頭では、エウジェニアはゴルチャコフに対してイタリアの風景を、「モスクワを思い出すでしょう、光線がよく似てる」と語りかけるも、ゴルチャコフはそれに黙すことで意志を表明する。同意しないということだ。しかしながら、「美しい景色は見飽きている、うんざりだ」と呟いているので、ゴルチャコフの心境としては”我が故郷モスクワの景色には劣るものの、モスクワを想起してしまうことは事実であり、それによって生じるノスタルジアは死に至るほどに耐え難い”という具合に感じているのであろうことがわかる。
サン・ピエトロ協会に向かうエウジェニアに「私は行かないぞ」と言いながらしれっと後についていっていることからも、台詞と行動に必ずしも一貫性があるとは限らず、主人公ゴルチャコフは葛藤の渦中にいることが既に冒頭で示唆されていることとなる。
ホテルにて管理人の女性に「彼は悩んでいるみたいね」と読まれることからも、ゴルチャコフの思考のゆらぎが観賞において重要な位置にあり、その意味で彼の台詞は己に対する言い聞かせとしての”呪文”の役割を担っていることがあると考えられる。冒頭などはまさにそうなのだろう。
詩、重力−−−−
本作は、状況説明が限りなく少ない。彼らがなぜイタリアにおり、どんな目的で、何をしている人物なのかがわかるのは物語の中盤手前あたりである。
それまで我々観客は漠然とした世界に浮遊することになってしまうことが懸念されるが、実はそんなことはほぼあり得ない。なぜならば観客は映画を見る前にあらすじを読むからだ。メディアとしての特性を活かした省略である。この時点でゴルチャコフが詩人であり、エウジェニアは通訳であり、彼らが目的をほぼ達成した旅の後半にいるということはわかるのである。しかし、国境の差だけは埋めることができない。(ロシア、イタリア文化圏で自然と了解される表現は物語の深みに関わるのだろうが、理解できずとも作品を愉しむことはできる。かつての観客、映画が劇場での一回性に前提されていた当時の環境が、”解らなさ”と”不可解な美”を愉しんだように。)
作中のとあるシーン、芸術の翻訳不可能性についてゴルチャコフがエウジェニアに語る場面では、どうすれば理解できる?と尋ねる彼女に対して、「境界をなくすんだ。国境だよ。」とゴルチャコフは語る。

このシーンにもある通り、ロシア人に特有の、”死に至る病”としてのノスタルジアは完全に理解することはできないであろうし、別のシーンでエウジェニアがゴルチャコフに被さるポーズがカラヴァッジオの「ナルキッソス」(上記画像)に酷似しているということも解りかねる。ましてや、ドメニコの狂信している聖カテリーナがどう言った人物で、何を象徴しているのかは、(少なくとも私は)予習なしには理解不能である。この点においては、国境を強く意識させたいタルコフスキー監督の恣意性が感じられる。
国境の差は無くすことができないものなので埋めようと努力する必要がなく、かつあらすじについては鑑賞前に把握するものであるから、いちいち作中で説明じみた表現はしなくて良いのだ。これによって生まれる無駄のない台詞は、そのひとつひとつが重力を帯び、詩的イメージとしての映像を助ける。
タルコフスキーは「詩という表現手段を使わなければ、その真実を伝えることのできないような領域が、人生にはある。」と言ってもいるので、当然ながら台詞にも拘りを持っているのだろう。
本作には、彼の父、アルセニー・タルコフスキーの詩集『雪が降るまえに』に書かれている詩が散見されるが、他に無駄な台詞がない分、詩が我々観客の意識を、姿勢を構築してゆく。
詩の内で思考するという特別な姿勢を我々は、監督,ゴルチャコフらと共に共有することを促されていることとなる。
アンドレイ・タルコフスキーはこうも言っている。「描写された複雑な現象の、より深い意義を見つけ出す助けになるものだけを、彼は手にするのだ。−−対象について語り尽くさないでおけば、観客に考える可能性が残される。−−なんの努力もなく観客に与えられる結論など、不要である。思考が誕生するときの苦しみと喜びを、作家と分かち合うことのできない観客に、作家は何かを語ることができるだろうか。」
光と影
タルコフスキーの作品では、光と、それによって生じる影の演出が表現として秀逸である。彼は火、水、風のモチーフを多用するが、光も同様にモチーフとして使いこなす。
光は火、水、風と違って流体ではない。しかし、そこに写っているものの見え方を変化、ときに流動させ、対象の向こう側に影という現象を生じさせる。

サン・ピエトロ教会にて、エウジェニアが神父に「女だけがこれほど神にすがるのはなぜか」と尋ねるシーンがある。ここで彼女は右目側から光を当てられているのに対し、一つ手前のショットでは、神父がほぼ同じ位置に立っていたにもかかわらず、かれは左目側から照らされていた。両者は光と影で顔が二分されているのだが、照明の位置を変えてまで左右の異なるようなショットにしているのは、そこに意味を与えているからだと考えられる。ここでは、女性と男性のコミュニケーションの不可能性、視野、視座の違いが表現されているのではないだろうか。

もうひとつ挙げるとするならば、ゴルチャコフとエウジェニアが、ロビーで管理人を待ちつつ会話を交わすシーンがある。このシーンは『ノスタルジア』の世界観を特に巧く表現しているように思える。
構図は、ソファに座る二人が非常に長い廊下によって分断されている。この配置は現実的に考えると少々違和感のある配置であるので、タルコフスキー自身が再配置したのではないかと思われるが、この配置によって二人の関係性が感覚としてなんとなく知覚できてしまう。会話の内容も二人の人種的な差異から、「残念ながら理解不能だ」という台詞がうかがえたり、彼らに僅かな逆光を当てることで哀愁漂う静謐なショットにしていたりと、本作がどのような作品であるかが暗喩されているシーンだ。
照らさないということは、それだけで大きな意味を選択していることとなる。
一つのショットに捉えきれないほどの意匠を施していながら、それらがまとまりを持って全体として美しい。絵画のような洗練されたショットに、ただただ感動するばかりである。
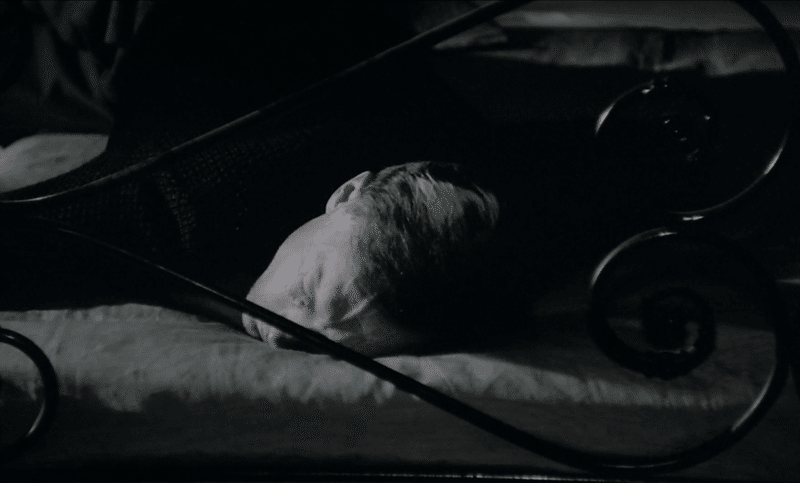
光は、あらゆるモチーフを流動させ、意味に現象を与える。
奥行きのある構図−−−−
僕がタルコフスキー作品で特に美しいと感じる表現のひとつとして、”奥行きのある構図”が挙げられる。
はじめにそれが現れるのは、エウジェニアがサン・ピエトロ教会に訪れるシーン、『妊婦のマリア』の前に立つエウジェニアに、神父は画面の外から「子供が欲しいか」と話かける。彼女からの返答を受け、ようやくカメラは左にパンをして神父を写し、「心を込めて祈りなさい」と諭される。いくつかの会話がなされたのち、神父が歩き始め、カメラはそれについてゆく。エウジェニアの正面にあたる位置でカメラは静止し、焦点は再びエウジェニアに定まる。奥行きを活かしたフォーカス送りが非常に美しいシーンである。
他にも、ホテルのロビーでのショットは一直線に伸びた廊下にかなりの奥行きが感じられ、陰影の妙もあり非常に美しく映っている。

初めてドメニコが現れるバーニョ・ヴィニョーニの奥行きも非常によかった。彼が画面奥でエウジェニアにタバコをもらい、「彼の彼女への言葉を忘れるな」と語るシーンでは、犬を連れたドメニコがゆっくりと手前に歩きだし、そのまま画面右手前の道にフレームアウトしてゆく。背後で流れる温泉の湯気や、左手に見える階段、右手の低い石塀の傾斜した構図に惹き立てられるドメニコの佇まいが美しい。

奥行きのある構図で最も印象に残るのはやはり最後のサン・ガルガノ大聖堂でのショットである。これまで何度かモノクロで描かれていたあの家は、この大聖堂の中に建造されているゴルチャコフの自宅?であり、その手前にゴルチャコフと飼い犬が跪いている。
このシーンの大聖堂が実物に比べ壮大で、とてつもなく巨大な建築に写っているのだが、それは遠方の建物がそう見えるように、大聖堂の奥側を大気に白んだかのように見せる工夫によってなされているのだろう。しかしそれ以上に、建造物を縮小スケールで製作し、遠近の工夫で周囲を肥大化させて見せているらしいから驚きである。これを知った時はかなり驚いたが、試しに手で家を隠してみると、確かに空間の広大な感じは失われる。タルコフスキー監督の表現の意地と発想力は圧巻である。
巨匠、タルコフスキー
彼は詩人であり、哲学者でもあり、そして映画監督であった。
僕は彼以上に詩的イメージを大切にし、守り抜いている映画監督を他に知らない。彼ほどあらゆる事象の本質を捉えきっている人間は中々いないだろう。そしてそれを言語化し、さらに、美しく映像に落とし込むことまでできてしまっているから、感動する他ない。
日本の映画や日本の俳句をこよなく愛し、日本人の世界感覚を称賛したアンドレイ・タルコフスキー。彼の哀愁に満ちた詩的イメージは、我々日本人に特有の詩的感覚と共通する感性があるのかもしれない。
美は国境を越えるのだ。
最後に
この作品に潜むイメージを手放したくない。
その一心でがむしゃらに、勢いに任せてここまで書いてしまった。
長ったらしい感想に過ぎない。
何を言いたいのか解らないような部分もあるだろうが、だが、とにかく書いてよかった。
今再び鑑賞してみると、まだまだ思うことがあった。
あれが書ける、これは解らない。
いつまで続いてくれるのだろうか。
生涯愛し続けることになるかもしれない。そう予感させられた、素晴らしい作品です。
参考図書
『終わりなきタルコフスキー』忍澤勉 著
『イメージフォーラム タルコフスキー、好きッ!』1986-11月号
参考記事
Jim Com .net【http://www.jimcom.net/nostalghia/】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
