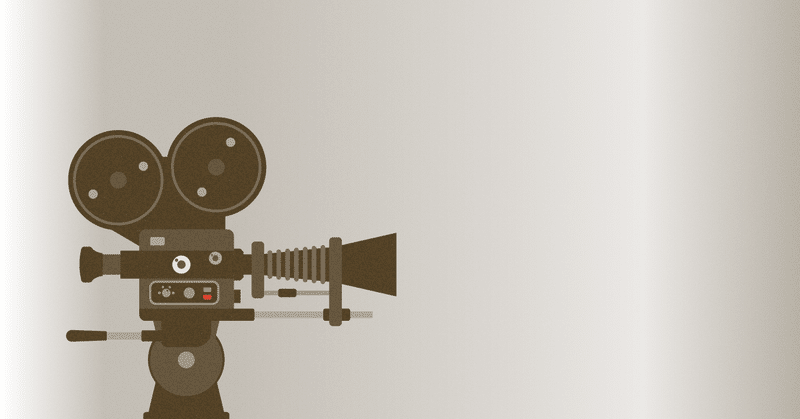
『の・ようなもの』:1981、日本
東京で二ツ目の落語家をしている志ん魚は23歳の誕生日を迎え、トルコ風呂へ行くことにした。その直前、彼は兄弟子の志ん米、志ん肉、志ん水、後輩の志ん菜たちが待つ師匠の家を訪れ、女性とセックスする時の注意事項を聞く。
志ん米は誕生日プレゼントとして金を渡し、志ん魚がトルコ風呂に入る様子を物陰から撮影した。志ん魚はエリザベスというトルコ嬢を紹介され、落語家をやっていると告げる。妻がいる志ん米だが我慢できなくなり、トルコ風呂へ行く。しかしトルコ嬢のアグネスは志ん米の態度に苛立ち、邪険に扱った。
エリザベスは志ん魚に名刺を渡し、出勤スケジュールを書く。「また来てね」と言われた志ん魚は、もう金が無いことを話す。彼は兄弟子たちが女性経験ゼロだと思い込んでカンパしてくれたこと、実は父親が買ってくれた過去があることを語った。エリザベスは名刺に自宅の電話番号を書き、「いつでも電話して。御飯でも食べに行こう」と優しく告げた。
後日、志ん魚はエリザベスの家を訪れ、英語の本ばかりが並んでいるのを見て感心した。2人でシャーベットを食べているとインターホンが鳴ったので、志ん魚は「隠れますか?」と告げて布団に身を隠した。
女子高で落語研究会の竹内由美、まりや、真代、佐紀が後輩たちに寿限無を教えていると、団地有線放送の女性ディレクターがやって来た。エリザベスは志ん魚を連れてレストランへ行き、料理を頼んだ。初めての料理やワインに、志ん魚は戸惑いを隠せなかった。
由美たちはディレクターから全国に顔が写るわけではないと聞かされてガッカリするが、八百屋のコマーシャルに出演した。志ん魚はエリザベスに卓球を教え、一緒に楽しんだ。彼はエリザベスに、「今は売れてないけど、将来は幸せにしますよ」と告げて笑った。
志ん魚は志ん米たちと共に、末広亭の深夜寄席に出た。志ん米が車で去った後、金の無い志ん魚たちは朝まで当ても無く時間を潰そうとする。そこへ愛人を連れた大物落語家が通り掛かり、金を恵んでくれた。
エリザベスが帰宅すると、妹の明子が来ていた。明子は「いい人がいない」という理由でアルバイトを辞めたことや、友達が犬をくれると言っていることなどを語る。エリザベスは金を渡し、ちゃんと仕事を持って頑張るよう促した。
文化祭で落語を披露することになった由美たちは志ん魚の師匠宅を訪れ、誰か暇な人でいいのでコーチに来てもらいたいと女将さんに頼む。そこで志ん魚と志ん菜が女将さんから指名され、彼女たちの学校へ出向いた。指導を始めた志ん魚は、由美に好意を抱いた。
志ん米は彼に、女子高生を紹介するよう要求した。志ん菜は姉に、落語を発表する良い場所は無いかと相談する。姉は知り合いであるオカマコンビの川島と川添に頼み、場所を用意してもらった。
志ん魚は兄弟弟子と共に、由美たちを誘って集団デートに出掛けた。志ん魚たちは団地有線放送のディレクターに落語の放送を頼むが、難色を示される。そこへ人気落語家の笑太郎が現れ、ラジオの生中継を始めた。
嫉妬心を抱いた志ん魚たちは、団地で天気予想のクイズ番組を始めることにした。由美たちも協力してビラを配り、当たればスーパーの割引券が貰えることもあって団地の主婦たちは強い関心を示した。スーパーは大喜びし、志ん魚たちが出る青空寄席の便宜も図ってくれた。
志ん魚がエリザベスの家へ行くと、彼女は風邪で寝込んでいた。エリザベスの高熱を知った志ん魚は、嫌がる彼女を背負って病院へ連れて行った。出船亭扇橋の元を訪れた志ん魚は、新作をやってみてはどうかと勧められた。「古典はダメですか」と志ん魚が言うと、扇橋は「お前の面白味が小さくなる気がするんだ」と告げる。
古典で頑張りたいと訴える志ん魚だが、扇橋は「お前のためを思って言ってるんだ。ゆっくり考えてみなさい」と穏やかに告げた。志ん魚はエリザベスに、「高校生の女の子と付き合うことにしました。だから、もう会えないかもしれないということで」と語る。しかしエリザベスが恋人じゃなく友達関係なのだからと言い、「黙ってればいいのよ」と軽く告げたので志ん魚は納得した…。
監督は森田芳光、脚本は森田芳光、製作は鈴木光、撮影はわたなべまこと(渡辺眞)、照明は木村太朗、録音は橋本泰夫、編集は川島章正、助監督は山本厚、音楽は塩村宰、主題歌は尾藤イサオ。
出演は秋吉久美子、伊藤克信、尾藤イサオ、加藤治子、小林まさひろ、でんでん、大野貴保、麻生えりか、五十嵐知子、風間かおる、直井理奈、春風亭柳朝(5代目)、入船亭扇橋(9代目)、内海桂子、内海好江、吉沢由起、鷲尾真知子、清水石あけみ、三遊亭楽太郎(三遊亭圓楽)、芹沢博文、永井豪、小堺一機、ラビット関根(関根勤)、黒木まや、大角桂子、小宮久美子、稲垣悟、大川まり、大田理奈、隼田勇蔵、菅野智子、小笠原勤、星野かおる、由良聡、金井久、大熊和子、松沢宏美ら。
―――――――――
それまで自主映画を撮っていた森田芳光の劇場映画デビュー作。監督と脚本の他、冒頭の『彼女はムービング・オン』とラストの『シー・ユー・アゲイン雰囲気』という2つの歌の作詞も「タリモ」名義で担当している。
出資してくれる予定だった人物が急病で倒れたため、森田芳光は両親に頼んで実家の料亭を抵当に入れ、3千万を借りて製作費を捻出した。風変わりなタイトルは、落語の演目『居酒屋』に登場する台詞から取られている。森田芳光は少年時代から落語ファンで、大学では落語研究会に所属していた。
森田監督は主人公に本物の若手落語家を起用する予定だったが、イメージ通りの人材が見つからなかった。そんな時、日本テレビで放送された『全日本大学落語王座決定戦』に出演していた伊藤克信を見て、主役に抜擢した。当時の伊藤は大学生であり、卒業後の就職先も決まっていたが、森田芳光と夫人の三沢和子に口説き落とされ、出演を了承した。
落語界からは、深夜寄席を終えた志ん魚たちに駄賃を渡す有名落語家の役で春風亭柳朝(5代目)、扇橋役で入船亭扇橋(9代目)、笑太郎役で三遊亭楽太郎(現・三遊亭圓楽[6代目])が出演している。イロモノ枠では、笑太郎の番組でクイズに答える主婦を内海桂子、師匠の女将さんを内海好江、オカマのコンビを小堺一機&ラビット関根(現・関根勤)が演じている。
エリザベスを秋吉久美子、志ん米を尾藤イサオ、由実の母を加藤治子、志ん肉を小林まさひろ、志ん水をでんでん(本作品でお笑い芸人から俳優へ転身した)、志ん菜を大野貴保、由美を麻生えりか、まりやを五十嵐知子、真代を風間かおる、佐紀を直井理奈、志ん米の妻を吉沢由起、有線放送のディレクターを鷲尾真知子(森田監督とは子役時代の同期)、有線放送のお天気お姉さんを清水石あけみが演じている。
由実の父を将棋棋士だった芹沢博文、エリザベスに挨拶される男を漫画家の永井豪が演じている(と書いたものの、永井豪がどこに出ているのかは分からなかった)。アンクレジットだが、自主映画の女王だった室井滋が亜矢役で出演している。
当たり前っちゃあ当たり前だが、伊藤克信は何の演技経験も無い素人なので、もちろん芝居は下手だし言葉の訛りもキツい。しかし、この映画の場合、それが大きな傷になっていない。むしろ、ヘタウマとでも言うべき味わいに感じられる。それは演出が巧みだとか、シナリオが良く出来ているってことじゃなくて、たまたま上手くハマっただけだろう。
一方、ビリングトップの秋吉久美子は惜しげもなくヌードを披露し、まだ若いけれど充分すぎる貫録と存在感を見せ付ける。年を取っても相変わらず魅力的な秋吉久美子だが、この頃の彼女はハンパなくキュートだったのよね。
冒頭、公園のベンチでラブラブモードの若いカップルが話していると、志ん魚が女の隣に密着して座る。カップルが困惑していると、彼は「お茶でも飲みに行きませんか。今、寄席が終わって暇になったんで、一緒に話でもしようかなと思って」と言う。
カップルが煙たそうにいると、「こんな男と付き合って将来、どうするんですかと」告げる。怒ったカップルが志ん魚に暴力を振るうと、攻撃が当たる度に拳銃の発砲音が入る。そこからカットが切り替わると志ん魚が結婚式の司会をしており、カップルがキスをして参列者に祝福される。
これが例えば「志ん魚が小遣い稼ぎで結婚式の司会を引き受けたら、揉めたばかりのカップルが新郎新婦だったので驚く」とか、そういうネタが用意されていれば分かりやすいオチが付く。しかし志ん魚にしろカップルにしろ、何事も無かったかのような様子だ。で、キスを志ん魚も祝福する中で、映画のタイトルが表示される。
「なんじゃ、こりゃ」と首をかしげたくなるような導入部だが、それが本作品の味である。そして、経験を重ねる中で少しずつ変化していったものの、森田芳光の根幹にある演出センスは、その冒頭シーンに凝縮されていると言ってもいいだろう。
志ん魚がトルコ風呂の受付でエリザベスを紹介された後、カットが切り替わると彼が泰明小卒の家を訪れて「誕生日を迎えて大切なこと」を諭されるシーンが描かれる。どういうことなのかと思っていたら、そのシーンが終わるとトルコ風呂でエリザベスが出て来る。
何を意図して泰明小卒のシーンを挟んだのか、まるでワケが分からない。そもそも、泰明小卒ってのが何者なのかも分かりにくいのだ。志ん魚の師匠の奥さんという設定なんだけど、そういうのを最初の内に分かりやすく示すための配慮は乏しい。志ん魚の師匠が扇橋なのかどうかも分かりにくい。師匠だったら「志ん」の文字が付いてなきゃ変でしょ。
志ん米がアグネスから邪険にされるシーンがあるが、特に何かオチらしいモノが付くことは無い。志ん魚が銭湯で志ん米たちに股間を披露すると、そこにいない女子高生たちの悲鳴が上がる。そこからカットが切り替わると、女子高生たちが寿限無を練習する様子が描かれる。
由美から「笑わせようとするんじゃないよ」と注意された後輩は謝罪し、今度の日曜日、お墓参りに行ってきます」と意味不明なことを言う。テレビ局が来たことが伝わった後、エリザベスの家を志ん魚が訪ねるシーンになる。インターホンが鳴ると志ん魚は隠れるが、誰が来たのか分からないままで終わる。
由美たちがコマーシャルに出ると、軽トラで野菜を売りに行った八百屋夫婦の元へ団地の主婦たちが殺到する。その中の1人はピーマンを買ったのに割引券を貰おうとして断られ、文句を言って去る。
コマーシャルを見ていた幼馴染が由美たちの元を訪れ、自宅へ招く。でも、そのシーンが描かれることは無い。その後も、シーンとシーンの繋がりは弱く、あちこちへ目が向けられる。どこに本筋があるのかさえ分からないぐらい、寄り道の連続で時間が過ぎて行く。
志ん魚が早い段階でエリザベスと親密な関係になるので、ここで話を軸に据えるのが最も分かりやすいと思う。しかし、しばらくすると、この2人が会わない時間帯に入る。志ん魚は由美に好意を抱くが、だからって2人の恋愛劇が充実するわけではない。エリサベスも含めた三角関係に焦点を当てる展開へ移行するでもなく、「志ん魚が天気予報クイズを企画し、団地の人々が盛り上がる」という展開で長い時間を費やしている。
望遠鏡を覗いて予想するけど大きく外す男と妻なんかも登場するが、志ん魚には全く関係が無い。っていうか、その番組自体、「まるで話が先に進まない」という状態を生み出している。
終盤、志ん魚は由美を旅館へ連れ込もうとして断られ、彼女の父に見つかって家へ招かれる。落語を披露した志ん魚は酷評され、由美にも「下手よ」と冷たい口調で告げる。実際、彼の落語は下手なのだ。それまでは能天気に過ごしていた志ん魚だが、そこで初めて本気で落ち込む。
その後、夜の街を歩きながら志ん魚がブツブツとモノローグを語る様子が描かれる。「祭り提灯に誘われて抜け道を入ると、神様は四畳半の狭さの中で明日を待つ」とか、「30過ぎの芸者衆と、40過ぎの浮気男が向島の屋根の下で寝ている」とか、小説でも朗読するかのような言葉を発しながら、たまに「シントト、シントト」と入れる様子を、やたらとグルーヴィーなフュージョンに乗せて描く。何だか良く分からないけど、何だか妙に引き付けられるシーンである。
ザックリと言うならば、これは「若い落語家たちの日常を淡々と描く」という映画だ。くだらない会話に花を咲かせたり、バカみたいな行動で楽しんだり、ちょっとした悩みを抱えたり、そういう様子が描かれる。起伏の激しいストーリーや、大きなドラマは用意されていない。極端に言ってしまえば、見終わっても何も残らないような作品だ。でも、なんか後味はスッキリしていて爽やかな気分になれる。
エリザベスは滋賀県の雄琴へ移るし、由美との交際は続くようだが落語が下手なのは全く解決されていないし、決して主人公に幸せな結末が用意されているわけではない。でも明るく穏やかな気持ちにさせてくれる、とても不思議な魅力を持つ映画なのだ。
構成や編集には粗さがあるし、まるで洗練されていない。普通に考えれば、お世辞にも出来栄えが良いとは言い難い。でも、そういう欠陥も含めて、愛してあげたいと思える映画だ。具体的に何がどのように作用し、その魅力を放っているのかは、ちょっと説明が難しい。っていうか正直なところ、良く分からないのだ。
たぶん、映画界では稀に起きる「奇跡の魔法に掛けられた作品」ってことなんじゃないかと思う。伊藤克信の素人丸出しの芝居、落語家の世界を舞台にした内容、いかにもインディーズ映画っぽい森田芳光演出、1981年という時代の空気。そういった様々な要素が偶然にも見事な相乗効果を発揮し、「なぜだか良く分からない傑作」を生んだんじゃないかな。
ちなみに、この映画は尾藤イサオが歌うオープニング曲『彼女はムービング・オン』とエンディング曲『シー・ユー・アゲイン 雰囲気』が、とても心地良い。両方とも森田芳光が「タリモ」名義で作詞し、浜田金吾(濱田金吾。元クラフト)が作曲して塩村宰が編曲を担当したジャズなのだが、その2曲だけで映画の評価が随分とアップするぐらいの魅力を放っている。
実のところ、映画抜きで歌を聴いただけでも気持ちいいんだけどね。でもエンディングに関しては、映画の雰囲気と曲がマッチして良い効果になっていると感じる。前述した「観賞後は爽やかな気分になれる」ってのは、エンディング曲の貢献度が高いんじゃないかな。シントト、シントト。
(観賞日:2018年1月22日)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
