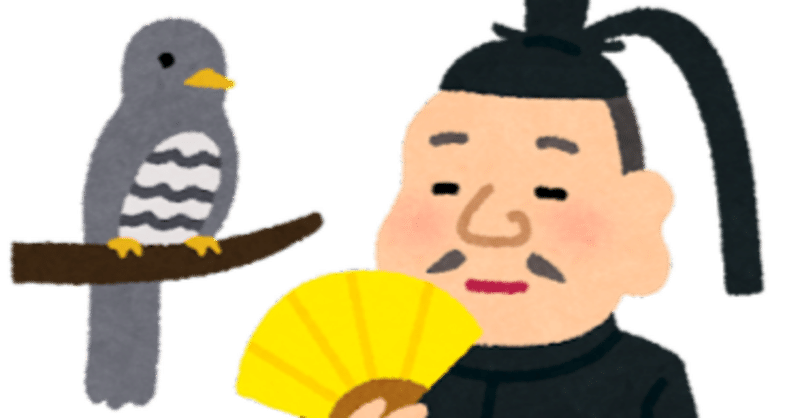
どうする家康」最終回「神の君へ」 「祝言の鯉」の話に秘められた家康の理想郷とは
はじめに
ようやく家康は、役割から解き放たれ、長い長い人生を全うしました。「とうとうその日が…」ではなく「ようやく」という言葉のが似合うように思われるのは、最晩年の家康の人生が、その思いに反して苦悩と孤独に満ちたものとして描かれたからでしょう。
「どうする家康」における家康像は、所謂、これまでの神君、狡猾な狸親父という両極端なイメージの双方を裏切る斬新さが見所でした。しかし、斬新な描かれ方をされた家康が、たどり着いた先は「人の一生は重荷を負うて遠き道をゆくが如し」という『東照公御遺訓』のとおりとなりました。何故、こうなってしまったのか?
ナレーション…あらため、お福は、御遺訓を引きながらも「遠き道の果てはまた命を賭した戦場にございました」とその人生が最後まで過酷なものであったことを強調しています。福の言葉は、困難の末に泰平の世を実現させた家康の偉業を顕彰する以上の意味を持ちませんが、物語は彼女の言葉を利用して、その裏にある、戦嫌いの彼の誰とも分かち得ない孤独と人知れぬ葛藤…そして、その先の絶望へ焦点を当てていきます。
つまり、後世の作り物とされる『東照公御遺訓』が描く苦労人像…そう語り継がれるようになった由縁を紐解くことが、「どうする家康」という作品であったのでしょう。
また「神の君へ」というサブタイトルも気になりますね。「神の君」ではなく「へ」とそこへ向かう方向が示されています。そこには、「神の君へ」向かう家康が、果たして幸せであるのかということを暗示しているようにも思われます。
そこで、最終回は、乱世を終わらせ安寧な世を成したことに家康は満足したのか、家康は幸せだったのか、「一人の人間」としての家康の人生を総括してみましょう。
1.それぞれの大坂の陣~乱世の終焉を見届ける憂鬱~
(1)遠い遠い過去となった「祝言の鯉」の話
阿茶に戦の身支度をしてもらう家康から始まります。小姓などの家臣ではなく阿茶にやってもらうあたりには、プライベートな一時を大事にする家康らしい思いもあるでしょうが、同時に心許せる者が阿茶しかいないということもほのめかしています。
そんな数少ない心許せる阿茶にすら「わしに言いたいことあれば今じゃぞ…これが最後かもしれん」と声をかけてしまう家康が哀しいですね。憂鬱とも感傷とも諦めともつかない弱気には、全てにおいて自信を失くした彼の本音が漏れていますね。
最後の戦に命懸けで臨む気迫ではなく、死に取りつかれたようなその言葉を背中で聞く阿茶の表情は、一瞬ですか憐れみと寂しさが同居しています。微に入り細に入る彼女の甲斐甲斐しさの根は慕う気持ちがあるのでしょう。
しかし、家康に振り返った阿茶は、すまし顔で「ありません、私はこれが最後とは思うておりませぬので」と素っ気ない答え。彼女なりに弱気な彼を励まします。かつては家康を叱咤する多くの家臣がいましたが、今や男勝りの阿茶だけしか、それができません(正信とだと互いにボヤきになってしまいますから)。彼女はわきまえているのです。
ただ、そこは家康の後半生の公私にわたるパートナー。ただ叱咤するだけでなく「一つだけ。よろしければあのお話をお聞かせ願いとうございます」と微笑みながら、おねだりをします。阿茶も、それなりな歳をかさねたメイクがされているのですが、好奇心に溢れた目だけは変わりません。
「あの話?」と問う家康に深く頷くと「鯉」と一言。訝る家康は「魚の鯉のことでございます」とまで言われ、ようやく信長が信康・五徳婚姻の引き出物として大事にせよと与えられた鯉を家臣が食べてしまうという有名エピソードのことと思い至ります。
この話、「どうする家康」ではこれまで二度触れられました。最初は、瀬名の慈愛の国構想によってまとまった徳川家の一家団欒の話題として。二度目は、病気の於愛との他愛ない語らいの中で。笑い話として語れるそれは、常に家康の日常的な幸せの中で愛する者に対して開陳されてきました。
恐らく徳川家中では、秘中の秘の幻の逸話があるらしい、みたいな形で広まっているのでしょう。聞く資格がある者は家康の身内に限られています。そのせいか、その詳細は、視聴者にも未だに明かされないままになっています。
「あれはな、信康と五徳の…」と静かに語る家康は当時を懐かしむ表情をするのですが、今までその話をしたときのような無邪気はものではなく陰があるのが印象的です。そのどことなく遠い目は、「祝言の鯉」話のあの時代と空気とは、あまりにも遠くかけ離れた場所に来てしまったという事実に軽く愕然としたのかもしれませんね。楽しい思い出すら、今の家康には自嘲の材料になりかねません。
(2)乱世の亡霊を体現する真田信繁と豊臣家最後の突撃
俗に言う大阪夏の陣は佳境に入っています。堀を埋められた豊臣方は籠城戦に持ち込むこともできないため、冬の陣以上に広範囲にわたる局地戦が繰り広げられたものの、連携の乱れなどから確実に豊臣方の戦力は削られていきます。後藤又兵衛の道明寺での戦死、長宗我部盛親の行方知れず(長宗我部勢の壊滅)など次々入る戦況報告が、刻一刻と追い詰められていく豊臣方の状況を物語っていますね。
そんな報告が飛び交う大阪城内で、手持ち無沙汰な真田信繁は一人、自身の名が刻まれた木片を、碁石を打つように床に打ちつけています。その脳裏に浮かぶのは、おそらく九度山での父、昌幸との対局です。突如、盤上の碁石を捨て、対局をひっくり返す昌幸に「汚い…」と信繁は不満げに呟きます。昌幸は「戦とは汚いものよ」と悪びれもせず、逆に信繁を盤上に引き倒すと、その耳元に「戦はまた起きる。ひっくり返せるときが必ず来る」と囁きます。そして、向き直ると、「信繁、乱世を取り戻せ。愉快な乱世を泳ぎ続けろ」と遺言を遺します。
父の言葉を、呆然と聞く信繁が印象的ですが、このことは計らずも、後世、「真田幸村」の名で知られる勇猛果敢で有名な武将が生み出されたのは、この瞬間であったことを示唆しています。つまり、父の戦国の世への飽くなき憧憬と羨望という呪詛が、信繁を戦国武将として完成させてしまったのでしょう。もしかすると蟄居したのが信繁だけならば九度山を降りず、兄の説得に応じたかもしれませんね。
父の怨念にも似た宿願をその身に宿した信繁は、まさに戦に飢え、戦を望んでやまない乱世の亡霊となったのです。前回、信繁は父の口癖「乱世を泳ぐことは面白きこと」を呟いていましたが、既に彼は信繁ではなく昌幸だったのかもしれません。
ジリ貧で後がない大阪城に大野修理が「家康が動いた。自ら戦場に出てきおった」との一発逆転の朗報をもたらします。修理の「茶臼山を奪い返す気であろう」との言葉に喜色満面に色めき立ち、「狸が!」と叫び、自らの名札を地図上の茶臼山へ起き、出陣させてくれと無言で懇願します。父の言葉に動かされるだけの信繁は、「ひっくり返せるとき」に飛びつきます。
そんな昌幸の意を汲むように彼を見た秀頼は「我らがこの戦に勝つ手立てはただ一つ。恐ろしき化け物の首を取ることである」と宣言し、修理が「目指すは家康の首ただ一つ!」と追随することで士気を高めます。気炎を吐く一同ですが、実質は追い詰められた豊臣方が徳川に抗するラストチャンスでしかなく、それも窮鼠猫を噛むような決死戦です。敵大将の首を取る以外に打つ手がないということ自体が、豊臣方の戦略的な敗北を決定づけています。また、秀頼は家康を「恐ろしき化物」と評しています。この短い戦の中で徳川方の恐ろしさを思い知ったと察せられます。敗北と恐怖心に打ち克つための最後の手段として、家康の本陣への突撃を敢行するのです。
にもかかわらず、秀頼の英断と鼓舞を受けた信繁は、我が意を得たりというと凄絶な笑みを浮かべます。最早、戦の勝敗も自身が生き残る算段よりも、武勇を誇り、戦という今を最大限愉しむことしか頭にないのでしょう。一発逆転は、その愉しみの最たるものです。真田昌幸の乱世への願望に憑りつかれ、戦に酔いしれる信繁の凄絶な笑みは、狂気にして狂喜といったところでしょうか。戦以外に生きる術を持たない武将の断末魔がここに見えてきます。
そんな乱世の亡霊たちを引き連れて滅ぶ覚悟をしている茶々は動じることもなく、「我が子らよ、恐れることはないぞ。この母は、どこまでもそなたらと一緒じゃ!」とこの戦の総責任者の一人として、彼らの庇護者として振る舞います。その、赤を基調とした麗しい具足姿と一歩も引かない堂々たる物言いに大阪城に集う剛の者たちも雄たけびで応えます。彼女にしてみれば、平和な世に生きられない哀れな猛者たちの母となって、最後を看取ってやるくらいしかないのでしょうね。悲壮だけれども覚悟を決めている彼女の言葉は力強く、兵を鼓舞します。
その様子に当てられた千姫が、今度は母に促されるまでもなく自ら「私も一緒じゃ。武運を祈る!」と茶々ほどではないにせよ、堂々と励まします。豊臣に…いや、正確には秀頼に殉じる覚悟を決めた千姫に恐れるものはありません。ただし、彼女は現在の戦局がいかなる状況なのかを理解していません。
また、茶々の真意、秀頼の引くことが許されない悲壮な覚悟など、彼ら二人の複雑な心境も見えてはいないでしょう。ただただ、愛しい秀頼と敬愛する義母と共にありたいという単純な願いしかそこにはないのです。
そして、この単純さ、純粋さが、結局、豊臣家を滅ぼす後押しになっていくことになりますが、その打算のない彼女の愛情を危ぶみ、そして痛ましげに見つめるしかない秀頼の眼差しが哀しいですね。"豊臣秀頼"という生き方を貫き、戦という手段を用いたこと自体は、母から与えられた思考の枠に縛られたままとはいえ、秀頼自身の本心の選択です。滅びることも百も承知の判断であり、そこに後悔はありません。
しかし、その選択に一抹の翳りがあるとしたら、それは、心優しい千姫を戦に巻き込み、兵を鼓舞する台詞を言わせてしまっていることに対してでしょう。士気にかかわるため、この場では口を挟みませんが、彼の本心は彼女だけは何とかしてやりたいと思っている。戦場にあって、この一瞬だけ、千姫のことだけを秀頼は考えているのです。
そして、この場面では描かれませんが、その秀頼の思いは茶々も同じだと察せられます。前回、江との対話で千姫はきっぱりと徳川との決別を宣言しましたが、そのことに最も動揺したのは茶々です。まさかに自分の選択が、実妹とその娘である嫁を仲違いさせることまでは想像が及ばなかったのでしょうね。それは千姫が優しい娘だったからです。
こうして、乱世の亡霊たちの意思は、改めて"豊臣秀頼"のもとで一つにより合わされ、大阪の陣のクライマックス、天王寺・岡山の戦いへとなだれ込みますが、その裏には秀頼、茶々の滅びを既に覚悟した複雑な想いがあることは見逃せません。
(3)乱世の亡霊たちと共に逝きたい家康
さて、対する家康は、着陣すると自らの馬印を「前へ出せ、敵から見えるようにな」と命じます。将兵らは士気の鼓舞のためと思い、戦慣れした大御所の命に粛々と従いますが、正信だけは無言なまま微妙な表情をしています。彼だけは、乱世の亡霊たちを自分に引きつけるために家康が自ら囮になるつもりだと察したのでしょう。
天王寺・岡山の戦いと言えば、真田勢と毛利勢の思わぬ猛攻に徳川本陣が恐慌をきたして、敗走、家康も切腹の覚悟を決めたと言われます。謂わば、豊臣方の武勇伝として判官びいきたちに愛される物語として広まっています。
しかし、本作では、本陣に深く踏み込まれることが家康の想定内、寧ろ、それを望み、相手を誘い出し、呼び込むための苦肉の策となっているのが興味深いですね。家康は、自身を囮にして、乱世の亡霊たちを根こそぎ引きずり出し、この場で殲滅するつもりなのです。
それは、茶々への手紙の一節「乱世の生き残りを根こそぎ引き連れて共に滅ぶ覚悟」の実行であり、また、阿茶に「これが最後かもしれん」と告げた真意ということにもなります。つまり、逸話とは違いますが、確かに家康はこの戦で死ぬ覚悟をしていたことになりますね。
そんな家康の真意も知らない大野修理は、前方に煌々と輝く家康の馬印にまんまと誘い出され、迷うことなく全軍突撃を命じます。眼前に広がるは、関ヶ原の戦い同様、高名な武将も無名な兵もない、ただただ人間同士の無残な殺戮が延々と繰り広げられるだけです。後藤又兵衛が戦死報告だけだったのも、背に十字架の陣羽織を着て、今この場で戦う明石全登の活躍が、他の将兵の怒号にかき消されていくのも、全て戦というものの非情さ、無常さを表すための演出でしょう。
次々と敵味方関係なく崩れゆく中、逃げ出そうとする兵を引き留め、「引くな、真の武士よ、我に続け!」とおだを上げる信繁の姿だけは際立ち、彼の猛攻によって、馬印は逸話で語られる通り引き倒されます。
徳川本陣は、これを機に一気に総崩れとなり、乱戦になりますが、本陣奥深くにいる家康は全く動じることなく、静かにその時を待っています。そして…長年の経験から敵の迫り具合を察すると、頃合いを見計って「家康はここじゃ!」と叫び、敵をより深く導こうとします。それに呼び寄せらるようになっている信繁たち豊臣方の将たちは、武功を目指す武将というよりも乱を求めて、ただただ戦場を彷徨う乱世の操り人形のようです。
なおも「家康はここにおるぞ!」と叫ぶ家康の隣で黙って鉄砲を抱えて横に立つ正信が良いですね。冬の陣の前、「信長や秀吉と同じ地獄を背負い、あの世へいく。それが最後の役目じゃ」(第46回)という家康の覚悟に対して、彼を孤独にしないため「それがしもお供いたしますかの」と言ったその思い、騙り者と呼ばれた彼の有言実行の真心です。
まあ、昔の正信ならとっとと逃げ出したはず(笑)それだけ、正信にとっても家康という主君は得難いということですが、それは家康が、あの正信にすら身体を張らせる人物へと成長したということでもあります。三河一向一揆で家康を狙い撃ちした鉄砲の腕前で、今度は家康を守るというのも、当時を思い返させる心憎い演出ですね。
家康の呼びかけに遂にたどり着いたのは、信繁以下、真田勢です。彼の姿を認めると、家康はあろうことか、前に進み出でながら「さあ来い…さあ、来い!」と挑みかかるように言うと、彼をつかまんと手を前に出し「共に逝くうぞ!」と言い出します。二度繰り返すあたりに、彼が最初の陣のときより決めていた覚悟が窺えますが、自らの命を省みないその姿は鬼気迫るものです。
その本気の「共に逝こうぞ!」が、静かに前回の茶々の締めの台詞「共に行こうぞ、家康」と静かに響き合っているのが絶妙ですね。頭の良い茶々は、この二度目の大阪の陣が豊臣家を滅亡に導く一手であることを理解しています。その上で、いざとなれば、自身が招いた戦の元凶の数々を全て自分の罪として引き受け、滅ぶ覚悟も見定めています。茶々のこの覚悟を支えているのが、家康からの手紙であることは、前回のnote記事でも触れましたね。
無論、家康は茶々のこうした思いを知っているわけではありません。ただ、「世のため」にあろうとして、想いがすれ違ってしまった家康と茶々が、周りのあずかり知らぬところで響き合い、二人で乱世の全てをこの戦でこの身と共に焼き尽くそうとしているのです。まあ、巻き込まれた者たちはたまったものではないのですが、徳川方の面々はともかく、豊臣方の牢人勢は自覚がなくとも望んでこの滅びの道に乗っているので自業自得…いや、本望でしょう。
それを象徴するのが、家康と対峙している真田信繁です。乱世が生み出した「恐るべき化け物」(秀頼)である家康は、乱世の亡にが憑りつかれた信繁にとって、これ以上ない相手です。その相手に「共に逝こうぞ!」と地獄に誘われるのは、武士として無上の喜び…嬉し気に微笑むと躊躇いなく襲い掛かります。すかさず放たれた鉄砲に真田勢は倒れますが、「乱世を泳ぐ」楽しみに信繁の動きは止まりません。己の命すら燃料でしかない彼に、天下といった先のビジョンなどありません。今というそのときの充実感しか求めていないからです。
所詮、真の武士なる者とは、乱世を望み、乱世を動力源とする恐るべき生き物は、己が生きるためにマッチポンプのように地獄を生み出し、そこに溺れ、そこで死ぬしかない哀れで愚かな存在であるということでしょう。結局、戦を捨てられない者は滅びるしか道がないのです。昌幸は、息子に残酷な贈り物を遺していったのかもしれません。
ただ、信繁は自らの愚かさと哀れさの自覚がない分、幸せかもしれません。その愚かさを重々わかった上で捨てられなかった家康は、「戦無き世」を求めながら乱を起こし、多くの人々を死なせている自身の矛盾とひたすら向き合ってきました。
思えば、天下一統前は、仕掛けられた戦、あるいは戦国を生き延びるために避けられない戦でした。つらいけれど仕方がないと言い聞かせることができたでしょう。また秀吉政権下の小田原征伐や唐入り、これは為政者の起こした戦でした。これまた、彼の家臣としては生き残るために参加するしかなかったと言えます。
しかし、秀吉死後の関ヶ原の戦い、そしてこの大坂の陣は違います。戦を避けようと彼なりの最善を尽くしたこと、そのほとんどが裏目に出て、己の存在自体が戦の元凶であることを思い知らされました。乱世を生き延びていく中で、知らず知らずのうちに戦国の世でしか生きていけない人間になり果てたのです。そして、だからこそ生き延びられた。それでも、彼は三成に言ったように、「戦無き世」を実現するために歩みを止められない、そのために戦が起きることも捨てられません。
その理由の一つは、瀬名を始め、家臣たちなど多くの者に託された「戦無き世」の願いを託されたからです。もう一つは、ここに至るまで、望まない形も含めて多くの者をその手で殺めてきたからです。かつて、信長は家康に「人を殺めるということはその痛み、苦しみ、恨みを全てこの身に受け止めるということじゃ」(第27回)と多くの犠牲を強いる天下人の心の闇を吐露してしまいますが、家康は自身が天下人となり、そのことを実感したはずです。家康の命は、多くの命と彼らの思いの上にあるのです。
そして、今川義元から学んだ王道、徳治の教えを知り、生来の優しさを持つ家康は、そんな自分の犠牲になってきた多くの命、自分に様々な思いを遺した多くの人々の心を無碍にできません。逃げ出すという選択肢はないのです。一方で乱世の申し子である自分に「戦無き世」を作る資格はないという根本的な矛盾も抱え込みます。
真摯な家康は、長い葛藤の末、天下泰平の願いを正しく次代に受け継がせ、過去の禍根を全て断ち切るには、戦の元凶である自分が戦を起こす者たちと滅びることだと思い極めました。そのプロセスは今までnote記事でも書いてきましたから、今更、くだくだと述べる必要はないでしょう。
ただ、この決断に至るまで、そして覚悟した家康の傷ついた心は、誰が癒せるのでしょうか。彼は自身の奪った命の供養と自身の罪深さを自覚し、ひたすらに「南無阿弥陀仏」の写経をしていました。それこそおびただしい数の枚数になっていましたね。しかし、どれだけ書いても、そして枚数を重ねれば重ねるほど、それがただの自己満足にすらならず、彼らの成仏にはならないことがわかってしまったのではないでしょうか。
彼を心から気遣う正信や阿茶は、寄り添ってはくれますが、この懊悩はただ一人の天下人である、自分一人で背負うしかありません。あまりの苦しさに、それを味合わせない親心から跡取りの息子とも分かち合わず、一人で抱え込みます。ただ一人、この気持ちがわかるであろう天下人、秀吉は、彼に自分の負の遺産の全てを押しつけて、あの世の住人です。
だから、襲い掛かる信繁を前にしながら、家康の視線の先に信繁がいません(視線の軸が微妙にズレています)。そして、両手を前に突き出す家康の脳裏に光るのは、彼ら戦をひたすら望む乱世の亡霊を生み出した欲望の権化、天下人秀吉です。秀吉と信繁が重なったそのとき、家康は「乱世の亡霊たちよ…わしを連れていってくれ!」と頼み込むと、諸手を広げ、信繁を受け入れようとします。
この懇願に、覚悟とは別のもう一つの家康の本音が見えますね。天下人として苦しみ抜いた彼はもう限界なのです。彼は、この役割をもってこの世から消えてしまいたい、早く楽になりたい…救われたいと願ったのでないかと思われます。「乱世の亡霊全てと心中する」…それは覚悟であり、甘美な死という救いだったのでしょう。天王寺口の戦いにて、家康が死を覚悟したという逸話が残った本当の理由は、家康の天下人としての深い懊悩が死を覚悟するものであったというのが「どうする家康」の解釈なのですね。
迫りくる信繁のアップで、このシーンは暗転…信繁の詳細は描かれませんが、乱世の亡霊の代表格でしかない彼の生死は、家康の懊悩の救いにも、悩みを深めることにもならないからです。あらかた方がついた戦場をとぼとぼ歩く修理が、六文銭を拾い上げ、息を荒くする。それだけで豊臣方の敗北が決定的になったことがわかる…それで充分なのです。
とはいえ、命がけの激戦だったようで、戦闘が終了した家康と正信の老人二人は地面にへたり込んでいます。正信の刀も綻び、折れていますから、乱戦の中を家康と自分を守るため奮戦したと知れます。肩であえぐ家康も同様で、襲い掛かられれば、本気で戦ったに違いありません。彼の身体に沁み込んだ戦場の倣いは、自然と彼を救うように動いてしまうのですね。経験と強い運が、結局、彼を救ってしまいます。
そんな家康の自殺願望に近い思いを半ば察していた正信は「また、生き延びてしまいましたな…」と慰めるように言うだけです。老獪な彼にしても、今の落ち込む家康にかける言葉はこれくらいしかありません。
そこへ「天守が…天守が燃えておるぞ!」の言葉に、急いで天幕をめくった家康は、轟轟と燃え盛る大阪城を目の当たりにして呆然とします。これは、大阪城にようやく徳川方が取りつき、大阪方にそれを止める力がないということです。また炎上自体には内部の裏切りも関わったと言われています。どちらにせよ、家康を悩ませた豊臣家…いや、秀吉の栄華と権威の象徴がいよいよ落城するのです。
追って出てきた正信が「とうとう、終わるんですな…長い長い乱世が…」と声をかけます。名実共に今度こそ、家康が天下を握った瞬間なのですが、そこには喜びも感慨も勝鬨もありません。ただただ、乱世の亡霊たちに置いて行かれ、まだしばらくは生きていかねばならない家康の虚ろな気持ちがあるだけです。
(3)千姫の無垢の両義性
山里郭に逃げ込んだ秀頼は、大野修理を通じて、千姫を返すことを申し出ます。この際、修理は自身が切腹する替わりに茶々と秀頼の助命嘆願をしたとの話もありますが、本作の覚悟を決めた茶々と秀頼には付き従う以外、彼の選択肢はありません。彼はどこまでも二人の意向に殉じるだけの男です。
さて、千姫を迎えに初がやってきたことを確認すると、茶々は「お千、輿を用意してある。出よ」と静かに告げます。このとき、画面はアップの秀頼をナメて、奥の茶々と千姫を捉える構図になっています。焦点が合っていなため秀頼の表情はぼやけていますが、彼の意向と茶々の意向が一致しての千姫脱出であることが窺えます。二人には背を向けながらも、秀頼の思いは千姫にあり、時折、はっきりはしないものの彼の表情が揺れています。
義母の言葉に秀頼を振り返る千姫ですが、彼の背中は何も答えません。「母上と殿は?」と問う彼女に微笑み返す茶々。切り返しショットのアップで捉えた千姫は、それだけで意図を察した千姫は、涙をためて首を振り「嫌でございます。私は殿と母上と共におりまする」と気丈に返します。彼女にすれば、既に徳川とは縁を切ったものだからです。押し問答の後、画面はまた秀頼をナメて、二人を捉えます。秀頼が耳をそば立てる中、千姫は「私は豊臣の妻じゃ。行くならば殿も母上もご一緒でなければ」と振り替えると「殿、一緒に出ましょう!」と呼びかけます。
しかし、秀頼は千姫へと振り返ることなく「余は最期まで"豊臣秀頼"でありたい」と意地を貫くと返します。彼の思いはおそらく千姫にあるのですが、"豊臣秀頼"以外の生き方を知らない彼には、その思いに応えてやれる術を持ち合わせていません。秀頼のその言葉に武将としての気概ではなく、宿命を受け入れる哀しい覚悟だけを察する茶々は哀しく微笑みます。
息子だけは助けたい思いと、それができない息子にしたのは自分であるという事実との相克は、秀頼の哀しい覚悟を認めてやることしかできません。それもまた自身の罪であることを、茶々はわかっているのでしょう。
しかし、それで納得できないのは、幼き頃から彼だけを見て、慕ってきた千姫です。振り向かない秀頼の前へ出ると、彼の手を握り頬に寄せ、「千は、ただ殿と共に…生きていとうございます!」と強く懇願します。一拍おいてからの、力強い「生きていとうございます!」の言葉に彼女の本音が垣間見えます。
心根の優しい千姫の心の底には、徳川と戦をする覚悟はなかったのです。ただただ、慕っている夫と敬愛する義母と共に生きていくために、彼らと同じ気持ちでいたくて、豊臣の妻である道を選択したのです。そこには、この戦が持っている滅亡の匂いがありません。前回の「徳川を倒しましょう」との言葉も、どこまでの覚悟であったか。
千姫の想いはまっすぐで強いものですが、その生を望む純真は単純です。ですから、自らの宿命を受け入れる哀しい覚悟をする茶々・秀頼母子は、彼女を置いておくわけにはいかないのです。彼らの宿命の道連れに相応しくありません。勿論、それ以上に、秀頼は彼女に生きていてほしく、また茶々に至っては義理の娘に対する愛情と共に、自分のせいで実の母子を仲違いに追い込んだ江への詫びという姉妹愛もあったと思われます。
ですから、秀頼は心を鬼にして、すまなそうな表情を浮かべながら、千姫の手を外し、その思いを拒否します。
何とかしてくれとすがりつく千姫を抱えた初に、茶々は万感の思いで「お千を頼んだぞ」と申し渡し、涙に塗れたその顔で正面を見据えます。泣きじゃくる千姫には見えませんが、その表情を見た初は、姉が乱世を生きる者たちと共に豊臣家を滅ぼす覚悟であることを改めて悟ります。ですから、何も言わず、千姫を連れていくことになります。思えば、茶々が夏の陣の開戦を決意した場に直面した初は、既に姉の悲壮感を察していましたからね。
さて、家康の本陣についた千姫は、家康の労いも聞かず、「大御所さま、我が母と夫をご助命くださいますよう。何とぞお願いいたしまする」と、あくまで豊臣の嫁であることを崩さないまま、助命を懇願、更には「豊臣にはもう戦う力はございませぬ。この期に及んでお二人を死なせる意味がどこにありましょう」と理を持って説得を試みます。いずれも、江が、茶々が千姫を教養ある女性として真っ直ぐな人間に育てたことを窺わせますが、その幼いとも言ってよい若さは隠しようがありません。
彼女の置かれた環境を考えれば、責めるのは酷ですが、彼女の本音が豊臣の宿命に殉じることではなく、「ただ殿と共に生きていとうございます」が本音であるのであれば、最初から彼らの意向に逆らうことになっても、彼らの助命のために動かねばならなかったでしょう。特に致命的だったのは、江との会話で「徳川の姫」であることを否定し、両家のパイプであることを拒否したことです。これは浅はかでした。冬の陣の決定打は、片桐且元と織田常真という両家を結ぶ交渉役を失ったことにありました。となれば、彼女は秀頼に寄り添いたいという純情のあまり、自身の役割を放棄し、間接的にこの事態を招いたと言えなくもありません。
既に手遅れなのです。しかし、今なお、その過ちに気づかない彼女は、豊臣の嫁として大御所と交渉しようとしています。ここは、「徳川の姫」にもどって、「お爺さま」と情に訴えるほうが効果的なのですね。すっかり、「豊臣の嫁」となり、自身を「大御所さま」と呼ぶ千姫に、家康はひたすらに虚しい眼差しを向け、自身が千姫にした所業に暗くなります。
見かねた秀忠は「戦の作法とは左様なものでは…」と駆け寄りますが、必死の千姫は父の言葉を遮り「大御所さまに申しておりまする!」と強気の姿勢を崩しません。近視眼的になっている彼女は、豊臣家中でもそうでしたが、この戦がどういう意味を持っているのかを理解していませんし、当然、その中で自分がどう処すべきなのかもわかっていないのです。
娘の父を父と思わぬ剣幕に啞然とする秀忠を尻目に、千姫をは土下座を繰り返し、ひたすらに大御所に懇願します。事態を察し、姉の覚悟を理解する初が、純情を炸裂させるばかりの千姫を痛々しく見つめています。この眼差しは視聴者に重なるところでしょう。
土下座する千姫を前に座り込んだ家康は「秀頼を深く慕っておるのじゃな」とせめてもの慰めの声をかけるのですが、ここが助命嘆願の攻め所と勘違いした千姫は「私だけではございません。多くの者があの御方を慕っております!」と、あろうことか秀頼の人望を口にします。
彼女はこの戦の本質を理解していません。ごく単純に言えば、秀頼が優秀であり、乱世を望む武士たちの思いに応えてしまう人望があるから、徳川への不満が大阪に集まり、戦となったのです。秀頼の才そのものが、戦の元凶の一つであるのは、前回の牢人らを前にした演説で明らかでしょう。その場面を見ながらも、彼を慕う千姫は、その美徳のみを信じ、問題点を見ようとしません。
千姫の言葉を致命的な一言と捉えた秀忠のなんとも言えな表情が印象的ですね。彼は秀頼にコンプレックスを抱いていただけに、その危険性を家康以上に理解していますから。それにも気づかない千姫がなおも笑顔で「あの御方は夢を与えてくださいます。力を与えてくださいます、前途ある若き才をお救いくださいませ」と美徳を連ねてしまうのが、もう何ともいけません。
秀忠は呆然とし、初は哀しい顔でうつむき、正信は渋面、正純は事態を静観しています。の場でこの発言が問題であることを理解していないのは彼女だけです。明らかに徳川家に禍根を残すその才能は、生き延びれば、本人が望まずとも第三、第四の大坂の陣が起こるだけ。その才が、公然とひけらかされたこの瞬間、秀頼の死は決定的になったのです。
謂わば、大局を見ることができない千姫の幼さが、秀頼処刑の最終トリガーを引いてしまったのですね。「どうする家康」においては、純粋な善意が誤解を招き、あるいは人の欲望をかえって刺激し、結局は事態を悪化、取り返しのつかないことを招くことが度々ありました。それは最終回まで徹底して貫かれたようですね。
善意や純情や志の高さは、大切なものであり、それなくして事をなしてはいけません。しかし、それだけでは駄目なのです。物事の実現には、純真を活かす知恵と慎重さ、そして力も伴わなければならないのです。「力なき正義は無能であり、 正義なき力は圧制である」というパスカルの言葉は、「どうする家康」を構成する大切な要素になっていますね。
千姫は知恵と慎重さに欠けました。彼女が「徳川の姫」として振る舞えていたら、「秀頼はバカなので皆に乗せられて戦をしました。暗愚極まりないので出家で許してください。暗愚を相手にしては徳川に傷がつきます」くらいは言えたかもしれません。まあ、それで助けるとは限りませんが。
千姫の言葉に改めて、自分が二条城で見た才気走った若者の姿(第45回)が思い浮かんだことでしょう。孫への情にほだされかけた家康は、自らを叱咤するように「すまん…ここでくじければ、ここまでやってきたこと全ては…」と千姫の懇願を拒否しかけますが、そこで彼を遮るように「私が命をくだします!」と秀忠が割って入ります。「そなたは…」と言いかける家康に「将軍として!」と叫びます。便宜上は、将軍秀忠のほうにその権利があるからこその台詞です。
この一瞬、命をくだす怯えと恐れで身震いする秀忠がよいですね。彼は初めて、自分の意思で人を殺める命令をくだすのです。それがいかに残酷なことであるのかは、先の戦いで家康から嫌というほど教えられています。人を殺すということは、大きな業を背負うことです。それを彼は、この一瞬で覚悟すると、今度は静かに「将軍として、命をくだす。秀頼には…」とここで一度、家康に振り返ってその意を汲んだ上で「死を申しつける」と裁可をくだします。視線を下に落としたまま、秀忠は「最後くらい私に背負わせてくだされ」と哀しい顔をします。
秀忠は、大阪の陣が始まってよりずっと、家康の間近で、彼が文字通り寿命と心を削って、鬼となるその覚悟と気迫で戦にあたる姿を見てきました。その形相に圧倒されながらも、心優しい彼はそのことに心を痛め続け、自身の不甲斐なさにも悩んだのでしょう。その優しさゆえに、家康が孫の夫を殺す命をくだすのを思わず止めに入ったのではないでしょうか。
二度繰り返された「将軍として」と言う言葉が、印象的ですね。逸話では秀忠が、秀頼処刑を強硬に主張したと言われます。しかし「どうする家康」では、家康の鬼気迫る哀しい様を引き取ろうとする優しさから、将軍としての覚悟を決めた結果となりました。
大御所政治では、西国関係は家康が決めていましたが、それを秀忠が決めたことになります。つまり、この決断で真に征夷大将軍になったのでしょう。息子の手を汚さぬよう尽くしてきた家康が、哀れむような父の目で家康を見ていますね。一人前になるとはこういうことなのかもしれません。そして、戦場を直接見た以上、秀忠も息子のために、何かを引き取っておく必要があったでしょうね。
しかし、そんな父子の感傷など、千姫の知ったことでありません。「鬼じゃ!父上もお爺さまも鬼じゃ、鬼畜じゃ!」と激昂してつかみかかります。恐ろしい形相になった千姫は、家康に向かって「豊臣の天下を盗みとった化物じゃ!」との捨て台詞を吐き、暴れます。先ほど、千姫の無垢な心が秀頼処刑を決めたと話しましたが、今度はそれが家康へ襲い掛かります。無垢であるだけに、その言葉には穢れがなく、嘘がありません。だからこそ、家康自身の非情な所業への罵倒として深く、深く突き刺さるのです。彼の呆然とした顔をには、その衝撃が浮かんでいます。言葉を失う秀忠も同様です。この助命嘆願の場面は、哀しいかな、親子三代の久しぶりの顔合わせでありながら、誰一人救わない無情に溢れていますね。
見兼ねた初が「これは姉と秀頼さまがお選びなったことでもあるのです」と、この結果こそが豊臣家の誇りを守ることであり、また乱世を終わらせたい姉の願いであると助言したのです。「憧れの君」に想い焦がれ続けた姉の真の願いを幼き頃から知っている聡明な初だからこその言葉です。
その言葉は慈愛に満ちていますから、千姫は一瞬収まりますが、わかったところで、いやわかればこそ、自分だけが置いて行かれることに耐えられません。「秀頼さまを返せ、返して!」と泣き叫び、その場から引きずり出されるしかありません。
孫の言葉に呆然としていた家康は初と目が合い、茶々の願いが乱世を終わらせるための死であったことをうっすら理解したようにも思われます。その場を去る秀忠や正信らに背を向け、一人、崖の上から、大阪城に想いを馳せ、静かに茶々と秀頼の運命に手を合わせていくのは、とても自然な流れではないでしょうか。彼の手紙は、たしかに茶々に届いているのです。ですから、家康は、自分が殺める彼らの痛み、苦しみ、恨みを全てこの身に受け止めようとするのです。
(4)茶々が今際の際に思い浮かべた人
一方、燃え盛る大阪城内では、茶々と秀頼たちが、その最期のときを迎えようとしています。まずは棟梁たる秀頼がまず切腹を試みます。その秀頼をナメた構図の先に見える茶々の表情には、息子が本当に自害してしまう戸惑いと恐怖…それでも目を逸らさず見届けようとする母の思い…と複雑な胸中が窺えます。
刃を突き立てるまでの秀頼のわずかな躊躇いに死に怯える彼の人間らしさが垣間見えますが、その瞬間、彼は作法通りの切腹をします。そして、呻きながらも彼が案ずるのは我が身ではなく茶々のことです。「母上、我が首をもって生きてくだされ」との言葉には、母を自分の我儘につき合わせた詫び、期待に応えられなかった不甲斐なさ、母だけは生きて欲しいという本音などがあるでしょうが、一方で誇り高い茶々が生き延びはしないという確信もあるだろうと察します。つながりの深い母子ですから。
修理の介錯によって、茶々の頬は秀頼の返り血にまみれます。それこそが、茶々の罪と言わんばかりです。嗚咽と共に抱きすくめる茶々のそれは本音ですが、「見事であった!」と褒めるのは、あくまで彼の名誉と誇りを保つ部分のが大きいでしょう。秀頼が"豊臣秀頼"として死んだのであれば、彼女もまた"豊臣秀頼"の母、豊臣家のお袋様として振る舞わねばなりませんから。
そして、「見事であった!」との茶々の言葉を機に、最後まで残った家臣郎党も次々と自害し果てていきます。茶々はひたすらに倒れていく彼らを呆然と見届けるしかありません。豊臣家の主は秀頼ですが、実質的な主は茶々です。彼女は、どんなに辛くとも、自分の起こした乱の顛末を逃げることなく、最後まで見届けようとします。ですから、涙と血に顔を濡らしながらも決して目を逸らしません。
残るは茶々と自決した者たちを介錯し続けた修理だけです。彼もまた「徳川は汚名を残し、豊臣は人々の心に生き続ける!」と叫ぶと、刃を己に突き立てます。内容自体は家康が予見したことですが、それを彼が言ってしまうのは、負け惜しみ以上にはなりませんね。「どうする家康」の修理は、茶々への敬愛と忠誠のため、虚勢を張り続けた男となってしまい、最期まで冴えない扱いだったように思われます。
さて、修理の介錯をし、全ての者の死を見届けた茶々は、その凄惨な場面への衝撃からか息も荒く、放心状態ですが…やがて我に返り一笑に伏すと、この戦のあとの未来に思いを馳せます。結局、彼女は、紆余曲折はあったものの、初志貫徹しました。天下を取ろうと戦い切りました。ですから、自らの愚かさへの自覚とある種のやり遂げた達成感、相反する心情を抱えています。それが不敵な笑いに出ています。
彼女は誰に言うでもなく「日ノ本か、つまらぬ国になるであろう。正々堂々戦うこともせず、万事、長きものに巻かれ、人目ばかりを気にし、陰でのみ妬み嘲る…」と、家康の築く安寧の世で、主役になるだろう民の愚昧さを罵ります。これは現代の我々にも通じますが、それを暗示しているのではありません。大衆全般の悪癖を語ったものです。
このような愚かで信頼のおけない者たちでは、世の中は立ち行かない。だからこそ、力のある者が総取りし、世を治めていくというのが覇道です。茶々は、誰にも虐げられないためにその強さを求めました。
こう考えていくと、茶々の言葉は、「天下の主役は民」「民に見放された時こそ、我らは死ぬ」(第7回)で今川義元が説いた言葉の反転になっていることに気づかされますね。義元の言葉は、つまり王道とは、民の善性と賢さを信じることが前提にあるからです。だからこそ、家康は三河一向一揆終結後、裏切られても、家臣と領民を信じ抜くという覚悟をしたのです(第9回)。
家康は、誰もが虐げられずに済む世界を指向しました。その根本にあるのは、優しさです。その究極は、瀬名の慈愛の国構想ですが、力なき善意は無力でした。だから、家康は優しさと力という二律背反のバランスに葛藤してきました。
話を戻しましょう。茶々は、民が主役になる平凡な世の中の愚かさをなじりながら、その国は「優しくて…卑屈でか弱き者の国…!」と吐き捨てます。しかし、この場面で注目すべきは、「優しくて…」で一旦、台詞が途切れて間が開くことです。優しさは、弱き者の美徳です。
権力者によって虐げられ、母を亡くした茶々は、強く生きようと狡猾に振る舞い、豊臣家を乗っ取りました。しかし、怨嗟と復讐に囚われた彼女の心は救われませんでした。結局、その頑なな心を救ったのは、前回の家康の手紙にあった優しさです。それによって、彼女が本当に欲していたもの、または、「憧れの君」の本質が優しさであることも知りました。
だからこそ、「優しくて」と呟いた瞬間に、そこにすがりたい素直な思いと羨む気持ちが湧き、自然と止まってしまったのです。この短い「…」という間にこそ、彼女の本音、感傷があることは見逃せないところです。
しかし、その感傷を振り切るようにして「卑屈でか弱き者の国…!」と言うと、天に小刀を突き上げ「己の夢と野心のためになりふり構わず力のみを信じて戦い抜く!」と叫びます。一見、勇壮な振る舞いと強気の文言ですが、遠景で後方からその様を捉えた構図のため、茶々の表情は見えずその思いは見えません。そして、静かに「かつて、この国の荒れ野をかけ巡った者たちはもう現れまい…」と結び、その涙を浮かべた顔で、寂しそうに周りを見回します。
そこには、先ほど自害して果てた武士たちの死骸、「己の夢と野心のためになりふり構わず力のみを信じて戦い」抜いた者の無残な末路があります。
ここで彼女がここで語った言葉は、現在の彼女の心境という以上に、自分たちの起こした大乱で死んでいった猛者らへのせめてもの手向けではないかと思われます。戦を求め、それを楽しむ者たち、乱世の亡霊たちの総大将となった豊臣家が、彼らを認め、褒めたたえてやることだけが、彼らの魂に報いることです。
茶々は、まさしく「乱世の生き残りを根こそぎ引き連れて共に滅ぶ」ために、彼らの魂を成仏させたのですね。彼女は敗軍の将として、最後の役割を果たしたのではないでしょうか。そして、この行為は、自身に未だにくすぶっていた戦を望む心をも完全に昇華させることにもなるでしょう。
さて、全てを言い終えた途端、天を仰いだ彼女は、ふっと優しい笑顔になると「茶々は…ようやりました」と満足気に呟きます。その表情はおろか、台詞も、そして声音すらも全て少女のときのものに戻ります(北川景子さんのこの変化は鳥肌ものでしたね)。今際の際に茶々は、少女の茶々に戻ります。ここで気になるのは、天を仰ぐ彼女の視線の先に誰がいて、誰に語りかけているのか、ということです。ここでは、二つの考えを述べておきましょう。
まず一つ目。天を仰ぐという行為だけを見れば、今は亡きお市と読むのは素直な読み方でしょう。前回の家康の手紙にて、お市の想いが何であったのかを思い返しましたから可能性は高いわけです。その場合、「ようやりました」は、母との約束「天下を取ります」に対して、全力で戦ったことを褒めてほしいという意味合いになり、彼女は負けたことにも満足していることになります。北ノ庄城の紅蓮の炎に消えた母が、今、同じく紅蓮の炎に包まれる娘を迎えにくる姿が、茶々の断末魔に見たものというのもわかりやすいかと思います。
ただ、個人的には、もう一つの解釈を押します。声音まで少女に戻った茶々が夢見心地に誉めてほしい人は誰かということです。それは、やはり「憧れの君」家康でしょうか?茶々は、前回のラストで「共に行こうぞ、家康!」と叫んでいます。この決意は、家康の「私とあなたですべてを終わらせましょう」と「乱世の生き残りを根こそぎ引き連れて共に滅ぶ覚悟」という家康の手紙の言葉にすがった乙女心というのが、前回note記事で触れたことです。
今、茶々は「乱世の生き残り」たちを敗者として全て引き受け、成仏させました。後は、家康が、自分もろとも乱世の亡霊たちの思いを引き受けて、「戦無き世」を見届け、そして滅んでくれるはずです。だとすれば、「ようやりました」は、家康に褒めてもらい、そして後はお任せしますという気持ちということになるのではないでしょうか。共に逝けることだけが、彼女の救いになります。
また彼女がその首を切り、自害する様は瀬名のそれとよく似ています。向きが真逆なのは、瀬名との対比でしょう。そして、彼女が自害した後のカットは、合掌し弔いの祈りを捧げる家康です。茶々の真意をしかとしらずとも、その死に安寧の世を誓っているはずで、それは奇しくも茶々の望んだ応えにもなるでしょう。
茶々の最期については、その美しさと共に様々な解釈ができそうですが、どういう解釈であるにせよ、彼女は彼女の人生を生き切り、ある種の納得をもって、昇華していったと信じたいですね。
こうして多大な犠牲を払い、乱世の亡霊たちは、燃え盛る大阪城の業火と共に消えていきます。大阪城の業火は凄まじく、京都からも見えたとか。寧々も見たと言われます。どんな気持であったのか、そこに思いを馳せるのも一興でしょう。
(5)「どうする家康」における大阪の陣とは?(2003/12/25追記)
家康の沈鬱な鎮魂の合掌、戦を回避しようとしたときは手遅れだった茶々、徳川三代の救われない心を見てもわかるように、本作の大阪の陣は殊更、虚しさが際立ちます。何故、悲劇が回避できなかったか、このことです。
お気づきの方も多いと察しますが、本作の大阪の陣は、築山・信康事件の反転になっています。この構成によって、戦の虚しさを表現しようというのが狙いだったのではないかと思われます。
具体的な両事件の対比は、人物たちによってなされています。つまり「茶々→瀬名」「秀頼→信康」「千姫→五徳」ということです。死際の母子のつながりの強さ、先ほど触れた瀬名と対比的に茶々の死に様、そして実家より嫁ぎ先を取った嫁…例はいくつもありますが、どれもよく似ていますね。
しかし、結果は真逆。徳川家は生き残り、豊臣家は滅びます。何がその末路の分かれ道だったのか。それはそれぞれの人物の言動と選択を検討すると見えてきます。
要因となった言動はいくつもありますが、ここでは一つだけあげておきましょう。それは戦に対する姿勢です。瀬名と信康は戦を嫌い、戦と罪無き者が死ぬことを避ける選択をしました(自己犠牲の善し悪しありますが)。五徳も信康の愛だけでなく、その理念に準じた面があります。
一方、豊臣の天下にこだわった茶々と秀頼は、葛藤はあったものの結局、徳川との全面対決へと進みます。精神的に幼い千姫は純情だけでそれに従うのです。それぞれの家の選択からは、戦を望む者には、それがすべて自分に返ってくるということでしょう。
ところで、大阪の陣は、家康が秀頼に恭順を迫った点からすると、小牧長久手~秀吉恭順のくだりの反転にもなっています。
つまり、秀頼は、自身が信長と秀吉の血を引くことを明言したことで、彼らがそれぞれに徳川家にしでかしたことの因果応報を引き受けることになったのです。彼自身の言動ではありませんから皮肉なことですが、戦を望んだ以上は仕方のないことでしょう。
しかし、それは家康には不幸なことですね。結果的に彼は、心ならずも、かつて信長から受けた艱難辛苦と秀吉から受けた屈辱の復讐を果たすことになってしまったからです。奇しくも、彼らが自分にしたやり方と全く同じ方法で…
つまり、大阪の陣の終結は、家康が彼らと同じく乱世を収める覇王となった瞬間でもあるのです。彼は孤独になるより他ないのですね。孤独になっていくことが避けられない家康…「どうする家康」のシナリオは、家康をとことん追い詰め、彼を心優しき哀しい覇王に仕立てていくのです。
戦嫌いの家康が覇王になり、戦嫌いゆえに自らが犯した罪を悔い、死なせた者たちの無念を思う…その運命の皮肉と因果応報が、この世の無常と無情の理となっている…ここに虚しさの原因があるのではないでしょうか。そして、彼はさらに孤独になっていきます。
(追記はここまで)
2.家康の目指した世の中にあったもの
(1)畏敬の念が家康を孤独にしていくまで
さて、「かくして戦無き安寧の世が訪れたのでございます。全ては神の君のおかげ」というお福の顕彰の言葉に合わせ、軽快ないつものオープニングが流れます。
安寧の世を象徴するのは、為政者をどう評しても罰せられない自由さにあります。秀吉ならば、自身を揶揄する落書だけで多くを殺していますからね。ですから、安寧の世では、家康を民が言いたい放題言っています。これは、「民を恐れさせるより、民を笑顔にさせる殿様のが、ずっといい。きっとみんな幸せに違いない」(第20回)の井伊直政(当時は虎松)の言葉の反映です。今回は直政が出ませんので、こうしたところに匂いがあるだけでも嬉しいですね。
しかし、あの浜松の団子屋婆さんがまだ生きていたことが、個人的には一番驚いたことです。彼女、100歳超えているんじゃないでしょうか?100歳以上生きたとされる南光坊天海もかくやという長命です。家康に直々に許可された悪口を言いまわっていますが、「大御所さま」という敬称がちゃんと付いているあたりに彼女の家康への変わらぬ敬意が窺えます。客の「情けない奴やで、わしも家康は大嫌いじゃ」「小賢しく立ち回ってかすめ取りよった腹黒い狸やさかいな」という悪口雑言にムッとしいてお盆叩きつけるのももっともです。
因みに団子屋婆さんを怒らせた二人組は、関西弁なので関西の人なのでしょう。ですから、豊臣びいきなのも致し方ないところ。おそらく、太閤殿下の人気は出身地の名古屋よりも大阪のほうがあると思います。大阪が日本第二の都市になったのは、秀吉の功績が大きいですから。万城目学「プリンセス・トヨトミ」という小説が成立するのも、その証拠のように思われます。
こうした世間の動向とは別に家康の人生を顕彰するため、徳川家中では、南光坊天海を中心に使えるエピソードの収集をしています。これが今回の家康ツアーズで流れた『東照社縁起』になるのでしょうね。天海はこの時期、日光山の貫主になっています。
それにしても、家臣らから出てくるのが、左衛門尉と数正に叱られまくった件、幼い直政に命を狙われた件とか、立派な話が全然出てこないのが、「どうする家康」を見続けた視聴者には納得ですね(笑)結局、採用された話も、稲が語った彦右衛門との別れの盃という情緒的なものです。これは、徳川家康がどこまでも感情豊かな普通の人間であったことを示しています。つまり、コミカルに描いてはいますが、天海の行っていることは、瀬名が、家族が、家臣が最も愛した家康の人間的な面を削ぐ作業であるということなのです。
そんな、度の過ぎた顕彰をぶち上げようとしている天海に秀忠は苦言を呈しますが、世間の憎悪を駆逐するためにも書かねばならないとその正当性を主張します。その天海が「かの源頼朝公にしたって実のところはどんなやつかわかりゃしねえ。周りがしかとたたえて語り継いできたからこそ今日全ての武家の憧れとなっておる」と頼朝を引き合いに出して揶揄したのは、天海役が、「鎌倉殿の13人」の主演:北条義時だった小栗旬くんで、大泉洋さんの頼朝を貶めるのが面白いというネタ要素だけではありません(こういうメタ的なネタ自体は大好きですけどね)。
後に家康が神君と称されたのは、彼が尊敬した頼朝に倣った結果だからです。つまり、この顕彰行為自体が、頼朝の真似なのですね。大本の鎌倉神君、頼朝がいい加減なものですから、当然、家康のそれも同じことになりますね。大事なことは、家康そのものを語り継ぐことではなく、彼を後の世を支える精神的な大黒柱にふさわしい人物に仕立てることにあります。まあ、大泉洋さんの頼朝にしても、そのまま鎌倉幕府の支柱になるとは思えませんしね←
ですから、この件で重要なのは、「人は誰しも間違ったり、過ちをおかしたりするものであろう」という秀忠に、天海が「人ではありませぬ。大・権・現!」と言い放つところです。関ヶ原の戦いの頃から、家康は周りから戦国最強の化け物と恐れられていましたが、それはあくまで徳川家の外からでした。しかし、家康の真実を知る者がほとんどいなくなった今、家中ですら彼の真実を見ようとする者はおらず、その実像とかけ離れた虚像が独り歩きし、あるときは恐れられ、または神として祀り上げられているのです。
視聴者がずっと見守ってきた家康の姿は、今、徳川家に都合の良い「正史」の中に埋没しようとしています。しかし、それは誰にも止めることはできません。当の家康にすら。何故なら、そうやって「正しい歴史」とやらは語られ、そこから外れるものは排除されるからです。
こうして、天下人になったがゆえに、家康には真の孤独が訪れようとしています。
そんな天海に近い立場で家康を「神の君」と顕彰し、「我らはそれを受け継ぎ、未来永劫、徳川の世を守っていかねばならぬのです」と竹千代(後の三代将軍家光)英才教育を施そうと躍起になっているのが、彼の乳母、お福です。ドラマで描かれた真実の家康とズレまくったナレーションを披露し続けたその人が、遂に登場しました。
当の竹千代が座を外し、聞いていないのにも気づかずに延々と語っていた様子からも、自分の語る英雄譚、神君家康公伝説にうっとりとしていたのでしょうね。彼女の語る「神の君」が、何故、劇中の家康から外れていくのか。それは、天海のシーンで説明されています。彼女の話の家康には、人間性が欠けていたからです。泣いて笑って怒って悩んで喜んで…そんな当たり前が彼女のナレーションからは削げ落ちています。
そんなお福の話を「終わりましたかな、結構なご高説でございました」と揶揄で混ぜっ返しながら、適当に返す正信、こいつは絶対聞いていませんね(笑)あるいは、ツッコミどころ多すぎで苦笑いしていたか、です。家康その人を知る正信が、お福の話を揶揄するのは当然ですが、その話を聞くべき竹千代までもが、「神の話なんざ聞きたかないよ」とうそぶき、絵を描いて遊んでいることが興味深いですね。
ここには、二つのことがほのめかされています。一つは「戦無き世」の申し子である竹千代は、戦の話にも興味を示さず、好きな絵を描いているということです。彼は、自分の思うままに生きている…いや、そう生きられる世の中なのです。
そして、もう一つは、竹千代が、世間の悪い噂にも、身内の過剰な顕彰にも呑まれていないということです。彼にとって、家康は敬愛する祖父という以上のことはないのでしょう。このことは、彼が物事の本質を素直につかみ取る能力があることを示唆していますが、これはその後のシーンではっきりと明示されます。
(2)家康を見送る権謀術数の謀臣たちの思いやり
さて、竹千代、お福、正信が駿府に来たのは、家康の見舞いが目的でした。体調が優れないため、股肱の臣たる正信だけが、寝室へ案内されます。正純に負ぶわれる正信も、大坂の陣後、一気に老け込んだようです。阿茶のお召し物が、喪服に準ずるような黒系になっていることに、家康の容態の悪さ、その世話をする阿茶の心痛が窺えますね。大病を患っているにもかかわらず、家康の世話をしているのは阿茶一人だと言います。
阿茶は「若い者たちは恐がって寄り付きませぬ。万が一、お世話をしているときに粗相があったり、もしものことがあった場合、いかなる処罰を受けるのかとあらぬことを考えて怯えておるのでしょう」と、泰平の世の若者たちの意気地のなさを情けなく思うような発言をします。戦場に出て、敵陣にて命がけの交渉もした男勝りの阿茶ですから、家康をただただ畏怖するだけの当世風の若者を不甲斐なく感じるのは当然でしょう。
しかし、理知的な阿茶は「もっとも誰もが神の世話をしたくないのが道理かもしれませぬ」と彼らを庇うような言い方もします。家康の後半生にずっと寄り添った阿茶だけが、力をもってこの世を平らげた天下人の宿命が孤独であることを、家康の苦悩から感じ取っています。
阿茶と正純は、家康と正信の対面が最後になるかもと察し、彼らが二人きりになるよう気遣います。正信は「殿、殿」と呼びかけますが、家康から返事はありません。病状が思わしなく、深い眠りについていると察したと正信は、彼の枕元に座ると今生の別れとばかりに「わしのような者を信頼してくださり、深く深く感謝しております。わしも、すぐに参ります。ま、ご迷惑かもしれませんがな」と自虐的ではあるものの偽らざる思いを素直に告げます。
騙り者の策士、本心を押し隠す口八丁の道化者を貫いてきた本多正信が、他の家臣団に劣らぬ家康への熱い思いを口にするこの瞬間は感慨深いですね。彼が家康に本気の本音を語ったのは、三河一向一揆で家康を罵倒したあのとき(第9回)以来ではないでしょうか。まあ、ひねくれ者の彼ですから、家康が寝入っている、誰にも聞かれないと思ったからこそ言えたのでしょうけど(笑)
家康を痛ましく見ながら礼を述べる彼の視界に入ってきたのは、病み、やせ衰えた家康の両手です。どんなに若作りをしても、手だけは年齢を隠せないとはよく言われますが、家康の手には長きにわたる苦労と葛藤が、その歳月と共に刻まれています。家康の人生そのもを象徴していると言ってもよいでしょう。だから、正信はその手にこれまでの家康の辛い人生を見て取り、思わずその手を握り締めると、万感の思いを込めて「殿…長きにわたり、まことにご苦労様でございました」と労います。
果たして、家康、起きたのか、それとも起きていたが辛くて反応しなかっただけなのか、そんな正信の労いに対して、その手を握り返します。家康の握り返しと力ない薄い微笑みには、長年の謀臣に対する感謝、そしてようやく彼の本心が聞けた安堵があるように思われます。本音を聞かれてしまった正信ですが、家康のその反応を逆らわず受けています。正信にとっても、最後の対面でわずかでもやり取りができたことは感じ入るものがあったのでしょうね。
二人の心が静かに通じ合った瞬間の静かな間が味わい深い一幕です。
対面が終わり、廊下を並んで歩く正信と阿茶。阿茶の「天が遣わした神の君、あるいは狡猾で恐ろしい狸、いずれにしても皆から恐れられ人に在らざる者になってしまわれた…」との言葉には、彼の側にいながら彼が畏敬の存在にされていくのを止めようがなかったこと、敬愛する男性が手の届かない遠くにいってしまった現実…彼女ならではの苦悩が窺えます。
家康への深い思い、助けてあげられない無力感から、立ち止まってしまった彼女は、涙声で「お幸せだったのでございましょうか?」と、抑えていた哀しみを、家康の無二の友となった正信にぶつけます。
正信は、縁側を向くと「戦無き世をなし、この世の全てを手に入れた。が、本当に欲しかったもの…ずっと求めていたものは…」と静かに語りながら、その結論を濁します。我が身を世のために犠牲にし、自身の幸せは何ひとつ手に入らなかったという言葉は、あまりにも無残で、可哀想で口にできなかったのでしょう。その言葉の代わりに、憐れむように静かに合掌します。
聡い阿茶にはそれだけで十分、理解できます。涙を一筋流し、沈鬱な表情を浮かべます。彼女は、今回の冒頭で例の「祝言の鯉」話を聞いています。だとすれば、阿茶は、その話だけにある楽しげな思い出こそが、彼の欲しかった幸せだと察したのではないでしょうか。しかし、それは過去です。二度と戻ることのないその時間は、決して手に入りません。
家康が、手に入らない幸せを求め、深く傷つき、苦悩し、そして孤独にこの世を去ろうとしているのだとすれば、これほど哀しいことがあるでしょうか。彼女には、家康のために涙を流してやることしかできません。
思えば、阿茶は、若かりし家康と共に過ごした瀬名や充実の壮年期の家康と過ごした於愛と違い、盛りを過ぎ徐々に衰えていく家康と共にいた女性です。家康の孤独と苦悩を見守り、それを看取る阿茶の心中を思うと、それもやり切れませんね。
こうして暮れゆく中、カメラは家康を思う二人の寂しい背中を捉えます。どこからか響く鐘の音は鎮魂のニュアンスがあります。謀臣、二人が家康を看取る…このこと自体が、家康の侘しい最晩年を象徴しているかもしれません。
(3)瀬名と信康の褒め言葉を自虐で返す家康の深い傷
元和2年4月17日、遂に訪れたその日…
家康は、暗がりの病床にて手慰みに象を彫っています。一心に彫るときは様々を忘れられるのかもしれません。因みに象がチョイスされたのは、日光東照宮の「想像の象」(狩野探幽)をスタッフが意識したからでしょうか?遺品の彫りかけを見た家光が後の大造営で彫らせたかも…と思わせますが、彼が東照宮という涅槃に入りかけているということも含んでいるのかもしれません。
あるいは彫っているのが獏をいう可能性もあります。その場合は久能山東照宮の楼門の獏の彫刻です。獏は鉄を食べると言われています。獏が鉄を食べられる世の中は鉄が武具に使われないほど平和ということになります。だから、家康の安寧の世への願いということになりますね。
病み衰え彫りにくそうに彫る家康を「殿…殿…」とどこからか呼ぶ声がします。一心に彫る家康は気がつきません。不意に病床に光が差し、我に返ると…
「もう出ていっても良いかしら?」と奥の襖を開けて、瀬名が出てきます。呆気に取られ彫りかけの象を落とす家康…まあ、そりゃそうでしょう。目の前で非業の死を遂げた亡妻が、かの日の姿のまま、何事もなかったように現れ、彼に微笑みかけているのですから「瀬名…」と呟いたままあんぐりするのも無理はありません。
驚く家康の前に「あぁ、くたびれた。、もう隠れなくてようございましょう」と笑顔で姿を現すのは、若々しいままの信康です。にっこり笑い、家康の前に居住いを正して座る二人は、彼がずっとずっと会いたかった、失われ二度と戻らない最愛の家族です。それが目の前にいます。思わず「お前たち、ずっとそんなところに」とわずかになじる気持ちが混ざるのも仕方ありませんね。
特に家臣団がほぼいなくなり、天下人としての孤独、老境の無力感を深めていたここ数年の辛さは筆舌に尽くしがたかったはずです。一番、辛いときに何故出てきてくれないのか、とも言いたくなるでしょう。とはいえ、「瀬名はずっと見守っております」(第25回)が、こういう形で回収されてくるとは、思いませんでしたね。本当に側で見守っていたとは。
ひたすら唖然とする家康をよそに、どうやら霊となって家康をずっと見守ってきたらしい二人は、家康に言いたかった労いの言葉をかけます。
まず、信康の「父上、戦無き世、とうとう成し遂げられましたな!」との言葉は、志半ばで頓挫した瀬名の慈愛の国構想が前提にあります。信康は自害したとき、「わしが徳川を守ったんじゃ。見事役目を果たしたんじゃ。父上にそう伝えてくれ。」(第25回)と叫びました。彼は、自身の自害によって、敬愛する父を守りその夢を託したのです。
ですから、自分の死を忘れることなく、報いてくれたことに感謝するのです。勿論、「人を殺したくない」彼にとっても、「戦無き世」は悲願であったのは言うまでもありません。
続いて、瀬名は「ようやりました。私の言ったとおりでしたでしょ。成し遂げられるのは殿だと。ご立派なことでございます」といつになく褒めそやします。生前でも、瀬名がここまで家康を褒めたことはないのではないような気がします(笑)ただし、「私の言ったとおりでしたでしょ。成し遂げられるのは殿だと」の言葉は、自害に及ぶ前に家康に伝えた「厭離穢土 欣求浄土」も「貴方なら出来ます、必ず」を回収したものです。
因みに彼女が、家康ならば「戦無き世」を実現できると確信をもって伝えたのは、彼が戦嫌いの泣き虫弱虫洟垂れの白兎だからです。「いいですか、兎は強うございます。狼よりずっとずっと強うございます。」(第25回)という励ましの言葉が思い出されるでしょう。自分の弱さを知るからこそのしなやかな強さを、彼女は信じたのです。
この瀬名の言葉をしっかり理解した家康は、晩年、秀忠の美徳を「弱いところじゃ。そして、その弱さをそうやって素直に認められるところじゃ」(第45回)と語り、自身の志を彼に引き継ぎましたね。このことは、家康の中で瀬名の思いが確実に活かされ、「戦無き世」の実現へとつながったということを意味しています。
つまり、家康は、正しく、死んでいった多くの人々の願いを胸に刻み、彼らの思いを昇華させるように「戦無き世」を実現させたのですね。だから、二人は家康のなしたことを心から労うのです。
そもそも、家康が「戦無き世」の実現のために天下取りを目指す決意をしたのは、瀬名と信康の無念の死がきっかけでした。それは、瀬名に志託されたことが大きいのですが、それと同じくらいに自身の不甲斐なさが許せなかった思いも強くありました。だから彼は力をつけ、知恵をつけ、弱い白兎を押し隠し、強くなりました。
しかし、それは正しかったことなのか…今となっては自身がありません。強くなった結果、彼自身が乱世の怪物となって、戦の元凶になってしまった事実があるからです。
秀忠にも自身の白兎としての弱さについて、「戦乱の中でそれを捨てざるを得なかった。捨てずに持っていた頃のほうが…多くの者に慕われ、幸せであった気がする」(第45回)と自虐的に語っていましたね。
更には、乱世を終わらせるために、家康は、結局、覇道を選び、力をもって多大な犠牲を払うという選択をしました。殺したくもない多くの人々を、彼は皆殺しにしました。家康は、茶々・秀頼は勿論のこと、大阪城に集った牢人たちも殺したくはなかったでしょう。
にもかかわらず、人殺しの業と罪を背負う覚悟をし、実行しました。そのこと自体に今更後悔はないでしょうが、千姫に言われたとおり「鬼じゃ、鬼畜じゃ」である自覚もあるのです。
元々、瀬名たちの死を無にしないための「戦無き世」の実現でした。ですから、二人の労いは、本当は家康が一番かけられたかった言葉だったはずです。しかし、「戦無き世」への道筋のため、彼自身はそれに最もふさわしくない人間となりました。実現したにもかかわらず、皮肉にもその言葉を受けることができないのです。
二人の真っ直ぐな心からの労いを直視できない家康を、カメラは右斜めからミドルショットで捉えます。こうすることで、家康の哀しみを表現しているのです。彼は己の罪深さから、「立派なことなんぞ、やってきたことは…ただの人殺しじゃ」としか返せません。「ただの人殺しじゃ」だけ、家康の顔のアップのショットになるのは、彼が自分の罪に深く傷ついていることを強調するためです。
家康は「あの金色の具足を着けたその日から、望んでしたことは一つもない。望まぬことばかりを、したくもないことばかりをして…」と、自らの人生が望まない戦ばかりの人生であったことを愚痴とも後悔ともつかないように続けます。これは、第45回で「昔のことばかり思い出す」と言った家康の脳裏に戦しか浮かんでいなかったことに呼応し、彼がいかにして乱世の怪物になっていったかを象徴しています。
しかし、乱世に戦国大名として生まれた彼には、これ以外に生き延びる選択肢はなかったのです。そして、そうやって生きてきた彼の犠牲になった命も数多ありますが、一方で救われた命があるのは第45回で氏真が言ったとおりですし、また第37回で家臣団の家康への感謝もそうしたことの一例です。自身の人生を振り返り、後悔と絶望しかない彼は、そのことを忘れてしまっています。そんな哀しい呟きをするだけの家康を瀬名は、静かに見つめ言うままにさせています。今は、まず家康の心の溜まり切った澱みを吐かせるしかないからでしょうか。
そこへ紙人形を持った竹千代が絵が上手く描けたからと見舞いの品のように持ってやってきます。病床の家康を気遣い、御簾を少し上げ、絵だけを差し入れようとするのですが、家康の元に訪れている二人の人物に気づき、不思議そうな顔をします。そして、信康と目が合った竹千代は軽くお辞儀をすると、家康たちの邪魔をしないようにその場を去っていきます。
実は瀬名と信康の登場は、家康の今際の際の妄想かとも思われましたが、竹千代の反応によって真面目に彼らの霊魂であることが確定したようです。ファンタジックな展開と笑うには当たりません。過去の大河ドラマでは「八代将軍吉宗」(1995)のように、最終回に死後の世界を描いた作品もありましたから、こういう展開も無問題です(笑)
竹千代と目が合った信康は、彼に縁を感じたからか「不思議な子でございますな…」と呟きます。
家康は「竹千代、跡継ぎじゃ」と彼の去ったほうを見つめながら答えます。そう、かつて竹千代(家康)が、かつての竹千代(信康)に、今の竹千代を紹介するのです。三人は「竹千代」という幼名でつながっているのです。
三代にわたる竹千代が揃うというドラマは、おそらくないでしょうね。単なるファンサービスではなく、「竹千代」という名をとおして、親、子、孫と「戦無き世」の思いはずっと、そして確かに紡がれていくことを暗示しているのです。家康の孤独で終わるものではないのです。
ですから、瀬名は「初めてお会いした頃の誰かさんにそっくり!」と言うのです。更に「あの子が鎧をまとって戦場を出なくてよい世の中を貴方さまがお作りになったのでしょう」と、家康が救った命、そして自分のなしたことが何かを改めて、指し示します。瀬名の言葉に破顔する信康の爽やかさが、家康のなしたことを肯定していて良いですね。彼は自分の思いが、今の竹千代の中で生きていることを感じたのかもしれません。
瀬名は「あの子があの子のまま生きていける世の中を、貴方が御生涯をかけてなしたのです」と家康の人生が無味乾燥なものではなく、意義のあったものであったと総括します。瀬名の優しい言葉に、家康は既に涙目です。ようやく、彼が本来の白兎に戻りつつあるのを認めた瀬名は「なかなかご立派なことと存じますが?」と今度はいたずらっぽく、家康を褒めます。
そこへ竹千代が差し入れた絵を拾い上げていた信康が、瀬名にそれを見せます。瀬名は破顔すると「存外、見抜かれておるかもしれませぬな。あなたが狸でもなければ、ましてや神でもないということを」と見せたその絵は兎でした。竹千代(家光)は、素直に育ち、物事を惑わされることなく捉え、そして戦ではなく芸事を愛する優しい子に育っています。徳川家は、家康が望む跡継ぎがいます。
また、竹千代のように、家康の真実を見、理解しようとする心ある人々が、今後も出てくることも暗示しています。多くの者がいなくなり、理解者もいなくなった家康は孤独感に押しつぶされそうでしたが、決して孤独ではないのです。彼の思いを受け継ぎ、「戦無き世」を指向してくれる人たちがどこかに必ず現れるはずだからです。メタ的に言えば、その理解者は「どうする家康」のスタッフであり、この作品を見て愛した視聴者も含まれるかもしれませんね。
竹千代は、絶望した家康に遺された「希望」の象徴だったのではないでしょうか。自分の人生に意味があり、自分の目指した世界は間違っていないという希望を知った家康は、滂沱の涙を溢れさせています。乱世の怪物は、ようやく「泣き虫弱虫洟垂れ」の家康に戻れました。瀬名は優しく「皆も待っておりますよ、私たちの白兎を」と、彼にこの世を去るときが来たことを告げます。彼らがここに来たのは、彼を迎えに来たのですね。
それにしても、家光の絵が効果的に使われましたね。近年、家光直筆の絵が発見されました。その中には、この絵ではありませんが、兎もあります。新発見を巧みに織り込み、家康の心を救うとは、粋な計らいですね。
(4)「祝言の鯉」が何故、家康の理想なのか
瀬名の皆が待っているとの言葉と共に、場面は暗転します。再び、暗転が解けるとき、それは家康が目を覚ました瞬間の主観の映像です。寝起きの彼の目線にあるのは、若き日の彦右衛門と七之助です。寝ぼけていた家康ですが、二人に今日が信康と五徳の祝言であることを知らされ、良き日に気分をよくします。眼前では、五徳との婚姻を嫌がる信康が逃げ回っていますが、これも日常の一部と微笑ましく家康は見ています。とはいえ、大事な息子の祝言に居眠りをしていたとは、太平楽というか、呑気というか(笑)
なんにせよ、今日は、劇中、度々出てきたあの「祝言の鯉」の話の日なのです。家康が楽し気に話すあの日は幸せな思い出そのもの…のはずですが、いきなり不穏です。というのも、二人の祝言のために美濃攻めの忙しさの合間を縫って自ら選び、徳川家に送った三匹の鯉が行方知れずになったためです。
家康は鯉が来た日のことを思い出します。ここで秀吉(当時は木下藤吉郎)が使者として表れるのが興味深いですね。この頃の彼は金ヶ崎よりも前ですから、まだまだ家中では小者ですし、家康との確執もありません。
秀吉は大中小の鯉がそれぞれ信長、家康、信康を指すのだと説明すると「なんとまあ、ありがてぇこってございませぬな」と祝うのですが、例によって例の如く、帰り際、真顔で「鯉の身になにかあったらわしゃ知らんで。気ぃつけやぁせ」とプレッシャーだか忠告だかわからないことを言うと、自分がつけていた花を家康に挿すと去っていきます。
毒のある物言いは、秀吉の家康への複雑な思いがあるのですが、死ぬ間際の秀吉は、本心で裏表がない家康が好きであったと言っています。ですから、この忠告も家康を気にかけてのものだったと考えてよいでしょう。だから、この日の思い出の二人は、良き時代のものです。
因みに信長は自ら鯉を選ったことからもわかるように、唯一の友である弟分と親戚になることを喜んでいるのが本心です。ですから、この日は幸福であったはずです。
もっともそれは鯉が行方不明でなければの話です。非常事態の中、既に鯉が捌かれていた、信長が祝言にやってきそうだなど不味い情報だけが家康に持ち込まれます。於大と台所の女房衆は、あからさまに何か知っていますが、いけしゃあしゃあと知らぬ存ぜぬを決め込みます。
台所に落ちた笄(こうがい)から平八郎を問い詰めますが、わざとらしく居直るばかりで小平太も取り合いません。夏目広次と忠真の元へ行った際は、例によって「広信!」と間違えるのですが、謝りつつも「それはどうでもいい」とうっちゃってしまいます…今考えても、家康、酷いですね(笑)
しかし、これらのわちゃわちゃ感…今となっては懐かしい限りですね。ろくでもないことが起こって家康が慌てて家中を練り回るというのは、岡崎の頃の徳川家中の平和な日常そのものでした。それは、家康が優しく弱い白兎でいられた「多くの者に慕われ、幸せであった気がする」(第45回)時代です。晩年の家康の本心は、ずっとこの時代に帰りたかったのでしょう。
結局、鯉に目がないという鳥居忠吉が呼び出され、家康は鯉を食べたか、否かと問い詰めます。しかし、老獪な爺である彼は「宝物を食うたりはいたしません…たぶん」「食うてはおりません…と思います」と要領の得ない返事ばかり。いやはや、この辺りのテンポのよいはぐらかしは、イッセー尾形さんの真骨頂ですね(笑)
業を煮やした家康は遂に太刀を引き抜くと「はっきりせい、もし食うたんなら…成敗せねばならん!」と凄みます。織田家との同盟すら危うくするこの事態に家康は真剣になっているのですが、家臣団らを見ると誰一人、動じていないんですよね(笑)全然、家康のこの様を怖がっていない。
いよいよ、忠吉爺は「食った…食うたかもしれません。きっと食った。食ったんじゃ」と相変わらず、はっきりしないことを言いながら、座り込むと「誰かが首を差し出さねばならんのなら、この老いぼれお願い申し上げる」と首を差し出します。既に信長到着の報もあり、切羽詰まった家康は、いよいよ斬ろうとするのですが、結局、太刀を下ろしてやめてしまいます。
止めた理由が「大事な家臣を鯉と引き換えにはできん」というのが家康らしいですね。三河一向一揆以降の彼は、何が何でも家臣と領民を信じ守りたいと誓っています。その心に嘘はないのです。
左衛門尉と数正は宿老らしく、信長とトラブルになったらどうするかと問うと、彼らに背を向けた家康は「そんな相手なら縁組みなんぞこっちから願いさげじゃ!」と不貞腐れたように開き直ります。家康は初期の頃からそうなのですが、臆病で弱虫な割に窮鼠猫を噛むというか追い詰められると大胆でそれでいて正しい判断をするところがあります。この点を家臣たちが信頼していたことは、第37回でも語られています。
「どうする家康」全般で語られた家康の美徳や家臣とのつながりが、この過去に集約されているのが興味深いですね。セットや役者の都合を考えれば、このシーンは、岡崎城のセットが組まれていた初期に撮られていると思われます。それを最終回に持ってきて、これまでのシナリオと呼応っせているのですから、古沢良太さんがかなり綿密に話を組んでいたと察せられます。
さて、家中のトラブルが政治的にも収まったように見えるところを見計らったように、忠吉がおどけるように「では鯉を食うてもお許しくださるので?」と急に角度の違う質問をしますが、その変化を読めない鈍い家康は、相変わらず不貞腐れたように「鯉は所詮、鯉じゃ。食うて何が悪い」と吐き捨てます。どうにでもなれ、という気分なのでしょうね(笑)
家臣たちは、この家康の言葉に「お言葉いただきました!」と声を出さず笑いあうと、宿老である左衛門尉が率先して「その言葉、待っておりました」と思わぬ声を家康にかけます。流石に「ん?」と振り返った時は手遅れ。於大が「よう申した、家康!皆の衆、殿のお許しが出たぞ」と女房衆を呼びつけ、それは見事な鯉の洗いが眼前に広がります。
やっと食えるという家臣たちのワイワイした言葉に、それぞれのキャラクターが出ていますね。左衛門尉は「これで晴れて鯉が食べられますな」と一同に呼びかけますし、数正の「こんな見事な鯉、食わない手はありませんからな」は…あー、これだけは松重豊さんの当たり役「孤独のグルメ」の井之頭五郎ですね(笑)鯉に目のない忠吉は「よだれがとまらんかった」。普段から織田家の圧迫を快く思わない平八郎は「何が宝物じゃ馬鹿馬鹿しい」、彼に追随する小平太は「信長に媚びへつらうならまだしも信長の鯉までへつらっていられるかよ」と少し理屈っぽいのが可笑しいですね。
左衛門尉に「まんまとかつがれましたな」と言われ、ようやく家康は、息子の祝言の日に家中総出で騙されたことに気づきます。しかも、来るはずのない信長が来るとまで思いこませるという念の入れようが、ひど過ぎますね(笑)
信長が来ないとわかり「良かった~」とへなへな座り込んでしまう家康ですが、「よくないわ!バカにしおって。主君を一同でからかうとはなんという家臣どもだ」と怒るのですが、いかんせん若いときの家康って貫録がない上に声も高めなので、迫力がないんですよね。ですから、忠吉爺に「殿、それが殿と家中の良いところじゃ」と悪びれもせずに返されてしまいます。しかし、三河一向一揆以降の彼らのつながりの核心をついた言葉であるあたりが流石です。信長が第27回で評した友垣のような関係です。
忠吉の言葉に思わず「もしわしがあのまま手打ちにしたらどうするつもりだったんじゃ」と問う家康に対して、穏やかに微笑した小平太は「左様なことはなさらぬと信じておりました」と答えます。名コンビである平八郎は小平太の言葉を引き取るように「皆、ようわかっておるのでござる、殿というお人を、そのお心を」と彼らしく真面目に答えます。
家康の弱く優しい白兎の心を皆がよく知り、それを受け入れ、信じていることを、家臣らから直接的に聞くことはありませんから、驚きます。しかし、彼らを裏切られても信じ抜くと覚悟している彼にとって、自分を信じていると応えてくれたことはこれほど報われることはありません。また、徳川家が一つの家だと感じられた瞬間だったはずです。ですから、家康は、彼らの言葉を噛みしめるような表情を浮かべます。
ここで、駿府の現在の家康が同じくシンクロしたように微笑みます。つまり、この「祝言の鯉」の場面は、家康の回想であり、同時に死出の旅路へ旅立とうとする家康の今際の際に見た夢でもあるのですね。最も幸せだったあの日こそ、彼が心から求めた日だったと改めてわかりますね。それは家臣団に担がれるという結構、最悪なエピソードなのですが、その裏にあった、家臣たちの日常的な信頼、そして彼を崇め奉るのではなく「友垣のように扱う」その主従を超えた対等な関係性の心地よさ、それを実感した日でもあったのですね。
さて、話はまた過去に戻ります。家臣たちは次々と家康に礼を述べていきます。そのことに感じ入る家康は涙が一筋、自然と流れます。そして、これからも共にある、支えると言ってくれる家臣たち…この様子には既視感がありますね。そう、第37回で三河家臣団が解散する際の家康と家臣団の別れのシーンです。あの場には、病の左衛門尉、出奔した数正、戦死した夏目広次がいませんでした。逆に、この場にはまだ直政がいませんし、また追放中の正信、まだ武士と認められていない半蔵がいません。
つまり、この回想と第37回の別れの場面、この二つをもって家康と家臣団全員との関係性が何かを描いたのですね。ですから、今回の家臣の感謝のとりは数正になっています。そして、第37回と同じく家康は「こちらこそじゃ」涙し、居住まいを正すと「心より感謝申し上げる」と一礼します。互いを思いやり、それに素直に感謝できる友垣のような関係こそ、家康にとって得難い宝だったのでしょう。
そして、この一礼をシンクロしている現在の家康もしています。そこへ「お幸せでこざいますな、殿」と瀬名が呼びかけます。老いた家康はその声に振り返りますが、その視線の先にあるのは、あの日の瀬名です。思い出の過去、今際の夢、そして霊魂として彼を迎えにきた瀬名、全てが一致したとき、彼は全てに納得したように「そうじゃな、わしは…幸せ者じゃな」と応えると、眠るように座ったまま逝きます。その彼を一筋の光が射しています。
結局、現実の彼は孤独なまま死んだため、救われず報われなかったと見ることもできます。だから、思い出の中で救ったと…しかし、彼が本当に欲しかったもの、求めたものは二度と戻らないあの日だったのです。それはどんなに「戦無き世」を築こうとも手に入ることはありません。ですから、この救われ方こそ、彼にふさわしいものであると言えるでしょう。託された人々の安寧の世への願いを現実に叶えながらも、彼自身は失われたあの日を希求し続けたのだとしたら…徳川家康という人はかなりロマンチストだったのかもしれません。
おわりに
それは過去か、涅槃か…信康と五徳の祝言は佳境を迎え、皆が楽し気に海老すくいを踊っています。信康はおろか、嫁にきた幼い五徳も共に皆と踊っています。今日だけは現実を忘れ、全力で祝いを楽しむ彼らに瀬名は「なんと良き光景でしょ…こんな良き日は二度ありましょうや」と微笑むと「まるで戦などないみたい」と話しかけながら、家康に酒を注ぎます。瀬名の言葉に応じるように「わしがなしたいのは、今日この日のような世かもしれんな…」と満面の笑みを浮かべます。
「是非とも貴方さまが作ってくださいませ」という瀬名のおねだりに「わしには無理じゃ」と家康はあっさり首を振ります。しかし、瀬名もわかっていたのか「ただの白兎ですものね」とからかい、家康はそれに腹を立てるでなく「そうじゃ」と破顔します。ここの二人の会話は、初回の家康の出陣に際しての二人の会話によく似ています。家康の弱さを愛する瀬名と自身の弱さを受け入れている家康というこの夫婦にしかできない会話ですね。だから、初々しく微笑ましいのです。
穏やかな夫婦は、楽し気に踊る彼らの姿にこそ、平和を見て「わしは信じるぞ、いつかそんな世が来ると」と語りあいます。
そんな夫婦の眼前には、未来の江戸…東京が広がっています。彼らがまだ見ぬ将来に思いを馳せているのか、それとも今、涅槃にて彼らが静かに現在の私たちを見守っているのか、その解釈は視聴者に委ねられています。
しかし、家康が「祝言の鯉」のあの日を理想郷と考えている一端は、このラストシーンにあるだろうと思われます。一つは先に述べた「互いを思いやり、感謝できる対等な友垣のような関係性」に中にこそ家康は、自分の存在意義を見出せるからです。
そして、もう一点は、この頃の家康にあって、老境の家康が見失ってしまったものです。それは、今は酷い世の中であっても「いつかそんな世が来る」と遠い将来に希望を抱けたことです。あの時代は徳川にとっては、武田の脅威もあって大変な時代だったはずです。にもかわわらず、あの頃に思いを馳せられるのは、きっと明日はよい日になる、よい日にしてやろうと未来に希望を抱き続けた時代だったからです。
家康が自分のなしたことを素直に受け入れられたのが、孫の竹千代という希望であったこと。そして、そのことがあの世へ旅立つことを受け入れた瞬間であったことも、このことに呼応しているでしょう。家康は竹千代をとおして、将来の江戸幕府が築く「戦無き世」の希望を見たのではないでしょうか。
このように考えていくと、ラストシーンが現在の私たちの時代へとつなげられたことは、今の私たちに多くのメッセージを投げかけているように思われます。
まず、家康たちが抱いた「戦無き世」という途方もない夢と志を、現代へ紡ぐ、あるいは投げかけたということです。ロシア×ウクライナ、イスラエル×パレスチナといった分かりやすい戦争だけでなく、世界には多くの戦争とその火種が燻っています。その大本になる貧困の問題も未だ解決していません。こうした中、安易に戦争を外交手段と認めて運用しようとしていないか、あるいは弱肉強食を肯定し、自己責任の名のもとに強い者が弱い者を虐げることを当たり前と思っていないか、など私たちの日々のあり方を問いかけているのではないでしょうか。
特に「どうする家康」では、戦争の持つカタルシス、武将たちの英雄性については徹底して否定的に描いてきました。また、自己犠牲的に死んだものたちについても、単なる美談にせず、その虚しさや愚かさについても気を配っていましたね。そして、女性や庶民といった大枠の歴史に埋もれ、見過ごされる弱者の物語を積極的にすくい上げようとしたことも特徴的でしたね。本作の「戦無き世」への願いは強いものでしたね。
そしてもう一つは、こういう悪いことばかり起きている現代において、人々が見失っていることは、希望を持つということです。こうありたい、こうしたいと希望を持つからこそ、それを叶える努力をするものです。しかし、そんなことは無理だと挑む前から諦めてしまっている面が、ないでしょうか。あるいは、理想に燃える人、無茶な希望を抱く人を嘲笑ってはいないでしょうか。
例えば、瀬名の「慈愛の国構想」は稚拙なものでしたが、それを実現不可能な夢物語と単純に冷笑的に見下すことは、希望を抱かず、諦めていることと同じです。家康は上手くはやれませんでしたが、少なくとも理想と現実を近づけようと努力しましたね。そこで、家康が見せたのは、自分自身だけは汚れることも辞さない、清濁を呑み込む覚悟でした。そして、それでもできなかった夢を次代に託すことで希望を遺しました。
大切なことは一人一人が、将来に希望を持ち努力すること、そして、その希望を次につなぐことなのでしょう。横のつながり、時代という縦のつながり、そうして連綿と「戦無き世」を希求する不断の努力をし続ける以外にないのかもしれませんね。
因みに家康の辞世の句の一つは、「嬉しやと 再び覚めて 一眠り 浮世の夢は 暁の空」というものです。大意は「もう起きることはないと思っていたが、また起きられて嬉しい、もうひと眠りしよう。この世は明け方の空のようだ」となりますが、どうでしょうか。彼は死を目の前にしても、明日への希望を持っていたと言えるのではないでしょうか。
私たちも、いつでも希望を忘れないようにしたいものですね。そうでないと、涅槃から瀬名と共に私たちを見守る家康にがっかりされてしまいますから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
