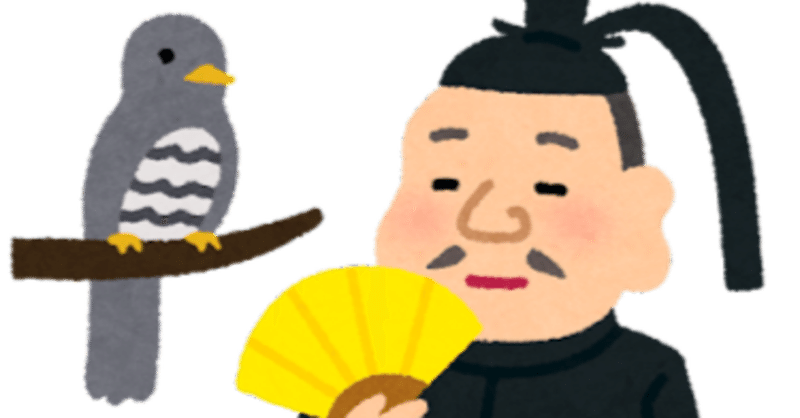
義元の遺言を氏真から託される家康~家康と氏真、義兄弟設定の理由~
はじめに
第12回「氏真」はタイトルどおり、氏真の君主然としても溢れ出てしまう家康への嫉妬、自身への絶望が強烈で、それだけに憑き物が落ちた最後の安堵と放心の表情が印象的でしたね。溝端淳平くん自身の若い頃の体験や思いを重ねたという演技は、確実に視聴者の心を揺さぶったのではないでしょうか。
ここで気になるのは、何故、氏真は「父親の愛情に飢えた若武者」として描かれたかということです。旧来的な公家趣味の「軟弱な暗君」という氏真のイメージは、後世に作られたものでしかありません。実際は優れた教養人であったことは、残された和歌からも察せられます。また武芸においても塚原卜伝に新当流を学んでいました(武術関係者では古くから知られています)。
初登場時に元康と棒術稽古をしていたことは、従来イメージを史実に基づいて塗り替えていますね。しかし、一方でやはり家臣を信じない暗君になっていきます。この狙いはなんでしょうか。
そして、このことは「どうする家康」では、野村萬斎さんという名優を据え、やたらと名君として描かれる今川義元にも言えることです。近年の義元は海道一の弓取りに相応しい武将として描かれることが多くなりましたが、一方で本作では彼を名君たらしめた母:寿桂尼と軍師:太原雪斎の存在が徹底的に無視されています。
この点は、古くからの大河ドラマファンや戦国時代ファンにはかなり不自然に映っているでしょう。特に太原雪斎は竹千代の師匠でしたから、登場して当たり前のところがありました。だから、彼らを敢えて出さず、回想で美化された名君、義元を何度も登場させることには「どうする家康」ならではのドラマ的な狙いがあると考えられるでしょう。
そこで今回は、今川義元と氏真親子のキャラクターが果たした役割から、第12回を読み解いてみたいと思います。
1.極まっていく氏真の孤独と焦燥
氏真の抱えた想いの正体は、第6回「続・瀬名奪還作戦」終盤で、偉大なる父、義元へのコンプレックスであることが明かされています。偉大な父に認めてもらえない、父からの愛情に飢えている孤独感が、家臣への不信につながり、余計に彼を追い詰めていきます。彼の父への敬愛の深さは、竹千代(信康)の「父上」で彼らを背中を撃つことを止めたこと、氏真が義元の具足と向き合う場面によく表れていますね。
そして、この氏真の姿と対照的なのが家康です。彼は義元から直々に期待をかけられ、初陣で重要な役割を与えられています。また氏真の思い人だった瀬名と結ばれ、子をなしました。更に家康とその妻子のために命をかける家臣もいます。
家康と氏康が反転しているけれど似た者同士であることは、以前のnote「「どうする家康」において、三河一向一揆とは何だったのか」でも触れたとおりです。氏真は、どうしても家康が気になって気になって仕方がないように作られているのです。
こうした氏康の抱えた今川家滅亡を前にした焦燥感と家康への嫉妬を端的に表すのが、アバンタイトルの回想シーンです。ここでは駿府では珍しい雪の降った日、身分にかかわらず、皆、雪に戯れはしゃいだ美しい過去が展開されています。そこでは、氏真は家康と稽古の手を止め笑い合い、瀬名と田鶴も互いに飛び回っています。義元すら無邪気に喜び、庭へ駆け出す始末(笑)皆が仲良く過ごしたあの幸せな日々です。
しかし、この回想では無邪気な義元のカットの直後に槍に首を括りつけられたカットが挿入されます。そして、笑い合う関口氏純・巴夫妻のカットの後には彼らの処刑が決まったシーン、喜ぶ田鶴のカットの直後は田鶴の壮烈な討ち死にが、それぞれ挿入されます。美しく幸せな思い出が無残な現実に打ち砕かれていくという悲壮さを抱えているのは、駿府を落とされる氏真しかありません。だから、この回想は氏真のものです(彼に近しい人物で構成されている回想ですしね)。
ここに止めを刺すように、陣ぶれを出したはずが岡部以外の家臣は参上していないという見捨てられた現実と駿府陥落が挿入されます。ひらすら悲惨な現実と誰も自分を理解しない孤独だけが氏真を襲い、荒れ狂い、岡部の進言どおり自害を一度は覚悟します。このとき、自害を押しとどめるのは、義元の言葉「お前に将の才はない」という一言です。
このきっかけは、とても重要です。氏真の駿府を落ち延び徹底抗戦する理由は、今川家という名家のプライドでもなく、駿河の盟主という自覚でもなく、まして家臣や民を慮るでもなく、父から認められたかったから将としての実力を証明したいという子どもじみた私情なのです。その私情がいかに内向きであるかを示すために用意されたのが、志田未来さん演じる早川殿(劇中では糸)です。史実にはない足が悪いという設定は、「足手まとい」と氏真が彼女を邪険にする材料として扱われます。この邪険は政略結婚で結婚させられた相手への気遣いの無さであり、また想い人(瀬名)と添い遂げられなかった未練でもあり、一事が万事、彼が自分のことしか考えていないことを証明しています。
ここで思い返すのは、義元の台詞「民に見放された時こそ、我らは死ぬのじゃ」(第7回「わしの国」)です。以前、noteで指摘したことの繰り返しになりますが、三河一向一揆編とは、家康が義元のこの言葉の真意を実践から体得し、家臣との信頼関係を築く話でした。そこで必要なことは「騙されようとも自ら家臣や民を信じるしかない」ということです。言い換えるなら、義元が説く将が将たる理由とは、家臣や民との信頼関係を築けることなのですね。
ですから、この徹底抗戦の決意と逃亡劇の時点で、彼に将の才がないことを自ら証明してしまっています。更に早川殿の北条家への亡命という手段を突っぱねるのも、やはり将としての才を示すという私情のためでした。彼女の足の悪さは、必死に氏真を追い慕う気丈さを分かりやすく説明するものでもあるのですが、その思いは全く届きません。
もう少し踏み込んで言えば、三河家臣団の形成と家康の成長に焦点を当てる「どうする家康」が家康の天下取りの軸に据えているのが、信頼関係だということでもあります。天下取りに一番必要なことは、武勇でも知略でもないのです。因みに本作で、武勇についての天賦の才を持つ者は信長です。第10回、側室問題で弓術の異常な連射速射能力の高さに驚愕した視聴者も多いと思いますが、あれは単なるお笑いのシーンではなく、その武勇の天才性の描写です(実際に武術に長けた岡田准一くんだからこその説得力が良いですね)。
そして知略については、既にその片鱗を見せている秀吉がその天賦の才を持つ者でしょう。当面の敵、信玄は両方兼ね備えたローマ人…じゃなくて巨人ですが、本作では既に完成された老練な武将として出てきているので天賦の才とはズレているでしょう。
武勇と知略に天賦の才を持たぬ「最も肝の小さいお方」(千代女)が将になるには信頼しかないのです。
2.私情に流される家康
完全に私情に流されている氏真に対して、家康もまた心中穏やかではありません。自身が育った駿府陥落への衝撃、未だ行方の分からない氏真への思いが突出しています。一方で既にいくつもの修羅場をくぐり抜け、三河国の盟主として苦悩しながらも、結果的に「正しい」判断をしてきた家康ですので家臣との関係は損なわれておらず、巧く機能しているようにも見えます。
しかし、生き延びた氏真が懸川城で立て籠ったと知ったときは、北条家に逃れる手段があるにもかかわらず、氏真が徹底抗戦の選択する理由を図りかね、その辺りから様子がおかしくなります。元々、氏真のことを考え過ぎていた彼は即決即断で、自ら懸川城へ出向き直接対決を選択します。
史実では、この懸川城の戦いは、苦戦続きですが見せ場もありドラマチックに見せることもできる戦いなのです。しかし、本作では何の策もなく同じ押し問答を繰り返すだけの凡戦が数か月間続いたと描かれます。これはあまり褒められた見せ方とは言えません。無為に兵を死なせ、兵糧を消耗する戦いに見せては、義元が化けると思った家康の将としての器に疑いが生じてしまうからです。しかも、膠着した戦況に対して、適切な献策をした大久保忠世を家康は感情的に𠮟りつけてしまう。平八郎が「忠世殿は悪くない」とフォローしてくれましたが、これはよろしくありません。家康もまた、氏真の思いに引きずられ冷静さを失っているのです。
こうした家康を無能と切ってしまうことも出来ますが、ここでは何故、家康がここまで冷静でいられないのか、ここを考えてみましょう。
前回、信玄と密約を結ぶ際、信玄に突き付けられた領土に見立てた餅を、家康は逡巡し少ししか食べませんでした。 これについて、私は信玄が突き付けた戦国武将の支配欲と弱肉強食の論理に呑まれきれなかった人間性があるからと読み解きました。この人間性は良心や優しさと置き換えても良いですが、実はこれがあるからこそ悩み続け、後悔を抱き続けてきたのです。
その後悔は、状況的に仕方なかったとはいえ、信長と清州同盟を結び、今川家を裏切ったときから始まります。吉良義昭を騙し討ちにしたときの涙目は噓ではありません。その後の駿府で殺された三河衆たちの問題、妻子救出のための戦と交渉、引間城の戦い、どれも本意ならざる多くの犠牲を強いてきたものです。
こうまでして今川家との関係がこじれたにもかかわらず、家康が時折、思い返し、心の支えにしたのは義元の数々の金言(「武を以って治めるは覇道、徳を以って治めるは王道」など)です。自分のしてきたこれまでのことが生き延びるための正しい判断であったということを理性で分かりつつも、今川義元に対する憧憬、生まれ育った駿府とそこに住む人々への愛着を家康は決して忘れずにこれまで過して来たのです。
道義に反した自分自身に苦しむからこそ、兄と慕った氏真と直接会って詫びなければならないと思い詰めるのです。そして、前回の田鶴を死なせた件がありますから、それを繰り返したくないのです。家臣に任せれば、戦いに勝てても、氏真の命を救い、詫びることは出来なくなる可能性があります。それは、信玄と同じ戦国武将の支配欲と弱肉強食の論理に自身も完全に呑み込まれてしまうことと同義です。
ですから、家康は必死に抗う。なかなか懸川城を落とせないことに対する信玄の武力を持った催促にも家康が「信玄は関係ない!」と激昂して返すのは、家康が人間性を失っていない証拠であり、また弱肉強食の論理に対する彼の必死の抵抗なのです。この抵抗があったからこそ、最終的に氏真に土下座をし、武田との盟約に逆らってまで北条家へと落ち延びさせるという判断が生まれるのですね。
つまり、ドラマ的には、どうしても家康に残った人間性を救わないことには、民を自ら信じることで「厭離穢土 欣求浄土」を築かせるのは難しいのだと思います。
こうした家康の苦悩を理解しているのが駿府の人質時代を共に過ごし、前回、駿府陥落に「わしらが育ったあの駿府が…」と衝撃を受けた鳥居元忠(彦右衛門)と平岩親吉(七之助)なのが巧いですね。彼らだけが第12回当初から、家康の苦悩を見抜き、それでありながらも三河国のために正しい道を選ばせるため、氏真がしたことを忘れるなと換言できる。この換言で、彼らは「今川家」を主語にせず、「氏真が」と彼を主語にしています。つまり、今川家に弓引くのではなく、我々に非道なことをした氏真を討つのだという言い方で、少しでも家康を楽にしようと配慮しているのですね。
その忠言を聞き入れ、攻めに転じる家康ですが、彼の顔は引きつっています。ここで彼らは、家康の氏真への本心に気づき、痛々しい眼差しを家康に向けます。平八郎がわざと氏真への槍の投擲を致命傷にしなかったことといい、彼らなりに家康と共にあろうとしているのだと察せられますね。
3.義元の遺言
さて、榊原康政が抜け道を見つけ、早川殿を捉えたことで事態は好転し、氏真との直接対決となります(お付きの者は当然、彦右衛門と七之助しかありえませんよね)。
この直前、氏真は辞世の句にするつもりで、「なかなかに 世をも人をも恨むまじ 時にあはぬを身の科にして」(訳:戦国の世も人も恨んではいない。ただ時代に合わなかった、この身が悪いのだ)と詠んでいますが、句の見事さに対して、達観とは程遠い氏真の心情が哀しく、痛々しいところです。句が見事なだけに、余計に彼の虚栄心が表に出てしまっています。
さて、氏真はあの頃と同じく一騎打ちを所望し、家康はそれに応じます。ここで、第1回「どうする桶狭間」での瀬名を巡る一騎打ちが回収されます。そして、このとき義元に手加減は相手へ侮辱、二度とするなと言われたことをきっちり守り、彼は一撃で氏真に勝利します。義元の教えは着実に家康の中で生きていると端的に示されます。その上で自害しようとする氏真を抱きとめ、死なせたくない想い、兄と慕う気持ち、そして心ならずも義元に、今川家に弓引くことになったことへの詫び…第3回から彼が抱えていた苦悩がようやくここで解放されます。
一方、氏真は家臣らから「わしの才は蹴鞠をすることだけじゃ」とバカにされ、義元から「将の才がない」と言われたことへの絶望を語り、家康への嫉妬を露わにします。何故、彼が家康に対して執拗に嫉妬するのか。それは彼が義兄弟の兄だからです。そして、家康の烏帽子親となった義父:義元は、家康に対して第1回で「息子よ」と呼び、金陀美具足の鎧を与えるほど将来に期待していました。教え導いて来たはずの義理の弟が真に息子である兄を追い抜くなど…
こうして、第1回から用意されたことが回収されていきます。氏真と家康は、偉大なる父今川義元の息子であり、合わせ鏡の関係だったのです。それは、家康自身もいつ氏真のように転ぶか分からない危うさを持つことを描いた三河一向一揆編でも匂わされていたことです。
ここに早川殿が表れ、「将の才がない」に続く義元の氏真への言葉「己を鍛え上げることを惜しまぬ者は、いずれ必ず天賦の才を持つ者をしのぐ」という人間哲学が伝えられます。実はこの言葉、氏真が武術稽古の際に家康にかけていた「努力すれば上達する」と同じ。義元が自分をよく見てくれていて、その努力の根底にあったその大切さを自分と同じように知っていた。だから、彼は父の言葉に納得します。
そして、義元が氏真の努力を早川殿同様によく知っていたからこそかけた愛情に満ちたこの言葉を、氏真だけでなく、もう一人の息子、氏真の弟、家康も聞くのです。つまり、この兄弟の和解につながる義元の遺言は、兄:氏真のかつての言葉と響き合う形で、家康にも伝えられる。ここが今回のポイントです。
さて、遺言を聞き、それに得心した氏真は、「何もできなかった」と認め、彼をずっと見守ってくれていた早川殿を幸せにするため北条家への亡命を恥も捨て家康に頼みます。ようやく憑き物が落ちた氏真の表情は虚無と晴れやかさが微妙に入り混じった表情をしています。悟るまでにあまりに多くのものを犠牲にしてきましたし、簡単にわだかまりは消えませんから当然です。溝端淳平くんの演技は、この難しい感情を表した表情が一番でしたね。この瞬間に、ようやく辞世の句の「時にあはぬ」に彼の心情が追いつきます。
しかし、このことは戦国大名から降りる氏真は、義元の遺言を活かすことが出来ないということを意味しています。だから、戦国大名から降りる決断をした兄を羨む家康に氏真は「そこでまだまだ苦しめ」と言い放つのです。突き放したようでもあるこの言葉は、自分が叶えることの出来ない父の言葉を弟のお前が継ぐのだという嫉妬の入り混じった呪詛と願いを託す激励の両面を感じさせる名言ですね。かつては自分を優しく導いてくれた兄にこれを言われたら、家康は死ぬまで、あるいは負けるまで戦国大名ゲームを降りることはできませんね。
一方で、早川殿に歩調を合わせる気遣いをしながら去っていく氏真(やっと人間性が復活したのですね)を見ながら、家康自身の駿府人質時代の蹴鞠をした楽しい思い出を思い返します。この回想は、第12回冒頭の氏真の楽しかったあの頃の回想とシンクロします。二人はもう戻ることができないあの時代を同じように大切に思い合っていたのです。哀しいながらも、どこか和解を予期させる形で、冒頭の無残に打ち砕かれた回想を回収しているのが巧いですね。二人はどこまでも兄弟なのです。
そして、この二人の回想がささやかに前回の瀬名と田鶴の回想と響き合っていますね。姉妹のような親友だった彼女らは悲劇的でしたが、兄弟のほうはまだ希望があるのです。
ところで、「わしの才は蹴鞠をすることだけじゃ」と自虐的に語っていた氏真ですが、公家文化を象徴する芸道に通じているということは、学問や有職故実に精通しているということです。これがいかに大切かは、昨年の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の北条時房が証明していますね。だから、後に今川家は、有職故実、式典に精通した「高家」として明治まで生き残るのです(維新後、嫡流は絶家しますが)。戦国大名を降りたことが回り回って今川家を残す。氏真は「正しい」判断をし、自分に合った生き方を選んだのですから、極めて有能な人であったと言えますね。
おわりに
武田との盟約を破り、北条家へ氏真を逃したことは信玄を怒らせます。この件が伝わったときの山県をナメて武田ルシウス信玄を映すというレイアウトが、前回、入念に恫喝し戦意を挫いて同盟を結ばせ、懐柔したはずの三河の小わっぱごときに噛まれた信玄の驚きの表情を見事に強調していますね。次の怒りのちゃぶ台返しにつなげる巧い画面構成です。
しかし、対する家康は、武田と戦になるかもしれないという状況に全く動じることなく、取り成すという忠次の言を退け、北条家と手を結んで武田と戦うか、あるいは…と思案する顔をします。この思案顔になんでもやって生き残って見せるという覚悟と悪意のようなものを漂わせているところが、今回の松本潤くんの一番いい表情ですね。
義元の遺言を氏真から「苦しめ」と託された家康は、「努力を続ける者は天賦の才をいずれ抜く」という哲学を胸に刻み、信玄との対決すら覚悟し、苦しみを受け入れようとする。これは、次のステージの始まりですが、一方で第1回からの様々な出来事が回収され、この覚悟につながった。つまり、「家康の今川人質時代と青春時代の終焉」が今回の話だったと言えるでしょう。そうなると、サブタイトルは「氏真」ですが、真のサブタイトルは「義元の遺言」ですね。桶狭間であっという間に死んだ義元の思いは、ようやく息子に全て伝わったのかもしれません。
今川義元を、徹底的に息子を教え導く偉大なる父とすること。その父の教えを実践から体得して成長する家康を描くというのが序盤から第12回の「どうする家康」でした。したがって、義元を偉大な父として描くには、母:寿桂尼と軍師:太原雪斎の存在は邪魔だったとのだと分かります。また、家康の対比として、間違った形の家康の成長を置いておくと、家康のある種の弱いけど健やかな部分というものが強調されます。だからこそ、義兄弟として氏真が同じく父に憧れる若武者として設定されたのです。
ちゃんと家康に焦点が当たるように魅力的なキャラクターが配置され、物語が組まれている。古沢良太脚本の巧さがよく分かりますね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
