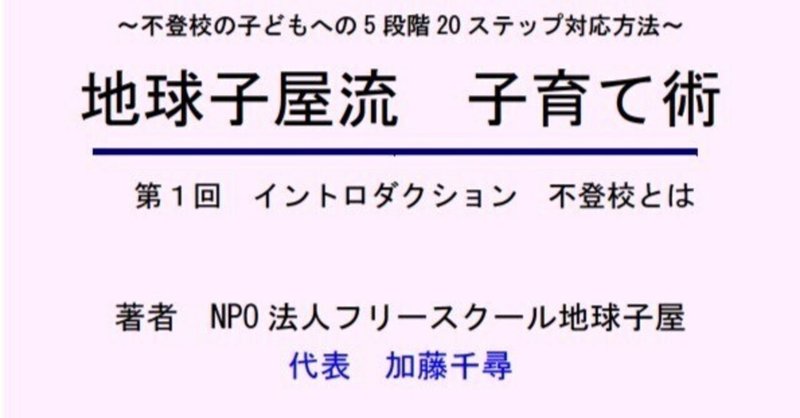
不登校になる、ということ
矛盾する自分
学校に行けない・行かないという状態の原因は無数にあります。原因をいくら探ってもあまり意味はありませんし、何か特定して「不登校の型」のようなものに当てはめようとしても判断をかえって誤る結果になりかねません。ただ、大多数の子どもは、学校には「行かなければならない」と思っているでしょう。
それはそうですよね。最近まで学校に行っていたわけですから。いくら学びには選択があると言ったところで、子どもにとって「学校」は行って勉強するところという強固な思い込みは形成されていると思います。
学校は行けなければならない場所との思い込みが強ければ強いほど、行けなくなった自分を責めますし、悪いことをしているという気持ちにもなります。
そうなんです。学校に行けない・行かない子どもの胸の内を聞けば、多くの子どもは行けるなら「行きたい」と思っているのです。でも行けない。
そして身体が動かない理由も分からない。という状態が実像のようです。もちろんそれに当てはまらない子どももいるでしょう。あくまで一般論としては、そんな感じであると理解してもらえると助かります。
この矛盾した考えに支配されている時、人間は簡単には動けません。どうしたらいいのか、答えが出ない中で、一生懸命考えているのです。
誰しも物を失くした時や道に迷った時には、立ち止まって考えることがあります。そういう状態を想像してほしいと思います。
人間関係が崩れていく
自分に起こっていることがよくわからない、頭と身体・心が矛盾しているから動けないという点を人間関係の視点から考えてみましょう。
最近まで学校に来ていたのに、学校に行けない、行きたくないと言い出したわけです。それをお友達が理解してくれるかというと、かなり難しい。お友達は、登校できているのですから、この自分の状態を理解してくれないと直感的に思います。
ご家族や先生はどうでしょうか。最近では、不登校についての対応も理解が進んできており無理に学校へ戻るように言うことは減りました。しかし、顔には書いてありますよね。
「どうして学校に来ないのか?」とか「来てほしい」と。
自分だって行けるなら行きたいよと心の中で叫びますが、行けていないのでどうしても何も言えません。黙っているしかできないのです。
こうして周りとの人間関係も少しずつ以前と同じというわけにはいかず、なんとなくですが周りの「なんで行かないの?」という視線がきつくなってくるのです。人間は、孤立すると本当に弱くなっていくものです。自分のことを理解してくれる人がいない寂しさ、キツさ、辛さは、子どもには荷が重すぎます。周りは理解しているようであっても、なかなか理解できるものではありません。
そして、自分の存在が無になっていき、、、
自分の中で何かが起こっているけれど、うまく説明できないし、頭の中は矛盾した考えがグルグル回っています。
行かなきゃいけない、けど行けない、どうしたらいいのか、とにかく行かなきゃいけない、けどどうしても行けない、どうしよう・どうしようと。
このようになってくると緊張状態がずっと続いているので、疲労もかなりのものになってきます。疲労が溜まってくれば、当たり前にできていたこともできなくなっていきます。誰もが簡単に思える歯磨き、風呂に入る、着替える、食事をするなど生活そのものが億劫になっていきます。うつ状態といってもよいかもしれません。
そんな状態が続いていたら、精神的に追い込まれていくのです。
そして自分は生きていていいのだろうか、何の価値もない自分は消えた方がいいのではないだろうか、自分はいらない存在だ、などの考えに支配されていきます。
そうなれば、自傷行為や自殺企図なども当然ながら視野に入ってきます。
とても危険な状態です。
学校に行けない・行かないことが、自分の生命も脅かすようなことにつながっていくのです。決して軽視してよい問題ではありません。
1学期に行けなくなった子どもが、夏休みに入り少しホッとするのですが、再び悪夢がよみがえってくるのが2学期が始まる直前です。
子どもたちに命を絶ってほしくはありません。
生きているだけで、どの子どもも価値があります。
そう思えるようになるには、本当にただただ生きているだけでいいんだ、価値があるんだということを目に見える形で示すしかありません。
その1つの方法がフリースクールのような場所である、と思います。
だからこそフリースクールのような家庭でも学校でもない第三の子どもにとっての居場所(安全基地)が、今の世の中に必要なのです。
