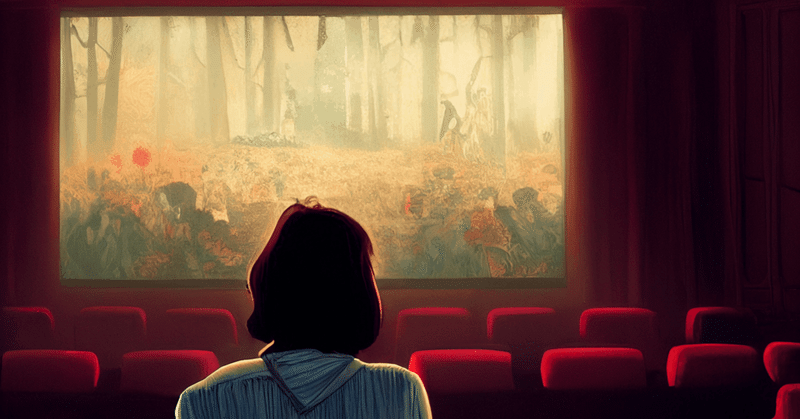
2022年観た映画8選
例年その年に読んだ本のうち、特に印象に残ったものをまとめているが、自分のもう一つの趣味である映画もやったらよいのではと思い、やってみることにした。
いざやってみるとこれがなかなか大変。まず、(本のほうでも意識していることだが)監督や作品の色のバランス、地域のバランスを整えるのが難しい。
また、本年はウォン・カーウァイ監督作品を数多く観た年だが、本音を言えば全部ここに載せたい。しかし、逸る気持ちを抑えなんとか二つに留めた(『花様年華』も『2046』も『欲望の翼』も本当は載せたい)。そして、香港や台湾も含めた中華圏という視点で見れば、じつに4作もランクインしている。こちらもバランスに配慮したといいつつ、バランスが悪くなってしまった結果をご容赦いただきたい。
はい、それでは変な前置きはやめて作品紹介に入りましょう。
ウォン・カーウァイ監督『恋する惑星』(香港)
香港出身の巨匠ウォン・カーウァイ監督の代表作である本作品。まず、邦訳が秀逸である。いや、秀逸という言葉じゃ足りないくらい素晴らしい。原題は重慶森林で、現地にある重慶大厦というビルの名前にちなんでつけたそう。いや日本人にわかるかい、ということでもっとよいタイトルをつけようとなり、スタッフ陣の奮闘の結果考えうる限りの最高の邦題が出来上がったわけである。
「その時、彼との距離は0.1ミリ。57時間後、彼は彼女に恋をした」
というあまりにも有名なセリフに代表されるように、本作では、人の行き来も、時間の流れも、あまりにもすべてが速い香港という都市の空間で、刹那的な恋愛物語が展開されている。前半と後半が全く異なる物語でありながら、目を凝らさないと気づかないような細部で実はつながっている独特なスタイルでもある。
本作に登場する印象的なセリフがある。
「いまどき、何にでも賞味期限がある。魚の缶、パイナップル、そしてサランラップにすら賞味期限がある。愛に賞味期限はあるのだろうか。」
金城武演じる恋愛依存体質な男による台詞である(ちなみにこの男、自分のもとを去った恋人が自分の誕生日に戻ってくることを信じ、誕生日までの一か月間、彼女の好物であるパイナップルの缶(しかも誕生日に賞味期限を迎えるもののみ)を買い、誕生日にも帰ってこないのをみて、一気に30缶分を一夜で食べたなかなかにやばいやつである)。
都市というすべてが速く、儚い空間において、真の愛は存在するのか。なにも哲学的で難解な映画ではないものの、鑑賞後に、本作のおしゃれな音楽と映像、登場人物の台詞に浸りながら、ふとそんな深遠な問いが浮かぶものである。
儚いといえば香港という都市がそもそもそうなのである。本作がリリースされた1994年はちょうど香港の中国への返還が近いづいている頃である。香港の歴史や運命はウォン・カーウァイ監督の作品において常に暗喩的な形で登場するテーマなのだが、本作を香港の儚さという視点からとらえるとまた違った深みが出るのではないだろうか。
ウォン・カーウァイ監督『ブエノスアイレス』(香港)
本作は、ブエノスアイレスで展開されるとあるカップルの愛憎劇である。
ファイ(トニー・レオン)とウィン(レスリー・チャン)は喧嘩しては別れ、別れてはまたやり直すを繰りかえるカップルだった。関係を「やり直す」ために、2人はイグアスの滝があるアルゼンチンに旅行しにいくことになった。しかし、道中で車が壊れてしまい、2人は再び喧嘩して別れた。2人とも故郷の香港に帰るお金がなかったため、そのまま別々で現地に住み着き、お金を貯めることにする。ファイはホテルで台湾人観光客を相手する仕事につき、ウィンは地元の不良と曖昧な関係に入る。ある日ウィンが大けがした状態でファイの家に転がり込む。こうして、2人は再び関係性を再開させる。ファイは怪我で体を動かせないウィンのために、食事を作り、部屋の掃除をし、彼の身体を拭いてあげるなど、徹底的に尽くす。だが、またしても2人の関係に暗雲が立ち込めるのであった、、、
香港を代表する2人のイケメン俳優レスリー・チャンとトニー・レオンによる本作は、2人の名演技やアルゼンチンの美しい風景も相まって、アジアを代表するゲイ映画の一つとしてしばしばあげられる。
「ウィンの手が早く治らないように祈った。一緒にいて幸せだったから」といったトニー・レオンによる切ない台詞、クールなレスリー・チャンが慟哭をあげるシーン、そして雄大なイグアスの滝の風景は、観客の心に忘れられない痕跡を残すであろう。
本作に関してもう一つ触れたいのが、政治に関する側面である。
パンフレットにあるコメントによれば、ウォン・カーウァイは香港の中国への返還に対する自身の意見をこの映画に投影しているという。そして、本作は返還が行われた1997年にリリースされている。また、本作の終盤で、返還と鄧小平の死を知らせるニュースが流れるシーンがある。ブエノスアイレスが地球上で香港の真裏にあることも興味深い。
この観点で、本作を眺めたとき、どのような解釈ができるのだろうか。個人的な解釈だが、2人の主人公ファイとウィンは香港の未来のありうる二つの可能性を暗示しているのではないか。詳細はネタバレになるためこれ以上触れないが、映画の最後までどちらも香港に帰らずに、香港の外側の世界でさ迷い歩いていることは、実に印象的である。
本作以外にも本年は様々なウォン・カーウァイ作品を鑑賞したが、そのうち『2046』は個別に詳細レビューを書いている。
ウォン・カーウァイ監督の作品は、物語、俳優陣の演技、映像、音楽すべてが美しく、観客に言葉に尽くせぬ感慨をもたらすとともに、香港という都市空間の儚さを申し分なく魅せてくれる。ぜひ多くの方にみてほしいものである。
チェン・カイコ―監督『さらば、わが愛/覇王別姫』(中国)
本作は、とある京劇(中国の伝統的な劇。日本で言えば歌舞伎があたるのだろうか)役者の波乱万丈な一生を描いた作品である。
彼が生まれたのは1920年代であり、清王朝が倒れ、新たにできた中華民国がまだ安定していない時期であった。彼は親に捨てられたことで京劇の道に入ったのだが、毎日の稽古は体罰が日常茶飯事なほど過酷なものであった。彼はこの世界で生き残るため、やがて自身のすべてを京劇に捧げることを決意する。
中国の近現代史を少しでも知っている方であればわかると思うが、その後の彼の人生は、中国における一番激動な時期とまさに重なっているのである。京劇役者として名を馳せた後は、日中戦争期間中の日本による占領、日本敗戦後の国民党による粗末な統治に翻弄され、やがて中華人民共和国が成立すると、反右派闘争や文化大革命などにより、役者を続けることすらままならなくなる。それでも、もはや自分の人格とイコールとなった京劇役者という仕事をなんとか彼は続けようとする。そんな彼がとった決断とは、、、
『ラストエンペラー』と同じく、中国の波乱な近現代史にひたすらに圧倒される名作である。おそらくこの時代を生き抜いた者の人生はすべて壮大なドラマとなるのではないかと思うほどに、中国の近現代史は波瀾で様々な騒擾に苛まれている。その中で辛うじて見いだせる一縷の人間の魂の美しさを、ぜひとも本作で見てほしい。
ウェイ・ダーション監督『セデック・バレ』(台湾)
本作は、日本が台湾を統治していた時代に起きた霧社事件を描いた映画である。霧社事件といえば、現地にいた日本人140人全員が、現地のセデック族に惨殺された悲惨な事件である(検索すれば実に悲惨な写真を目にする)。なぜ日本の現地における統治がこのような結末になったか、その顛末を描いた超大作である。
日本がかつて台湾を統治していた時代、日本は現地にいる先住民族であるセデック族に対して同化を進め、現地の警察は彼らに差別的な言葉をかけ、乱暴な扱いをすることが日常茶飯事であった。このままでは民族としての誇りが消えると感じた頭目のモーナ・ルダオは叛乱を決意するのであった。。。
まず、本作で感心したのは、日本人の描き方である。作品の構成上、日本人側が完全な悪とされてもおかしくないのに、日本人側にも多様な人物がいたことが描かれている。小島という現地の言語を覚え、文化にも精通した日本人が登場するが、彼の家族が事件に巻き込まれたことを知らされた際の彼の表情はなんともいえぬ悲痛に満ちていた。そして、映画の最後で少し紹介されている事件後の顛末をみると、小島は事件後も事件の陰影から抜け出せなかったようである。
多様なのはセデック族側もそうである。当時、花岡一郎と花岡二郎という日本人として育てられたセデック族の二人が登場する(ちなみに二人は兄弟ではない)。そして、抗争が起きると、二人は実に難しい立場に追い込まれることになる。
歴史を通じてずっとそうであるが、戦争が起きるとついつい二つのグループの対立という風に単純化して物事をみるようになるが、その間に挟まれる無数の存在がいるのである。
もう一つ、考えさせられたことがある。
本作に登場するセデック族は、首狩りを習俗に持つ。男は成人した際に、戦士になった証として、人の首を狩らねばならない。そして、戦士にならないと先祖たちが待つ死後の世界に行けない。また、首によって先祖との交霊が成り立つなど、首狩りは宗教的な意味を持った習俗でもある。
日本の統治下でこの首狩りは禁止されてしまい、彼らは民族の誇りを奪われたと感じるようになる。しかし、何も日本に限らず、近代的な国家であれば、人を殺める行為はそもそも許されない。ここに、近代と前近代的な社会の本質的な衝突をみることができる。
セデック族は何も自分たちが近代的な技術をもった日本に勝てると思っていたわけではない。台湾統治を開始した初期のころに、日本政府の計らいでセデック族の一部は日本本土を訪れたことがある。彼らは、日本の技術の高さ、人・物量の多さを知っていたのである。そして、実際に現地では、近代的な技術・制度の受け入れや、日本への同化がある程度進んでいた(先に紹介した花岡一郎、花岡二郎が代表例である)。このまま時間が経てば近代的な社会となり、物質的には豊かな社会になる可能性すらあったのである。それでも、現世における利益以上の容易には説明できない何か、信仰や民族としての誇り、を彼らは選択した。思えば、人生の意味づけの仕方は多様である。近代的な社会に生きる我々は、ついつい現世における豊かさや達成で自身の人生を意味づけ、信仰といった前近代的な情念を目の当たりにすると理解できないと感じるが、決して人生の意味づけ方は一様ではない。
相容れない近代と前近代の衝突、そして個人の人生の意味づけの仕方の対立として、本作を見ることもできる。
「文明が我らを跪かせるのなら、我らは野蛮の誇りを見せてつけてやる。」
セデック族の頭目、モーナ・ルダオの威勢に満ちた台詞には、語りつくせぬ悲壮感を垣間見ることができる。
ヴァレンチン・ヴァシャノヴィチ監督『アトランティス』(ウクライナ)
本作は、ウクライナ人の映画監督ヴァシャノヴィチ氏によって2019年に制作された作品である。
舞台は2025年のウクライナ。ロシアとの全面戦争が終結して1年後という設定である。今般のウクライナ戦争が始まる前に制作された映画であることに驚きを隠せないものの、一方で2014年のクリミア併合以降両国は常に断続的な紛争状態にあったことを思うと、これはいつか来る日常としてウクライナ人に受け止められたのではないかという思いも頭によぎる。
物語は、地雷処理の仕事をする元兵士の男性と戦地に残された死体捜査の仕事をする女性が出会う話である。
本作は、死と生のコントラストを強調する演出が多く、死に満ちた世界で僅かな生を紡ごうとすることを実に見事に描いた作品であった。
未確認の死体が大量に埋められた土地で働く人々、かつて多くの人が働き戦後に閉鎖された巨大な工場の前に佇む黒い服を身に纏った2人、数々のシーンが印象に残った。もっとも印象に残ったシーンが、主人公が、国外に住む選択肢があるにもかかわらず、「もう普通の人のようには生きれない。ここで生きていくしかないんだ」と語ったシーンで、戦争は命や環境のみならず、人の心をも破壊することを強く印象づけられた。本作品を通じて、戦争は生命や尊厳を置き去りにするということを改めて痛感した。
戦争は、たとえ戦闘が終わっても、なかなか終わらないものである。ウクライナのゼレンスキー大統領が国会演説で触れたように、戦後復興はかくも重要である。今世界中からウクライナに差し伸べられた手が、これからも長くそこにあるべきである。
最後に、願わくは、戦争で苦しむすべての人たちに一日でも早い安寧が訪れることを切に祈りたい。
ルカ・グァダニーノ監督『君の名前で僕を呼んで』(イタリア)
本作は、北イタリアを舞台とした、とあるカップルの愛の物語である。
北イタリアで暮らす17歳のエリオは家族とともに夏を過ごしていた。そこに大学院生のオリヴァーが考古学の教授である父をたずねてやってきた。多感な時期にあるエリオは当初オリヴァーに対して距離をとっていたものの、やがて自身が初めて出会う感情を彼に対して持つようになり、抑えられなくなっていく、、
北イタリアの美しい景色とともに、本作では、美しい音楽や文学作品の引用がふんだんに使われている。そして、エリオとオリヴァーが織りなす美しく
も切ないラブ・ストーリーに心を酔いしれられることであろう。
Call me by your name. I'll call you by mine.
(君の名前で僕を呼んで。僕ので君を呼ぶから)
本作のタイトルにも使われているこちらの台詞は実に印象的である。相手の名前で自分を呼び、自分の名前で相手を呼ぶというのは、自分の中に相手を、相手の中に自分を見出す行為と解釈することができる。思えば、エリオのほうは初めて自分がゲイであることに気が付き、オリヴァーはこれまで隠してきていた。相手を前に本当の意味で素直にいることができるからこそ、このような台詞が出てくるのであろう。これほどに美しく純粋な愛を表現する言葉を私は他に知らない。
もう一つ印象的な台詞を紹介したい。エリオの父による言葉である。
How you live your life is your business. Just remember our hearts and our bodies are given to us only once and, before you know it, your hearts worn out and, as for your body, there comes a point when no one looks at it much less wants to come near it. Right now there's sorrow, pain. Don't kill it and with it the joy you felt.
(お間の人生はお前の物、だが忘れるな、心も体も一度しか手にできない。そして、知らぬうちに、心は衰える。肉体については、誰も見つめてくれず、近づきもしなくなる。痛みを葬るな。感じた喜びも忘れずに。)
心も体も一度しかないからこそ、痛みも喜びも含め、人生を最大限に生きるべきである。本作でエリオの父がこの言葉を発した背景はぜひ本編をみてほしいが、まさに痛みも喜びも含めて、本作はすべての人に忘れられない愛の余韻を残すのではないだろうか。
ダニー・ボイル監督『イエスタデイ』(イギリス)
ある日突然、世界の人々からビートルズに関する記憶が消え、ただ一人の売れないミュージシャンが彼らの曲を覚えていた。彼はその記憶を頼りに曲を出し、やがて大スターになるが、、、
本作は、突拍子もない設定の非常に愉快な作品である。さらに、言わずと知れたイギリスの大スター、エド・シーランが本人役として出演するなど洋楽好きにはたまらない作品ともなっている。(ちなみに、ビートルズの故郷であるリバプールの街並みが登場するが、サッカーチームのリヴァプールFCのファンである私にはたまりませんでした(笑))
愉快なコメディでありつつ、ビートルズの素敵なメロディーと詞に彩られながら、本作は本当の幸せとは何かを実に素敵な形で示している作品でもある。そして、意外な人物が登場するが、ビートルズファンでなくとも心を動かされるシーンである。
愉快な笑い声をあげながら、時には少し涙も浮かべる、そんな素敵な作品である。
ヨアキム・トリアー監督『わたしは最悪。』(ノルウェー)
本作は、飽きっぽくすぐに目移りしてしまう主人公ユリヤが自分探しをする物語である。
秀才だったユリヤは大学で医学部に入るものの、何か違うと思い心理学部に入りなおす。しかし、そこでも違和感を感じたユリヤは、写真家になることを決意する。こうして二転三転していくうちに30歳を迎える。不安なユリヤの人生に待ち構えていたのは、別れと、それと同じくらいのトキメキであった。。。
自分探しというよくあるテーマではあるものの、その果てに見つけられるのは一つの正解ではなく、複数の自分のあり方で、その複数の自分を自分で認められるかどうかが大事なのではないかと思わされた。人生は常に悲しい別れと胸躍るトキメキが待ち構えている。その一つ一つを通じてみつかる自分を、大切にすることが自分探しと自己実現を共存させられる秘訣なのだろうか。
一つの映画を観たというより、一人の人間の素敵な人生の一コマを観た気がする。自分の人生に悩む人にぜひみてほしい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
