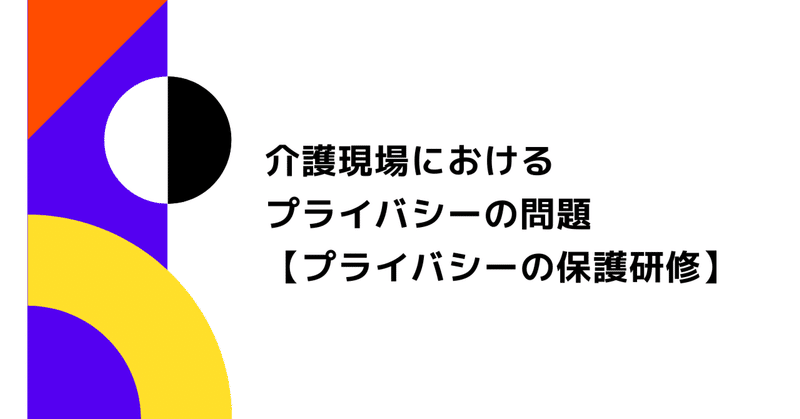
介護現場におけるプライバシーの問題【プライバシーの保護研修】
こんにちは、とも(@tomoaki_0324)です。
私は作業療法士として6年病院で勤め、その後デイサービスで管理者を4年、そして今はグループホーム・デイサービス・ヘルパーステーションの統括部長をしています。
日々忙しく働かれている皆さんに少しでもお役立てできるよう、介護現場のリーダーや管理職に必要な知識と情報をシェアしていきたいと思います。
今回は「介護現場におけるプライバシーの問題」について解説していきます。
介護職として勤めていると、誰しもご利用者の『プライバシーの問題』に、ぶつかったことがあると思います。
介護現場では知らない間にプライバシーを侵害している場合もあれば、どうしてもプライバシーを守るのが難しい場合もあります。
そして放っておくと大問題まで発展することも…。
年に1度の研修で、全スタッフへ"プライバシー保護の取り組みに"ついて周知させることは非常に重要です。
研修講師にあたっている方、これらの研修を受けたけど疑問が残っている方、介護保険サービスの中で働くすべての方に何らかのヒントを見つけて頂ければ幸いです。
プライバシーとは

プライバシーとは、
個人や家庭内の私事(わたぐしごと)・私生活。個人の秘密。また、それが他人から干渉・侵害を受けない権利のことです。
具体的すると下記のようになります。
個人的な日常生活や社会行動を他人に興味本位に見られたり、干渉されたりすること無く、安心して過ごすことが出来る自由
自分が望む生き方を自由に選択し、他からの支配や干渉を受けず、自分の考えたやり方で行動し、その行動の結果に責任を持つこと
個人の容姿、人格、性別、考え方、宗教、思想、生き方、病歴、経歴、前科等が国家や他人に否定や干渉されたり、差別や誤った印象を受けない権利
個人の情報を自己でコントロールすることができる、もしくは事業者に提供した個人情報が法律に則り保護される権利
個人の顔や体等を許可なく撮影されたり、公開されない権利
個人が開示した情報を公衆へ誤認させるような印象操作を受けない権利
昔はプライバシーというと、「個人の『私生活における自由』を他人にみだりに見られたり、干渉を受けないという権利」というイメージでした。
しかし、インターネットの発達と普及による情報化社会において、
電子データ上の『個人情報の保護と削除についての権利』もプライバシーとされています。
また「個人が持つ多様な考え方や価値観が尊重されることや、経歴や宗教、思想などによる不当な差別や偏見を受けない権利」もプライバシーと考えられるようになりました。
プライバシーの侵害とは
"プライバシーの侵害"とは何なのかを具体的にお伝えしますと下記のようになります。
私生活を興味本位で探ったり、覗こうとしたり、住居等に侵入したりすること。
他人に知られたくない個人の秘密や私生活について、公開したり、噂を流したり、干渉したりすること。
個人情報の公開により、他人に自己の真の姿と異なる誤った印象を与えること。
氏名や肖像を他人が自分の利得のために流用すること。
自分の姿が映り込んだ写真を許可無くテレビやインターネット上等に公開されること。
個人情報が流出したことにより、日常生活や精神的に支障をきたすこと。
自分の望み通りに選択することができず、行動が他人の裁量に委ねられる状態。
容姿、人格、性別、考え方、宗教、思想、生き方、病歴、経歴、前科等を理由として、差別や偏見を持たれたり、社会生活において否定や干渉を受けること。
このようにプライバシーの侵害とは多様な価値観の混在する現代社会において、個人の権利と自由が、他人により侵害されることを意味しています。
介護施設ではプライバシーが守られない!
プライバシーとは何か、プライバシーの侵害とは何かを理解すると、介護現場ではプライバシーを守ることができないことがわかります。
当たり前ですが、自宅で自立した生活を送ることができれば、自分の思い通りに生活を送ることができます。
好きな時にお風呂に入り、好きな時に外出し、好きな時に食事をとることができます。
しかし介護施設で介護サービスを受けると、施設のタイムスケジュールに合わせた生活を送らないといけません。
介護サービスでは、入浴日が定められ、毎日お風呂に入ることができなかったり、施設の都合により午前や午後に入浴時間が割り振られたりします。
また、食事においても、同じ空間に居る他人と同じ物を食べるなどバリエーションが少なく、同一のことを強いられる環境です。
自分の望み通りに行動を選択することができず、自己決定権がありません。
それは、介護サービスを受ける要介護高齢者のプライバシーが守られないことを意味しています。
プライバシーの概念が変化し、多様な価値観や個人の自由が尊重される社会において、残念ながら介護サービスでは、業務の都合により真逆のことが行われている状況です。
介護を受ける側の気持ち
要介護高齢者介護が直面するプライバシー侵害について介護を受ける側に立って想像してみましょう。
①事故防止を目的に様々な行動を監視、もしくは禁止される。
②入浴の際に裸を介護職員に見られる。業務時間の都合で丸洗いされる。
③昼食やレクリエーションのバリエーションがない。
④排尿や排便をしている姿を安全のため介護職員に監視される。
⑤排尿や排便を失敗する姿を多くの介護職員に見られる。
⑥送迎の際に部屋の中まで施設の職員が迎えにくる。
⑦入所すれば生活全般の行動を施設職員に見られる。
⑧入所して介護を受けると、個人の自由な行動が制限される。
⑨要求や要望が多いと、あの人はワガママでうるさい人という印象を付けられる
高齢者は日常生活において、自分のことが自分で出来なくなり、やむなく介護を必要とする状態に陥ります。
介護をお願いするということは、自分の身体や生活の場を他人に見られ、干渉されることで、精神的な苦痛を味わうことや、介護を受ける高齢者が職員に気を遣い我慢する状況が発生するということです。
介護に携わる職員は、そのことを理解し、必要以上に要介護者のプライバシーが侵害され、人としての尊厳が失われないように注意が必要です。
介護現場のプライバシーを考える
介護度が重度化するほど、個人のプライバシーは無くなっていきます。
4つのパターンに分け、プライバシーのことを考えてみましょう。
1、自立した元気な高齢者の場合
若者から、「年だから無理しないでね」などと声を掛けるたり、
または、自分より年配だからと気を遣って、電車の席を譲ろうとすると相手の高齢者はどう感じるでしょうか。
「ありがとう」と感謝されることもありますが、人によっては「自分のことを年寄り扱いして、余計なお世話だ」と急に怒り出したりもします。
容姿、性別、年齢等を理由として、差別や偏見を持たれた、または社会生活において否定や干渉を受けたとされプライバシーの侵害にあたるかもしれません。
難しいですね…。
2、介護度の軽い要支援者(軽介護)の場合
介護職員は見守りによる介助が中心になります。
このような方には、危ない時に、「気をつけてくださいね。」「大丈夫ですか?」と声をかけ、必要時に対応することで解決することが多いです。
しかし伝え方によっては、「健康な自分が歩いているだけで、『気を付けてね。』と何度も心配されるから億劫だ」と感じる方もおられます。
他にも、「トイレに行くとき、『大丈夫ですか、手伝いましょうか?』と何度も心配されるのが嫌だ」、「階段を登るときに『段差があるから、危ないですよ』と何度も言われるとムッとする」、などがあります。
自分の行動に対してあまり干渉されると、いい加減にほっといて欲しいと怒り出すことは当然です。
要支援者の場合はまだまだ自立していることが多く、できる限り人には頼りたくないと考えている方が多く、過剰な安全確認やできない前提の対応は、そのご利用者のプライバシーを侵害していることになると理解しておく必要があります。
3、介護を必要とする要介護度1~2(中等度介護者)の場合
要介護1~2というレベルは、
転倒のリスクがある
認知症による物忘れがある
脳出血等の後遺症により入浴などに若干の介助が必要
このような段階です。
そして要介護1~2の方は介護サービスを利用し下記のように感じる方ておられます。
送迎の際は、毎回玄関まで他人が上がってくる
入浴の際は職員が付き添い、裸を他人に見られる
介護職員にいろいろと確認や質問を繰り返される
自分の行動に、見守りや介助が必要となり自由が無い
バリエーションの無い食事や介護サービスが繰り返され飽きる
入浴や排泄時には自分の見られたくない姿を他人へさらす
ご利用者が介護に対し拒否をされたり、腹を立てる様子は 、プライバシーの侵害からの当たり前の反応であることを常に念頭に置いておくべきです。
苦痛の無い生活を送れるよう配慮が必要になってきます。
《よくあるエピソード》
トイレ介助の時に介護職員が、「終わったら教えてくださいね。」「立ったら危ないから呼んでくださいね。」とご利用者へ声を掛けその場を離れた。結局、ご利用者から呼んでもらえず、気になって確認するとトイレで転倒していた。
介護職員は利用者へ、「だから危ないってさっき言ったのに!」と言った。《問題点》
介護職員はよく、「高齢者は自分が危ないことをわかっていない!」と決めつけ対応している場合がよくある。
実際は、「恥ずかしい」、「干渉されたくない」、「人に迷惑を掛けたくない」という理由から、自分で解決しようという行動であることを理解しておく必要がある。
危ない・出来ない前提の声かけや対応をしている場合、さらに事故が増える結果となる。
4、介護を必要とする要介護度3~5(重度介護者)の場合
要介護3~5というレベルは、
移動時は車いすにしても歩いてにしても、介護職員の確認と介助が必要となる
認知症が重度化すれば、行動全てに介護職員の見守りや監視が必要となる
自分が望んでやりたいことは、もはや実現しないかもしれない
このような段階です。
そして要介護3~5の方は介護サービスを利用し下記のように感じる方ておられます。
入浴では体を見られ、他人に体を洗われる
日中はオムツの着用により、排尿や排便の自由がなく、その排泄物を職員に見られる
ポータブルトイレがベッドの側に設置され、室内の環境が介護優先となる
食事はミキサー食などに限定され、自分の好きな物を食べる楽しみは失われる
送迎時やホームヘルパーは、ベッドを設置している寝室まで入ってくるため、私生活の場を他人に見られる
施設へ入所すれば他人との共同生活を送り、時間の区切られた自由の少ない環境で過ごす
このように自由な選択による活動はほとんど失われます。
また自分の恥ずかしい姿を介護職員にゆだねる必要があります。
このようなことから、私たちは普段からご利用者や入所者の声に耳を傾け、なじみの人間関係を築くことが必要です。
要介護者が精神的に苦しむことのないよう心がけましょう。
《問題点》
要介護度が高くなると、プライバシーを侵害しないことが難しい状況となる。
介護職員は、その状況を理解した上で対応しないと、介護を受けるご利用者は訴えることができない弱い立場にあり、「恥ずかしい」、「我慢している」、「苦しい」という精神的な苦痛を強いる状況に陥り、人としての尊厳が失われてしまう。
介護職員が利用者に対して、上手に声をかけ、利用者の要望を聞き出し、丁寧な介護を提供し、信頼される人間関係を築くことで、不穏や問題行動を減らし、介護事故やトラブルを防ぐことが出来る。
要介護高齢者に求められる介護とは、自分の家庭で過ごすような自由や安心感を提供することである。

職員の個人情報とプライバシー
一緒に働く職員にもプライバシーがあり、個人情報を守る必要があります。
どの会社でも職員の個人情報は円滑な業務運営を目的として管理されています。
業務中に知り得た情報は必要目的以外で使用することは禁止されています。
また、職員同士で人の噂を流したり、悪口を言ったりするのはマナー違反になります。
自分が陰で言われたら嫌な事はみんな同じです。
自分の口から余計な個人情報を垂れ流すと、尾ひれがついた噂が流れるかもしれません。
人の批判ばかりして、口が軽いと信用を失い、誰も本音で話してくれなくなり孤立してしまいます。
介護の仕事はチームワークが必要なため、円滑なコミュニケーションが必要不可欠です。
人間関係が崩れると、職場の雰囲気が悪くなり、仕事が苦痛になります。
その影響は介護の質の低下としてご利用者へ現れてしまいます。
働きやすい職場を目指すなら、施設で働く職員の個人情報とプライバシーが守られ、良識のあるコミュニケーションにより、良好な人間関係を築かれることで、互いに協力しながら介護の業務に当たることができる職場を作ることでが必要です。
まとめ
介護の仕事は、要介護者のプライバシーへ介護職員が介入しているという自覚が必要です。
施設の職員に頼らざる得ない要介護高齢者は、弱い立場にあるため、もしかすると施設職員の顔色をうかがい、我慢をしているかもしれません。
要介護高齢者に「できないから」、「あぶないから」、「わからないから」などと決めつけ、強い口調で注意したり、介護をしてやっているといった感覚や態度を見せてはいけません。
ご利用者のプライバシーが無くなると言うことは、人としての尊厳が失われることを意味しています。
私たちは介護を提供することでサービス料を頂いているということを忘れず、仕事としてご利用者の尊厳が守られた介護を提供しなければなりません。
自分がされたくない、見られたくない、言われたくない、望まないことは、子供も大人も高齢者(要介護者)も同じです。
ご利用者の体のことについて、バカにしたり、裏であだ名をつけ呼ぶこともプライバシーの侵害です。
信頼関係が無い新入職員が「空気が読めず」、「間合いが読めず」、要介護者のプライバシーを侵害してしまい、怒鳴られたり、介護拒否をされることは当たり前のことです。
ベテラン職員はその点もしっかり配慮しておく必要があります。
おわりに
介護施設では、「絶対にご利用者のプライバシーを守りなさい」と言われても、非常に難しいです。
職員はご利用者の安全や見守りを優先させるがために、プライバシーを侵害してしまうケースは生じます。
よって介護を受ける高齢者にどれだけ精神的な苦痛を与えず、施設にいながらも家庭で過ごしているような自由で安心した気持ちで過ごしてもらえるのかが重要な課題となります。
要介護者としっかりとした人間関係を築くことで、要望を聞き出したり、プライベートゾーン(距離)を縮め、恥ずかしいという気持ちを和らげ、上手に対応できるように心がけていきましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今後も、管理職又はリーダーであるあなたにお役立てできる記事を投稿していきますので、スキ・コメント・フォローなどいただけると大変嬉しいです!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
