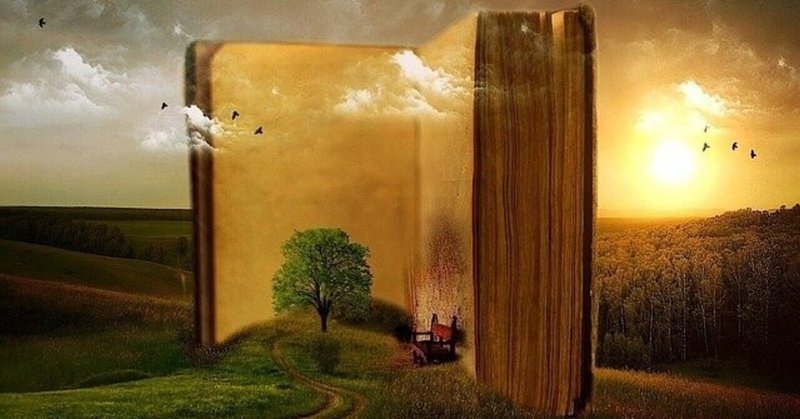
「なるほど、本か!」
英国の代表的なロマン派詩人ワーズワース(William Wordsworth)の"The Tables Turned"(邦訳「発想の転換をこそ」)は、本を捨てて自然に出ようというメッセージを力いっぱいに押し出した痛快な詩である。岩波文庫の『イギリス名詩選』(平井正穂編)に収録されているこの詩に出会ったのは学生時代だったが、生活が苦しかったうえ、本分たる研究(の真似事)のための文献解読にも四苦八苦し、文字通り書物の海に圧倒されている若きわが身を朗らかに笑い飛ばしてくれたものだった。
さあ、君、立ち上がるのだ! 君の本を捨てるのだ!
さもないと、君の腰はほんとに曲がってしまうぞ。
立て、立ち上がるのだ! もっと明るい顔をしたらどうだ。
なぜそんなに刻苦勉励して本を読むのだ?
Up! up! my Friend, and quit your books;
Or surely you'll grow double:
Up! up! my Friend, and clear your looks;
Why all this toil and trouble?
なるほど、本か! 本を読むのは骨が折れるし、きりがない。
それよりも外に出てきて紅ひわの鳴き声を聞くがいい、――
その歌声のなんと快いことか! 誓ってもいい、
本に書かれている以上の叡知がそこにある。
Books! 'tis a dull and endless strife:
Come, hear the woodland linnet,
How sweet his music! on my life,
There's more of wisdom in it.
科学も学問ももう沢山、といいたい。
それらの不毛の書物を閉じるがいい。
そして、外に出るのだ、万象を見、万象に感動する
心を抱いて、外に出てくるのだ。
Enough of Science and of Art;
Close up those barren leaves;
Come forth, and bring with you a heart
That watches and recieves.
(※上記引用の段落と段落の間には省略があります。詩を「中略」にするのはいかにも無粋ですが、やむを得ぬ措置とご了解ください。)
書物の海の波間に翻弄されながら、遅れてやってきた青春の様々な悩みにも追撃されていた当時の私は、この詩にそうだそうだと快哉を叫んだ。(実のところ図書館の個室にこもって、本を傍らに積んで寝ていただけだったくせに。)
かといって、この一篇を読んで書物への懐疑に目覚めたわけではなく、日々文献を追うことへのなんとなしの気疲れが形をとって表れたというにすぎない。思えば、詩を真似た言葉の断片を盛んに作って、しゃらくさい「学問的」気風とやらに撃鉄を食らわせてやろうと足掻いていたのもこのころだった。そしてこの「なるほど、本か!」というフレーズが、それ以降の学生時代において自分をかえって奮い立たせ、密かな座右の銘となり、時には悪魔的な呪術(怠けるおまじない)として機能したようでもある。
文献を読んでもさっぱり理解できぬ!→「なるほど、本か!」
翌日のゼミの報告準備が間に合わない!→「なるほど、本か!」
レポートがまったく書けん!→「なるほど、本か!」
そういった具合の気分があまりに昂じて、冗談が通じる同期の学生を数人募り、「なるほど、本か」という逆説的な題名の「勉強会」を立ち上げて仲間内で遊んでいたことが懐かしく思い出される。かつての自分には、そういう意味不明の行動力があったらしい。(いいからちゃんと勉強しなさいよ。)
この声高に「本を捨てろ」とそそのかしてくるワーズワースとは、果たして如何なる詩人であるのか。
夏目漱石は、小説でも評論でもたびたびワーズワースに言及していることが知られている。漱石のワーズワースをめぐる言説は、最初期の論文である明治25年の「老子の哲学」から、晩年に近づく大正4年の「私の個人主義」まで、ほぼ生涯全般にわたって続いているという。
【参照】https://www.jstage.jst.go.jp/article/hikaku/41/0/41_36/_pdf/-char/ja
漱石は「老子の哲学」において、老子とワーズワースの学問無用論(≒書物否定論)に共通性があると述べている。ただし老子があらゆる書物の全否定論であるのに対し、ワーズワースは天然の書を肯定するとの差異を指摘する。ワーズワースが肯定する「天然の書」がどういうものか具体的には明確ではないが、まさに彼が残したような、自然についてうたった詩などが想定されているのだろうか。
また、明治26年の「英国詩人の天地山川に対する観念」という評論では、英国の自然主義詩人の特徴と流れを整理しており、特にワーズワースの詩の特徴を詳しく分析している。漱石は、スコットランドの農業詩人バーンズ(Robert Burns)と比較しながら、ワーズワースの特徴として、自然に対する観念が他の詩人と異なるという重要な指摘をしている。漱石によれば、ワーズワース特有の自然観念とは、自然を「哲理的直覚」をもって把握することである。すなわち山や水を、単なる物質としての「山」や「水」として見るのではなく、そのうちに何らかの霊的存在(spiritあるいはforce)を見出すというのがワーズワースの態度だという。その主義とするところは"Plain living and high thinking."(平凡な生活に高尚な思考)であり、もとより「俗界を眼下に見降だし」ているのであって、虚栄を闘わせる輩に対して気に障るということがないと述べている。まるで精神的な貴族のような存在だ。
これらの評論は、いずれも漱石が20代の時に書かれたものだが、表現が硬質かつ難解で、青年漱石の「力み」のようなものを少し感じさせる。
あるいはまた、以前の記事で、哲学者・鶴見俊輔によるホワイトヘッド(Alfred North Whitehead)のハーバード大学での最終講義の逸話を紹介した際に、ワーズワースに触れたことがある。精密さを信条とする哲学を何十年も続けたよぼよぼのホワイトヘッドは、「Immortality(永遠性)」と題したその最終講義の終わりに、「Exactness is a fake.(精密さは作り物だ。)」という境地をぼそりとつぶやいた。
鶴見さんは上記の価値とimmortalの部分を「永遠は価値観を抜きにしたところにはない」と表現していた。また、ホワイトヘッドが著書『科学と近代世界』に、英国詩人ワーズワースの詩についての一節を設けていることを特に指摘していた。晩年の鶴見さんには、ホワイトヘッドのExactness is a fake. とimmortalityと詩の結びつきが、より直接的に、明確に意識されている。
(下記拙文より引用。太字は引用時の加工。)
晩年のホワイトヘッドを詩の境地に至らしめる誘因のひとつとなったのは、おそらくワーズワースの存在だった。ホワイトヘッドのワーズワースへの関心について、今原典にあたって検討する準備がないが、参照論文(URL下記)によれば、ホワイトヘッドによるワーズワースの自然観とは、漱石の指摘した霊性に加えて、普遍性を伴って理解されるものである。「ワーズワースは、…永続性を存続する場にいるような自然の詩人である。」(『科学と近代世界』)と述べるように、自然が、終わらないものへの希求と結びついている。
【参照】https://www.jstage.jst.go.jp/article/processthought/19/0/19_91/_pdf/-char/ja
(なお、この論文では、上に述べた漱石によるワーズワース論にも言及している。)
以上のようにワーズワースは、直観力豊かな漱石によれば、ただ素朴に自然を愛しただけでなく、自然に霊性を見出して、その高き魂のうちに生きる詩人だった。のみならず、分析力豊かなホワイトヘッドによれば、普遍性・永続性の詩人でもあった。
現在の自分はむしろ、余暇を書物に耽溺するような暮らしになっていて、再び学生時代を取り戻しているような感覚にも襲われる。しかも学生時代とは違って自由に読み散らかせるのだから、その状況を悪くないと思っている。だから、本を捨てようという心境にはない。もしたとえ「なるほど、本か!」と本をなげうって、部屋の外に出たとしても、すぐに豊かな自然の霊性を感じ、それと一体化することは環境的にも難しい。
なのにこのワーズワースの詩がふと思い出されるのは、なぜだろうか。単なる若き日の苦悩を懐かしんでいるだけかもしれない。つまらぬ書物に時間を浪費したときに感じる虚しさを、書物は自然に勝てないという、慰めの論理のうちに解消しているだけかもしれない。霊性と永続性を圧倒的に示す、実在としての自然が目の前に復活してこないならば、いつまでたっても心の底から「なるほど、本か!」と叫べる日は来ないとも思える。そうしているうちに書物の海に、自然とは違った霊性と永続性を見出して、ぶくぶくと溺れている可能性もある。書物を手放せない世界というのは、果たして幸福なのか不幸なのか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
