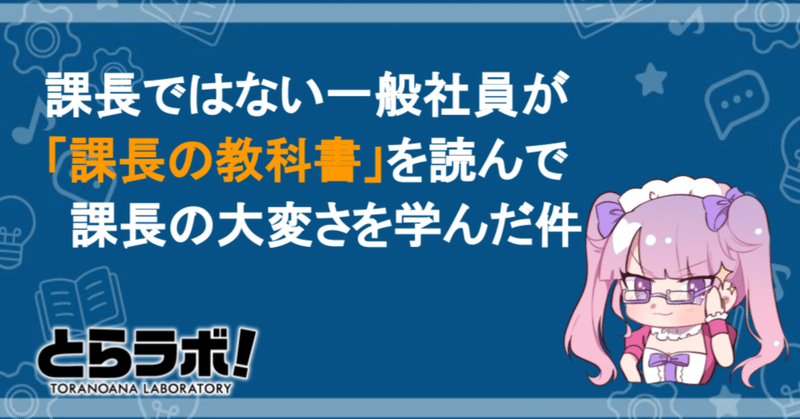
課長ではない一般社員が「課長の教科書」を読んで課長の大変さを学んだ件
📝 PICK UP!

はじめに ~本を読んだ背景~
皆さんこんにちは。虎の穴ラボの下野です。表題の通り一般社員の自分ですが、ふと「課長と一般社員、ひいては部長は何が違うのだろう?」と感じることがありました。
そこで、世間的にも評判の良いこの本を読んで課長について学んでみようと思ったのがこの本を読んだ背景です。
もし皆様の中で
・課長はいつも俺に仕事を押し付けてくるので嫌い!
・課長は全然実務をしないじゃないか!
などと憤怒している方がいらっしゃれば、是非この本を読んでもらいたいと思います。
きっと相互理解が進み、お互いのことを思って優しくなれると思います。
その結果、働きやすい空気になれると凄く良いことですね。
当然、課長を目指す方にとっては必読の一冊だとも感じました。
今回は本書の2章までの内容について触れていきます。
第1章 課長について
課長と部長の違いについて
「課長の仕事といえばマネジメント」という大雑把なイメージしか元々持っていませんが、一般社員からみると「課長も部長も上の役職」くらいの認識です。
しかし、本書にはこのように違いが記されていました。
【課長とは】
・接する部下はエース級から問題社員まで玉石混合
・課長の仕事は「部下・顧客・部長」の三方向に目配せをしつつ、対立する利害を調整すること
・課長にとっての予算は達成しなければならない物
【部長とは】
・接する部下は課長であり、そもそも課長になれるエース級人材
・部長の仕事は経営者の右腕として活躍すること
・部長にとっての予算は人を動かす政治的なツール
会社の実情によって多少なり違うところはあると思いますが、課長の方が板挟み間が強いのでは?と感じますね。
課長と経営者は何が違う?
また本書には課長と経営者の違いについても触れられていました。大きな違いとしてはリーダシップとマネジメントの比重に大きな違いがあると記してありました。
リーダーシップ
・目を向けるのは未来のことであり、事業のよりよい未来について語り、考え、反芻し、計画して練り上げる。
その考えを周りに共有して人々を説得し、リーダーシップを持つ人間が思い描く未来の中で「あなたも成功できる」と関心を向けさせること。
マネジメント
・部下の才能、スキル、知識、経験、目標といった要素を観察し、部下がそれぞれ成功できる将来計画を立てること。
もちろんどちらのスキルも一定量求められるものではありますが、それぞれのスキルを業務に使用する比重が異なるということですね。
課長はマネジメント寄りであり、社長はリーダーシップ寄りとなります。
確かに、実際の会社を見ていてもそのように立ち回っているイメージが強く、深く頷ける内容でした。
また、リーダーシップの方がマネジメントよりも後天的に鍛えるのが難しいとも記してありました。
産まれもってのカリスマや人を惹きつける力などは先天性の要素も確かに大いにありそうです。
課長の最も大切な仕事とは?
本書によると、課長の最も大切な仕事とは「モチベーション管理」であると記してありました。
そのため、課長になった場合実務からは一線を引いて、まったく新しい仕事に就いたと考えるべきとヒントがありました。
なるほど!これこそ課長が最も大事にすべき仕事ということのようです。
実務からマネジメント職に社内転職したというようなイメージを持った方が良さそうに感じました。
ここの意識を持たずに「あの人は課長になった途端、輝きを失ってしまった…」といわれるのは、ここに原因があるのかなとも感じます。
また、従業員のモチベーションと企業の業績には密接な関係があるということは、経営学の世界ではデータによって証明されています。
課長のモチベーション管理によって会社の業績が左右されるといっても過言ではありませんね。
モチベーション管理の本質
ここまで読むと「よし、モチベーションを高め続ければいいんだな!」と思いましたが、当然そんなに簡単なことではありません。
そこで、本書では「モチベーションを維持する」ことがモチベーション管理だと記してあります。
「高め続ける」ではなく「(ある程度高い水準で)維持する」ほうが難易度も低く、再現性が高く感じます。
具体的には部下を一人の人間として気にかけて「能力だけではなく人間性に興味を示していること」でモチベーションを維持する手法が適切であるとのことです。
その結果、部下が「自分は会社に大切にされている」と実感でき、内側からモチベーションが湧き上がる状態を維持し続けることこそ「モチベーション管理」の本質だと述べていました。
※金銭や成果だけでモチベーションを管理しようとしても持続性が無く、一時的な側面が強すぎるので両輪が大事
部下をひとりの人間として気にかけるとは?
部下をひとりひとり大事にすることは分かりましたが、具体的にどうすればよいのでしょうか?そのヒントも本書には記されていました。
日本オラクルの初代社長の佐野氏が用いた手法で、部下各人のプロフィール(性格、家庭環境、長所、短所、モチベーションの源泉 etc…)を徹底的に熟知せよ。
はじめにこの内容を読んだ際「ここまでやっている人がいるのか」と、とても驚きました。
ここまでくれば最早仲の良い友人や親友クラスではないでしょうか?
確かに、ここまでされると「ひとりの尊厳ある人間」として扱われていると感じてしまいそうですね。
リーダーは部下の下僕である
アメリカのAESコーポレーションという会社の理念には「リーダーは部下の下僕である」という企業理念があることを本書で知りました。
この言葉だけ聞くと「何のことやら?」と感じてしまいますが、ここまでに触れてきた「モチベーションを維持するために尽くす役割」と一緒に考えるとなるほど!と思える理念でした。
先述の部下各人の詳細を熟知し、部下の思うところをや求めるところを理解して、部下が思うように存分能力を発揮するための環境整備を行うのが課長の仕事であるならば、「下僕」として献身的に仕えるといった意図が読み解けます。
とらのあなの課長ならば、部下の好きなアニメも把握しておくべきかもしれません(笑)
ちなみに、私は魔法少女リリカルなのはが好きです!(唐突な宣伝)
アニメに限らず趣味のことならば、日頃は口下手な部下も流暢に喋ってくれるかも知れませんね!
課長は価値観の通訳者
ここまでは主に部下の方々に対する姿勢について触れてきましたが、課長といえば企業の上層部と現場といったどちらの顔も立てる必要がある役職ですよね。
本書に「課長は異なる価値観を持つ世代間の通訳者であれ」と語られていました。
具体的には「若い部下」と「ミドルエイジの部長や社長」の間に立つ通訳者です。
時代の移り変わりとともに価値観も変わり「お互いの考え方が理解できない」という問題に直結している企業も多いはずです。
そこで共通の価値観である「顧客第一主義」という共通認識をベースにお互いが歩み寄れるように両者の言い分を通訳して橋渡しすることこそ、課長に求められるスキルの1つでもあるということでした。
Z世代などといって一括りにせずに、お互いひとりの尊厳ある人間として相互理解を深めていきたいですね。
下記の本も最近読んだのですが、Z世代についての偏見や思考の癖が解きほぐされるような良書でした。
自分はゆとり世代ですが、時代背景によって何を重視するかは当然変わっていくものだと思っています。
「何を大事にする傾向が強いか」という情報を頭の隅に入れておくことで、若い世代の方々とも話しやすくなりますね。
(あくまで"傾向"なので、その方が何を大事にしているかはコミュニケーションを通じて掴んでいくしかありません)
第2章 課長が持つべき8つの基本スキル
第1章で触れてきた課長ですが、持つべき8つの基本的な下記スキルが記されていました。
1.部下を守り安心させる
2.部下を褒めて方向性を明確に伝える
3.部下を叱り変化を促す
4.現場を観察し、次を予測する
5.ストレスを適度な状態に管理する
6.部下をコーチングし答えを引き出す
7.楽しく没頭できるように仕事をアレンジする
8.オフサイト・ミーティングでチームの結束を高める
ここでは、中でも特に印象深かったものをいくつかピックアップして紹介していきます。
部下を守り安心させる
これは部下との信頼関係を維持するためのスキルです。
基本的に売上が上がっているなどの良い報告はすぐ届きますが、悪い報告(入金が遅れそうだ等)は届きにくいものですよね。
課長としてはこういった「悪い報告」をどれだけ早く教えてもらえるかが死活問題であり、それは日頃の関係性による影響により変わります。
そのため、悪い報告を受け取った場合下記のような対応が必要となります。
①部下の失敗をそのまま部長や経営者に伝えてはならない
この課長に相談したら何でも筒抜けだ!と思われてはならない。部下から秘密を守る課長だと思われることが重要ということです。
誰がやったかという問題よりも「問題が起こったことの対処」という火消しをまずは行い、「なぜ起こってしまったか?」という再発防止の二軸で進めるのが大事だと私は感じました。
罪を憎んで人を憎まず、のような精神であることは大切ですね。
②部下の失敗は課長の失敗と思え
部下が「何かあれば課長に守ってもらえる」という実感を持って業務に専念できる環境を整備することが大事です。
具体的にはミスの犯人探しが始まった場合、部下の失敗は自分の失敗として部下を守る行動を見せることです。
たしかに、部下もそんな懐の深い課長の下でなら業務に専念できると感じました。
同時に「この人のためなら頑張れる」といったモチベーションの源泉にも一躍担ってくれそうです。
部下をコーチングし、答えを引き出す
この話をする前に、軽くティーチングとコーチングの違いについて触れておきます。
ティーチングは、部下に答えを与える形で指導して、上司が身につけている仕事の知識や技術を提供します。
コーチングは、部下から答えを引き出す質問を投げかけたり、共感や傾聴の姿勢から気づきを与えたりする方法です。
簡単に言えば、答えを直球で教える or ヒントを出して自分で答えにたどり着かせるといった違いですね。
今回はそのコーチングが大事という話です。
コーチングの前提として「問題の答えは、その人の中にこそ存在する」という発想なので、あくまで自力で答えにたどり着かないと意味がありません。その答えを引き出すために課長に求められるのは「質問力」というわけですね。
そんなコーチングをしていく上で重要なことが本書には記されていました。
コーチングにおける3つの目的
目的1:潜在能力を引き出す
部下の中に眠っている潜在能力を開放することで、パフォーマンスを向上させる
目的2:思考プロセスを鍛える
コーチングを繰り返すことにより、部下自信が課題に対して自身で課題を解決するスキルを向上させる
目的3:モチベーションを高める
コーチングをすることで、部下としては「課長が自分のために時間を割いてくれている」と感じます。この実感こそがモチベーション管理の本質に繋がります
目的をひとことでまとめると、コーチングを通じて部下のスキルアップとモチベーション維持の2つをまとめてフォローしようということですね。
コーチング 3つの心構え
心構え1:部下の価値を認め、可能性を信じる
精神面では部下のことを大切に思う気持ちこそがコーチングの鍵になります。部下の価値を認め、可能性を信じ期待していることをしっかり言葉にして伝えることが重要です。
心構え2:秘密を固く守り、信頼関係を築く
ここでも秘密を守るというワードがでてきましたね。部下には質問されても答えたくないこともあり、言いたくない秘密まで言う必要はないことを言葉ではっきり伝えることが重要です。
心構え3:コーチングですべての問題が解決できるとは思わない
コーチングはあくまで手段であり、万能薬ではないということですね。ときにはアドバイスや指示を与えたり、褒めたり叱ったりする行動も必要です。
心構えとしては部下に期待をして秘密を守り抜く姿勢、それを言葉にするのが大切とのことでした。また、時には指示したり褒めたり叱ったりと、コーチングは万能薬ではないという意識を持っておくことも大切ということですね。
コーチング3つの禁止事項
禁止事項1:アドバイスや指示、提案などは決して行わない
話をするとついつい指示をしたくなりますが「問題の答えはその人の中にある」というコーチングの鉄則を思い出し、信じて待つことが重要です。
たった一度のコーチングで答えにたどりつくことはレアケースなので、繰り返し何度も根気強く行う姿勢が大事です。
禁止事項2:YES/NOで答えられるような質問は避ける
YES/NOで答えられる質問は誘導質問になってしまうため、コーチングを台無しにしてしまいます。
出来る限りどうにでも答えられる質問(オープンクエスチョン)をするように心がけるべきです。
禁止事項3:「なぜ?どうして?」と質問するときには非難の意味を込めない
「なぜ?どうして?」というワードは本人にその気が無くても、受け手は責められているような気持ちになってしまいます。
ネガティブな印象を与えないように表情や声のトーンなど、細心の注意を払ってこのワードを使うようにしましょう。
難しければ「別に全然非難しているわけじゃないけど、なぜ~」といった形で思い切って言葉にしてしまいましょう。
指示をぐっと我慢したり、オープンクエスチョンを行っていくのは課長自身でトレーニングが必要になると感じました。
普段の会話で意識して聞き上手、質問上手になれる努力が課長には求められますね。
さいごに
全6章からなる部分の2章までをご紹介しました。
課長はプレイヤーから一線を退き、部下に今度は成功体験を積ませるために全力を注いでいる役職といったイメージを持つことが出来ました。
課長の方も部下の方も、この本を読むことでお互いが理解しあいスムーズに仕事ができると楽しそうですね。
特に部下からには無い視点が手に入るので「課長はこんなことを思って今発言してるのかな?」と推測できるようになればコミュニケーションもより円滑になるのではと思いました。
第3章以降は課長がより活躍するためにといった内容について掘り下げられていますので、課長職に就いている方で本書を読んだことが無い方は是非この機会に本屋に立ち寄ってみてはいかがでしょうか?
(2023/7/19時点では、Kindle unlimitedに入っていれば無料で読めました)
一緒に働く仲間を募集しています
とらラボでは現在、各職種にて弊社求人へのご応募を積極受付中です!
カジュアル面談について
普段の業務への質問はもちろん仕事と趣味の両立やオタク業界についてなどなど、とらラボの中の人とざっくばらんにお話しませんか?
履歴書や職務経歴書は必要なく、もちろんその後ご応募いただいた際の選考結果にも影響しませんのでご安心ください。
オンラインでの実施なので遠方の方も大歓迎です!
