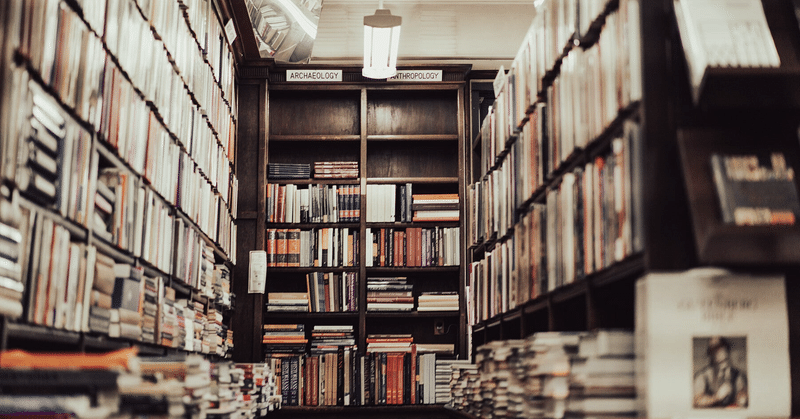
恋と学問 第26夜、なぜ源氏物語は誤読されるのか?
作家で評論家の丸谷才一(1925-2012)に、「恋と日本文学と本居宣長」という本があります。宣長の「もののあはれ論」について書かれたものの中では、短くまとめられていて読みやすい好著です。そこで丸谷さんは、宣長の著作「石上私淑言」(紫文要領と同時期の成立)を引用してから、次のように言う。
要するに、儒教的なものが欠落してゐるせいで日本では恋愛小説がよく書かれた。それだけの話である。しかし重大なのは、たつたこれだけのことを言ふために宣長がどんなに苦労したかといふことである。彼は孤立無援の闘ひを敢行しなければならなかつた。参考書もなく、語り合ふべき先輩も友達もなく、たつた一人で考へなければならなかつた。その点、わたしたちとはまるで違ふんです。ぼくたちは何しろ西洋文学を知つていますから、文学で恋愛をあつかふのは当り前だと思ふ。それがいいか悪いかなんて、そんなことで悩むのは時間の浪費だくらゐに思つてゐる。しかし宣長は違ふ。当然のことながら彼は西洋文学をまつたく知らなかつた。文学と言へば中国文学と日本文学だけといふ条件で、この問題と取組まなければならなかつた。しかもその中国文学は圧倒的に聳え立つ先進国の文学で、普通の知識人が考へてゐる日本文学の位置は決定的に低かつた。・・・つまり、西洋の恋愛文化がまつたくない状態で、その助けをちつとも借りずに、宣長は、恋愛が大切だといふ『源氏物語』と『新古今』の文学的主張を擁護しなければならなかつたのです
(丸谷才一「恋と日本文学と本居宣長・女の救はれ」講談社文芸文庫、2013年、64-65頁)
これは、恋愛をほとんど描かなかった中国古典文学と、恋愛ばかり描いた日本古典文学を、比較する中で出てきた言葉です。江戸時代の日本では一般に、日本文学は低級で中国文学は高級だと見られていました。前者は「百人一首かるた」のように大衆の玩具になる一方、後者は誰もが幼い頃から寺子屋で教わり、こぞって学者が研究するような対象でした。宣長はこの「常識」をひっくり返した。
丸谷さんは、「恋が人生にとって重要である」なんて、今となっては言うまでもないことだが、江戸時代の思想状況でそれを言うのは勇気が要ることで、宣長は完全に孤立無援だったと言います。宣長の孤独はそのとおりでしょう。ただ、人生における恋の地位が宣長の頃と比べて向上したかと言えば、私は疑問に思います。宣長が奉じた思想の孤独は、今もなお変わらないのではないか?
今夜は紫文要領の第3部「恋愛と物の哀れ」の第3章、「物語は訓戒を主題としない」(岩波文庫版、126-138頁)を扱いますが、そこで宣長は、過去の源氏物語研究がどんな具合に誤読して来たかを総覧しています。ところで、誤読が起こる究極の原因は、恋が人生の重要事であることを、私たちが本当は信じていない所にあるのではないか?事実、この令和の時代にも、源氏物語の内に恋とは別の思想を読み取る人が後を絶たないのだとすれば、 丸谷さんのように「恋が大切だということは今となっては当たり前」とは言えないのではないでしょうか?私たちの「常識」を再検討してみる必要を感じます。
いきなり結論から述べてしまったきらいがありますが、続けて宣長の議論を見てゆきましょう。この章に挙げられている誤読の例を箇条書きにしてみます。
1.「春秋」における人物評価を参考にして、勧善懲悪のために書かれた
2.好色淫乱の描写は反面教師であり、読む人の戒めになるように書かれた
3.読む人を「五常」の道に引き入れ、仕舞いには「中道実相」の理(ことわり)を悟らせるために書かれた
4.盛者必衰と会者定離の理を知らしめて、「煩悩即菩提」の理を悟らせるために書かれた
5.男女の仲を主に扱ったのは、「詩経」の中にある「関雎」と「螽斯」という詩に詠まれている、「夫婦和合の道が王道治世の始まり」の思想に基づく
6.読む人は、天台宗の「四教五時」の教えと引き比べながら読まなければならない
7.「荘子」の寓言を模倣して書かれた
8.文体は「史記」を参考にしていて、特に「横並びの巻」は「列伝」の影響である
9.人物評価の書きぶりは「資治通鑑」の影響で、言葉遣いを真似ている
よくもまあ、これだけ多くの「珍説」が続出したものだと、宣長でなくても呆れるほかないのですが、律儀なことに宣長は、これらの全ての説について、いちいち根拠を挙げながら反論しています。あまりこだわっても仕方がない所なので、私としては次の言葉だけ引用して先に進みたいと思います。
巻々の中に人を教へ人をいましめたる事もあるは、すべて此の世にありとある事を広く書ける物なれば、其の中には人をいましむる事もあるべきことわり也。それをとらへどころにして、一部の本意をみないましめと見るははなはだ偏見也(130頁)
【現代語訳】
人を教えさとしたり戒めたりする場面もあるのは、源氏物語がこの世にある全てのことを広く書いたものだからです。この世の全てを表現するからには、戒めを含むのも当たり前のことです。その箇所にだけ着目して、物語の主題をひとえに戒めと見るのは甚だ片寄った意見です。
忘れてはならないのは、誤読をいくら批判したところで、生産的な知見が得られることはなく、なぜかくも源氏物語は誤読されるのか、素直に恋の物語として読まれないのか、その根源にある理由を探らないことには先に進めない、ということです。宣長は理由を直接的には述べていません。誤読という名の「抵抗」の強さを、くりかえし語るだけです。・・・そこから先は自分の頭で考えてくれ。これが読者に宛てられた隠されたメッセージなのです。
一応の答えはあります。先ほども言いましたが、私たちが本当は恋を人生の重要事だと信じていないからです(信じているのならば、石山寺伝説や浄土思想=主題説などの珍説が、いまだに幅を利かせているはずがない)。次に考えるべき問題は、「なぜ信じることが出来ないのか」にあります。
私たちが本当の恋をしていないからでしょうか?それとも、自分の恋をまともに解釈したことがないからでしょうか?前者の可能性も大いにあり得ますが、「現代人は愛しうるか」(D.H.ロレンス)という大問題に突き当たって、収拾がつかなくなる恐れがありますので、今夜は後者にねらいをしぼってお話します。
宣長は源氏物語を読んで、この恋で埋め尽くされた物語は、読者に「物の哀れ」を知らせるために書かれたと信じた。先に挙げた9つ解釈(誤読)に比べて、まったく無理のない、やさしい読み方です。しかし実は、この素直な読み方を採用するのは全然やさしいことではなかった。
恋と聞けば好色淫乱のこと、不道徳で非合理のこととされ、そこに生活の指針や人生を導く哲学など含まれるわけがないと、世間の常識は考えます。恋に「高揚感」以上の意味があるとは考えません。だから源氏物語を素直に読むにはまず、恋という現象について、常識が教えるのとは別の洞察をつかんでいなければなりません。
宣長がその洞察を充分に得ていたことは、第2夜に詳しく述べておきました。実体験として大変困難な恋をしてはじめて、宣長は源氏物語が分かるようになったのです。どんな文学作品もそうですが、特に源氏物語は、読者の経験量に相応した姿しか見せてくれません。だから、ある人の眼には淫乱を勧める書と映り、別の眼では物の哀れを知らせる書と映っても、不思議ではないのです。
内田樹がレヴィナスについて言ったように、ある種の本は「真に理解するためには読者の成熟が要求される」ものなのですが、源氏物語はまさにそれに該当します。やさしく読むことはかんたんです。なんという好色淫乱の書だ、けしからんと。いや、逆でも良い。好色を戒めて浄土思想を伝えようとしたのだと。こうやって読めば世間の常識に抵触しないし、自身の恋愛経験の意味を解釈する手間もありません。ただし、この読み方は読者にむなしさを残すだけです。世間の常識や己の価値観をそのまま、作品に投影して確認するだけの作業に、一体どれだけの意味があるのか?
本当に物が分かるとは、対象に特有の抵抗を受け入れるということと同じです。誰だって当初は抵抗を苦痛に感じます。源氏物語を読むために、自身の恋の意味を再検討するなんて、よほどの物好きだと思われるかもしれません。しかし、その抵抗を克服した先でしか出逢えない、対象の本当の味わいがある。それを知ることに無上の喜びを感ずる人は、苦痛を承知で抵抗を受け入れます。反対に、抵抗を避けようとする人は、対象に常識や価値観というフィルター(色眼鏡)をかけて、なるべく対象に特有の危険と出逢わないようにします。
素直に読むとは、こういう危険から逃げない覚悟の上に成り立つ行為です。だから、素直に読むことはかんたんだなんて、とんでもない誤解であって、知らず知らずの内に受け入れている種々の前提を洗い出して、それを一旦白紙に戻す作業が必要になります。(ちなみにこれは、20世紀初頭にドイツの哲学者フッサールが「エポケー」(判断停止)と呼んだのと同じ精神の態度です)
源氏物語を読解する条件として、宣長が読者に要求しているのは、こういう作業です。しかも現代では、これに加えて、さらに微妙な問題が生じます。
先ほど、源氏物語の主題は浄土思想にある、といった類いの「曲解」が、現代にすら横行していると述べましたが、それは主に学者たちの間で通用している珍説に過ぎず、多くの読者はキチンと素直に恋の物語として読んでいるではないか?このような疑問は当然ありうるわけです。では、私たちは源氏物語を正しく読めるようになったかと言うと、そういうことにはならない。微妙な問題はここにあります。
恋を恋でないもの(勧善懲悪や浄土思想など)に読み替えている相手には、それを指摘してやるだけで事が済みますが、恋の物語として読んでいる人に向かって、「あなたの読み方は誤読ですよ」と言っても、なかなか納得してもらえないでしょう。「恋 vs 非恋」よりも「恋A vs 恋B」の対立の方がさらに複雑です。
むろん宣長も、問題の存在には気が付いていて、今夜の範囲から外れますが、かなり先の所で次のように言っています。
恋の歌をよまむに、今人ごとに色好まぬはあるまじけれども、古へのやうに命にもかくるほどのわりなき恋する人もすくなかるべし。此のすぢに命をすつるものは今もおほけれども、其のおもむき心ばへは古へと大きにこと也。されば恋せぬ人も恋の歌はよむ事なるに、みな古歌の情にならひてよむなれば、恋の歌よまんとては、ことさらに古への風儀人情をしらではかなはぬ事なり(169頁)
【現代語訳】
恋の歌を詠もうにも、今だって色を好まない人はいないだろうけど、古代のように命を懸けるほどに狂おしく恋をする人は少ないでしょう。恋のために命を捨てる者は今も多いけれど、その味わいや心持ちは古代と大きく異なります。現実に恋をしていない人が恋の歌は詠む際には、古歌の心を参考にして詠むものなのですから、恋の歌を詠もうとするには、なおさら古代の風儀人情を知らないでは済まされないことなのです
これは、なぜ現代人の心情をそのまま詠んではならず、古今集などの古歌を参考にしなければならないのか、と問われた時に返した宣長の回答です。恋の意味が変わったのである。古代人がした恋の味をよく知って、その心を歌に詠まなければ、いつまでも不味い歌を詠むことになるぞ、と。
少し回りくどいですか?ならば、「浮舟を見よ」(前夜を参照)と言ってしまった方が、話が早いかもしれません。浮舟のように文字どおり命を懸けて恋愛したことが、私たちにあるでしょうか?浮舟にとって恋とは、己の実存に関わる揺るがせに出来ない問題で、恋を駄目にするくらいなら身を滅ぼすことを選ぶほどに、彼女自身の人生の価値を左右していました。
ひるがえって、私たちはどうでしょう?恋はかけがえのない経験でしょうか?音楽や野球と変わらない、代替可能な趣味嗜好の一つに成り下がってやいませんか?これが恋Aと恋Bの対立です。恋という言葉が意味するところのズレによって、源氏物語を恋の物語とみなして読んでいても、誤読することはあり得るのです。
最後に、この種の誤読の典型をお見せして、今夜は終わりにします。源氏物語の最初の愛読者と言っても良い、菅原孝標女(更級日記の作者)による誤読です。
かたちありさま、物語にある光る源氏などのやうにおはせむ人を、年に一たびにても通はし奉りて、浮舟の女君のやうに、山里に隠しすゑられて、花、紅葉、月、雪を眺めて、いと心細げにて、めでたからむ御文などを、時々待ち見などせめとばかり思ひつづけ、あらまし事にもおぼえけり
(菅原孝標女「更級日記」岩波文庫、1963年改版、35頁)
【現代語訳】
光源氏などのような容姿端麗な貴公子に、年に一度だけでも良いから通ってもらって、浮舟の女君のように、山里に隠し置かれて、花、紅葉、月、雪を眺めながら、とても心細げな様子で、男の立派な恋文が時おり届くのを待ち暮らす、というような種類の生活を思いつづけ、ひそかに願望として育って行った
浮舟の君がうらやましい。彼女みたいに貴公子に言い寄られて匿われてみたいわ。・・・この受け取り方が、浮舟の苦しみ抜いた恋を全く分かってやれていないことは明らかです。しかし、一般に人は他人を見るより自分を見るほうが苦手なものであり、私たちも実は、大なり小なり同じ種類の誤読を犯していることには気が付きにくいものです。源氏物語の作中人物たちの恋愛経験は、恋の楽しみにせよ、悲しみにせよ、私たちよりずっと深いものでした。彼等の恋を私たちの恋と同列のものにみなして読むかぎり、両者のズレは埋まらず、誤読は避けられません。
現代の読者は、想像力と、己自身のつたない恋愛経験の解釈を総動員して、このズレを埋める努力をしなければならない。すっかり埋まることはないかもしれないけれど、少しでも近づかないと読む甲斐もないからです。冒頭に掲げた「なぜ源氏物語は誤読されるのか?」という問いへの答えは、そのような努力を読者が回避し続けたことに求められます。その積み重ねが「源氏物語の誤読史」として、宣長の眼前に立ちはだかっていたのです。
今夜はこのへんで。
それではまた。おやすみなさい。
【以下、蛇足】
今回は、源氏物語の誤読の歴史を、宣長がまとめている箇所を扱いましたので、誤読が起こってくる由来を私の見解も交えながら述べてみました。
宣長はここで9つの誤読を例示していますが、いずれも反論が容易なものなので、軽くあしらっているような印象です。この次の章「不義密通すら主題ではない」は、少し趣が異なります。これは10個目の誤読ということになりますが、宣長はかなりの紙数を割いて、この読み方に反論を試みています。
不義密通=主題説を唱えたのは、安藤為章(あんどうためあきら/1659-1716)でした。彼は宣長がひそかに師事した国学の創始者・契沖(1640-1701)の直弟子であり、宣長の立場から見れば兄弟子にあたります。彼が44才の時の作「紫家七論」(1703年の成立)は、宣長をして「かならず見るべき物なり」(26頁)と言わしめた画期的な源氏論ですが、そこに書かれている主題に関する説には、どうしても賛同しかねたのです。
国学というと、ひとかたまりの学問のジャンルで、誰しも主張する所は似かよっていると思われがちですが、そんなことはありません。むしろ宣長は為章の説を否定することで、己の源氏論を確立しました。そのあたりの事情をよく理解するためにはまず、宣長の批判を聞く前に、為章の説に耳を傾けてみた方が得策だと思います。
というわけで、次回は番外編として、「宣長の参考書」である「紫家七論」を読み解きます。お楽しみに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
