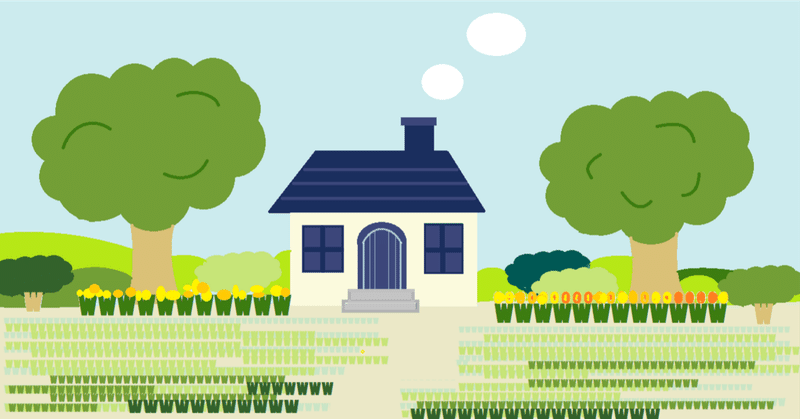
衣食住の話~家の巻~
衣食住への関心が、私の中で年々高まっている。人間だれしも一度は、このテーマに関心を持つのではないかと思うが、私の場合、七年前(二〇一六年)にそれは起こった。
はっきりとしたきっかけがある。父が亡くなった。遺された家族の生活再建のために、生まれ育った家を離れる必要が生じた。まず私は一年がかりで遺産を処分し分割し、私以外の「構成員」が住む場所の選定と、不動産業者との交渉を手がけた。それが終わると己の家を建てる番になった。
生まれ育った家を離れることと、新たに家を建てることが、これほど発見に満ちたことだとは、その状況に置かれるまで知らなかった。私は冷淡な人間で、己の家族を家族と見なさないような態度でしか、己の家族と接して来なかったし、物理的にも大学時代は離れて暮らしていたというのに、「イザとなれば帰れる家が無くなった」という事実は、私の心に意外なくらい大きな穴を空けた。
穴が空いたら当然埋めなければならない。幸いにも銀行から金を借りられたので、遺産の全額を前金に入れて家を建てた。そのとき、多くの発見をした。
「家とは内密な空間である」
家を建てるとは、どんな家を建てるか考えることだ。参考材料は「間取りマニュアル本」か?不動産業者のアドバイスか?どちらも試したが、全然しっくりとこなかった。結局、参考にしたのは己の生まれ育った家だった。具体的には、私が生まれた(東京の)足立の家と、高校時代に引っ越した文京の家だ。
足立のほうは長方形の土地に長方形のニ階建てが素直に建っていた。文京のほうは三角形の土地に合わせた複雑な形の三階建てが建っていた。前者は丈夫だったが、後者は水漏れが絶えなかった。前者は水回りのもの(キッチン・バス・ランドリー)が一階に集中していたが、後者は元歯科医院だった中古物件ということもあり、二階にキッチン・ランドリー、三階にバスという特殊なつくりだった。前者にも後者にも共通するのは、玄関が土間のように広い点で、自転車を家の中で保管していたので長持ちした。
今述べた点はすべて、いま住む家を建てる際の参考材料になった。自転車が置ける広い玄関。一階に集中させた水回り。正方形に近い土地に正方形に近い二階建て。
結果として、新しいが目新しくはない、「主観的に親しみやすい家」が出来上がった。どうしてこうならなければならなかったのか?六年近く経った今も、ふと考えることがある。結論から言えば「家は内密な空間だから」ということに尽きる。
「主観的な親しみやすさ」は合理性よりも優先順位が高いものだ。と、このとき悟った。このような間取りにすれば効率的な動線になりますよ、だとか、そのようにしては空間を有効活用できませんね、だとか。マニュアルやアドバイザーなどが提供する理屈に従っているかぎり、「主観的な親しみやすさ」は手に入らない。親しみやすさの演出のために何が必要か?よく考えてみるといい。合理性について考えるのは、そのあとでいい。家の本質は「空間活用の合理性」ではなく、「内密な空間の演出」にこそある。
もっともらしい理屈で合理的に作られた家は、決してあなたに馴染まない。家を建てようとするなら、だれしも「個人史」をひもとかなければならない。何に親しみやすさを感じるかは人それぞれだからだ。繰り返すが、家とは内密な空間である。したがって、普遍的な(どの時代、どの地域にも当てはまる)理想の家は存在しない。
ならばなぜ、このような雑文を今したためているのかと言うに、「家のことは一般論に収斂できない」という「一般論」を、自ら家を建てることを通じて発見し、それを書き残しておきたく思ったからである。
終わり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
