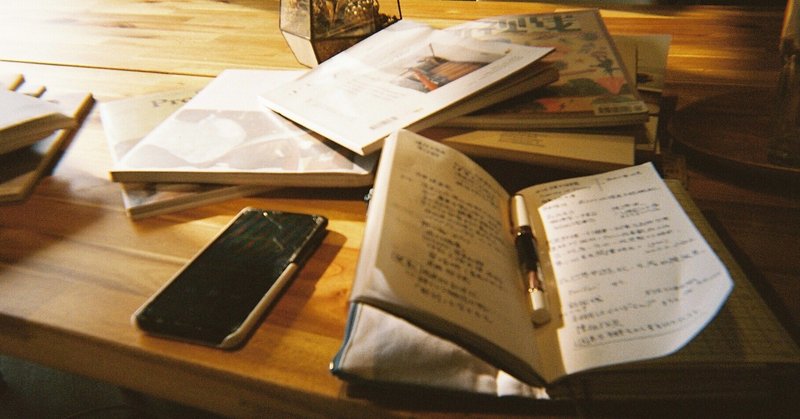
台湾3週間目(3/8~3/16)
4月、店のあちこちで新生活という言葉が踊る時期。私も新生活商機のターゲットだった。引っ越しをして、部屋を整えるためにIKEAや家具屋を走りまわり、そしてしっかり私の財布からはごっそり万札が飛んでいった。
つまり、そんなこんなで文章を書く時間を取ることができなかった。

というのは多分言い訳で書かないといけないと思いながらも後回しにしてきた。台湾3週目の記録。別に滞在していた時間に区切りをつけて、新しい生活を受け入れることに抵抗しようとしていたわけではないと思う。なんか、なんとなく。日々の生活に追われて書くことができなかった。社会人になるということは、そのなんとなくが増えていくことかもしれないと思うと今から少し鬱屈な気持ちになる。
1.中国語
最終週は「人」に会う機会に恵まれた1週間だった。この台湾滞在のために続けてきた言語交換で出会った人、2人出会った。2人ともある程度日本語が理解できる人だったというのは大きいが、それでも8割中国語で会話することができたという経験は自信に繋がった。3週間滞在してレベルが上がったかどうかは判断しかねるが、中国語の吸収力は確実に上がった。オール中国語の動画をみるのも以前より苦ではなくなった。しかし、それ以上に台湾にいるとYoutubeが台湾仕様になるのでアルゴリズムを通して多くの台湾の動画をみることになった。(帰国して3週間経つと、帰国直後の「耳が中国語に慣れた」的な感覚は急激に薄れたがそれでも中国語に対する障壁が少なくなった)
2.フェミニズム
台湾在住でフェミニズムに強い関心、かつ行動に移している方に出会う機会に恵まれた。今まで見てきて感じた疑問を台湾に長期住んでいる人に聞ける(それもフェミニズムに関して)って本当にラッキーだ。台湾のフェミニズム浸透具合や、「女書店」(台湾にあるフェミニズム専門書点)は扱うテーマに多様性という問題点という話があり興味深かった。

晶晶書庫という、1990年代に出来たLGBTQ専門の書店(今は本以外のものも売っている)に訪問。女書店といい、ずっと前からこのような場所があって、今も存続しているという点がとても興味深い。こういう性的マイノリティーのための空間があるっていいなぁと思ったが、ふとわざわざ「性的マイノリティーのための空間」ってなんだろうと思った。性的マイノリティーが”安心感を感じられる”空間だとしたら、他の空間は安心な空間ではないということだ。その空間の在り方についての関心の窓がフワッと開いた感覚がした。
3.書店巡り
3週間目は静かな書店巡りになった。拡張するよりは今まで行ったことのある書店に長く滞在するという体験をした。あとは、単純に体力に限界が来ていたので、ゆっくり休む空間があるブックカフェを中心に回る。
これはまだ仮定の話だが、図書館の形態をとっている施設が目につく。この一週間だけでも2件、滞在中計4軒廻る。

ちなみに最終的に書店は62軒廻ることができた!
買った本は全て合わせて10冊以上。

今は亀の歩みで読み進めている。
今回の書店巡りを2つの言葉を抽出したいと思う。
特に台湾での書店巡りには「韓国の書店巡りという補助線」が引いて見たもの、体験したものを解釈したという特徴が大きい。
今まで書店から通して「社会」を積極的に知ろうとした国は韓国が唯一だった。(日本は除外)それゆえに海外の書店の全てが韓国の書店事情だった。けれど、今回台湾で書店を廻った経験を通して、当たり前だが韓国の書店が全てではないことに気がついた。言い換えると、韓国の書店=「海外」の書店という雑なイコール式を作っていたことに気がついた。
以上の視点の習得は、書店巡りが「韓国」に限定していた自身の視野の狭さに気づくことになり、可能性を広げることができた。
もう1つは、「昔実行したくても実行する力量ができず残った後悔を再度自分で取り戻した」ということ。韓国の書店を巡る際にも記録を残して、共有したいという意思はあったものの、行う術を持っていなかった。しかし、台湾では「台灣書店巡遊」というタイトルをつけてインスタのストーリーで記録・共有することができた。今後も継続的に記録して発信するということをやっていきたい。
4.台湾を知る
3週目で一番大きい点は1.台北以外の都市に行った。2.現地在住の人に出会ったの2点だ。2週間で得た知識や疑問に思ったことを提げて現地在住の人とキャッチボールしていくことでより精密に構成していく作業。また、台北=台湾という構造になっていた視野に「台中」「新竹」を入れてもっと違う姿、生活があることを理解する作業から多角的に台湾を見ることができた。
①新竹に行く

新竹は高鐵で台北から約1時間の距離にある場所。目的は「或者書店」という新竹にある書店を訪問すること。

高鐵や、新竹市内の交通の弁の悪さ(特に台北との差が著しい)、そして新竹は或者書店が手がけた文化施設が多く存在しており「或者」文化圏が形成されていたこと、そして新竹市役所、新竹駅が日本統治時代の建物が今も使われているいた。
②台中に行く
新竹から台中は高鐵ではなく普通列車で行く。「海側」「山側」という路線に分かれており、かなりときめく。
台中は日本の地方都市の特徴であるように中心地を離れるとすぐ住宅地になること、そして古い書店が多いこと、最後に新竹程ではないものの交通の弁が大して良くなかった。

最後は台中から、台北に高鐵で帰る。しかし、台中駅と高鐵の台中駅はかなり距離の差があることを把握しておらず最後かなり焦った。
5.記録について
記録を残す。
どこまで残すか、どのような手段で記録するか。記録する時間をどう確保していくか。
この半年間、トラベラーズノートや、万年筆など記録に関する品をたくさん買い、実践していった。その結果がこの台湾留学で如実に現れた。
記録していくことは、完璧主義から離れることだと思う。完璧になるのを待っていて記録ができずに流れていった時間や、(後悔の)記憶が積まれていった。
台湾もそれを全て完璧に克服したわけではない。ただ以前ではできない方法で記録していき新しい記録の扉を開いた(自分調べ)ような気分だ。
(1)行く前
事前にどのような心持ちで留学を迎えたか、目標についてNoteに記す。
(2)滞在中
写真、日記(トラベラーズ)、Note、インスタグラム、フィルムカメラの5週類で記録を撮る。特にインスタグラムのストーリーで行った書店をレポすることは今までになり取り組みだったが周りから好評で嬉しかった。
(3)行った後
Note(今書いているもの)、滞在紀を別にまとめる。
→滞在中のようにタイムリミットがないので逆にのびのびになり「完璧」にしなければという影がちらつく。影を振り払いながら今のろのろと書き中。
親に出世払いをするとまで言って、7枚の支援申請書を書いて望んだ(長すぎると文句を言われ結局最後まで読まれず)今回の台湾滞在。
まるで頭の中を2次元から3次元にする作業をしているようだった。立方体を書くときに最初四角を書いた後、奥行きの線を斜めに入れる、まさにその作業だ。
奥行きの線だけを書いても、まだ立方体は完成しない。また立方体が完成しても中は空っぽです。その中に中身をたくさん詰めれるようにしたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
