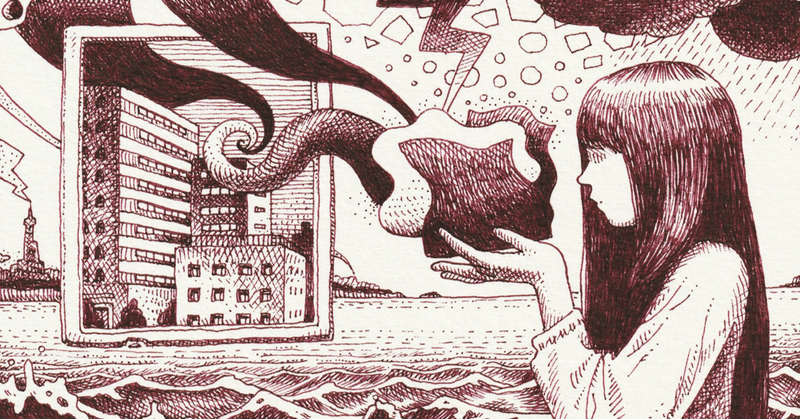
「声」を伝える文学 アレクシェービッチ『チェルノブイリの祈り』
2015年にノーベル文学賞を受賞したアレクシェービッチ。代表作『戦争は女の顔をしていない』で知られている。
今回は彼女のもう一つの代表作、『チェルノブイリの祈り』を読んだ。
旧ソ連のウクライナ領で起きた原発事故。その事故を様々な形で体験した人々(多くはベラルーシに暮らしている)に対して取材を行い、彼らが語った言葉をそのまま叙述していくスタイルが取られている。
冒頭のインタビューの語りから引き込まれる。消防士であった夫を亡くした人物による語り。これを読んでいるときの感情をうまく言い表すことができない。印象に残ったのは最後の部分。
私たちが体験したことや、死については、人々は耳を傾けるのをいやがる。恐ろしいことについては。
でも……、私があなたにお話ししたのは愛について。私がどんなに愛していたか、お話ししたんです。(27-28頁)
筆者自身は自分へのインタビューでこのように語っている。
何度もこんな気がしました。私は未来のことを書き記している……。(33頁)
まさに、事態はその通りである。「チェルノブイリ」自体は過去のものとなりつつあるのかもしれないが、そこで人々に起きたことは、未来でも起こり得る。
古代ギリシャの哲学者、アリストテレスは『詩学』で以下のようなことを述べている。
歴史家はすでに起こったことを語り、詩人(劇作家)は起こる可能性のあることを語る
アレクシェービッチは歴史家ではない。それは彼女は作中で各タイトルに「声」や「合唱」という言葉を用いていることからもわかる。彼女は歴史を書いているのではなく、無数の人々によって詠まれた詩を伝えているといった方が正確だろう。
歴史は忘れ去られる。それに抗うかのように、彼女は人々の声を丹念に書き記す。
ぼくは証言したいんです。僕の娘が死んだのは、チェルノブイリが原因なんだと。ところが、ぼくらに望まれているのは、このことを忘れることなんです。(49頁)
私はこわい。愛するのがこわいんです。フィアンセがいて、戸籍登録所に結婚願をだしました。あなたは、ヒロシマの〈ヒバクシャ〉のことをなにか耳になさったことがありますか? 原爆のあと生き延びている人々のことを。かれらはヒバクシャ同士の結婚しか望めないというのはほんとうですか。ここではこのことは話題にならないし、書かれない。でも、私たちチェルノブイリの〈ヒバクシャ〉はいる……。(121頁)
1945年、原子爆弾が二度投下された。
1986年、チェルノブイリ原子力発電所事故が起きた。
2011年、福島第一原子力発電所事故が起きた。
あの震災から10年という言葉が連呼される。だがこの10年間、人々は本当に事態と向き合ったのだろうか。勝手に区切りをつけて、原発事故も「過去のもの」にしていないだろうか。
作中で映画カメラマンが以下のように述べている。
いつだったか、強制収容所にいたことがある人々を撮影したんです。彼らは、おたがいに顔を合わせるのを避けたがった。ぼくにはその気持ちがよくわかる。みなが集まって、戦争の思い出話に花を咲かせるのはなにか不自然なものがあるんです。ともに屈辱を体験した人間、あるいは、潜在意識の奥底で人がどんなものであるかを知ってしまった人間は、おたがいに避けたがるものなんです。チェルノブイリで、ぼくが知ったり感じたりしたこと。そのことは話したくないんです。(128頁)
この語りとは真逆と感じたのが、相馬市長の雄弁な挨拶だ。「われわれ」という主語から始まり、「大きな成果をあげた」と述べる。まるで戦勝スピーチのようだ。
聖火リレー2日目。出発式で相馬市長が「放射能によって病気になった福島県民はおりません」と挨拶。急に胸が苦しくなる。私は原発事故で心身共に体調を崩された方を無数に知っています pic.twitter.com/29DRIqL1k2
— 三浦英之 新刊「白い土地」重版出来 (@miura_hideyuki) March 26, 2021
『チェルノブイリの祈り』では、当時のソ連共産党がいかに情報を隠蔽したのか、いかに作業にあたる人々を英雄に祭り上げて事故に「勝利」しつつあるかのように振る舞ったのかが随所に書かれている。果たして「勝利」とは何か。
戦争だといわれています。戦争世代の人々は比較している。戦争世代? あの世代の人は幸せじゃないですか! 彼らには勝利があった。勝ったんですもの。私たちは? 私たちはあらゆるものを恐れている。子どもの身を案じ、まだ、いもしない孫のことを心配している。みながうつ病気味で絶望感をいだいている。チェルノブイリは、暗喩であり、象徴なんです。(218頁)
ちょうど聖火リレーが始まった。復興の象徴として、福島県がスタートの地に選ばれた。
では、復興とは何を意味するのだろうか。何の復興なのか。誰のための復興なのか。「私たちはあの震災、あの原発事故にもかかわらず、皆さんの支援のおかげで立ち直れました」と世界に示せというのだろうか。
でも、これもやはり一種の無知なんです、自分の身に危険を感じないということは。私たちはいつも〈われわれ〉といい〈私〉とはいわなかった。〈われわれはソビエト的ヒロイズムを示そう〉、〈われわれはソビエト人の性格を示そう〉。全世界に! でも、これは〈私〉よ! 〈私〉は死にたくない、〈私〉はこわい。チェルノブイリのあと、私たちは〈私〉を語ることを学び始めたのです。自然に。(253頁)
相馬市長の挨拶の主語は「われわれ」だった。
「われわれ」ではなく、「私」の声を届けること。「われわれ」の「合唱」で「私」の声をかき消さないこと。オリンピック、復興、絆といった大きな物語に回収されないこと。もはや語るすべを失ってしまった人々の声に耳を傾けること。このことが求められていると思う。
もはや語るすべがない人々の声にどう向き合うのか。こうした視点から書かれた本に、石牟礼道子の『苦海浄土』がある。アレクシェービッチが石牟礼のことを知っていたのかは分からない。だが、時や場の違いをこえて、二つの作品は共鳴しているように感じずにはいられない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
