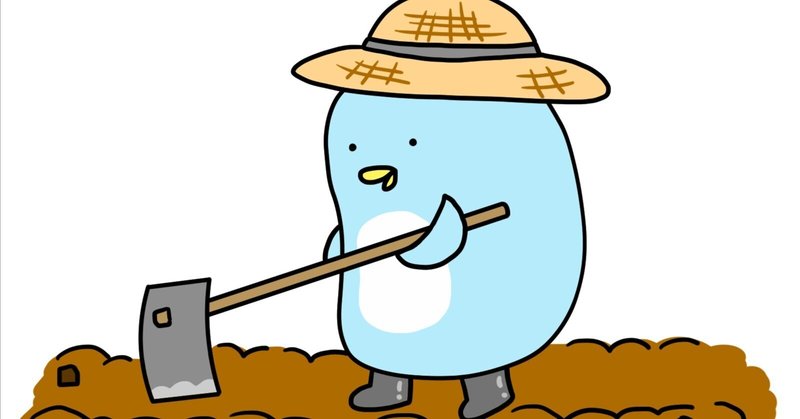
【歴史概要88】倭の朝貢・倭国大乱
①日本には6世紀ごろまで倭人によって書き残された歴史的な資料がほとんどない。ゆえに中国大陸の歴史書を参考とする。
②日本は倭と呼ばれていた。古代中国の王朝は黄河流域の内陸部にあった。満州や朝鮮半島、倭などの東方に住む異民族をまとめて東夷と呼んだ。
③後漢の時代に成立した歴史書『漢書』の「地理志」によればBC2世紀からBC1世紀ごろ倭には約100の国があった。倭人は朝鮮北部の楽浪郡(漢王朝の支配地域)に度々使者を送っていた。
④5世紀に成立した『後漢書』の「東夷伝」には57年に倭の奴国王の使節が後漢を訪れて光武帝から臣下のしるしとして金印を授与されている。奴国は九州北部にあった小国と云われている。
⑤『後漢書』の「東夷伝」には107年に倭の師升(すいしょう)王が後漢の安帝に160人の生口(奴隷)を献上したという記録が残っている。
⑥中国大陸の王朝は周辺の異民族から献上品を受ける代わりに相手国を臣下とみなして保護して返礼を与えた。
これが朝貢である。倭にとって大陸の王朝に認められる事はステイタスであった。
⑦『後漢書』の「東夷伝」には倭国大乱という戦いが記録されている。2世紀後半後漢において桓帝から霊帝に移行した時期にあったとされる。日本列島内の様々な勢力が争い、有力な盟主がいない状況であったとされる。
⑧『三国志』の「魏志倭人伝」(魏志東夷伝の倭人条)に同様の記述がある。奈良県天理市の東大寺山古墳からは後漢の霊帝の時代の年号が刻印された鉄剣が発掘されており近畿地方にも中国王朝と関係を持つ小国があったと云える。
⑨大乱の経過は不明な部分が多く、九州北部の小国が連合して
近畿に攻め込んだか、近畿の勢力が九州に攻め込んだと考えられている。どちらが優勢であったかはわからない。
⑩倭国大乱の時期は九州北部から瀬戸内、近畿では高地性集落が増えている。戦争になった場合に守りやすいためである。この頃は武具や鉄器が発達した。
⑪倭国大乱を通じて小国同士の統合が進んだ例としては近畿地方を中心に広範囲で同じような土器が広まっている事だ。同時に銅鐸がすたれていく。各地で銅鐸を祀る宗教的な習慣をもった勢力が制圧された。
⑫倭国大乱の収束とともに邪馬台国の卑弥呼が出てくる。
■参考文献
『30の戦いからよむ日本史 上』小和田 哲男 日本経済新聞出版社
学習教材(数百円)に使います。
