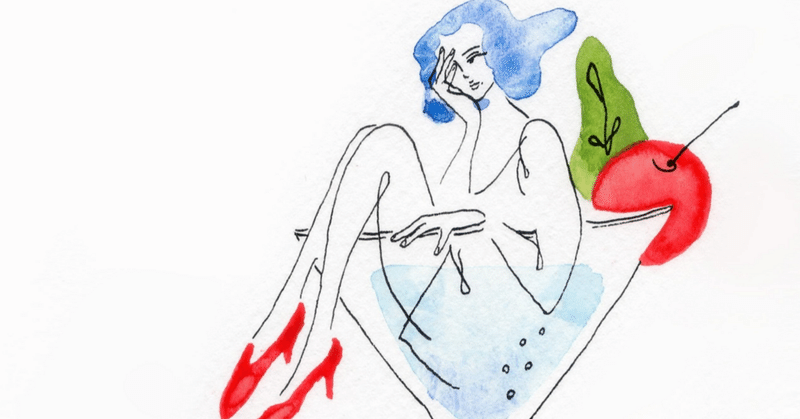
"もし僕らの言葉がウイスキーであったなら"
「これはね、村上春樹が愛したお酒なんだ」そう言って、ウイスキーグラスに注いでくれるカティサーク。帆船に黄色のラベルが目印、ブレンデッドウイスキーと呼ばれるそれをひと口。胸が熱くなって、どきどきするのはお酒のせい?それとも、なんて想いながら見つめ合う瞬間。そんな夜を、愛していた。
*
昨日は越してきて初めて、夜の街へ出かけた。地元のお洒落な場所なんて行き尽くしたと思っていた高校時代。大人になってから歩く街はなんだかきらめいていて、違う街みたいだ。きっと、それは何年も歳を重ねて見えるようになった景色。お小遣いを必死に数えなくても大丈夫になったことを、嬉しく、少し切なく思う。お小遣いの代わりに握りしめた自由は、わたしを新たな出会いへと運ぶ。
出かけたのは飲み屋さん。何軒か巡りながら、その場所場所でのおすすめを頼む。一杯飲んで、さっと出る。そんなことができるようになったのだな、わたし。ひとりで満足気、大人への階段を上がった気分だ。
締めに人生2回目のオーセンティックバーを訪れた。と言っても親戚の知り合いがやっている場所。流石に知らないバーに入る勇気はまだない。最後の勇気とともに扉を開けると、優しくおじいさんが迎えてくれた。メニューのないバー、おそるおそる頼むカクテル。カウンターだけの小さなお店は、光が美しくたゆたう。「グラスホッパーを、お願いします」と言うわたし。おじいさんの振るシェイカーの音が響く。
棚に並んだウイスキーを見て、アイラ島のものがあることに気づく。「これって…」「ああ、アイラ島のウイスキーですよ、知ってらっしゃるんですか?」わたしは記憶の底を探り当てて、「あの、、たしか村上春樹のエッセイで…」「もし僕らの言葉がウイスキーだったなら?」「そうです!」だいぶ昔に読んだエッセイの記憶が正しかったことに安堵し、そしておじいさんが知っていることに嬉しくなる。それから、二人で少しウイスキーの話をした。
わたしは元々ウイスキーが好きなわけではない。どちらかというと実は苦手。けれど、大学時代に付き合っていた恋人がそれはもうお酒が好きな人で、毎日聞かされていたおかけで詳しくなっただけなのだ。そんな甘くて苦い記憶が、今のわたしに寄り添ってくれる。
「テイスティングしてみて」とアイラ島のウイスキーを出してくれるおじいさん。少し飲んで、スモーキーな香りにクラッとする。大人の味を、美味しく感じられるようになったことが歳をとったことの証。
カクテルの名前、ウイスキーの名前。おじいさんとやりとりする会話。わたしはずっと、一人ではなかったことに気づく。もう恋人たちの記憶は、わたしの染色体に刻まれていて、彼らの思い出が今のわたしをつくっていて。昔の恋人がよく作ってくれたカクテル、一夜を過ごした彼と飲んだウイスキー。お酒とともに解かれてゆく思い出は、わたしのこころをあたためる。
「綺麗な飲み方をしますね」そう言ってくれたおじいさんには悪いけれど、わたしの酒癖はひどいものだ。つい最近までひどい飲み方しができなかった。そんな若さが失われてゆくことに、苦い微笑みと一抹の寂しさを抱える。
歳を重ねて見える景色がある。そして、歳を重ねるごとに知る新しい自分がいる。人生に飽きてる暇がないくらい、毎日はめくるめく幸運と不運。出会いも別れも、増えてゆくだけの人生だから、今日の出会いを慈しみたい。
1秒後には思い出になる今を生きるわたしたち。美しいことばかりではないだろう、悲しいことも苦しいことも溢れてゆくだろう。それでも、時間は"美化"という魔法をかけてくれるから。だから精一杯この世界を楽しんでやろうと思う。恋人たちの想い出ともに生きるわたしを、出会うたびに変わってゆく自分を。
最後にカティサークをいただいた。昔の恋人が教えてくれた、村上春樹の愛するウイスキーを。バーの片隅で、彼と笑い合うわたしが見えるようで、煙が目にしみる。ほろ苦く、微かな甘さを感じながら、わたしも歳を重ねる。ウイスキーのように、熟成されてゆく人生はどんな味になるだろうか。死んだ後でしか分からない"何年もの"が、長く続くように。
いつか会ったら乾杯してください、わたしの苦い失敗と甘い思い出を囁くから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
