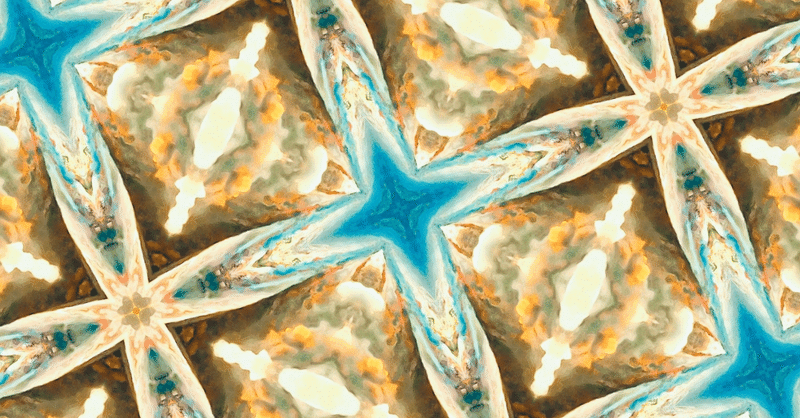
【小説】目に見える祝福
人の言葉が、物質となって見えるようになった。
そんなことを言うと、頭がおかしくなったと思われるに決まっている。だから絶対に私はそれを人に言うまいと決意を固めた。生まれてこの方、意志薄弱を絵に描いたような生き方をしてきた私でも、流石に最低限の思慮分別は身に着けている。恐らくは。
他人からどうやっても理解されそうにないが、それは同時に確かに事実なのだからしょうがない。
『人の言葉が物質となって見える』。
もっと分かりやすく言えばそう、誰かが発言する度に、ぽろぽろと何かしらの形が産まれてくるのだ。
「おはようございます」
住んでいるマンションの、顔見知り程度の隣人からの言葉には、薄っぺらい、サンドイッチ用の食パンのような欠片がぽろん、と零れる。
「相沢さん。この前頼んでたプレゼン資料、もう終わってるかな?ちょっと早めに貰いたいんだけど」
仕事のペースが合わない上司の言葉は、中学生が初めて作ったバレンタインのチョコレートみたいに歪な形のブロックのようなものが、ざらざらと湧き出す。
私はそれらの物質を眺めていると、何だかおかしくなって、自然とへらへらしてしまう。そんな私を見る他人からは、大概怪訝そうな顔をされる。そこで慌てて顔を取り繕う。
私はそうやって、「社会」の一端を必死に掴んで生きている。そんな自分が嫌いではないのが救いだ。
そもそも、私がこんな体質(という表現が適切かは分からない)になったことには、ちゃんとしたきっかけがある。
うちの会社の経理、池永くんのせいだ。
その日、私が早くお昼ご飯の時間にならないだろうかと、頭の端っこでぼやぼや考えながら、大して重要でもないメールの文章をこねくり回していたときのことだ。池永くんが私のデスクまでひょっこり現れた。
「相沢さん、この領収書、間違ってます」
「へ?」
社会人らしからぬ相槌を打った私を無視して、池永くんは私が経理に提出した書類の何が間違いなのかを滔々と話した。
池永くんの論理的な説明を耳で受け止めながら、私は彼の書類に落とされた目元や、日本中のサラリーマンが何千人と付けていそうな、ブルーのネクタイが時折揺れるのを目で追っていた。
「‥‥‥あのう、聞いてますか」
池永くんの心地よい声に、ぐしゃり、と苦々しい皴のようなものが混ざった。しまった、と思った私が慌てて顔を上げると、彼と思いっきり顔を見合わせる形になった。
「相沢さん、言いたくないんですが。前にも同じことをお伝えしたんですよ」
ひゅっ、と流れ星のような煌めきをまとった欠片が、池永くんの肩から落ちた。
「たかだか経費の領収書ぐらい、と思っている方は多いかもしれないんですが、それでも一々チェックしてこうやって小言を言わなければいけない僕らのことも考えてほしいんです」
池永くんの渋く響く声音に、ぽん、と小さな石を投げ込んだ時のような波紋が広がっている。彼がやや躊躇いがちに言葉を発する度に、さっきの欠片がどんどん落ちては、床に転がり、一瞬にして消えてしまう。
余りにもその光景が綺麗で、私は思い切り目を見開いた。そして、池永くんから今度は本気で苛々したように「相沢さん、聞いてますか!」とトゲのある言葉をぶつけられた。
そうして彼から産まれた欠片は、私が今まで見て来た中で一番美しい物質だった。
「池永くん待って」
「はあ?」
「やだ、もっと拾いたいのに。すぐ消えちゃう」
「あのねえ‥‥‥」
「分かった。これからちゃんと経費計算も溜め込まずにやります。書類の不備も無くします。極力」
だから、と私は池永くんの言葉を遮るようにして言った。
「あなたの話、もっと聞きたい。一緒にお昼食べに行きましょう」
池永くんの返事より先に、昼休憩を知らせるチャイムがオフィスに響く。
「ほら、早く」
じれったくなり、池永くんの手を握ると、彼が「いや、あの」とまごまごし始めた。
きらきらと輝く物質が、さっきよりも明らかに質量を増している。勢いよく動き出した工場から増産されているような、その煌めきを目に焼き付けながら、私はにっこりと微笑んだ。
「ねえ、一生私と一緒におしゃべりしてくれる?」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
