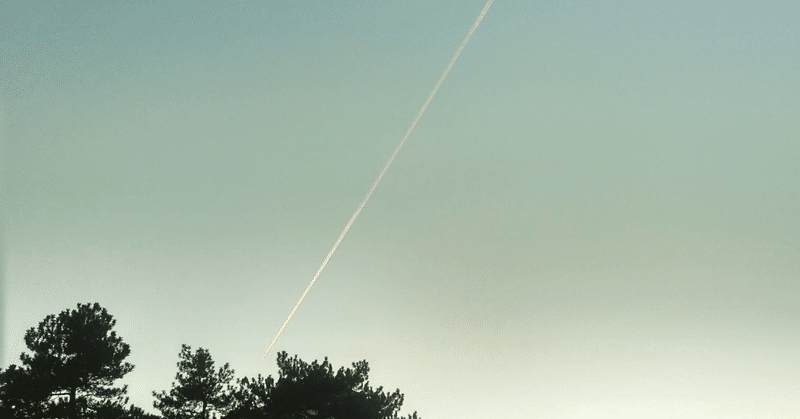
【エッセイ】例えば緩い幸せが
2011年1月
京都から乗車したサンダーバードが、まだ暗い道を規則正しい音を立てて北上する。
滋賀県に差し掛かったあたりから車窓に写る景色は真っ白になる。
私が住んでいる町に雪は積もらない。
だからか、幼い頃から雪を見ると無条件で喜んだ。
いつだったか。
大学近くの居酒屋を出た後に、ふわふわと雪が舞う冬の空を見上げてはしゃいだら、君は言った。
「俺の生まれ故郷の雪は尋常じゃない」
私達は無邪気に返した。
「羨ましい」だなんて。
2人乗りの座席を回転させて、私たち4人は対面で座った。泊まる予定も無いから荷物も少ない。
昨日の深夜に連絡を受けてすぐに富山へ向かう事に決めた。居ても立っても居られないのは皆同じで、始発で行こうと決めた。
皆、無言だった。
けれど、眠れなかった。
京都駅で買った缶コーヒーはすっかり冷めてしまって、飲む気にならない。
車両の前の方では私達と同じ位の年齢の学生達が大きな荷物を足と足の間に挟み、ぎゅうぎゅうになりながら談笑していた。
北に進むこの列車に乗り、彼らはおそらく何処かで冬休みを楽しむのだろう。
今日も明日も明後日も、自分達が死ぬ可能性などこれっぽっちも、微塵も感じずに。
君が「風邪が治らない」と言って、でもそんな事は多分明日になればどうでも良い事になってると思っていて、
とにかくこれから始まる就活が憂鬱だと嘆いたあの日から一年以上経つ。
髪染め直さないとなあ。
スーツって入学式の時のでいいのかなあ。
説明会の予約入れなきゃ。
嫌だ嫌だといいながら、結局は皆が前ならえとすることを、君はあの狭い部屋の中でどれ程したいと願ったのだろう。
風邪は治るどころか、
冬休みが終わった時には病名が付いていた。
君は、「あんな田舎には絶対戻らない」といつも言ってたけれど、4年になる頃には部屋を引き払って私達の知らないあの北国へ帰ってしまった。
「確かに尋常じゃないわ」
富山に降り立った私達は、その光景に思わず声が出る。
私達は道路脇に聳え立つ圧倒的な雪の塊に息をのんだ。
底の薄いスニーカーで踏む雪はぼそぼそと音を立てて、足先を直ぐに冷やした。
乗り込んだタクシーでは、行き先が病院だったのにも関わらず人懐こい運転手が一方的に話をする。
学生4人組は、たとえ浮かばない顔をしていても側から見れば箸が転んでもおかしい年頃に見えるのだろうか。
「関西からきたのかい?」
「海老は食べて帰りなね。白海老。鱒寿司なんかよりも絶対食べなね。」
ぼうっと聞いていた割には覚えている。
陽はとっくに登っている時間だったのに、道路の両脇の雪のせいか街全体が薄暗く、とても静かで、運転手の明るい声だけが場違いに車内に響いた。
私は泣くだろうか。
泣かないだろうか。
私の知ってる君は今も元気なまま。
髪が抜けたって、アザが消えなくったって、綺麗に染めた金色の髪をかきあげて屈託無く笑う姿しか浮かばない。
薄暗いリノリウムの床を、雪で湿った靴裏がキュッと音を鳴らした。エレベーターの横にある案内板に目をやる。ICUは3階だったが、私達がここにとご両親に呼ばれたのは5階だった。
個室に設置してあるベッドは、君が持つ180cmの身体が存分に支配していて、逞しい両足は今にも歩きそうなほどしっかりしているのに、それなのに、もう二度と目を覚ます事は無いらしい。
長きに渡る与薬、闘病生活の末に目の前に横たわる君の顔は私の知っている君では無かった。
私は、皆は、その事実を受容れているのかすらよく分からなかった。
たった1時間のテレビのドキュメントで、全く関係のない人が亡くなっても涙は簡単に流れるものなのに。
でもそれは、受容れるも何もする必要がないから無責任に流せるのだろう。
君を看取って、私たちは白海老も食べずにサンダーバードに乗って帰った。
疲れているのにやっぱり寝れず、喋る気にもなれずに、iPodで音楽を聴いて目を閉じた。
思い違いは空のかなた
さよならだけの人生か
ほんの少しの未来は見えたのに
さよならなんだ
昔 住んでた小さな部屋は
今は他人が住んでんだ
君に言われた ひどい言葉も
無駄な気がした毎日も
あの時こうしてれば あの日に戻れれば
あの頃の僕にはもう 戻れないよ
たとえばゆるい幸せがだらっと続いたとする
きっと悪い種が芽を出して
もう さよならなんだ
恋人との別れの詩なのだろうか、
過去の自分との決別の詩なのだろうか。
何にせよ、私たちが蔑ろにしながらもひたすらに謳歌した4年の青い春に、終わりを告げられているみたいだった。
あれから10年が経つ。
君が生きていれば今月で33歳になる。
33歳の君を簡単に想像出来てしまうのは、君の23年の生涯のうち、最後の4年間を色濃く共有出来た友人の特権だろう。
君は恐らく富山に帰ろうとせずに、どこかの都市でサラリーマンをして、そこそこ稼いで、もしかしたら良い父親になっていたかもしれない。
あの時病室で流せなかった涙は結局はどこにも持ち越す事は無かった。
あの日サンダーバードの中で見た学生の様に、私は今日も明日も明後日も、自分達が死ぬ可能性などこれっぽっちも微塵も感じずに生きていくのだろう。
でもその代わりに、私はこの10年、路頭に迷う日やどうしても悲しい日に「こんな時君ならどうしただろう?」と想像を重ねる事で君の死を受容れてきたと思う。
そして10年経っても明確にあの日の事を文章に書くことが出来た。
サンダーバードから眺めた車窓、圧倒的な雪、タクシーの中での会話、君が横たわる病室、帰りに聴いた音楽。
それも、ずっと忘れないでいると思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
