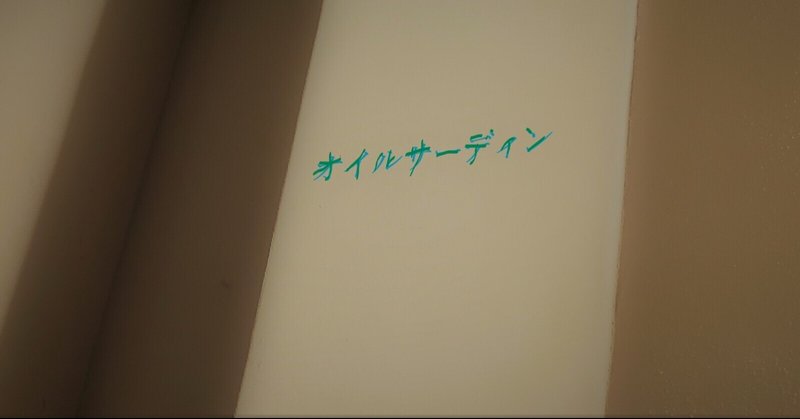
オイルサーディン
そのバーの内装には見覚えがあった。
コンクリート打ちっぱなしの「オシャレな」バー。
もっともずいぶん昔のことなので、今でもそういうのが「オシャレ」なのかは知らない。
ともかく私の大学時代はそうだった。
水森も私も、酒を飲む店なんてチェーン店の居酒屋くらいしか行ったことがなくて、ちょっとオシャレなバーとやらに行ってみよう、ということになって二人で出かけたのだった。
大学に入って最初に言葉を交わしたのがこの水森で、1、2年の頃はよく一緒に遊んだ。そのうち、別に仲たがいしたわけではないがそれぞれ別に仲の良い友人ができて次第に会うことも少なくなり、大学を出てからは一度も会っていない。
もうずいぶん昔のことだ。
その「オシャレな」バーに入ってはみたものの、カウンター席に座るのはちょっと気おくれがして、小さな二人掛けのテーブル席に座った。
大学時代に一度だけ入ったことのあるそのバーの、その時と同じ席に座っている。
たしかあの時はあまり大きくない音量でマイケル・ナイマンの曲がかかっていた。
これもその頃の「オシャレ」だった。
クレスプキュール。
しかし今は音楽はかかっていない。
そして向かいには昔のままの水森が座っている。
水森がこちらに身を乗り出して、
「なあ、あの女、カッコイイな」
と言ってきた。
もう、少し酔っているようだった。
誰のことを言っているのかはすぐわかった。
私たちがこのバーに入った時には、まだ早い時間だったからか、先客は一人しかいなかった。
バーに入ってどこに座ろうかと店内を見渡した時、カウンターに座っているその女は目を引いた。
金髪のボブ。
青いコート。
私は「うん、そうだな」と小さな声で答えた。水森の声が結構大きかったので、あの女に聞こえたら恥ずかしいな、と思った。
「俺、ちょっとトイレ」
と言って水森が席を立った。
ちょうどそこに、店員がおつまみを運んできた。
オイルサーディンを缶のまま、上に刻んだねぎを乗せて火にかけたものらしい。
まだグツグツいっている。
視界のすみで青いコートの金髪の女が立ち上がったのが見えた。
もう帰るのかな、と思ったが、女はこちらの席にやって来る。
そして私の前に、今まで水森が座っていた場所に腰かけた。
女が当たり前のようにそこに座ったので、私も当たり前のようにその女を見た。
色が白く、目が大きい。
美人と言えるのかもしれないが、なにか人を不安にさせる顔だった。
目と目の距離なのか、目と口の距離なのか、なにかほんのちょっとだけバランスがおかしいような気がした。
ひどく顔が大きく見える。
真っ白で、大きい。
私も少し酔っているのかもしれない、と思った。
女はこちらをまっすぐに見つめて、
「あなたのどこが最低なのか、教えてあげる」
と言った。思ったより低いしゃがれた声だった。
女はオイルサーディンに手を伸ばした。
右手の親指と人差し指を無雑作に缶の中に突っ込む。
火傷してしまうのではないか、と心配したが、女は平気な顔でオイルサーディンを一匹つまみ上げ、それを自分の前に、取り皿ではなくテーブルの上にじかに置いた。
「ひとつめ」
と真っ白で大きな顔で女が言った。
親指と人差し指に付いた油をゆっくりとしゃぶり、それから話し始めた。
「あなたが高校一年の時のクラスメートで、赤井君ていう子がいたの憶えてる?」
高校一年?
赤井君?
「ちょっと吃音があって、背が高くてひょろっとしてて、おどおどした感じの子。
あなたとは友達、という訳じゃなかったけど、席が近かったせいもあって、けっこう話していた」
何の話をしているのか。
「ある日あなたのクラスに転校生が来たの、武田君っていう子。
思い出せない?
大柄で、わりと活発な子で、すぐにクラスになじんだわ」
高校一年の頃の転校生。
それはなんとなく憶えているような気がする。
「武田君が転校して来て一週間くらいたった日、掃除の時間、渡り廊下のそばで男子が何人かでたむろしていたの。わりとクラスの中でもなにかと中心的な感じの子たち。
あなたはそのグループに入っていたわけじゃないけど、その時はたまたまその中にいた。
転校生の武田君もいた。
赤井君はいなかった」
女は自分の前に置いたオイルサーディンを右手の人差し指でつついた。
何か汚い物でも触るように。
テーブルの上に直接置かれたオイルサーディンは、もう食べ物のようには見えなかった。
「そこで、赤井君の話が出たわよね。
グループの中でもリーダー的な感じの子が、赤井君のしゃべり方をからかうようなことを言った。で、他の子もそれにあわせるように赤井君のことを馬鹿にしたようなことを言った。
武田君はちょっと困ったような顔で聞いていた」
急に、その時の光景をはっきりと思い出した。
その時の日差しの当たり具合も、辺りのざわめきも。
その場にいた武田君の顔も。
その時、私もやはり赤井君を馬鹿にするようなことを言ったのだった。
まわりに調子をあわせてうっすら笑いながら。
実際には赤井君のことをそんな風に思ったことは無かったのだが、その場の雰囲気でそんなことを言ってしまったのだった。
「その時に転校生の武田君があなたの方を見た。憶えてるよね」
そう。憶えている。
あの目は忘れられない。
「あなたは割と真面目だと思われていたし、赤井君ともよくしゃべっていた。武田君もそれを見ていたから意外だったんでしょうね」
そう、たぶんそうだろうと思う。
あ、こいつ、こんなこと言うんだ、という目。
「なにが最低なのかわかる?」
と女が言った。
「あなたは自分が赤井君のことを悪く言ったことなんて何も気にしてない。ただ武田君にどう思われたか、それだけが気になっているの。
もう赤井君の顔も憶えていないのに、その時あなたを見た武田君の表情は忘れられない。自分が何をやったか、それが良いことだったのか悪いことだったのか、そんなことはあなたには意味がないの。ただ他人にどう思われているか、それだけが気になっているの。
それって最低だと思わない?」
女の言葉がゆっくり地面に染み渡るように私の中に染み渡り、それは少年時代のちょっとした取るに足らない思い出などではなく、その頃から今にいたるまでずっと途切れることなく続いている自分の本質であり、そしてそれは本当に最低だな。と思った。
本当に最低だ。
女は大きくうなずいて、そしてもう一度オイルサーディンの缶に手を伸ばした。
今はもうそんなに熱そうでもない。
女はまたオイルサーディンを一匹つまみ上げてテーブルの上に、さっきの一匹に並べて置いた。
「ふたつめ」
と女が言った。
私が最低であることを示す二つ目の話が始まるらしかった。
水森はまだトイレから戻ってこない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
