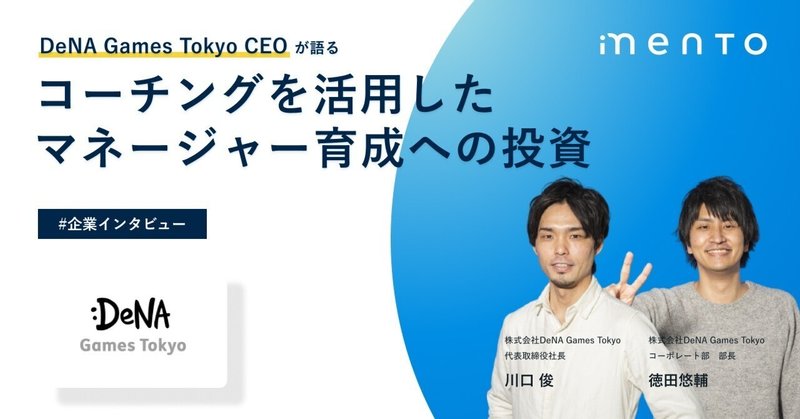
DeNA Games TokyoのHR組織に学ぶコーチングを活用したマネージャー育成への投資


自分自身で内省して変化・成長できるリーダーの育成にmentoを導入
ーmento for Businessの導入背景を教えて下さい
徳田さん(以下、徳田):コーポレート部門長として、「未来に向けての投資」という部分と「直面していた課題」の2つの点で打ち手を探していました。
DGTは事業を大きくしているフェーズで、組織も拡大しています。そのなかで、事業を引っ張る存在であるリーダーを、“強いリーダー”へと育てあげることが中期的に不可欠でした。業務パフォーマンスは高い人材がそろっているものの、チームをまとめる「リーダーシップ」の発揮には別スキルが必要ですからね。
そしてパフォーマンスを安定させること。これが直面していた課題です。あらゆる状況でも安定した成果を出すには、自分自身の力で内省して、気づき、成長できる人材であること。それが組織の成長という視点でも必要でした。この2点から、コーチングという手法を検討することにしました。
川口さん(以下、川口):上長として、日々のマネジメントでは部長陣が直面している課題やトラブルに対して解決のサポートは心掛けていました。ですが、人材開発といえるレベルのマネジメントやサポートとなると、そこは僕の得意な領域ではないとも感じていて。そして、徳田が言っていた「安定感」は、僕自身も感じていた課題ですね。

育成マネジメントのアウトソースにより、育成の質を上げる
ー育成をアウトソースしようと思った背景について
川口:自分のスタイルと違ったやり方を求められたり、取引先とのやりとりで納得しにくいオーダーが出たときなんかに、判断が鈍ったり、その問題にとらわれてパフォーマンスが明らかに下がるなど、自分が“ブレる”感覚があって。その“ブレ”を客観的に把握して自分でシューティングできる力が、特に部長以上のマネジメント層には必要だと考えていました。
そこで徳田が提案してくれたコーチングという方法に目をつけました。以前別のタイミングでコーチングを受けたことがあり、よい感触だったので「これはいい機会かも!」と思ったんです。
徳田:僕としては、コーチングは「マネジメントのアウトソース」という感覚でした。本来、マネジメントというのは組織への深い理解や関係値を求められるので、アウトソースするという発想が出てきにくい領域だと思います。
ですが、人材育成レベルのコーチングに関してはむしろ外部へ発注したほうが質も上がるのではと仮説を立てたんです。というのも、直接業務に関わるようなトピックであれば、マネージャー陣が責任を持って厳しいオーダーをしなければならない場面もあります。一方で、具体業務に限らない抽象課題の内省という観点では、業務接点の無い方と対話してこそむしろ深く内省に集中出来るという仮説があり、そこを外部のコーチにアウトソースするようなイメージでしたね。

自分と向き合うコーチングが“セルフリビルド”のカルチャーにマッチ
ーコーチングの対象メンバーは?
徳田:リーダー育成という点では社員を3階層に分けていて、そのうちトップにあたるリーダーを対象にしていました。執行の責任を持つ各開発部門の部長ですね。育成のアプローチとしては内省を促すことを目標にしました。
2階層目、例えば全社横断型のプロジェクト責任者や開発部門内のミドルマネージャーに対しては、各部長が1on1をおこなうなどで定期的に育成に取り組んでいます。1on1で短期的な課題解決に取り組む一方で、メンバー一人ひとりの成長を促すために育成のゴール設定や、そこへのアクションプランの策定も毎月行い、僕と川口と担当の部長とでチェックしています。
ーmento for Businessを選んだ決め手は?
徳田:シンプルな機能性や、コスト感が見合った理由が大きいです。
川口:以前僕は別の企業から提供されていたサービスを受けたのですが、プログラムがパッケージ化されていて、導入にあたっては費用的にも時間的にもコストが高いという印象でした。自分には不要だなと感じるプログラムもあって、少し使い勝手の面に課題があったんです。
徳田:その点、mento for Businessはテーマを個別にカスタマイズできたりレイヤー毎に使い分けたりと、コーチングを受ける人一人ひとりに合わせて内容を変えられるというのが魅力的でしたね。それから、何といっても参考になったのはSNSなどでの評判のよさ(笑)実際に利用した人のエンゲージメントの高さがどのサービスよりも際立っていて印象的でした。サービスを知ったのも、Twitterでフォローしている人が体験談をつぶやいていたからなんですよ。
また、導入に向けて社内のリーダー・マネージャーを巻き込んでいく際に、弊社の場合は「なぜコーチングを導入するのか?」という疑問の声はあまり挙がらなかったです。組織の思想とコーチングがマッチしたのかなと感じています。
川口:DGTでは、行動指針「REBUILD」を一歩深めたような「セルフリビルド」というワードをメンバーたちが生み出しているぐらい、内省に対する意識が強いと思います。自分のリーダーシップの幅を広げたいとか、組織にいい影響を与えたいという想いがある部長ばかりで。むしろこの機会になんとか自分も変わってやろう、という気持ちが伝わってくるメンバーが多かったですね。
コーチングを経て、大きな変化を遂げたメンバーの存在
ーコーチングを受けてみて、どんな変化がありましたか?
徳田:僕自身は、人とのぶつかりや意見の相違があったときにうまく折り合いをつけるのが苦手だったんです。コーチには自分が「正しい」と思っていることに対して、別の目線から問いを立てて考えていくという「一人二役」的な考え方をサポートしてもらい、考え方を少しずつ変化させていきました。
川口:徳田は本当に変わりましたね。他責思考だと「あっちが悪い」で終わりにできるから楽じゃないですか。でも、そこをずっとコーチのサポートを受けながらもがいているのを見てました。逃げずに自分自身と向かい合ってくれたのはコーチがいたのも大きいと思います。コーチングの後に何らかのアクションを起こしてくれることが増えて、まさに「人材開発」といえるような変化をもたらしてくれたと思います。
徳田:僕と同時にコーチング受講した他部門の部長の変化も劇的でした。
川口:その彼は元々クリエイター出身だったので、組織マネジメントや採用、人事評価などそれまでと違う情報のインプットにかなり疲弊していた印象でした。自信もないし部長を辞めたいという話も聞いていたほどです。
徳田:元々、すごく真面目で一生懸命なマネージャーで、ゲームの企画を作っていたときには「ユーザーに面白いコンテンツを届けたい」という純粋な動機があって、それに基づいて行動できていたのですが、マネージャーになってから悩むようになっていたんです。
川口:そこで彼にコーチングのトライアルを受けてもらったところ、その3ヶ月間でかなり変化したんですよね。一言でいうと「部長らしくなったな」と感じるんです。ミーティングでもあまり発言しない、など気になっていた点も少しずつ乗り越えてくれました。部長としてチームを率いる自信がついたんだと思います。
徳田:思考プロセスが変わったというか。何のために部長をやっているのか、部長として何ができればメンバーがハッピーになれるのか、という根っこの部分に向き合ってくれて、そこから彼自身の“色”が出てくるようになっています。

継続的なコーチングで目指す、強い組織づくり
ーmento for Businessの投資対効果について
川口:まだ詳細は追いきれていませんが、例えば徳田がいるコーポレート部で見ると徳田ともう一人のマネージャーがうまくタッグを組んでマネジメントできているなと感じるようになりました。
コーチングを始める前後はちょうど退職者が続くというつらいタイミングでもあったのですが、その頃と比べると安定しているし、強いメンバーが増えているというのは僕も感じることができています。
先ほど苦しんでいたとお話した部長が率いる部門も、その部長と配下ミドルマネージャーの信頼関係が課題の一つでしたが、彼がコーチングを通じてその課題に真摯に向き合って変化を見せているので、関係性もよくなったかな。少しずつではありますが、一枚岩になりつつあるという印象を受けています。
その部門は100人くらいの社員がいる部署ですが、リーダー層のチームワークがうまく固まれば我々の目標である強いリーダーの育成、そして組織開発へとつながっていくのではと期待感もありますね。
徳田:その変化を見ていると、コーチングプログラムを継続するしかないなと思わされました(笑)。導入に悩まれていたら、まずは体感してみるのが良いと思います。特にシニアなレイヤーのマネジメントについて、外注したほうが費用対効果が高いと思わせられるようなマネジメント領域があることを、実感出来るかと思います。弊社のケースでいうならば、代表の川口が無理に配下部長の育成に一人で思い悩むのではなく、プロコーチの力を借りながら自身のマネジメント負担を軽減して他アジェンダにも集中出来ましたので、人材育成と業務効率化の二軸から組織強化ができるというメリットも大きいですね。
ー今後の組織づくりや人材育成についてお伺いさせて下さい
川口:ゲーム運営という一本の柱だった事業を、多角化していきたいと計画しています。構想段階だった企画を事業として動かしていく時期に入るので、そこでワークできるリーダーをできるだけ増やしていくことが第一のミッションですね。
徳田:僕は、事業が多角化するなかで、自分の経験則だけで教えられないことが増えていくだろうと予想しています。その為に、今は部長クラスを対象にしているコーチングを、その配下のミドルマネージャーマネージャー層まで広げていこうという取り組みを考えています。コーチングを組織にインストールすることで組織力の底上げをしていきたい。
それから、コーチングって「抱えている問題に対して答えが出たからもう大丈夫」という類のものではないなと実感しているんです。一度落ち着いたと思った問題がまた噴出したり、何度も向き合わなければならなかったり。だからこそ、“問い続ける”サポートをしてくれるコーチングの必要性はこれからもあり続けると思います。
-----
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
