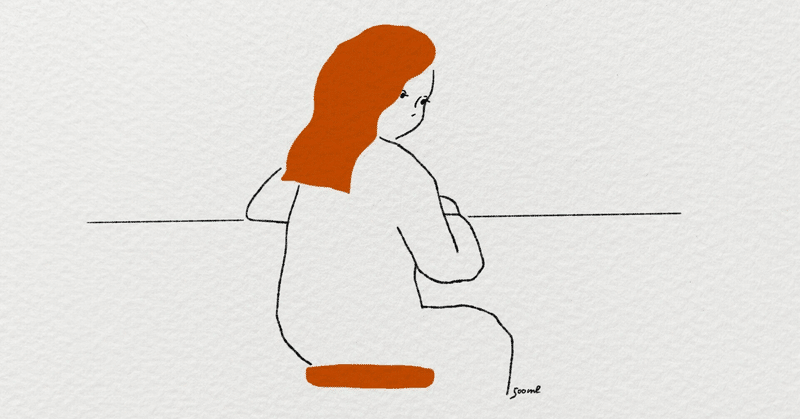
とある洋画を見た、弱っている私
※以下には映画”The Tender Bar”のネタバレが出てきます。読んだら映画を楽しめないような内容ではないと思いますが、ネタバレが気になる方はご注意を。
ここ数日、うつ症状のひどい日々を送っている。
感情が動かず表情が変わらない。何かしたいと思う反面やる気は起きず動けない。身体が冷える。なのに負の感情は増幅する。などなど。
おそらく疲労のせいだ。ここ1年で初めてといっていいほど行動量が増えた期間が非常に短期間だがあった。
予期していたが、それでも心がついていかない。
おそらく、気温の変化もあるだろう。急に寒くなったから吐き気や首凝りがひどい。
たくさん試みたいことがあるのに、なんで身体は動かないんだろう。
はつらつとした自分でいるという夢をへし折られて、さらに気持ちは滅入る。
少しだけ何かしたいなと思えた今日、アマゾンプライムで”The Tender Bar(邦題:僕を育ててくれたテンダー・バー)”を見た。
知らない映画だったが映画の説明欄とタイトルから、バーでの会話がキー要素になるのではと思い興味をひかれた。
以前から、バーやカフェ、ごはん屋さんなどで繰り広げられるお話が好きだ。
映画では”コーヒーが冷めないうちに”とか、ドラマだと”珈琲いかがでしょう”や”深夜食堂”、ゲームだと”コーヒートーク”とか"ファミレスを享受せよ"など。
他人だった人たちが偶然一つの空間に集まる。出会う。会話する。偶然何かが起きる。
そんな偶然の何かを観測するのが、予測不能で楽しい。
海外映画でそういうシーンがメインとなるものは見たことがなく、期待と面白いのかという不安半分で見た。
結果、自分と主人公の重なる部分がとても多いと感じたり、”居場所”や”キャリア”、”生き方”といった自分の興味関心にとても近いテーマが多く語られていた印象で、期待を大きく上回る満足感を得た。
ネタバレへの配慮や情報の正確性、批判などを気にして怖くなってしまうので、普段は作品の感想を発信したりはあまりしないのだけれど、珍しく書いてみようと思う。
間違っているところがあったらごめんなさい。
映画は同題のエッセイが元になっている。
舞台は1970年代のアメリカから始まり、当時9歳の主人公のJR(ジュニア)が大学を卒業し社会に出るまでを描く。
映画では、イエール大学に進学したJRが周囲の人間の階級を意識する描写があるなど当時の時代背景が色濃く描かれていたが、知識が乏しく理解できなかったので調べてみた。
第二次世界大戦以降、好景気となり多くの家庭が中流階級となったとされる60年代とは打って変わって、ベトナム戦争や景気の低迷を受けて衰退の時代とされる70年代米国。
そんな時代にJRは子ども時代を送ったのだった。
大学へ進学したJRが階級を気にするシーンがあった。
大学で恋した相手、シドニーはJRいわく”上層中流階級の下”で、シングルマザーの母親や親せきと祖父母の家で暮らすJRは、シドニーと話したり家に遊びに行ったりした後「シドニーは上流で、僕は下流に感じる」と話していた。
当時の時代背景を考えると、資本主義かつ経済が低迷する時代、貧富の差が拡大してそれがアイデンティティーとして取り込まれることは当たり前だ。
今の日本と重なるな、なんて思いながら見ていた。
そして一番印象的だったのが、幼少期の主人公の表情がずっと柔和であまり変化がなかったことだ。
子どもは感情表現が豊かで、とくに映像作品内では純粋無垢だったりアクティブだったりすることが多いためそう感じたのだと思う。
JRは9歳の時、ラジオDJである父親と別れて母方の祖父母の家に引っ越し、大学入学まで暮らした。
どんな子ども時代を学校で過ごしていたのかは詳しくは描かれていないが、「イエール大学に行って弁護士になってほしい」という母親の願いを最優先に生きていたのだろう。勉学に励んでいたのだろうと思う。
母親にどれだけ期待の言葉をかけられても笑顔、父親代わりのような存在の叔父に「スポーツはあきらめろ」と言われても文句ひとつ言わない。
「ここにある本を読み切るまで口をきいてやらない」などどんな理不尽なルールを言われても文句を言わず、理由も聞かず、穏やかな顔をして従っていた。
そんな子ども時代のJRの様子を見ていると、なんだか幼いころの自分を見ているような気がした。
親の求める何者かになるために奔走する、そんな彼が。
正直、子ども時代のことはほとんど覚えていない。家でひたすら勉強させられていたこと以外は。
だが、今になって思う。私は勉強させられていたとき”嫌”と言ったのだろうか。
学外での勉強、特に塾に通い始めたときはとても楽しかった。
反面、学校は退屈だった。勉強が面白くないからだ。
塾に通うことも親に言われてだったけれど、結果私はハッピーだったのだ。
だから、たぶん文句を言っていなかったんだと思う。
それってすごくJRと似ているなと。
親の期待にこたえたら、大変な思いをしている母親が喜んでくれる。
頭がよくなっていい大学に行けば、疎遠になっている憧れの父親もきっと認めてくれる。
そんなJRと、頑張って育ててくれている両親を喜ばせたかった子ども時代の私は、とても似ていると思う。
”勉強ばっかりは嫌だ”なんて考えはたぶん当時の私の1割ほどで、それよりも勉強が楽しい割合、そして親に褒めてもらえる割合の方が私には重要だったのだ。
家庭での価値観がまるっきりトレースされる形で子どもに移るのは、子どもが親に認められたいからだと思う。
逆に、成績が落ちると親に嫌われる・見放されると思っていたのだろうか。
JRについても、自分についてもわからない。
それでも、頭のいい自分を見てほしかった。理想の自分を見せて、褒められたかった。
だからこそ両親に反抗するなんて考えはなかった。きっと私のように、JRにも反抗期はなかったのだろうと思う。
その辺は原作のエッセイには描かれているのだろうか。読んでみたいと思う。
母親の願い通りイエール大学に入学し卒業できたJRは、作家という夢を抱きながらも一歩を踏み出せずにいた。
別の恋人がいる元恋人、シドニーのアドバイス通りにNYTimesに面接に行き、無事採用されるも、望んでいた記者としての採用をされることはなかった。
社会に出てからのJRの行動も自分に重なるところが多い。
他者のアドバイスをうのみにして行動するところ。それが、それだけ正解だと信じてしまうところ。一歩踏み出せずに弱気になってしまうところ。
他者の価値観が自分のものだと勘違いするところ。
全て、私にも経験があることだ。
親の世界の中だけで生きていると、自分で決断するという感覚があまりない。親の正解が子の正解だからだ。
親の正解を勝手に推測したり、言われたことを守ることが人生の道しるべとなる。
だからこそ、親がいないと弱気になる。決断できなくなる。
今は思う。
弱気になっているということは、自分が弱いからではなく、あまり自分の心がやりたがっていることではないのかもしれないと。
弱気な自分に自分で鞭を打てるのなら、それは心からやりたいことなのだろう。
でも、弱気な自分に悶々としているだけで、人から言われてやるのは、なぜ弱気なのかに向き合うことをすっ飛ばしていると思う。
ただ、作中でJRは、自分でその弱さに向き合うきっかけを作りだした。
そのシーンはぜひ映画を見て知ってほしいと思う。
自分が自分を見つめようとしたときにやっと、自分の人生の主体性を獲得できるのだと改めて思わされるシーンだった。
そして最後に、予想通り映画の象徴的な場となった叔父が勤めるバー"The Dickens"。(イギリスの小説家、チャールズ・ディケンズからとった名前)
祖父のたばこを買いに来たJRがお客さんに飲み物をおごられて、祖父のお駄賃でおごり返したり。お客さんや叔父とボウリングに行くまで仲良くなったり。大学生となったJRが失恋に悩んで涙したり。
JRにとって、おとなに子ども扱いされず対等にかかわる場であり、成長を見守ってくれる場であり、作家という夢を語る場としてとても重要な居場所だったのだと思う。
叔父が店についている鐘を鳴らすと、JRがイエール大学に入学したことが客らに告げられる。
店内にはJRのことを知らない人もいるのかもしれない。それでも、知らせるのだ。
祝福の声が上がる。ざわめく。話し続けている人もいる。
そんなうれしいローカルニュースが聞けるバーに、私も行きたいと思う。
最後のシーン、作家になる決心がつき一人でマンハッタンへ飛び立つJRは、仲良くなった客や叔父にバーの前で見送られた。「戻ってくるなよ」と言われながら。
なんて素敵な居場所だろうか。
「また来てね」ではない。JRをよく知る人々だからこそ、彼の背中を押すことができるのだ。
JRにとってバーがなかったらどうなっていただろうと思う。
本棚に本が詰まっているバーで叔父に「作家になれるかもしれない」と言われなければ、彼の夢はなかったかもしれない。
バーの客と知り合っていなければ、ボーリングで遊んだりしていなかったかも。
”なかったら”なんて想像は難しいし、どのみちJRは本の面白さから自分で作家を目指していたかもしれない。
でも、バーだからこそ話せたこともきっとある。バーだからこそ知り合えた人もいる。
彼の”家庭”という限られたコミュニティでは”出会い”という偶然が起こる確率は格段に減る。テクノロジーが発達していない当時であればなおさらだ。
子どもや若者の居場所に関心がある私にとって、この映画のバーでの描写は、そういった観点から見ても非常に興味深かった。
現代について考えてみる。
テクノロジーはあっても、出会いの偶然が生み出す影響は少ない気がする。
なぜなら、オンラインでのたくさんの情報や人との出会いは、自分から何が必要なのかを提示しないとうまくいかない。
それってとっても資本主義的で、恣意的だ。
ニーズの等価交換。制限されたコミュニケーション。自分のバイアスに影響される無尽蔵な情報の供給。
反面、バーなどの多様な他者が一定数集まり交流する場では、誰がいるかわからない。何を話すかもわからない。
だからこそ起きる偶然がある。その場だからこそ発する言葉がある。表現がある。その場だからこそ来る人がいる。
その場にいるという緩やかな連帯は、オンラインの連帯よりあやふやだが安心する。全くの他人でも、場を共にしているだけで他人ではない気がしてくる。
そんな関係性は、世の中からどんどん消えつつあると思う。
核家族化、リモートワーク、地域活動の減少。経済格差の広がり。
私も孤独で、みんな孤独なんだろうなと思いながら、そうじゃないのかもしれないとうらやんで。
社会にあふれている何者かのうちの一人にもなれず、自分の存在意義を追い求める。
存在意義なんてない。というか、存在意義なんてものは、他者に自分を規定されることになってしまうから、考える必要がないんだと思う。
だって、自分が幸せでいるために生きているのだから。
そんな、なんだか当たり前に思える事実から、なぜ目を背けさせられているんだろう。
それは、他者のために生きる時間をささげなければいけない人が増えているからだと思う。
学校では成績上位だったり先生に都合のいい生徒が評価される。
親の望む子でいたいと思う。
経済的に、他者へのサービスでお金を稼がないと生きていけない。それは、会社に勤めるひとも、経済的に困窮していて子ども時代から働くという選択を余儀なくされているひとも含む。
孤独を感じるから、他者のために何かをする。推し活など。
”優しすぎると人生を無駄にする”とか”もっと自分勝手に生きたら楽になる”とか、そんな短絡的で鋭利な言葉があふれていて、私は嫌になる。
でもそんな言葉には、一定数のいいねがついている。
優しいことは素敵なことだ。他者を優先できることだって、素敵なことだ。
なんでそのひとがそう在るのか、きっと知らない。私だって知らない。
世界中の人々の、みんながなぜみんなで在るのかなんてわからない。
自分では、自分がなぜこんな自分なのかわからない。
わからないのに、誰かの幸せをなんで他者が定義づけられるのだろう。
なんで優しさを否定するのか。私は泣きたくなる。
バーやカフェなど、居場所として機能している場所は、ひとを受容してくれる。
他者であり続けることもできるし、関わろうとすることもできる。
そんな、自分が自分でいられる場所が、もっともっと増えたらいいなと思う。
そんな活動に、貢献できたらと思う。
そして、私は私の居場所を探している。
思いのほか長くなってしまったし、なんだか思っていることを五月雨に書きなぐったような文章になりました。まあいいや。
最後になりましたが、ここまで読んでくださりありがとうございました。
そして、ヘッダーには素敵なイラストをお借りしています。ありがとうございます。
