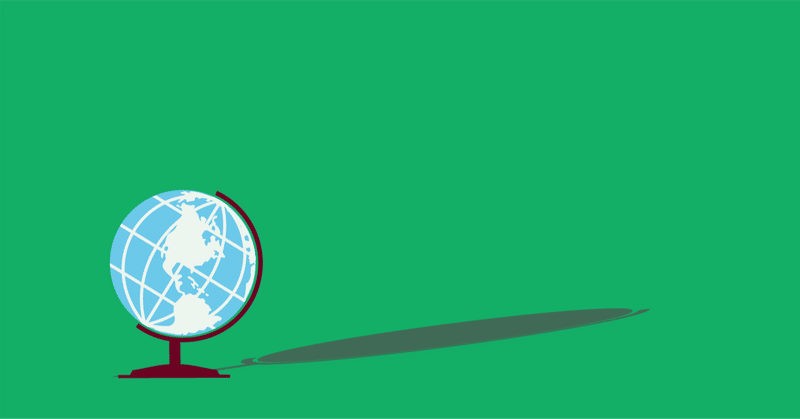
人新世の「資本論」を読む #106
自己紹介はこちら
デザインスクールでよく聞かれるのが「Anthropocene(アントロポセン)」という単語。日本語では人新世(ひとしんせいorじんしんせい)と言われています。「デザイナーになりたいのならば、この単語を学ばなければ」と手に取ったのが、新書大賞2021で大賞を受賞している『人新世の「資本論」』でした。
ということで、今回は「人新世の資本論」を読んで思ったことを書いてみます。あくまでも個人の感想であり、要約や解説ではないことをご了承の上お読みいただければ幸いです。
第一章 気候変動と帝国的生活様式
本章では、気候変動が資本主義に由来することが示されます。
産業革命以降の人類の経済活動が地球システムへの負担を増やしていることは一目瞭然だ。(中略)だが、なぜこのような事態になってしまったのだろうか。その理由を明らかにするためには、資本主義のグローバル化と環境危機の関係性をまずはしっかりと理解しなくてはならない。
ここで、キーワードになるのが「外部化」です。帝国的生活様式と呼ばれる先進国の大量生産・大量消費の社会を維持するためには、グローバル・サウスからの労働力の搾取と自然資源の収奪が必要であることが指摘されます。
中核部での廉価で、便利な生活の背後には、周辺部からの労働力の搾取だけでなく、資源の収奪とそれに伴う環境負荷への押しつけが欠かせないのである。
そして、グローバル化が進みきって外部化ができなくなった後は、仕組み上資本主義は維持できないことが示唆されます。
資本は無限の価値増殖を目指すが、地球は有限である。外部を使いつくすと、今までのやり方ではうまくいかなくなる。
結局地球はひとつしかなく、すべてはつながっているということだ。外部化や転嫁が困難になると、最終的に、そのツケは、自分たちのところへと戻ってくる。
大航海時代や新大陸発見、ゴールドラッシュ、植民地時代、帝国主義など第二次世界大戦以前まではフロンティアが残されていて、そのフロンティアを開拓することこそが発展と直結していました。しかし、フロンティアを失った資本主義は外部化ができなっているようです。
第二章 気候ケインズ主義の限界
本章では、「グリーン・ニューディール」や「SDGs」といった既存の対策では気候変動は解決できないことが説明されます。そこでキーワードになるのが「デカップリング」です。
今まで連動して増大してきたものを、新しい技術によって切り離そうとするのが、デカップリングだ。つまり、経済が成長しても、環境負荷が大きくならない方法を探るのである。
経済成長と気候変動対策は両立できるはずだという主張もありますが、経済成長がうまくいく分だけ二酸化炭素排出量も増えてしまう「経済成長の罠」と、生産性が上がると経済規模も拡大するという「生産性の罠」の存在から、デカップリングが幻想であると筆者は主張します。
ということは、経済成長と地球環境のトレードオフを迫られることになります。こう問われると、もちろん経済成長を諦めて、地球環境を優先しなければ、人類は滅亡へと向かってしまいます。こうして「脱成長」という選択肢が浮かび上がってきます。
第三章 資本主義システムでの脱成長を撃つ
本章では、資本主義と脱成長は両立できるのかという問いを考えます。しかし、経済成長と資本主義は切っても切れない関係であるため、資本主義そのものを見直さなければ環境問題を解決できないということになります。
資本主義こそが、気候変動をはじめとする環境危機の原因にほかならない
そこで、現れるのがマルクスの考えを基にした「コミュニズム」です。
第四章 「人新世」のマルクス
ここで、ついに「脱成長コミュニズム」というポスト資本主義たりえる解決策が提案されます。ここでのキーワードは「コモン」です
<コモン>は、水や電力、住居、医療、教育といったものを公共財として、自分たちで民主主義的に管理すること
資本論を執筆時点のマルクスは、生産力至上主義とヨーロッパ中心主義を特徴とした進歩史観をもっていたそうです。しかし、晩年のマルクスはこの両者の考え方から決別し、持続可能性と社会的平等を基礎とする脱成長コミュニズムを掲げるようになっていったそうです。
第五章 加速主義という現実逃避
マルクス主義の誤解とは、このマルクスの発展途上の思想が書かれた資本論だけを参考にしている点だそうです。つまり、生産力至上主義とヨーロッパ中心主義から抜け出す前の未完成の思想に基づいている「マルクス主義」がまかり通っている現状なのです。
また、資本主義において人間の労働における「構想」と「実行」が分離されたこと、一部の専門家しか扱えない「閉鎖的技術」が重視されたという点も伏線として書かれています。
第六章 欠乏の資本主義、潤沢なコミュニズム
資本主義とコミュニズムの社会を比較し、コミュニズムがもたらす豊さを具体的に説明します。
マルクスによれば、「本源的蓄積」とは、資本が<コモン>の潤沢さを解体し、人工的希少性を増大させていく過程のことを指す。つまり、資本主義はその発端から現在に至るまで、人々の生活をより貧しくすることによって成長してきたのである。
ここで、重要なポイントは、本源的蓄積が始まる前には、土地や水といったコモンズは潤沢であったという点である。共同体の構成員であれば、誰でも無償で、必要に応じて利用できるようにものであったからだ。
こうして、本来誰のものでもないor誰のものでもあった「公富」が、誰かが「私財」として所有権を主張するようになることで、人工的に希少価値が生まれるということです。
また、使用価値と価値の違いにも言及されています。
「使用価値」とは、空気や水などがもつ、人々の欲求を満たす性質である。これは資本主義の成立よりもずっと前から存在している。それに対して、「財産」は貨幣で測られる。それは、「価値」の合計である。「価値」は市場経済においてしか存在しない。
価値を上げるためには希少性をあげようとして効率化や独占が進んだ結果、使用価値を必要とする人に届かなくなるのが、資本主義で起きる弊害です。
資本主義は、自らのために「人工的希少性」を生み出す。だからこそ、潤沢さこそが資本主義の天敵なのである。そして、潤沢さを回復するための方法が、<コモン>の再建である。
この<コモン>として相応しいのが、多くの人が使える「開放的技術」であるようです。
第七章 脱成長コミュニズムが世界を救う
脱成長コミュニズムの5つの柱として、以下のような具体的な提言がなされます。共通しているのは、使用価値を重視しようということ。経済成長のためではなくて、生きるために必要な労働をしようということでしょうか。
1. 使用価値経済への転換
2. 労働時間の短縮
3. 画一的な分業の廃止
4. 生産過程の民主化
5. エッセンシャル・ワークの重視
第八章 気候正義という「梃子」
これまでの提言が不可能ではないことを証明するために、バルセロナなどによる実践例が紹介されています。気候正義や食料主権といった使用価値を重視する動きもあり、これこそが脱成長の「梃子」になるのだそうです。システム思考でいう「レバレッジポイント」ですね。
おわりに 歴史を終わらせないために
ここまでの主張の実現はできるのだろうかという疑問に対して、3.5%という数字を挙げて締めくくります。
「三・五%」の人々が非暴力的な方法で、本気で立ち上がると、社会が大きく変わるというのである。
その未来は、本書を読んだあなたが、三・五%のひとりとして加わる決断をするかどうかにかかっている。
まとめと感想
脱成長コミュニズムによって環境問題と資本主義の問題を同時に解決できると考えるのは、システム思考的だなと感じました。では、その解決策をどうすればいいのかについては方針が書かれているものの、その行動を個人レベルでどうすればいいのかまではまだまだ考える余地がありそうです。ここを考えるのが、まさにデザイナーの役割かもしれません。
いただいたサポートは、デザイナー&ライターとして成長するための勉強代に使わせていただきます。
