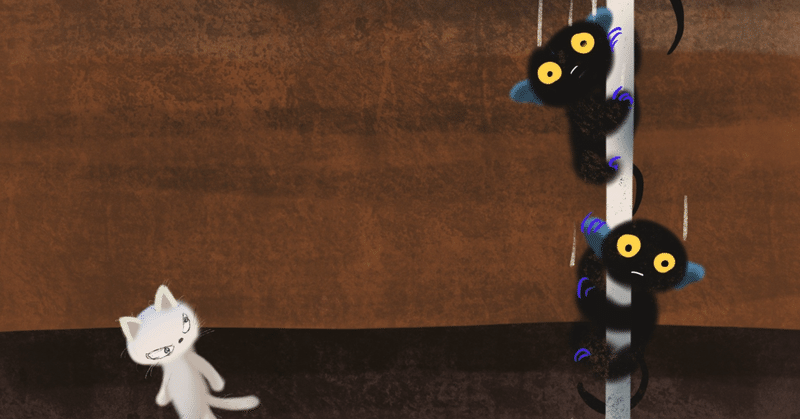
デザインは、社会的差異を具現化する。(『欲望のオブジェ』) #331
工業製品や、それが近代社会の生活のなかではたす役割について議論をはじめようとしても、いつもけっきょくは、「グッド・デザイン」論で終わってしまう。だとすれば、商品として流通するものの歴史が、歴史研究の一分野として本格的にとりあげられる望みはないのか? 本書『欲望のオブジェ』が、それに対する私の答えだった。
そんな挑発的にも思える一文が前書きにある『欲望のオブジェ』は、構造主義的な視点で近代デザインの歴史を語る一冊。副題が「デザインと社会 1750年以後」であるように、社会背景からデザインを語る視点が特徴的である。
なお、この記事は本書の要約や解説ではなく、個人的な学びを中心にまとめていく。
デザインは進歩を隠蔽する
第1章「進歩のイメージ」と第2章「最初のインダストリアル・デザイナー」を通して1750年代以降のデザインの歴史を紹介しながら、デザインがアートから独立していく様子を明らかにしていく。
ここで明らかになるのは、デザインは産業革命や資本主義がもたらす「進歩」を社会に受容させる役目を担っているということ。特に当時のイギリスでは新古典主義という昔ながらの意匠が流行しており、進歩に抗う消費者心理が強かったようだ。
進歩というものはありがたいにちがいないけれど、逆に苦労と面倒の種にもなる。われわれのそれに対する反応は、しばしばアンビヴァレントだ。進歩が与えてくれる改良や安楽さを欲しながら、それによって自分たちが大事にしているものを手放さなければならばかったり、自分たちの基本的な仮定をくずして、新しく、なじみのないものごとに身を合わせなければならなくなったりすると、それに抵抗しがちである。
われわれは、デザインの意味を知るためには、偽装したり隠蔽したり、また変貌させたりするデザインの力が、近代の産業社会の進歩にとってなくてはならないものだったことを認識しなければならないのである。
この時代におけるデザインの役割を示す具体例として、ジョサイア・ウェッジウッドという企業家による陶器製造を取り上げている。ここでデザイン(特にインダストリアル・デザイン)の誕生のカギとなったのが「カタログ」だ。
というのも、産業革命以前の手作業による製造の時代は実物をそのまま購入していたのだろうが、産業革命以降の大量生産の時代では見本やカタログといった完成予想図をもとに買うという新たな購入方法が生まれた。この時、カタログと同じ商品が届くのかという問題が生まれたのだ。今でいう「画像はイメージです」の起源かもしれない。
しかしながら、見本やカタログから販売するためには、製品が質的に完全に均一化していなければならない。わずかな見本を頼りに一式揃えて買う者は、当然、自分が見た見本と寸分違わないものを受けとると思うはずではないか。
つまり、カタログと同じ商品とみなせるような品質で生産できる陶器の形状や模様を設計する必要があった。また、陶器を実際に製造する人が毎回商品にアレンジを加えても困るということもあり、設計と製造の分業が押し進められたらしい。こうした経緯から商品の設計を担う職業が誕生し、これが最初のインダストリアル・デザイナーであるという。
工業製品の家庭用品化
本書では、工場で使われていたモノを家庭用にデザインすることで需要を喚起してきた歴史も一貫して描かれている。前述の話は陶器製品の工場での生産方法におけるデザインの話だったが、デザインは工場で取り入れられた進歩を家庭に広めることにも成功していく。つまり、デザインは工業製品を家庭用品に「偽装」してきたのだ。
たとえば、第5章「家庭」で取り上げられるミシン。1850年代にアメリカで登場したミシンは工業用だった。業績不振にあえいでいたシンガー社は、工業用ミシンを家庭用ミシンとして販売しようと試みる。
しかし、課題となったのは「ミシンは工場で労働者階級の少女が使うもの」という消費者のイメージで、このイメージを払拭するべくデザインが利用された。このように、工場で利用されていたものを家庭用にデザインすることで生活必需品を増やしている。売上を上げるには需要を喚起しなければならないからだ。
工場用が家庭用になった後は一家に一台の生活必需品になり、さらには、一人一台、一人複数台の時代になっていく。たとえば、テレビが街頭テレビだった時代から家庭に1台、各部屋に1台と需要は増えていった。本書は1980年以前の社会について書いているため触れられていないが、アップルが1984年にマッキントッシュを、2007年にiPhoneを販売したことでコンピューターがスマートフォンとして普及していくまでの流れも同様に説明できそうだ。
デザインは社会的差異を具現化する
ここまで進歩と新古典主義という差異や工業用と家庭用という差異に着目してきているように、本書の中心テーマは「デザインは社会的差異を具現化する」だ。この差異に注目してデザイン史を描く本書は、まさに構造主義的なアプローチだと言える。
第4章以降は様々なモノ(オブジェ)を取り上げながら、デザインが社会的差異を具現化している事例が繰り返し示される。以下にその社会的差異を列挙してみる。
男性↔女性
大人↔子供
中流階級↔労働者階級
使用者↔奉公人
家庭↔工場
管理職↔事務員
電気↔ガス
ここで重要なのは、こうした差異がデザインによって過度に強調されるということだ。たとえば、男性用は大きくてシンプルで女性用は小さくて装飾が施されているというデザインの違いによって、たくましい男性性と繊細な女性性という社会的観念が記号化されていく。以下の引用文の「こうした特徴」とは、ヴィクトリア時代における男らしさ・女らしさである。
こうした特徴は、現実にあったというよりも、観念として存在した。ひとびとはそういう観念になじむために、それらの真実性を証すものを必要とした。フィクションや教育、宗教などがすべてこれに寄与する。そしてまたデザインもそうだった。
「清潔さ」という差別意識
この社会的差異を生み出していくと、そこには優劣の評価も合わせて生まれる。この差異の中で最も恐ろしいのが清潔か不潔かである。個人的には第7章「衛生と清潔」が本書で最も印象的な章だった。
衛生の概念が普及した19世紀頃、デザインは「この新製品は衛生的で清潔である」という差異化を行っていった。たとえば、白や滑らかさなどの五感に訴えかける特徴によって清潔さを可視化した。衛生的であるという目に見えない概念を具現化するにはデザインが必要だったのだ。
一九三〇年代にこのかた数十年間にわたって、清潔の美学が家庭の風景の規範になる。きれいなことを目に見えるかたちで示すことが、あらゆる家庭用品の正しい外観として問答無用に受け入れられていたらしい。
ただし、この衛生観念に基づく清潔さのイメージは他の二項対立とも紐づいていく。鉄道で労働者階級が座る座席よりも中流階級の座る座席の方が清潔な印象を持たせて社会的階級を差異化したり、ガスで動く機械よりも電気で動く機械の方が清潔という印象付けに利用されていったのだ。
この清潔さを利用した差異化が怖いのは、差別意識の助長につながりかねないからだ。つまり、二項対立のうち劣っているとされる側は不潔であるという認識になってしまう。そして、この病気への忌避感は本能に訴えかける強烈なメッセージとなり得るため、清潔さを連想させるデザインは評価されやすい。
こうした清潔さの差異化はパンデミックによってさらに強まったように思う。マスク、ワクチン、消毒液、パーテーション、オンライン、無観客。清潔さが最優先となったことが思い出される。実際にどちらが感染拡大を抑えるかという科学的根拠よりも、「清潔さ」というイメージが重要視されているケースもあったのではないだろうか。
清潔は健康と直接に結びつき、その関係は科学的に証明されているけれど、清潔だとか汚いとかいうのは、美醜とほとんど同じほど主観的なものだ。
こうした清潔さをデザインに利用する手法は、環境問題でも同じように効果的なのかもしれない。クリーンエネルギーという言葉もあるように「環境に優しい=清潔」という印象が定着しつつあるが、デザインが清潔さという印象で偽装しようとしている社会的差異は何かと問うべきかもしれない。この偽装が蔓延っていることを指摘しているのが「グリーンウォッシュ」だろう。
筆者はデザインを構造主義的なアプローチで捉え直すために本書を上梓したと書いているが、2024年に生きる私たちから見れば「清潔であることは良いのだろうか?」という脱構築的な視点も読み取れる。「過剰な清潔さはむしろ免疫機能を弱めたりアレルギーを発症させる」という説もあるが、清潔なものほど良くて不潔なものは避けるべきという単純な二項対立では語れないということに気づく必要があるのかもしれない。
いただいたサポートは、デザイナー&ライターとして成長するための勉強代に使わせていただきます。
