
重要なのは「変化を受け入れ、行動すること」「真摯に取り組むこと」——アーキテクチャーフォト® 後藤連平さんに聞く、〈Webメディア〉と〈まち〉
「街づくり」はとても複雑なものです。
そこに住む住民はもちろん、商いを営んでいる人、デベロッパー、行政……などさまざまな主体による活動の上に成り立っています。各々の活動はお互いに何らかの影響を与え、結果的にまちという姿で現れます。そう考えると、それらの主体が街づくりを意識することから、本当の街づくりが始まるのではないでしょうか。
人びとがインターネットに触れるようになってからわずか数十年でTwitter、Instagramを筆頭にしたSNSの発展などインターネットを取り巻く環境は大きく変化しています。
2003年に個人サイトとして始まり、2007年から本格的に活動を始めた建築系Webメディア「アーキテクチャーフォト」は、「建築」という専門メディアの視点から、そうした目まぐるしい「変化」と並走し、その時々でより良い発信のあり方を考え続けてきました。
そうしたアーキテクチャーフォトの道のりからは、同じく「変化」を取り扱う街づくりにおいても学ぶことが多くあるはずです。
また、インターネットによって発信がしやすくなった中で、街づくりにおいても、その魅力を発信するための「メディア」的な視点がより必要になってくると思われます。
そこで、今回は「まち」を構成する大きな要素であり、まちの魅力度に大きく影響のある「建築」を20年にわたり、幅広く見てこられたアーキテクチャーフォトの創設者であり編集長の後藤連平さんに、「Webメディア」という視点から、まちや街づくりについてどう感じるか、お話を伺いました。

後藤連平(ごとう・れんぺい)
1979年静岡県磐田市生まれ。2002年京都工芸繊維大学卒業、2004年同大学大学院修了。建築と社会の関係を視覚化するメディア「アーキテクチャーフォト」編集長。アーキテクチャーフォト株式会社代表取締役。
組織系設計事務所勤務の後、小規模設計事務所に勤務。TwitterやFacebook、iPhoneが登場する以前の、2003年からウェブでの情報発信を始め、2007年にアーキテクチャーフォトの形式に改編。たった独り地方都市ではじめた小さな建築メディアを、現在月約50万ページビュー以上にまで育てる。
メディア活動を通して、”作品の魅力を遠くまで伝える方法論”を開発して実践。”設計者に仕事が生まれるサイクル”も構築。
建築実務から編集の世界へ──アーキテクチャーフォトを始めるまでのキャリア
──今回のインタビューでは建築系Webメディアとして建築やインターネットに長く接してきた後藤さんの立場から、どのようにまちや街づくりが見えているのかお聞きできればと思っています。
まずはアーキテクチャーフォトを始めるきっかけからお伺いできますでしょうか。
中高生の頃からものづくりやデザイン、ファッションが好きだったので、その流れで建築にも興味を持ちました。
とはいえ、最初から「建築をやるぞ」と決めていたわけでもなくて、在籍の途中から建築かデザインかを選べる京都工芸繊維大学に入学しました。
大学に入ってから、恩師のひとりであるエルウィン・ビライ先生を知りました。建築業界で世界的に知られた雑誌『a+u』の編集をしていて、京都にいるにも関わらず世界中のあらゆる建築を知っている上に、当時の建築界を牽引していたヘルツォーク&ド・ムーロンやピーター・ズントーなどの建築家とも親交が深いのが凄いなと思い、ビライ研に入りました。
ビライ研では、設計だけではなく編集のような課題にも取り組んでいて、そこでの経験は大きなターニングポイントだったと思います。
また、ビライ先生が出題していた課題に「自身の作品でポートフォリオをつくる」というものがありました。それは、一般的なA3用紙にプリントして、ファイルに整理するものではなくて、過去の作品を見直したり編集したりして本の形式にするという課題でした。
当時、僕はズントーの作品集をよく読んでいたこともあり、布貼りのハードカバーのポートフォリオをつくって提出したのですが、それが割と評判が良かったんです。
絵画でも額縁に入れると見え方が変わったりしますし、本づくりでもレイアウトやページの流れによって写真の見え方が変わりますよね。そうした「編集をすること」によって見る人の印象を変えることができることに気づき「編集って面白いな」と思ったんです。
また、大学院に進んだ後の就職活動では、先の布張りのポートフォリオをバージョンアップさせたものを作成して活用しました。
当時、A3ファイルのフィルム越しに作品をみせるということが、どうしても納得できなかったことを憶えています。このこだわりは、就職活動的には意味のないものだと分かっていたのですが、編集という視点では今も正しいこだわりだったと思っています。
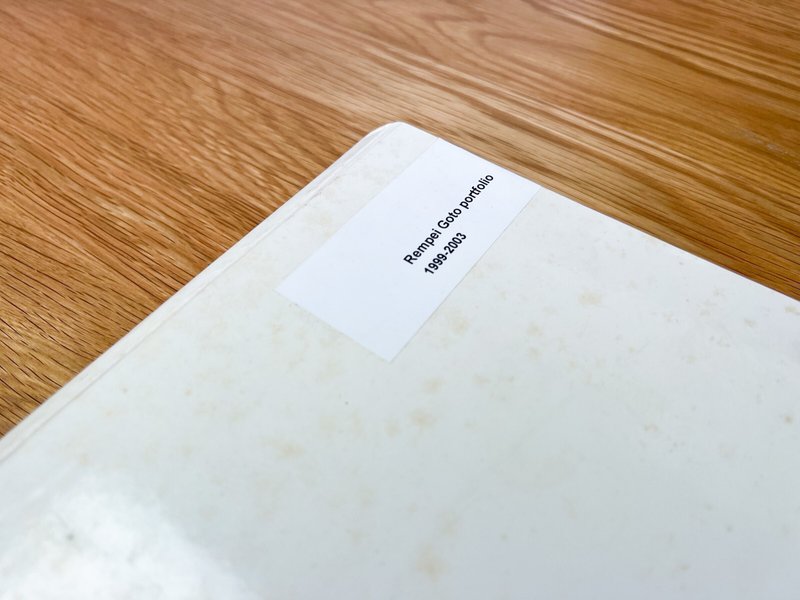


──編集の面白さとの出会いは大学時代だったんですね。
そうですね。ビライ研で編集の面白さを知ったあとは、大学院に進み、もう一人の恩師である古山正雄先生に学びました。
古山先生は都市解析の専門家ですが、安藤忠雄さんについての著書『壁の探求』等で建築批評家としても知られていました。ぼくはどちらかというと後者に興味を持ち研究室に入ったんです。古山先生の指導も印象的でした。短い時間で本質を掴んで端的な言葉で指摘をする。その切れ味に痺れましたし、多くを学びました。
そのような学生生活を送り、卒業後は、設計者として東京の組織設計事務所に就職しました。
編集の楽しさや批評の面白さを経験していたので、新建築社や彰国社のような建築の出版社の入社試験を受ける選択肢もあったのかもしれません。でもその時は、「設計の実務って実際どういうことをやってるんだろう。つくってる現場を見てみたい」という思いの方が強かったんですよね。
組織設計事務所に就職して、そこで分譲集合住宅の設計に関わっていたのですが、ある時、自身の設計へのモチベーションを意識させられるできごとがありました。
それは、一個下にすごく元気な後輩が入ってきて「なんでそんなにやる気があるの?」という質問をさりげなくした時でした。
その後輩は、僕の問いに対して「大きなお金が動くことで『自分はすごいプロジェクトに関わっているんだ』と感じてやる気が出ます」と言っていて。その時、僕は分譲集合住宅を設計する時、仕事としてのやりがいは感じていたものの、そういうモチベーションを持てていなかったことに気づいたんです。そして、建築のどこにモチベーションを感じるかはひとそれぞれだと気づきました。
そこから、自分が建築分野でよりモチベーションをもって取り組めることってなんだろうと考えるようになりました。
その後、組織設計事務所を辞めて、地元の設計事務所に入って住宅の設計をするようになり、今度は「個人のお施主さんのために働く」という、集合住宅の設計とは異なる仕事を経験することになります。それも面白かったし真剣に取り組んでいましたが、何か他に道があるのではないか、という漠然とした気持ちも捨てきれていませんでした。
そうした心情の中で、同時並行的にアーキテクチャーフォトにつながっていくウェブサイトの運営にも力を入れるようになっていったんです。
──やるべきことを見つけるのに色々な経験をされたというのはキャリアの話としても面白いですね。そして、そこからネットでの発信を20年以上も続けているのはすごいですね。
京都で学生だった頃や東京で組織設計事務所に所属していた時にも、建築家と呼ばれる人達と、交流することはほぼなかったのですが、段々とアーキテクチャーフォトという名前が知られるようになって、そういう方々から信頼を得ると情報を連絡してもらえるようになったり、アーキテクチャーフォトで作品を紹介させてくれるようになっていきました。
そのあたりから、アーキテクチャーフォトで建築を紹介することに対して御礼のメールをもらうようになったのですが、その時に「真摯に建築をつくろうとしている設計者をサポートした時に自分の中で喜びを感じたりモチベーションが大きく上がる」と自覚したんです。
また、実務の中で、自分が考える建築を実現することの難しさや住宅を一軒建てる事がどれだけ大変かを感じられたのも大きかったと思います。それがすべての建築を設計する人達へのリスペクトにつながりました。
ネットでの発信を20年続けることができているのは、そうした経験があるからでしょうね。
──インターネットで本格的に発信を始めたのは何故だったのでしょうか?
たまたまネットの面白さに気づいていたというのもあると思いますが、静岡という地方都市にいたのがすごく影響していると思います。メディアと言っても紙の本をつくるとか展覧会を開くとか、場をつくるとか色々な方法があると思うんですけど、それは「どのまちにいるか」でできることが制限されてしまいますよね。
地方都市にいた僕にとっては、活用できるものがインターネットしかなかったんです。
──「どこに住んでいたか」でメディアの選択肢が必然的に決まってしまったということですね。
「変化の早さ」に対して──「メディアが社会をつくっていた時代」から「社会の動きの変化に合わせて変わっていくメディアの時代」へ
──後藤さんが大学を受験する時に「東京に憧れがあって東京の大学も受けていた」とおっしゃっていましたが、静岡に住んでいた後藤さんの「東京への憧れ」はどこから生まれたものだったのでしょうか?
街とメディアの関係性を考えた時に、かつてはパルコのセゾン文化など、メディアが東京のイメージや文化を発信していた時代があったと考えています。
メディアが発信することで、地方にいる後藤さんのような方が「東京」という街のイメージを知る。それはつまり、メディアとまちは密接な関係性を持っていたということだと考えているのですが...
1997年に創刊された『FRUiTS』という雑誌があったんです。その雑誌は原宿のファッションにフィーチャーしたストリートスナップを紹介するというもので、僕の東京への憧れはその雑誌から影響を受けて生まれたものだったように思います。
2000年前後はユニクロのようなブランドやファストファッションもまだ普及していなくて、どんな洋服やCDを選んで買うかが自己表現になっていた時代だったと思うんですよね。
今はInstagramなどでダイレクトに自分の着こなしを発信して、いいねをもらうのが自己表現の一種になっていますが、90年代は「このアーティストが好きでCDを買いました」など音楽やファッションに対する購買行動がコミュニケーションの中で重要だったような気がしていて。
その中でも僕は「ファッション」に興味があったので、高校の同級生と一緒に『FRUiTS』をいつも買って読んでいたんですよね。だから、僕は『FRUiTS』を通して東京を見ていて、「東京は『FRUiTS』に載ってるような人ばかりがいるまちなんだ」みたいにめちゃくちゃ思い込んでいたんです(笑)
当時、『FRUiTS』に載っている人たちが着ているような服を隣町の浜松で探し出して買っていたのですが、それを着て家族で東京に行った時に、駅に降り立ってみると「あれ、ぜんぜん『FRUiTS』に載ってるような恰好している人いないな」と気づくわけです(笑)
それは、メディアによって肥大化した東京のイメージが僕の脳内にインプットされちゃってたってことですよね。
──なるほど。やはり、かつてはメディアがまちのイメージをつくってきた側面はあるんですね。一方で、現在ではメディアが「東京」というまちのイメージに対してそこまでの影響力を持てていないように思えます。その背景にはインターネットの普及や発展があると思っています。
アーキテクチャーフォトは個人サイトを含めて20年運営されていますが、長くインターネットに触れてきて、インターネットの大きく変化した部分やターニングポイントだと感じたことはありましたか?
僕がインターネットに触り始めたのが1998年くらいですね。
当時はADSLなどの常時接続もない時代でした。接続した分だけ課金されてしまうんです。なので、夜中の11時くらいから朝方まで定額でインターネットを使えるNTTの「テレホーダイ」というサービスを契約していたのですが、インターネットを使うためにその時間まで待つんです(笑)
そんな状況なので、当時は誰もがインターネットを使っているわけではなくて、「ネットで何かをやる」というのはアンダーグラウンドな雰囲気があったんです。
そうした状況に対して大きなターニングポイントだったのが、2007年のiPhoneの登場と普及だったと思います。それによってインターネットが「一部のコアな人が使うもの」ではなくて「皆が常時接続して調べものをしたりするもの」というように一般化されていったと思うんですよね。
この地域想合研究室.noteのように「noteでオウンドメディアをやる」というのも、もはや誰もインターネットをアンダーグラウンドなものとして見ていないからできることだと思いますが、実は20年遡るとそうではない時代があって、ネットをベースとすることは当たり前ではなかったんです。
──その変化に合わせてアーキテクチャーフォトも変化してきたのでしょうか?
そうですね。昔は「Yahoo!カテゴリ」のような様々な分野の情報が人力で集約されたサイトにまずアクセスして、目的とするサイトを探し出して訪問する人が多かったと記憶しています。その後、Google検索のような単語を入力してプログラムで収集された情報の中から目的にあうものを探し出すサイトが一般化していきました。さらにSNSが普及して、アプリを開くだけで膨大な情報が得られるようになりました。
このような変化の中で、ネット上の人の流れは大きく変わり続けてきました。
アーキテクチャーフォトも最初はウェブサイト単体しかなかったのですが、その流れに伴って、Twitterを活用し始め、その次にInstagramを活用し出し、ウェブサイトだけではない発信の仕方を模索していくようになっていきました。

2020年くらいまではアーキテクチャーフォトのTwitterのフォロワー数が35,000くらいで、今では53,000(2023年3月時点)くらいになっているのですが、このTwitterのフォロワー数の増加が象徴するような見られ方の変化もありましたね。これまで建築界隈だけに見られていたものから段々と業界の外の人たちも見るようになってきているんです。
ただ、SNSなどの流行や、それによる社会全体の変化はこちらでコントロールができないことだと思っていて、そう考えると主体的というより社会の側に合わせて発信していかないとメディアは必要とされなくなってしまうんだろうなという感覚は常にあります。
──今は具体的にはどういう層まで広がっているのでしょうか。
めちゃくちゃ有名なYouTuberがフォローしてくれてびっくりした、とか極端な例はありますけど(笑)
最初はアーキテクチャーフォトの更新情報をTwitterに流していたのですが、その時代は建築家だけに情報が届いていたような気がしています。これは、建築家が他の分野の人達と比べて言葉を扱うことに慣れていて、既に多くの方々がTwitter使って持論を発信していたからだと思います。
一方でInstagramは、活用当初からクライアント層というか「写真をみて自分が家を建てるときの参考にしたい」という人たちが集まっていることが分かっていました。そこでInstagramを活用する時は、あえてそうした層に向けて発信をするようにしました。
そうすると、やはり住宅の投稿にいいねがすごいつくようになって、専門家ではない層にも届きだしたという実感が出てきたんですよね。
──どういう人に見られるかによって媒体に合わせて伝え方を変えているということですね。ここ最近は「コンセプト圧縮」など伝え方の面でどんどんアップデートをされているように感じしているのですが、こうした伝え方はどのような変化に対応して生まれたものなのでしょうか?
「コンセプト圧縮」は、ウェブメディアとして編集のオリジナリティを生み出すための苦肉の策として編み出した側面があるけど。
— 後藤 連平🌐 (@remgoto) December 13, 2022
ぼく自身が、開発して誰よりも実践しているから、必然的に上手くできる。
そういう、自身の方法を「方法論」的に確立していくことは、設計においても重要ではないだろうか。
やはり時代の流れや社会などの環境の変化による影響が大きいですね。
今InstagramやTwitter上には、画像を無断でコピペして色々な建築家の作品を紹介するアカウントがたくさんあります。こうしたアカウントは、アーキテクチャーフォトがSNSを使い始めた当初はあまりなかったと思うので、SNS上だけを見てみても環境がすごく変化しているんですよね。
アーキテクチャーフォトは建築家の作品を紹介することが活動の主体になっているので、この変化の影響はすごく大きいんです。
同じ方法を取れば簡単に反響を集められるのは分かっているのですが、既に確立したメディアが同じ方法を取ることは難しい。そうした環境の変化のなかで、アーキテクチャーフォトが続いていくためには「言葉を丁寧に扱うこと」が重要になるのではないかと考え出したんです。
その結果生まれたのが「コンセプト圧縮」です。
建築家が考えたことを、我々編集者でコンパクトにまとめて、写真とセットで提供する。それによって作品の良さがより伝わりやすくなりますし、差別化もできる。
ただ、同時に「理念を持ってやっている」ということを伝えていかなきゃいけないと思っています。
結局そういうアカウントと競っていくには「理念がある人がやってるメディアだ」という属人的な部分で対抗するしかないような気はしているんですよね。

──昔はメディアが社会をつくっていたのに対して、アーキテクチャーフォトのようなメディアは社会の動きに合わせて変わっていっているというのは対比的で面白いですね。
TwitterなどのSNSが出てきて、誰でもメディアであるという状況になっていますよね。
アカウントが数えきれないほどある状況に対してひとつのメディアがすべてに影響を与えるということはもはや無理だと思っています。
ただ逆に考えると「ひとつのメディアが主導権を持つのは無理だ」と割り切ってしまえばやるべきことが必然的に変わってきたり、見えてきたりすると思うんですよね。
──そういう社会の状況に対してどう対応していくか、ということがメディアに求められるようになっているということですね。
変化を受け入れて、どう行動を変えていくか
──今まではメディアが「変化」にどう対応していくかというお話だったと思います。街づくりも「まちを変化させていく」行為で、東京を筆頭に色々なところで開発が行われていてまちの姿はどんどん変わっていっています。そういうまちの「変化」に対して、感じることはありますか?
僕は、そういうまちの変化に対して「良い」「悪い」と断定するようなことはあまりなくて「変わっていくもの」だと思ってしまっているところがあるかもしれないですね。
東京に関しては、住み始めてからまだ5年と短いからかもしれませんが。
地元である浜松の話をすると、浜松は25年くらい前の中心市街地は栄えていたのですが、郊外にショッピングモールができると、みんな郊外の家とショッピングモールを車で行き来するのがメインになり、中心市街地のお店への足が遠のいてしまったんですよね。
中心市街地に行くのは、公共交通機関を利用してお酒を飲む時が多くて、僕が高校生の頃行っていたファッションストリートのほとんどが居酒屋になってしまって。それは、個人的に色々な思い出があったので悲しかったですね。
でも同時に、それはショッピングモールを成立させた法律など政治レベルの話や様々な分野のビジネスモデルの変化などが影響していると思っていて、そこのファッションストリートのお店の人が頑張れば、そうはならなかったという問題でもなかった気もしているんです。
また、建築の文脈だとショッピングモールの存在が中心市街地を破壊しているという批判もあると思うんです。でも、僕はショッピングモールがバリアフリーで空調も効いていて、散策していると快適で楽しいということをユーザーとして経験しちゃっているんですよね。
なので、まちの歴史を継承していくことや近代建築の保存運動などの感覚は分かりつつも、快適性と利便性と都市の意義性みたいなものが上手く融合するようにしないと、残っていかないとも思うんですよね。
──建築とかデザインを伝えることを生業にしている後藤さんが「郊外のショッピングモールが好きなんですよ」というのも面白い話ですね。
都市と地方の両方で長く暮らした経験が大きいと思います。実際に生活者として、そのまちで暮らすと意義や意味を超えた切実さに向き合うことになると思うんです。
実際に浜松に住んでいた時には毎週のようにショッピングモールに通っていましたよ。もはや日常生活から切り離すことはできないわけですし、それを実際に体験しているから考えられる建築やまちがあると思っていました。
これはインターネット上でもよく言われている話ですけど、イオンの中にはヴィレッジヴァンガードがよく入っていると思うのですが、そういうお店がないと、地方都市にはちょっと変わった本をリアルで見て買う場所がほとんどないんですよね。
ヴィレッジヴァンガードは幅広い雑貨を扱う複合型書店。店ごとにさまざまなカルチャーが紹介され、幅広い文化に触れることができる。
だから、地方都市はイオンが出てきたことによって、そういう文化的なところが担保されているという側面があると思うんです。そう考えると、必ずしもショッピングモールを善悪で分けることはできない。なので、良い面は良い面として評価できればいいんですけどね。
──以前お話を聞いたストリートスケートボーダーの小林万里さんは長野県松本市出身で、中高生の頃はスケートボードを享受するにはムラサキスポーツしかなかったという話をしていました。
ただ、ムラサキスポーツのようなショッピングモールに入っているお店でスケートボードに出会った人たちが一度東京に行った後に地元に戻って、スケートボードショップを開き、そこでまた文化を広めるということが起きているらしいです。つまり、ある意味ショッピングモール発でも文化が繋がっていると言えるのかもしれません。
イオンが建った後に生まれた子ども達にとってイオンは文化の中心地だったみたいなことは言えそうですよね。
日本橋高島屋史料館 TOKYOでは8月27日(日)まで「モールの想像力-ショッピングモールはユートピアだ」と題した、ショッピングモールの文化的意義について考察された展示が催されている。
昔「浜松建築会議」というイベントを友人たちと開催したことがあったのですが、そこでイオンの話になって、東京を拠点とする建築家の方が「イオンができてそこに人が集まったとしても、中心市街地がなくなった後にイオンが収益性がなくなって撤退したら、あなたたちはどうするんですか」という話が出たんですよね。
それを聞いて「確かにそうだ」と気づかされ、街づくりはそこまで先のことを考えなくてはいけないと思ったのですが、同時に住む人は今の利便性を求めていて、10年後のために便利なイオンに行くのをやめようみたいなことも難しい話ですよね。ただ、こういう視点も大事なんだと思っています。
──ショッピングモールができて変わってしまった中心市街地に対して「変化を受け入れる」という話は興味深く聞きました。一方で、先ほどのお話のように短期的な経済性で流行りだからという考えだと、数年後に誰も人が来なくなってしまうかもしれない。街づくりは色々な視点から考えることが重要だと改めて感じました。
例えば、建築等の保存の話になると、アカデミックに建築に携わる人たちの中からは絶対に保存しなければという意見が出る一方で、事業的に建築を考える人たちは「そこに経済的なインセンティブが働かないと保存に繋がらない」という話をするじゃないですか。
僕は、大学で研究をしていたので学術的な世界の意義も分かりますし、組織設計で設計をしていた時は完全にビジネスの世界でしたし、両方の世界にいたのでどちらの意見もすごく分かるんですよね。
ただ、折り合いをつけるのが成熟した大人の役割だと思うので、どっちかに振り切れるのではなくて良いバランスを探すのが一番良い方法ではないかと思っています。
──まちがある層の人たちだけのものみたいになるのも良くないと思いますし、そこにいるさまざまな立場の人の意見を上手く拾って良いバランスを探していくことが街づくりには必要なんでしょうね。
「育てる」「深堀りする」がまちの魅力に繋がる?
──静岡・京都・東京と3都市に住んだ後藤さんが、今までの経験を踏まえて、住んでみたいと思う都市はどういったところでしょうか。
個人的には、バリアフリーとか子育て世代に優しい所がベースにある街だと住みやすいかもしれないと思いますね。
さきほどの話に繋がりますが、浜松にいた時には子どもがまだ小さくてショッピングモールによく行っていました。エレベーターがベビーカーを何台も並べられるくらいめちゃくちゃ広いし、床に段差がないからベビーカーを押しやすくて、移動しやすさが徹底されているんですよね。
建築に携わっていない人が「バリアフリーがすごいからショッピングモールに行こう」とはならないと思うんですけど、無意識のうちに移動しやすさみたいなのを感じているからこそ、ショッピングモールに足を運んでいるという面もあると思います。
一方で、東京に家を探しにきた時とかにベビーカーを押していて、東京駅でエレベーターを探すのがめちゃくちゃ大変だった経験があって。階段でしか行けないルートがあったり、隠しエレベーターみたいなのを探さないと上下の移動ができないつくりになっていたり(笑)
安藤忠雄さんは自身の建築を語る中で「段差がないと足腰が弱くなる」とは言っていましたが、でも、社会全体を見渡すとやっぱり楽な方が良いとみんな無意識に思っているような気がします。もちろんある程度の負荷は必要かもしれないですが、スマートフォンが主流になったのはやっぱりインターフェースがめちゃくちゃスムーズで快適だから皆手放せなくなっているという側面があると思うんですよね。そういうことを前提とした上で、建築や都市を考えなければいけないのではないでしょうか?
だから、そういう快適な都市…もしかしたら、そういう都市は怖いかもしれないですけど(笑)そういう状況を踏まえて考えられた街だと良いですよね。
──このnoteのきっかけとなった東京大学と新建築社との共同研究では、駅近ではなく歩きで楽しめる都市の魅力を考えることからスタートしたのですが、後藤さんの利便性や快適性の話を聞くと、駅近で移動が便利であることによっぽど勝る魅力がないといけないのだなと改めて思いました。
僕が発見した話ではないんですけど、駅近に関連して思い出した話があります。ネイルサロンはホットペッパービューティなどのウェブサイトでお客さんが店を決めるようになっているから路面にある必要がなくなって、マンションの上層階の一室とかでも成立するようになっているらしいです。
つまり、インターネットによって必ずしも道に面した一階部分のような目に入りやすかったり分かりやすい場所にお店を借りなくても事業が成立することが促進されていて、それはすごい面白いなと思いました。
──なるほど。かつては駅近が便利でその一択しかなかったと思うのですが、今のネイルサロンの話を聞くと、必ずしも駅近だけが便利と限らないものが出てきている可能性もあるわけですね。そうした便利さの多様性を捉えると、必ずしも駅近と繋がらないものが出てきて、それによってまちのつくられ方が変わることはありそうですね。
僕の住んでいる駅の近くに、雑誌の表紙になるようなラーメン店ができたのですが、割と駅から離れているのに、めっちゃ行列ができているんですよね。
それを見ると、やっぱりコンテンツが重要なんだなと思います。だから、コンテンツ力のある人を育てていく、みたいなことは重要なんでしょうね。
若い店主が始めた面白いお店って地価の問題で駅から離れてたりすることも多いじゃないですか。距離と魅力を天秤にかけて、魅力があればみんな行くということは間違いないですよね。
──究極的にはそういうコンテンツ力を引き出せるようになることが、街づくりに関わる僕らが目指すべきなことなのかもしれませんね。
富山の井波で「職人に弟子入りできる宿」Bed and Craftを展開する建築家の山川智嗣さんへのインタビュー記事では、その土地を訪れた時に「木彫」とその職人たちに出会い、その魅力を伝えるために自身もまちに住み、徐々に活動を広げていったことが語られている。
もし後藤さんが街づくりを発信する立場になったら、どういうところから考えますか?
アーキテクチャーフォト編集部でも議論したことがあるんですけど、発信と現実があまり乖離していない方が良いと思っています。
実態とかけ離れた表現を採用してしまうと、実際に訪れたときに「あれこんな感じだったっけ?」みたいなことが起こると思っていて。
アーキテクチャーフォトでは「これが、めちゃくちゃ良い建築なんだ」ということを過激な表現でプッシュしていくのではなく、むしろ冷静に捉えて説明していくことを大事にしているんです。
頂く資料の中にはストーリー性を持たせたいと思い、過剰な表現が使われている時もあります。それに対して編集者側が判断して、表現の過激さを適切な塩梅に落としていくことがメディアにとっては大事なことのような気がしています。
もちろん、まちを宣伝する時に誇張したくなる気持ちは分かるのですが、それがどんどん過激にエスカレートしていくと実態と乖離したまちのイメージが構築されていってしまうと思うんですよね。そうなると、発信によって足を運んでくれたとしても、「イメージしてたのと違った!」とむしろマイナスな効果を生んでしまうと思います。
なので僕がどこかのまちのことを発信するとするなら、なるべく現実とメディア上で見えるまちのイメージが一致しているようにした上でアピールしていく方法を考えたいですね。
──そう考えると、街にある本質的な良さみたいなところを深堀りしていかないといけないのでしょうね。街の本質を深堀りしていった結果、発信したいことが出てくる、というプロセスが良いのかもしれないと思いました。
そうですね。そう考えると発信よりもリサーチの方が最初は必要なのかもしれないですよね。
リサーチによって素晴らしいものが見つかれば、分かりやすい表現をとったとしても嘘ではなくなるので。ぱっと見ただけのものを、言葉の力で過剰に魅力的に表現してしまうとかは良くないと思いますね。
──なるほど。街づくりを考える時に「育てる」ということの他に「深堀りする」ということも考えられそうですね。
後藤さんの経験から生まれるまちに対する視点を通した話を色々と聞けて、興味深かったです。本日はありがとうございました!
ありがとうございました!
インターネットを通して「建築」を発信してきた後藤さんから、意外にも浜松という地方都市における住民目線でのまちの見方、間違いなくまちのひとつの中核を担っているショッピングモールは文化であること、街づくりの未来にとって考えなければならない視点について話が聞けたのはとても興味深いものがありました。
東京大学との共同研究の中で、ディレクターである小渕祐介先生が「最近は個の建築より、都市計画の方面に興味がある学生の方が増えてきた。」とおっしゃっていたことを思い返し、まち(都市)は建築の集合体であり、計画していく難しさと面白さがある、と改めて感じたインタビューでもありました。
文化としてのまちを考える際に、また後藤さんに、深掘りした話を聞いてみたいです。
聞き手:福田晃司、春口滉平、今中啓太・齊藤達郎(NTTアーバンソリューションズ総合研究所)
構成・編集:福田晃司
編集補助:小野寺諒朔、春口滉平
デザイン:綱島卓也
