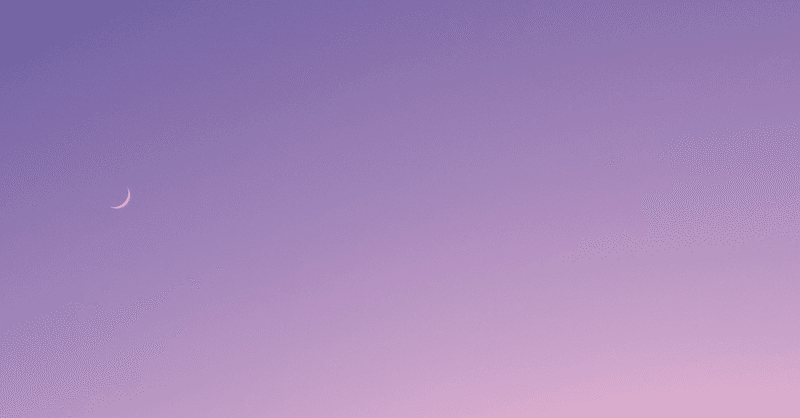
【大正の少女雑誌から】#7 月観る、君想う
ずいぶん久々の更新となってしまいましたが……
今回もまた、大正乙女たちの歌や詩をご紹介します。
今回のテーマは「月」です。
当時の少女雑誌を見ると、大正乙女たちにとっても、月は詩情をかきたてるモチーフのひとつだったようです。
大正時代といえば、ヨーロッパの耽美主義や世紀末芸術の影響も受けた、感傷的なムード漂う時代。夜を好み月を愛でるというのは、まさにこの時代にふさわしい表現・作風だったのではないでしょうか。(当時の人気挿画家のひとりである高畠華宵も、名前自体が「夜」ですね)
月明き夜なりことばのとぎれたるこのひとしきを夜がらすの鳴く
北海道 若山聖子
たそがれて月浮く水にすゝぎする乙女子の手の白く光れる
佐賀 野の鳥
映像喚起力が素晴らしいと思う二首です。
一首目は、まるで映画のワンシーンのよう。月夜の静寂に「ことばのとぎれたる」、その心情を代弁するかのように響く鴉の声が、言葉にできない空白を強調してドラマティックなものにしています。
二首目も、水面に映る月が少女の白い手に形を崩されながらきらきらと零れ落ちる、神聖な美しさが目に浮かぶようです。
冬の夜の月は恐しむつまじき二人をねたみし友の瞳に似て
長野 湖きよこ
月のいろ大聲上げて叫びたしこの胸のいろ寂しみのいろ
新潟 森井きみこ
この二首を読むと、人は月を見るとき、鏡に向かうように自分を見るのかもしれないと思わされます。
秘密の絆で結ばれたふたりを、冬の月だけが見下ろしている。それが睨まれているようで恐ろしいと思うのは、己の心ゆえ。
冴え冴えとした月の光に、胸に秘めた思いが重なって叫びだしたくなるのも、己の心ゆえ。
けれど月は、ただいつもそこで輝いているだけに過ぎない──
われとわが影をふみつついつまでもあるいてゐたき月のしづけさ
東京 弓路葉子
がた馬車の窓より晝の月を見て菜の花みちをゆられつゝ行く
中京 瓔珞
こちらは、情景描写に惹かれた二首です。
月の出ている帰り道、照らされた自分の影を見つめて歩きながら、静寂に身を委ねている──日暮れが早い冬の頃の下校や、習い事の帰り道のことを思い出しました。
次の歌の「がた馬車」というのは、がたがたと大きな音を立てて走る質素な乗合馬車のことだそう。そんな馬車に座って、菜の花が咲く田舎道を揺られつつ、真昼の白い月を見ている女の子。まるで、『少女パレアナ』や『赤毛のアン』といった少女小説のワンシーンのようです。
「月かげ」
シットリ湯気の篭ったお湯殿
窓から蒼白い月影がさし込んで
心地よく濡れた湯槽にパッとちって居る
青みを含んだ月の湯槽
灯に反いて乳房のあたりへ香り高い石鹸を塗った
灯に反いた胸が美しい
あゝ、私も月の光を浴びて居る。
めぐる血潮の幽かなかほりが
ボーっとした湯氣の中へ伸びていく心地がする
いつ迄も/ \゛斯うして居たい。
仙台 平野小枝子
こちらは口語詩ですが、ストレートな官能性に驚いて取り上げたものです。少女らしからぬ、と一瞬言いたくなりますが、むしろとても少女らしい詩ではないでしょうか。鏡の中の自分に恋する少女の頃にしか、きっとこんな陶酔的な詩は書けない……気品ある文体の中に、『痴人の愛』のナオミのような奔放さも感じます。
「月夜のポプラ」
淡靑い静かなお月夜に──
庭のポプラの銀の葉が
をどりくるふよ
ギララララ……
面白さうに
ギララララ……
淡靑い静かなお月夜に──。
満州 ■田和喜子
最後のこちらは、オノマトペに中原中也を感じた口語詩です。
ポプラを「銀の葉」と表現したのは、月の光に照らされた様子からでしょう。その葉が、風に吹かれて一斉に身を震わせる──
「ギララララ」というオノマトペのリフレイン、冒頭のフレーズと同じフレーズを最後に配置するなど、まるで童謡の歌詞のようにきれいにまとめられているところにも、この少女の美意識を感じます。
さて、今回は以上となりますが、投稿作品を通して改めて感じたのは、読者投稿欄に集う少女たちの「美しさを見いだそう」「それを表現しよう」ということに、とても積極的な姿勢でした。
たとえ月の出ていない闇夜だったとしても、彼女たちはきっと、どこかに何かを感じ取って美しい夢を見ようと努めたのではないかとさえ思います。
美しいものを探そうとする、感じ取る、その心こそが美しい。
その心を持っている人こそ、いくつであろうと少女なのだと思います。
※引用についてのお願いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
