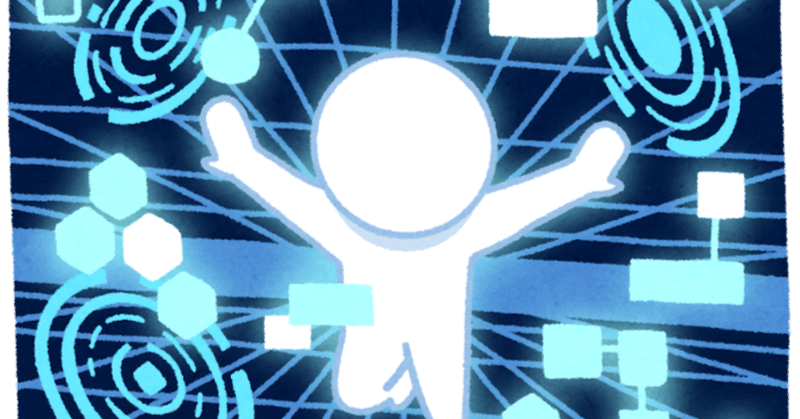
『スノウ・クラッシュ』を読んで世界をアップデートすることについて考える
■ 伝説の予言の書みたいになってた『スノウ・クラッシュ』の新版が出たぞ
「配達人<デリヴァレーター>は一種の特権階級<エリート>だ。」
メタヴァース等の言葉を生み出し、シリコンバレーの起業家たちの間で熱心に読まれたと評判の『スノウ・クラッシュ』が先日復刊した。
今を遡る事30年前、1992年の小説『スノウ・クラッシュ』は、よくわからない「高速ピザ配達」の話から始まる。
舞台は、近未来の「マフィアの牛耳るピザの高速配達と、音楽と映画とソフトウエア<マイクロコード>作りしか無い国、アメリカ。」
アメリカは凋落し、連邦政府は、今やなにをやっているのかよくわからないような状態。そして世界は独自のルールを持った「フランチャイズ国家」なる疑似国家めいたものにより分割統治されている。
どういう紆余曲折があって世界がそんな風になったのかは必ずしも明かではないが、現代でも、例えばapple税などと揶揄されるように、我々をある意味統治しているように感じられる存在は国家だけではない。
国境を超えてインターネット世界を支配するビッグ・テック、非中央集権的なクリプトの文化、新たな現実空間を目指すバーチャルリアリティ。世界というべきものが物理空間だけに存在するものでは無いことは、21世紀の現在では、だんだんとリアルに、身近に感じられるようになって来た。世界は、物理という実体のようなものの上に、見えないヴァーチャルなレイヤーを何重にも重ねたようなものだ。その各層に描かれる世界の地図は、物理の国境とは大きく違っている。我々は、様々な世界に部分的に属しながら暮らしている。
領土の問題があるかぎり、物理空間にフランチャイズ国家のようなものが出現する可能性はあまり高くないかも知れない。海上自治区のような理想郷は、今はまだ一部の億万長者たちが夢想するものでしかない。それゆえに今メタバースと呼ばれているような、バーチャル世界のものに期待が集まっているのだろう。情報通信が発達した未来において、伝統的国家の力が弱まっていく、少なくともなにかしら在り方が変わっていく、という予想は、現代では全く荒唐無稽ではなくなった。
今や、そんな預言書めいたポジションに収まることとなった『スノウ・クラッシュ』。宣伝されているとおり、「メタバース」「アバター」といったものが舞台装置として登場する。こうした用語を生み出したのが本作だということだ。他にも、ウェアラブル端末めいたものを装備し、あらゆることを記録する「ガーゴイル」や、データベースを管理する執事のようなAI「ライブラリアン」といった、現在では定番とも思えるような、いかにもサイバーパンクSFな風情を盛り上げる要素がちりばめられている。時代を考えると先駆的な作品であったことは間違いないだろう。
後世のSF作品は、直接にせよ間接的にせよ、過去に書かれた作品の影響を受けざるを得ない。『スノウ・クラッシュ』が預言書めいて見えるのは、それだけ多くの後世の作品やビジネスマンに影響を与えたという事だろう。一種の予言の自己成就のようなことかも知れない。今読んで、ここからビジネスのヒントを、というのは短絡的過ぎる気がするが、刺激的な作品とはどういうものか、という事を感じるにはよい題材であるように思う。
以下、若干のネタバレを含む。
実は、冒頭の「高速ピザ配達」のような、スタイリッシュでスピーディーなアクション的展開はこの物語の本筋では無かったらしく、ピザのくだりは開幕でやけに凝った魅力的な設定のようなものが描写されるものの、そのあとで全然出てこなくなる。
『スノウ・クラッシュ』の本筋は、「言語」を巡る想像力の物語だ。メタバース的な世界は、もちろん全てコンピューターの言語により記述される。空間そのものも言語によって成り立っていて、世界の法則も全て言語によって作られる。そういう意味では、言語が魔術的な力を有する世界だ。
一方現実でも、有名なエスキモーの雪を表す言葉の話のように、言語が世界の認識のようなものに影響を与えるという説がある。こういう言語的相対論のようなものには、色々と批判もあったりするようだが、不思議と魅力があって、決定的ではないにせよそういう面はあるのではないかと、わりと広く受け入れられている考え方だ。そして、コンピュータの世界における言語のように、人間が使っている言語が実はコンピュータプログラムのように人間を「書き換える」ことができるものだとしたら・・・本作はそういうお話だ。
そういう込み入った部分がありつつも、カタナを装備したハッカーが現実とヴァーチャル世界で立ち回るポップな作品でもある。想像力を掻き立てるSF的なギミック・ワードのようなもの・・・少し斜めにズラしたような、シニカルかつコミカルなセンスのあるサイバーパンク的なアレ・・・も十分楽しめることだろう。「メタバース」「アバター」といった後に定着する言葉を生み出したような、言葉のセンスの良さが感じられるエンタメ作品としても鑑賞できる。
■ 言葉やテキストのパワー
「ヤバい」で終わらせない語彙力は、世界を楽しむ力を増してくれる。
物語のように、人間をハック可能にするような圧倒的パワーを持った謎めいた古代言語、のようなものは、今のところ現実世界には存在しない。しかし、『スノウ・クラッシュ』が多くの人にインスピレーションを与えたように、言葉には、多くの人の想像力のようなものに作用するという圧倒的なパワーが既にある。
言葉によって現実を解釈・記述すると、どうしても情報量が少なくなってしまう。我々は歴史の中で、鮮やかな現実を描き出そうと、多くの語彙を生み出し、絵画の技術を向上させ、映像の精細さを追求してきた。動画のような情報量の多いメディアは、より現実を損なわずに写し取る、そういった方向性の中で開発されてきたものだろう。様々なメディアが発達する中で、言語というオールドメディアは、どうしても人間の想像力を刺激する事でしか、物事の鮮やかさを表現することが出来ない、という制約を抱えたままだ。言葉が通じなければ全く意味をなさないという不便なものでもある。
しかし一方で、現実にないものを描こうと思った場合、情報量の少ないメディアのほうが有利なことがある。テキストの世界では、「目の前に雲をつくような摩天楼がそびえている。」と記述するだけで、ビルを建設することが可能だ。「周囲には、ビルの谷間を縫うように高速エア・カーの飛行レーンが絡みつき、その中を多くの光が飛び交っている。」「なめらかなビルの表面には極彩色の動画公告が次々と映し出され、エア・カーは、人々の肥大化した欲望が埋めつくす中を飛行する。」などと書いておけば、なんとなく未来都市っぽいもの(たいていは過密で退廃的だ)を実にお手軽に建設することが出来る。
言葉が運搬する情報量は少ないが、読み手の頭の中には、膨大な情報が既にある。言葉はそういうものと結びつくことで、現実以上のものを想像させることができる強力さを備えたメディアだ。
言語が容易に作り出すものは風景や空間のようなものだけではない。言葉は「フランチャイズ国家」「スピード・レゲエ」「情け容赦ない格闘術」「ヤングマフィアの全国大会」といった、モノではないものも生み出すこともできる。こうした「SFによくあるような耳慣れない言葉」みたいなものは、作品にポップな印象を与える道具として導入されることが多いわけであるが、そういったディティールが人々を魅了し、なんなら現実に作ってみよう、みたいな刺激を与えることもある。もしくは、現実にそれと似たようなものがある事に気づかせてくれたりする。
近未来を描いた作品に見られるような、現在にもあるものが進化してちょっと奇妙なものになっていたりだとか、現在新しいと思われてみるものが、過去の遺物として笑われるようなものになっていたり、といった光景は、あたかも現実に新しいフィルターをかぶせるように、我々の見る風景をアップデートしてくれることがある。一冊の刺激的な新しい本を読むことは、自分が感じる世界に新しいレイヤーを一つ増やすようなことなのだ。
未来は、やってくるだけのものではなく、実際には我々が作っていくものである。容易にはコントロールできない事も多々あるが、結局は、未来は我々が作りたいと想像するものの中にあるはずのものだ。未来を想像していくために、言葉をアップデートすることはすごく重要な事だ。まだ見ぬものを、多くの人が共通の言葉でイメージするようになった時、その未来が現実のものとなる可能性は高まる。あとは技術的なハードルを超えるだけだ。
昨今ではSFの持つ力が各所で取り上げられるようになってきた。そうした、SF作品の可能性を考える上で、『スノウ・クラッシュ』は一度は読んでも良い作品だろう。優れたイメージ・エンジニアリングに触れて、現実と未来、つまり世界をアップデートしよう。
サポートまでは言いません!だって、スキ!みたいなやつなら、ただで喜ばせることが可能ですもの!
