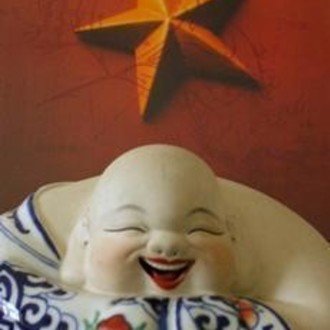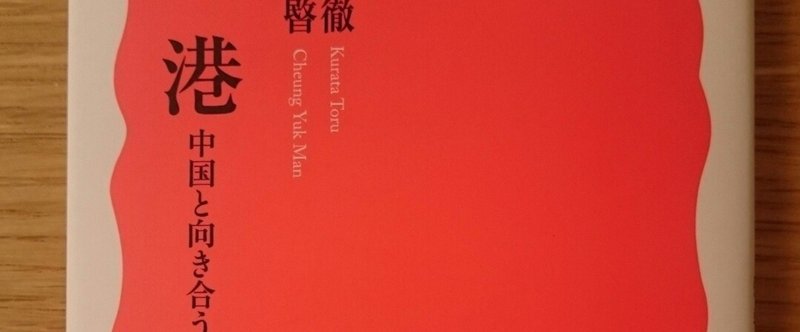#香港返還
【読んでみました中国本】現代から過去へ、香港のリマーカブルな時代をたどる推理小説:「13・67」陳浩基・著/天野健太郎・訳(文藝春秋)
先週、「『英雄本色』が放映3日間で興行収入2017万人民元(約3億4000万円)となった」という記事が中国の新聞に流れていた。
香港映画「英雄本色」は1986年、今では世界的な名監督の1人となったジョン・ウー(呉宇森)の出世作である。日本では「男たちの挽歌」というタイトルで、1987年で公開された。
日本では劇場公開後にビデオになってからこの映画はバカ売れした。ちょうど公開時にわたしは仕事を辞
【ぶんぶくちゃいな】香港返還20週年・その1:「手弁当でフェイクニュースに対抗する」社会記録頻道 SocREC
香港のメディア界では日本よりも速いスピードでネットに移行している。
今年に入ってから約30年、香港の世論を牽引してきた大衆紙「アップルデイリー」(「りんご日報」)の経営不振が大きく喧伝されるようになっているし、民主派に長らく愛されてきた「明報」もその中国政府への傾倒が人々の口に上っている。中国政府機関に脅された企業が、中国に批判的なメディアに広告を落とさなくなってきたからだ。
いち早くその変化