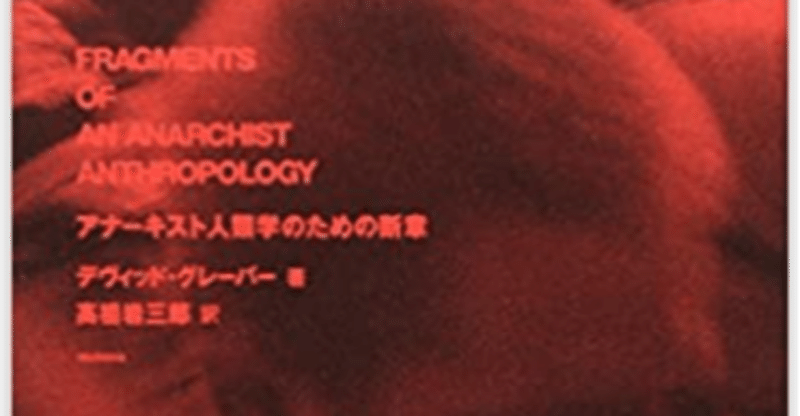
野党が本気で政権を狙うなら、本気で連立政権を志向するなら、デヴィッド・グレーバー『アナーキスト人類学のための断章』に学べ。
一つ前のnoteで「野党が本気で政権を狙うなら、将棋のAbemaトーナメントに学べ。大臣副大臣政務官候補3人一組で各大臣について「立憲チーム」「共産チーム」を作って、公開ディベート。連立政権の「影の内閣」選びと「公約」づくりプロセスをまるごと公開ネット中継する。そのうえで総選挙に向かうべし。」というのを書いた。これ、実は本当は「デヴィッド・グレーバー『アナーキスト人類学のための断章』に学べ。」ということも一緒に言いたかったのだが、あまりに盛りだくさんかつ方向性が違うので、分けて書くことにする。
前のnoteで、分かりやすく「ディベート」をすべし、と書いたけれど、ディベートと言うと、正反対の立場で、相手を論破する、ということをイメージさせてしまう。相手を論破するようなことをしたら、「共通公約」にも辿り着かないし、むしろ仲が悪くなって、連立政権が遠のくじゃあないか。そういう反論が当然予想される。
note本文では、「立憲チーム」と「共産チーム」がするのは「政策すり合わせディベート」である、と僕は書いているのだ。相手を論破するのではなく「合意できる点を探る話し合い」をしていく、というイメージなのだ。
政党は、その根本的な信念とか価値観が異なるから別政党になっているので、そこまで話を突っ込んでいくと、絶対に合意などできない。そこを攻撃しあったら、喧嘩になる。というか戦争にまでなるのである。
そうならないための、知恵、方法論ということについて、僕が学んだのが、『ブルシット・ジョブ』や『負債論』の著者、デヴィッド・グレーバーの『アナーキスト人類学のための断章』という本なので、そのことを紹介していきたい。
まず、「アナーキズム」「アナーキスト」というと、無政府主義、革命主義、過激派、とみんな身構えるが、グレーバーが言うのは、全然、そういうことではない。
僕がこの本の感想を書いたnote「『アナーキスト人類学のための断章 』 デヴィッド グレーバー (著), 高祖 岩三郎 (翻訳) 『負債論』『ブルシットジョブ』著者の、若き日の、活動の原点ともいうべき本。アナーキストのイメージが180度変わるので、著名にビビらず読んでみよう。」から引用する。
著者は、政府こそ、暴力装置である。とまず置く。マックス・ウェーバーの言うような意味で。とすると、政府を持とうという志向は、すなわち、(今、もし反体制であったとしても)、暴力により他者を支配しようという志向だということ。左翼や社会主義や共産主義も、権力奪取に成功し国家となった瞬間に暴力装置として、たいていは国民を弾圧し、反対派を粛清する暴力性をあらわにする。いや、反体制闘争のさなかでも、内部にも外部にも暴力的闘争を持ち込む。著者は、そうした「異なる考え方の人間を暴力によってコントロールしよう」という志向自体を否定する。つまり「アーキズム、政府の否定、国家の否定」とは、暴力で他者をコントロールしようということ自体の否定なのだ。それを「アナーキズム」と呼んでいるのだ。いや、それ以上のことを言っている。自分と違う考え方の相手に対し、自分の考え方に屈服させて、考えを改めさせようということ自体を否定する。
つまり、アナーキズムと言うのは、ディベートとは正反対の考え方、ということなのだな。相手の考え方を否定しないで、政治的な合意に達しようという立場をアナーキズムというわけ。そうすると、暴力装置としての政府がいらなくなるでしょう。
じゃあ、どうやって合意に至るのかというと。僕のnoteから引用するね。その中に本からの引用が入っている。
平和的な合意形成のしかたをもとにした社会を志向するのが「アナーキスト」だと、筆者は言う。
本書より引用すると「誰も他人を完全に自分の考えに転向させようとしないし、そうしてはならない。だから議論を行動に関する具体的な設問に集中させ、誰も自分の原則が破られたと感じないように、みなが参加していける計画を導き出すことを目指すということである。」
普通、人が、暴力的で無いと考える「多数決による民主主義」について著者は「暴力による少数派への強制」が現れるのと、多数決民主主義が現れるのは同時だと指摘する。多数決型民主主義は、軍事制度の成立と一体のものだという。多数決という形で、少数派に意にそわないことを強制するのが「政府」だとすると、それを否定するのがアナーキズムなのだという。
人類学的知見から、様々な社会で、そうした、権力性を徹底的に排除しようということを原則として成立している例が見出されるという。「未開だから、そうなっている」わけではなく、むしろ先行する権力志向、国家思考を否定する形で、集団の中に「国家への暴力的、他者否定的志向」が生じるのを排除する様々な知恵が組み込まれた社会のあり方が存在する。
そうした社会のあり方を、未来に向けて志向するのが、アナーキストということだ。
繰り返し引用するけれど
「誰も自分の原則が破られたと感じないように、みなが参加していける計画を導き出すことを目指すということである。」
つまりアナーキスト的理論化とは、他者の基本姿勢の過ちを証明する必要性にもとづくのではなく、それらがお互いに強化しあうような企画(プロジェクト)を見いだそうとする運動なのである。
立憲民主党と共産党が、お互いの信念の違いを攻撃しあわず、具体的に共同で参加しうる、解決すべき課題への具体的行動についてだけ、合意できる地点を探す。そういう話し合いを、webで公開された場所で、いかに「喧嘩せずに」行えるか。その姿を晒すことが、野党が、政権担当能力があり、選挙における協力共闘が、単なる選挙のための野合ではなく、政権獲得と運営への意志に基づくものであることを示す、最善かつ唯一の方法だと思うのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
