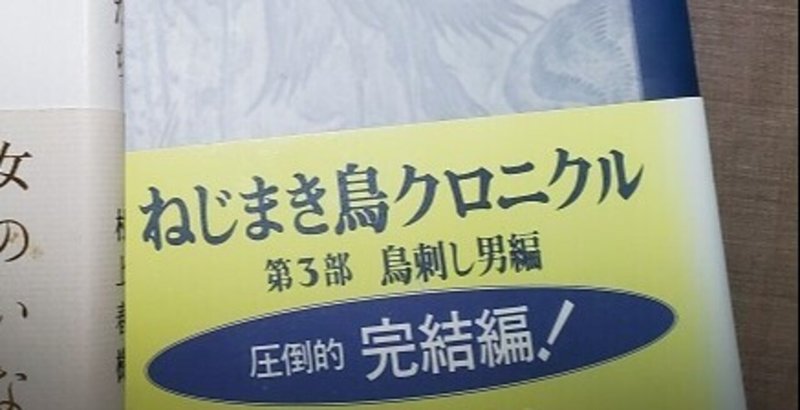
さっきのnoteの続きから『ねじまき鳥クロニクル』について考えているのだが。ネタバレ注意。というかネタバレしまくりです。村上春樹が小説を書き続ける「無かったはずなのに生々しい、暴力・加害者としての記憶」強迫観念について。
※さっきのnoteというのは「『女のいない男たち』「ドライブ・マイ・カー」を再読した後、『ねじまき鳥クロニクル』三巻だけを引っ張り出した。ついで「MOZU」を観たくなった。のはなぜかというと」」
https://note.com/waterplanet/n/n55c0b39810ef
その続きから、『ねじまき鳥クロニクル』について考えているのだが。ネタバレ注意。というかネタバレしまくりです。読んでからという人は、こちらを先にどうぞ。
この小説の「政治と暴力」というテーマについていうと、それが極限までいったノモンハンと満州国の話が、およそその1/3を占め、それが綿谷ノボルという義兄を通じて、現代の日本と主人公の人生に及んでくるのだが、そこから妻クミコを取り戻そうと、主人公、岡田が最後に、クライマックスで、井戸の壁を通り抜けた世界で振るう暴力のリアルさなんだよな、最大の問題は。あのリアルさは、村上春樹が大学生として生きた、70年安保前後の、学生運動の果ての陰惨な暴力を、あたかも村上春樹自身が体験していたかのような(加害者として振るっていたかのような)肉体的リアルさをもって描かれる。バットで、人の頭を思いきり殴り、叩き割るという行為。ちょっと引用するね。
どこからかナイフがやってきた。それはセーターの襟元を勢いよく切った。僕はその刃先の動きを喉に感じた。でもそれは僅かな空間を残して、僕の身体にかすりもしなかった。僕は身を捩るようにして横に飛び退き、体勢を立て直すのももどかしくバットを宙に振るった。バットはおそらく鎖骨のあたりを捉えた。急所ではない。骨を折るほど強い打撃でもない。でもかなりの痛みは与えたようだった。相手がひるむ手ごたえをはっきりと感じ取った。はっと大きく息を吸い込む音も聞こえた。僕はコンパクトにバットスイングしてから、そのバットをもう一度相手の身体に叩きつけた。同じ方向に少しだけ角度を上に変えて、息遣いの聞こえたあたりに。
完璧なスイングだった。バットは相手の首のあたりを捉えた。骨の砕けたような嫌な音が聞こえた。三度目のスイングは頭に命中し、相手をはじき飛ばした。男は奇妙な短い声を上げて勢いよく床に倒れた。彼はそこに横たわって少し喉を鳴らしていたが。やがてそれも静まった。
(中略)
激しく歯を食いしばり、重い窓を開けるように、肺の奥にためていた空気を静かに吐き出した。身体の震えはまだ引かない。あたりに嫌な臭いが漂っている。それは脳味噌の臭いであり、暴力の臭いであり、死の臭いだった。それらはみんな僕が作り出したものだった。
いまどきの若い人は、「バイオレンス小説でよくある描写じゃん」と思うかもしれないけれど。70年代に入っての新左翼内ゲバがヒートアップした時代には、本当にこういう風に、路上で、相手セクトのアジトを襲って、相手幹部のアパートの寝込みを襲って、こうやって殺したということを、普通の大学生だった若者たちがしていたのだよ。村上春樹はそのど真ん中の世代で、そういうことがいちばん激しく行われていた大学の一つ、早稲田大学で学生時代と、その後の何年間かを過ごした。そういうことから彼自身は距離を置いていたのだが、同じ時代の、ごく身近にそういうことがあった。村上春樹とその小説を理解するには。彼がその時代を生きた人間だということは、きちんと理解した方が良いと思う。なぜ僕がこういうことを書くかは、下のnoteを読んでくれるといいかと思う。
井戸の底の暗闇の壁を抜けた先の世界での、「異世界での生々しい暴力」。それが自分なのではないか。この作品では「現実世界のことではなかった」ということで、主人公はちょっと心からほっとする。彼が井戸の底の世界で綿谷ノボルをバットで殴り殺したとき、現実世界では、綿谷ノボルは、長崎で多くの人の前で講演中に脳の血管が破裂して、意識不明になって回復不能になっていた。
村上春樹は、その小説の長い遍歴を通して、「自分は現実世界では暴力を行使しなかった、加害者ではなかった」はずなのに、なぜか、加害者であったという「体感」だけが残っている。そのこととどう折り合いをつけるか、という長い旅をしているように思われる。
以前に何度か論じた『ノルウェイの森』→『色彩を持たない多崎つくる』の、25年の時をまたいで書かれた連作もそうだし。今回、気づいた『ねじまき鳥クロニクル』→『ドライブ・マイ・カー』もそうだ。
これもまた、以前に論じた、「納屋を焼く」→『ダンス・ダンス・ダンス』→この関連を発見して作品化したのは映画「バーニング」(韓国のイ・チャンドン監督)なんだけれど。
「やっていないと思うんだけれど、自分は、本当は現実にも、ひどい暴力をふるっていたのではないか」ということに対し、初期のおしゃれ村上作品は、そういう気配をおしゃれ都会派小説の下に隠していたのが、だんだんとその感覚、実はやっていたような感覚・あるはずのない記憶に追われているように見える。その生々しさを封印するために、小説を書いて、パラレルワールド、異世界に暴力を封じ込めようとしているように見える。自分は少なくとも「現実世界」側では暴力的な人間ではなかった、「悪意と暴力」側の人間ではなかったという小説を書き続けている。
小説家が小説を書き続けるためには、それくらい強い「書かなければ生き続けられない」という、内的動機、オブセッション(強迫観念)が必要な感じがするのだよな。
村上春樹小説が圧倒的に売れるのは、主人公が善良で知的な人に思える、権力からも美貌からも遠いのだけれど、社会から距離をおいて誠実に知的に生活の細部を大切に生きているという主人公像が、読者が主人公視点と同化して読み進めるときに、なんともいえぬ「理想的なアバターを着ている」ような感覚にあると思うのだけれど。事件に巻き込まれるとしても、それは主人公の過失落ち度でない「被害者」や、「被害者の友人や恋人や夫」という善意の立場から巻き込まれていくのだよね。
なんだけれど、そういう小説を書いている村上春樹の底にあるのは、「自分が暴力的加害者であったという、現実ではないのに生々しい感覚、記憶」なのではないか。ということを、読んでしまうのだよな、僕の場合。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
