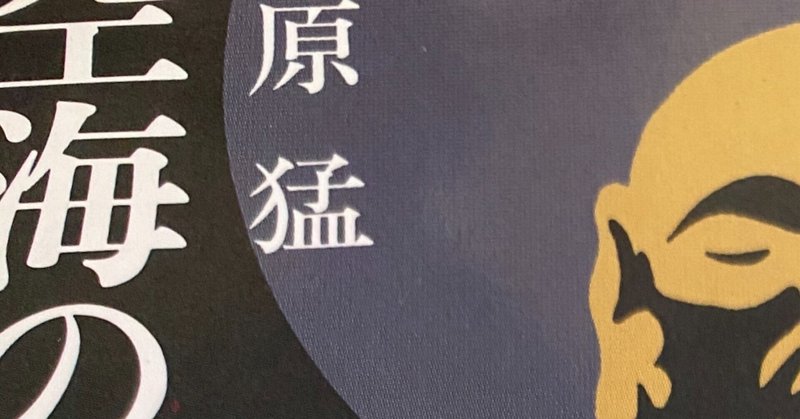
相即相入の思想が「多」であることを肯定する -梅原猛 著『空海の思想について』を読む
(このnoteは有料に設定していますが、全文無料で公開しています)
◇
相即相入ということについて思いをめぐらせようというとき、梅原猛氏の『空海の思想について』も強力な導きの糸になる。
相即相入とは、他と区別されたある一つの物事の中に、それとは異なるものとして区別されたはずの他の全ての事物が入り込み、関係しているということである。
例えば、「自己」の中に無数の「他者」がつながっていること、今現に生きている他者から遠い過去を行きた他者まで、ありとあらゆる他者がつながっており、あるいはもっと直接に入り込んでいること。そういうあり方を相即相入という。
「私の中に、他者なんて入り込んでいない」
とおっしゃる方もいるだろうけれども、それなら例えば、昨日食べたカレーの中に入っていたビーフは、ある一頭の牛であり、あなたとは別の生命体だったはずである。あるいは一人の生命を形成するに至った遺伝情報も、元々は多数の祖先たちのものだった訳だし、私たちが何かを言ったり考えたりするときに使っている言葉というものも、多数の人の死を超えて伝承・変容してきたものである。
一つの生命の中には、他の生命が多数、無数に、入り込んでいる。
もちろん、相即相入は物質的なものの時間を超えた共有ということに限られない。あらゆる存在はそもそも相即相入している。というか、真に存在するのは、その中に無数の差異化の傾向を含んだ大きな「ひとつ(一者)」であり、その「ひとつ(一者)」の中に物質=エネルギーが生じ、生命が生じ、神経系が生じ、人間が生じ、意識が生じ、言語が生じる。
そうしてその言語と意識から、「私と他者」であるとか、「善と悪」であるとか、「生と死」であるとか、ありとあらゆる対立関係にあるペアを分別する営みが動き出し、あるパターンでの分別を反復することで、あたかもそういう区別が世界の始りからあったかのような雰囲気を、意識に対して醸し出す。
そうした分別をせざるを得ない、分別をすることと同義である意識=言語にとっては、「一者」である世界の真相が、互いに区別され対立関係にあるもの同士が「相即相入」している事態として浮かび上がる。
相即相入を、一即多・多即一、ということもできる。
※
梅原猛氏の『空海の思想について』に、次のような一節がある。
「一切の世界は、一つの陀羅尼中に、あるいは一つの梵字に集約される。・・・あらゆる梵字が、その一字の中に全世界を、全存在を、全真理を、含んでいるのである。」(梅原猛『空海の思想について』p.114)
阿字でも、吽字でも、どの梵字でも、一つの「字」の中に、全世界が「含」まれる。
一つの字に「世界」が「含まれる」とは、梅原氏によれば「単に、世界の本質が含まれているというようなものではなく、世界がその差別のままに、そっくりそのまま含まれている」ということである(p.113)。
一つの字に含まれる世界は、どこか遠くにある「本質」的な何かではなく、私たち一人一人が現に生きて経験している憎しみや悲しみや煩悩にまみれた(?)”この”世界そのままである。
この現世が”そのまま”、そこに無数の差異化の傾向を含んだ一者そのものなのである。
「大日如来が、もし法界性身にとどまるならば、それは大した力を持たない。それが大きな力を持つのは、その姿を変えて、さまざまな姿で現れるからである。それが報身、応化身、等流身である。・・・このように四身の別があるが、結局、すべてが大日如来の姿である。区別の面から見ると、それは違っているが、平等の面からみると、それは全く同一であるということになる。(pp.88-89)
一者である「大日如来」を、「区別の面から見るか」「平等の面から見るか」。
中沢新一氏の『レンマ学』この言葉に言い換えると、区別の面から見るのがロゴス的知性であり、平等の面から見るのが「ロゴス的知性とレンマ的知性のハイブリッド」の知性ということになろうか。
梅原氏は続ける。
「大日如来はその因縁に従って、さまざまに現れるのである。そして、その現れによって、そこに差異があるのである。」(pp.89-90)
差異は、どこかで初めから「ある」ものではなくて、差異を生じる、差異「化」する、分別する、現れる動きの軌跡あるいは痕跡である。
※
ちなみにこの「一者」における差異化の動きとは、人間において一つには「時間」の軸、シンタグマの軸として痕跡を残す。過去、現在、未来の区別。言葉を発する時の主語、動詞、目的語のように配列される要素同士の区別とその線形配列いう姿をとる。
また他方では、一つの時間軸に並行する他の無数の時間軸、そしてパラディグマの軸として潜在的な分別の可能性を生み出す。
この二つの直交する軸の上に並んだ個々の要素は、互いに他とは異なる、他とは差異化された個でありながら、同時に他の全てと「ひとつ」につながって、縁起のネットワークを織り成している。
※
人間の意識と言語は、最初から最後まで「分別」をする働きであり、分別の動き・処理の結果=産物のみを認識し記述する。ここから離脱することは、一つの生命体として生きながらであるかぎり不可能と言える。
しかし、この分別を差異そのものを「相即相入」しあう関係と「として」理解することもまた、"レンマ的知性とロゴス的知性のハイブリッド"としての人類の知性ならばできるのである。
その知性は、「ひとつ」である、言う前に、「差異がある」「多数である」という。その上で、無数に異なりながら相即相入している、と言うのである。
多であることが一つであることであり、一つであることが多であることなのだ、という言葉で言わざるを得ないところに至る。
このnoteは有料に設定していますが、全文無料で公開しています。
気に入っていただけましたら、ぜひお気軽にサポートをお願いいたします。
m(_ _)m
関連note
ここから先は
¥ 190
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
