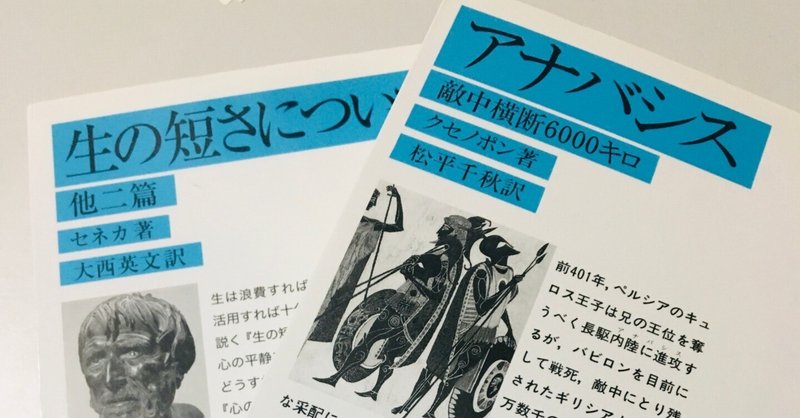
#018-晴耕雨読的な話
8月も終わりに近付き、仕事もかなり落ち着いてきました。
毎年6月〜8月上旬は休みなく働き、仕事が一段落するお盆あたりで体調を崩してペースダウンするというサイクルです。
仕事が忙しい時期には趣味である読書もほとんどできないのですが、最近は時間が取れるようになりました。
今日は農業の話題ではなく、最近読んだ本の話などを書きます。
晴耕雨読
「晴耕雨読」という四字熟語自体は意外にも(?)中国の故事成語ではなく、
明治時代に日本でできた言葉のようです。
ただ田園詩人と呼ばれた陶淵明の詩にも「畑仕事のあとに書物を楽しむ」というような描写が出てくるので、古来から農業と読書は相性が良かったのかも知れません。
晴れた日には田畑を耕し、雨の日には本を読むという生活は一種の理想とされています。
現代の施設園芸だと雨の日にも仕事はあるのですが、仕事のあとに本を読むのはとても良い気分転換になります。
最近の読書
基本的には現代をテーマにした社会科学分野の本が好きで小説や古典などはあまり読まないのですが、最近は古代ギリシャ・ローマ系の本に挑戦してみました。
大学時代に授業でプラトンなどを何冊か読みましたが、そもそも論旨が掴めない上に註釈や解説文が本文の倍くらいあり、とにかく読むのが苦痛でした。
しかし最近は新訳版などの読みやすいものも多く出ているようでしたので、以前から気になっていた本を読んでみました。
1冊目「アナバシス」 クセノフォン著
古代ギリシャ時代の軍人・哲学者であったクセノフォンが、自身が参加した戦いについて書いた本です。
あらすじだけ聞くと、「300(スリーハンドレッド)」のように今すぐにでもハリウッドで映画化しそうな話です。
〜「アナバシス」あらすじ〜
紀元前401年。主人公クセノフォンが所属するギリシャ人傭兵部隊1万数千人は、ペルシア帝国の王子キュロスに付き従い、ペルシア王位簒奪のための反乱に参加した。
無類の強さを発揮するクセノフォンたちであったが、首都バビロンを目前にした戦いで王子キュロスがまさかの戦死、友軍にも裏切られ、敵国の奥深くにて突然孤立してしまう。
全滅の危機が迫る状況のなか、故国を目指すギリシャ兵たちの6,000kmにも及ぶ脱出行がいま始まる・・・
ものすごく面白そうです。
しかし実際に読み始めると、古典に慣れない身としてはなかなかのハードルがありました。
ここを発って行程2日、10パラサンゲスを進んで川幅3プレトロンのプロサス河に到着、そこからさらに行程1日、5パラサンゲスでピュラモス河に達した。川幅は1スタディオンあった。(中略)ここにはスパルタ人ピュタゴラスに率いられペロポネソスから廻航してきた35隻の艦船が、キュロスのために待機していた。この艦隊をエペソスから先導してきたのはエジプト人タモスであった・・・
万事この調子です。
よく分からない距離を進み、知らない場所に着くと、知らない人がキュロス王子のために待機していた、という事しか読み取れませんでした。
川幅の単位が変わるのもよく分かりません。
しかし我慢して註釈を参考にしながら読み進めると、だんだん話が掴めてきます。
最終的には冒険譚としてかなり面白く読むことができました。
また古代軍事史を研究する上での資料価値もあるようです。アーサー・フェリル著「戦争の起源」でもかなり引用されていました。
2冊目「生の短さについて 他二篇」 セネカ著
古代ローマの哲学者・政治家であったセネカの著作で、現代風に言えば「生きるヒント的エッセイ」のような内容ですが、2000年を経てなお色褪せない人生哲学が詰まっています。
「人生は短い、くだらないことに時間を使っている暇はない」と繰り返し説き、「哲学を学べ ≒ とにかく勉強しろ」というような結論に至ります。
すべての人間の中で唯一、哲学のために時間を使う人が(中略)真に生きている人なのである。(中略)彼はまた、あらゆる時代を自分の生涯に付け加えもする。
「勉強することで、過去の人々の経験や英知を自分のものにできる」という意味だと解釈しますが、ニュートンの「巨人の肩に乗る」やビスマルクの「賢者は歴史に学ぶ」などの言葉にも繋がる「知識を継承することの意味」を考えさせられます。
また過去の賢人たちの言動を多数引用し、ストイックで芯のある生き方を称揚する様は、中国史上屈指の名文の一つに数えられる文天祥「正気の歌」に通じる精神性を感じました。
一方セネカはかなりの毒舌も炸裂させており、その面でも楽しむことができます。
ただただ酒と性のためにだけに時間を浪費する者もいる。(中略)彼らほど恥ずべきことに没頭している者はいない。
この手の連中のなかに、自分の髪の乱れは気にしても、国家の乱れを気にする者が一人でもいようか?(中略)見栄えの洒落た人間でありたいとは思っても、立派な心の人間でありたいと思う者が一人でもいようか?
とにかく怠惰な人たちを叱責し、豊かな人生の為の精神修練を勧めます。セネカ哲学を実践するのはなかなか難しそうですが、我が身を振り返る良い機会となりました。
以上、最近読んで面白かった本の話をさせて頂きました。
また農業関連の本や、そうでない本も色々と読んで感想を書きたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
