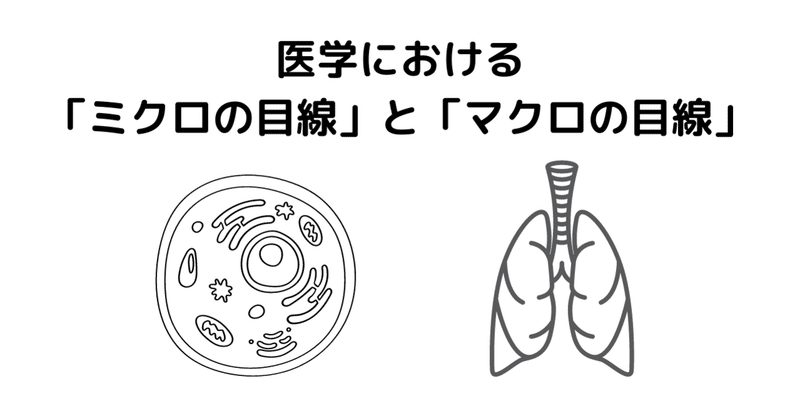
医学における「ミクロの目」と「マクロの目」。
最近更新できておらず、記事を楽しみにしておられた方、申し訳ありません。せめて「日記」的にでも記事を定期的にUPしていこうと思います。
今日のテーマは「医学」へのアプローチの仕方です。ミクロな目線とマクロな目線。2つの視点をうまく行ったり来たりすることが学びの効率化に大事だと思います。
生物の基本「細胞」から、医学を語る「ミクロの目」
生物の基本は「細胞」です。われわれ人間も、細胞の集まりです。
だからこそ、医学を学ぶ上で細胞について学ぶことが必須です。これは「基礎医学」の目線ですね。ミクロな目線です。細胞生物学、生化学や分子生物学を学ぶときの目線です。
「~~系」とか「○○科」という臓器・機能別に医学を語ろうとする「マクロの目」
その一方、わたしたちが臨床医学を学ぶ際に馴染みの深いのは「循環器科」「呼吸器科」というような分類ではないでしょうか。
体の不調を訴えて病院に行く際に、「○○科」というふうに専門科が分かれています。
これらは人の機能を「役割」別に見るマクロな視点です。
ひとつの細胞がたくさんのコピーを作り、それぞれがちょっとずつ違う特徴を持つようになり、グループ別に役割分担するようになりました。
人間社会に似ていますね。途方もないほど昔は、生きていくために食料を取りに行って、それを調理して、食べて、穴をほったり焚き火をしたりして安全に夜寝るための場所を確保する。こういったことを全部やらないといけなかったかもしれません。
でも今はたくさんの人が協力して生きられるようになった。各自は「自分の得意なこと」だけすれば、生きていけるようになった。われわれの細胞も同じように役割分担し、グループに分かれました。だから、医学を学ぶマクロの視点というのは「臓器別」アプローチになります。そして圧倒的にこのアプローチのほうが「身近」ですね。
マクロな視点は具体的には、、、
生きるのに必要な酸素・栄養をすべての細胞に行き渡らせる役割(循環器系・血液のうちヘモグロビン)。
そのための酸素を取り込み、燃焼物の二酸化炭素を排泄する役割(呼吸器系)。
栄養素を上手に取り込む役割(消化器系)。
取り込んだ栄養から、「エネルギー」を作ったり、蓄えたり、古くなった細胞を作り変えたりする役割(肝臓・代謝系)。
その結果生まれた不要物を排泄する役割(腎・泌尿器系)。
全身の細胞がてんでバラバラに活動せず、互いに秩序を守って協力し合うための情報伝達(内分泌)の役割。
体外から侵入した微生物を排除するための役割(血液・免疫系)。
一つの個体として、獲物を確保したり、捕食者から逃げたりする役割(筋骨格系)。
外部からの情報を把握し、それに適切に反応するために司令を出す役割(神経系)。
自らのコピーを作るための役割(生殖器系)。
もちろんそれぞれの役割分担が明確に線引できるわけではないですが、こんな感じ、と考えていくとわかりやすいでしょうか。
臨床医学を学ぶ上で、「臓器別」に学ぶのは「そう分けたほうがイメージしやすい」し「わかりやすい」からでしょう。さらに「○○系」というのは、もう少し大きな概念で「臓器グループ」とでも言いましょうか?臨床医学の授業の「科目」はこの「系」に分けられているといえます。
基礎医学(ミクロ)と臨床医学(マクロ)の「シームレスな行ったり来たり」の学びを提供できないだろうか?ということを模索しています。
大学医学部での医学教育が学生たちにとって難解かつ退屈な理由は、低学年で(実際にどう役立つかイメージしにくい)ミクロの授業に徹し、高学年になってやっと(イメージしやすい)マクロの目線で学ぶという古典的な「基礎医学」→「臨床医学」という順番にあると思います(それだけではないはずですが)。
一般の方向けに医学を説明する上で、この「ミクロの目」と「マクロの目」を上手に行ったり来たりしてわかりやすくできればいいなと思います。また、医療従事者の卵たちへの授業を組み立てる上でも、この「両方の視点」から有意義に迫れる方法を考えていこうと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
