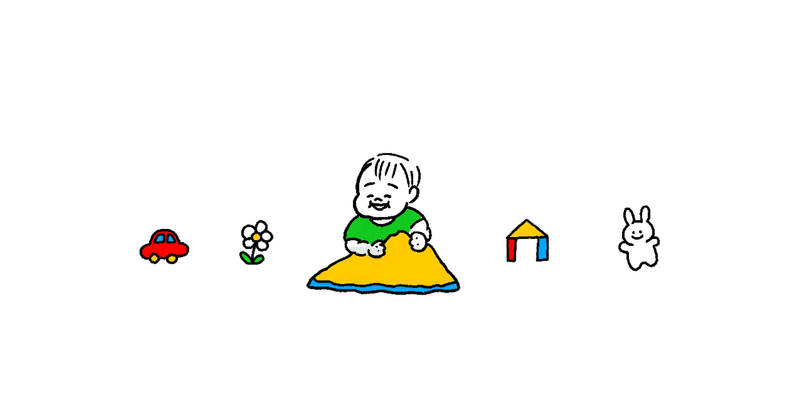
学歴と仕事の関係6
前回までのお話
慶應生の私、苦しい就活を経て2014年4月、社員食堂等の運営会社に入社する。OJTがまた大変で、色々な人と関わりながら、学生食堂・ホテル・社員食堂の3箇所の現場研修を経て、10月には希望通り本社の管理部門に配属され、現在に至る。
今、改めて問う。何故私はあんなに就活に苦労したのか?
その答えは「学校」と「働くこと」の分断ではないだろうか。キャリア教育とか、アルバイトとか、そんな表面的なことではなく、根はもっと深く、暗い…。
「普通の会社員」として働くイメージがない!
子どもの頃は、大人から「君たちには無限の可能性がある」と言われた。でもそれって、すごく曖昧な言葉じゃないだろうか?それを聞いた時私は、「まだ若いから大丈夫、何とでもなる!」という根拠のない自信を持っただけで、何に努力をすれば良いかよくわからなかった。
学生時代、総合的な学習の時間で「職業調べ」をする機会があった。働く大人に仕事内容や、どうやってその職業についたのかをインタビューをして、皆の前で発表をするというものだ。小学校の頃は確か、交番のお巡りさん、中学生の頃は、通っていたヤマハ音楽教室のエレクトーンの先生にインタビューをした。小学校のことはほとんど覚えていないが、中学生の頃は、一人一人レジュメを作って発表したので、クラスメイトの発表内容も少し覚えている。医師や看護師、美容師、通訳、声優など、専門職ばかりだった気がする。いわゆる普通の会社員について発表した人はいたかもしれないが記憶がない。職業といったら専門職、という思い込みがあったののだろう。少なくとも私は、発表するなら「カッコいい」職業の方がいい、とかそういう見栄もあり、家族に相談する時、「誰か知り合いにすごい人いないの?!」とか聞いていた。今思えば大変失礼な話だ。会社員と一口に言っても、仕事の種類は山ほどあるということを知ったのは、それから5年ほどして就活を意識し始めた頃。いわゆる普通の会社員の仕事内容を全く知らずに始まった就活だった。
就活セミナーを受けた際、キャリアコンサルタントの方に、「一番身近な社会人は家族です。ぜひご家族の方に話を聞いてみてください」と言われたことがある。話を聞いてみるにしても、私の父は理系の技術者で全く畑が違うし、母には聞こうという気が起こらなかった。(あまり本人が話したがるタイプではなかったというのと、パートタイマーだったので参考にならないだろうという思い込みがあったからだと思う。きっと私は正社員以外の働き方の人を見下していた)
そんな感じだったので、私は2012年の秋〜冬の、いざ就活スタートという段になって、自分の持っているカードの少なさ、弱さに気がついたのだった。
慶應の学歴、語学が人より得意なこと、大学1年生の時にドイツに短期留学していたこと、大学の成績はそこそこいいこと。これだけのカードで私は戦わなければならない。
運動部で仲間と力を合わせた経験も、サークル活動の輝かしい功績も、アルバイトで自らのアイディアによって売上に貢献した実績も、私にはなかった。
選ばなかった専門職の道
就活で苦戦し始めると、私は周囲の専門職になるために勉強している友人達が羨ましくて仕方なくなった。医学部に行けば医師になれる。その他の理系分野であれば企業との繋がりがある。教職を取っていれば教師に、法学部であれば法曹界を目指せる。公務員試験の勉強をするのも一途で良い。
どれも選ばないのは自分で決めたことだ。これらの職業に魅力を感じなかったのと、勉強から逃げたかったのと、理由はその両方だ。決めた自分の責任だということはわかっていたが、不安に押しつぶされそうだった。
なぜ人は専門職を目指すのか?
私は専門職の道をあえて選ばなかったが、当然選ぶ人も多い。選ぶ人はなぜ選ぶのか?
もちろん、その職業に魅力を感じて自ら目指したという人も多いだろうし、それは素晴らしいことだ。でも、そうでないパターンもあるのではないだろうか?
理由は色々あると思う。親の影響で、とか、食うに困らないから、とか。
でも、突き詰めれば答えはこれなのではないだろうか。
サービス業など誰でもできそうな仕事は下に見られがちだし、収入も低い。それは嫌だ。だから、誰にでもできない仕事に就けば、馬鹿にされないし高収入を得られる。
じゃあどうやって、誰にでもできない仕事に就くのか、というと、大人は「とりあえず勉強していい学校に行っておけ!」と言うのだ。いい学校に行った後のことは、「キャリアは後から付いてくる」みたいに思っているので、多分よく考えていないのだ。
結局、何を、どう頑張ればいいのかとかは大人もわからないし、不安なので、とりあえず結果がわかりやすい「勉強」を推奨する。推奨された方も何のために頑張って勉強するのかよくわからないから、志望校合格より遠くのゴールが見えずにモヤモヤするのだ。
私はこれが世代間で繰り返されることで、自己肯定感が低くなっているのではないかと考えている。
そしてこの自己肯定感の低さこそが、学歴と仕事の関係に大きな影響を及ぼしていると感じている。
次で最後くらいだと思います。続く!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
