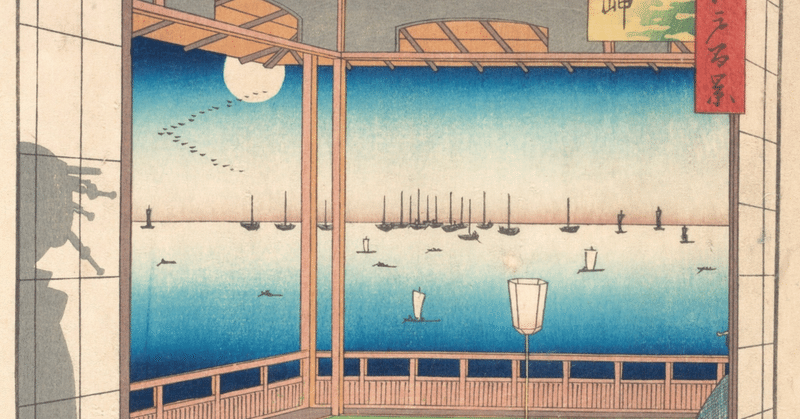
駅舎の妖精
「カレーだよ、ここに来たらこれ一択」
メニューを前にあれやこれやと悩む私たちの眼前に、にゅっと大きな手が伸びてきて、「激馬カレー」の文字をとんとん軽快に叩く。見上げるとチェックのワイシャツのおじさん。礼を言うと、彼はうんと頷いて、私たちが注文を終える時には向こう側のカウンター席へと消えていた。
本州の最果て。青森県。津軽地方。太宰治が生まれ育ったこの土地に、私たちは来ていた。いわゆるゆかりの地巡りというと聞こえはいいが、太宰の本を読み始めて間もない、まあただのミーハー心満載の旅である。
五所川原駅から約二十分、車体に「走れメロス」号と書かれたオレンジ色の津軽鉄道に揺られて早朝八時半に金木駅に着いた。金木という町には太宰の生家である「斜陽館」がある。
スマホで写真を撮ると確かにその姿はネットで見た通りのまんまであるのだが、これがまた、今は閑散と静まり返った金木の空き家を横目に道を抜けた先に、どおんと立派に構えているのだから、その大きさ、放たれる過去の威光というのは、やはり実際に訪れてこそわかるものである。太宰の家は金持ちであった。
中は中で立派なもので、吹き抜けの天井は高く、部屋数は全部で十九もあり、階段はエッシャーの騙し絵かと見紛うほど。
あまり豪邸っぷりを書くのも太宰が可哀想なのでこの辺にしておきたいが、ここで私たちは大いに楽しみ、所要時間三十分のはずが、実に二時間半もいた。お昼目前である。午前中に行きたい目当ての観光場所が他にいくつもあったから、内心ひやひや、しかしここが旅の一番の目的であったから急ぐのも本末転倒というわけで、そんなこんなで長居となったが、そのせいで後の予定をぐるぐると頭の中で組み直す羽目になった。
それから大急ぎで数件めぐり、途中おしゃべり好きなガイドさんの話を一時間立ちっぱなしで聞いて、ふっと気が遠くなったりもしつつ、金木の町を歩きに歩いて、そうして芦野公園前の駅舎についたのは十五時だった。
朝からほとんど何も食べていない。はらぺこでたまらなかった。日頃デスクワークばかりの貧弱な体は、少し歩いたくらいで疲労もひどい。この辺りには昔競馬場があったようで、馬肉が名産であったから、赤い屋根がトレードマークの駅舎でひとやすみしつつ、馬肉カレーを楽しもうという算段だ。
そういうわけで話は冒頭に戻る。歩き疲れて入った駅舎の中は、おそらく最近改装でもしたのだろうか、喫茶のような洒落た雰囲気がながれていた。想像していた以上の落ち着ける空間に、ほっと息を漏らしながら、メニューを見ながら馬肉カレーは一つだけ頼んで、あともう一つはせっかくだから違う料理を頼んでみようかなどとやいやい話していたが、不意に現れたおじさんの一言が決定となった。馬肉カレーふたつと、食後に珈琲ひとつを注文する。
馬肉カレーは美味しかった。からっぽの胃に染み渡る。やはり人間、くたくたになるまで動き、腹を空っぽにしてこそ食べ物の旨みがわかるものだ。うまいうまいと感嘆しながら食べるも、ふと、この後の残り時間が少ないことに気がつく。東北の電車は少ない。1時間に一本しか来ないものだから、ここで食べて、芦野公園を散策して、また戻って電車に乗らなければならない。一六時の電車は間に合わないだろう、となると十七時か。ともかく食後にゆっくり珈琲を飲んでいる時間はないと思い直し、カウンターまで歩いていき、珈琲はいますぐ出してくださいと頼んだ。
席へ帰る途中、壁に貼られている鉄道の時刻表を見る。紙に書かれた時刻表は数字が縦並びで、慣れていないと読みづらい。
「十六時にくるよ」
不意にまた横から声がする。あのおじさんだった。
「もうすぐ来る。写真だけなら撮れるよ。ここから外に出ていいから。のっちゃ駄目だよ。まあ俺、ただの客なんだけどね」
ただの客だったのか。
扉を開けて数段あがるとすぐに津軽鉄道のホームへと繋がっていた。春になるとこの芦野公園前の桜の下を通り抜ける津軽鉄道が見られる。今は秋のはじめであったから、辺りは緑のみだったが、階段の傍に、ほおずきがうつくしくオレンジ色の実をつけていた。
あいにくの曇り空ではあったが、津軽の曇天もまた趣があっていい。少し肌寒くなってきた空気をすいこむ。
「来た?」
「いえ、まだ」
振り向くとおじさんが後ろ手で扉を閉め、同じく外に出て来ていた。
「ここまでどうやって来たの?」
「金木から歩いてきました」
「歩いた?ふうん」
聞かれたことにただ答えるだけの、関東人らしい距離のある返答をしているうちに、遠くの方に豆粒のようなオレンジ色の列車が見えた。津軽鉄道だ。ぐんぐんと近づいてくる。来た!と今日何度か見たはずの津軽鉄道に浮かれ、スマホのカメラを慌てて起動して構える。列車は思いのほか遠くに停車し、またしても慌てて走り寄り、前から横から撮る。よく見れば、オレンジの車体はほおずきみたいだ。秋の津軽列車もやっぱりいいものだ。
発車し去り行く後ろ姿も抜け目なく抑えると、視界のすみっこで、おじさんもスマホを構えて追いかけていた。
それから食事を済ませ、珈琲を飲み終わり、会計のため席を立つ。太宰もここの駅舎によく来ていたらしく、駅舎の本棚には関連書籍が並ぶ。ぼんやりと壁を見上げると、文豪ストレイドックスのポスターが貼ってあった。
「これは文豪をテーマにしたアニメでね」
またしてもおじさんの登場である。
「見たことあるんですか?」
アニメの話題まで提供してくれるとは思わず、こちらも流石に面白くなってきた。太宰治に興味がある素振りもあまりなく、失礼ながら見ているはずがないと踏んだのである。
「あるよ」
恐れ入った。
「芦野公園にある太宰の銅像見るなら、ここから出て右にまっすぐいって、踏切超えた先にあるから。ま、俺ただの客なんだけどね」
店を一歩でて、私たちは顔を見合わせて吹き出した。結局彼は誰だったんだろう。それにしても、あまり嫌な感じのしない、お節介というほどでもなく、ふとした時にちょうどよく現れては、一言二言のこし、気がつけばふらりとまたいなくなる、不思議な調子の人だった。上司だったら弄りたくなるとか、同僚だったら仲良くなってる、とかあれこれ花をさかせながら、彼の教えてくれ得た通りに踏切を渡る。
なんにせよ「おじさん」と呼ぶのもあんまりだということで、「駅舎の妖精」と呼ぼうということになった。ふらりと現れふらりと消える。太宰が好きだったのだろうか。それとも鉄道好きか。はたまたカレー好きか。どこの誰とも分からない。
ただ私たちが知っているのは、彼が店員ではなく、客だということだけだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
