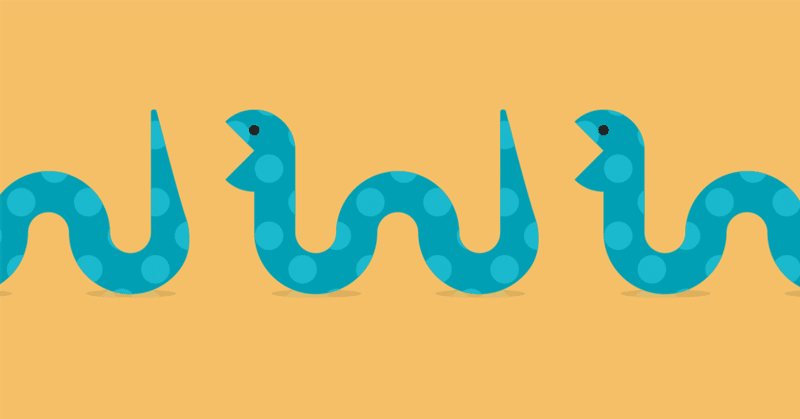
『獣の奏者』で初めての上橋ワールド
上橋菜穂子さんの著作は未読だったのだけど、先日、上橋さんの作品に大っ変お詳しい方とたまたまお話する機会があり、これも何かのご縁と思い初心者向けのオススメ本を伺ってみたところ、『獣の奏者』や『孤笛のかなた』を教えて頂きました。
で、読んでみたのがこちら。
『獣の奏者 1 闘蛇編』- 著者:上橋菜穂子さん
まるでRPGゲームのような
予備知識ほぼゼロで読み始めてみると、いきなりの別世界。だって、当然のように「闘蛇」だの「獣ノ医術師」だの「霧の民」だの、初めて見る言葉がいっぱい。むむ、どうやらこれは、ゴリゴリのファンタジーか!(←ここで気づくんかい!)
私の場合、大きくなってからもそれなりに読んだり観たりした馴染みのあるファンタジー要素多めの作品としては、『ハリー・ポッター』シリーズぐらいかも?DisneyやPixerやMarvelもある意味そうかな。
でも大体これらの作品って、ファンタジーの世界とリンクする現実世界の要素も存在感があるから、現実の延長としての没入感を楽しむパターンが多い気がします。
現実世界と完全に一線を画したファンタジーを最後に読んだのは、いつだろう?もしかしたら、小中学生の頃に読んだ『ナルニア国物語』シリーズが最後かも知れない。…いや、違う!ナルニア国だって、現実の子ども部屋のタンスの中から行くじゃないか!
ここまで最初から徹底した別世界で始まるファンタジーと言えば…そうだ!ゲームだ!冒険系RPGなら、いきなり勇者とか出てくるし。あ、てことは最近では『葬送のフリーレン』もまさにそのタイプですね。エルフ、勇者、僧侶、戦士、薬草。ふふ。フリーレンの方がよりゲームっぽいですね。
『獣の奏者』は敢えてRPGゲームに準えるとしたら、ドラクエよりもFFとかSaGa寄りかもなあ?(←イメージ違ったらごめんなさい)
独特の世界観
通常、魔法とか剣とか勇者とかってなってくると、フリーレンも含め何となくどこぞのヨーロッパ風な雰囲気の舞台がテンプレだけれど、この『獣の奏者』の世界はまたちょっと違う。
少なくともこの1巻では、魔法らしい魔法や剣は出てきませんでした。でも、不思議な巨大生物や、全く想像のつかない植物や食べ物がバンバン出てきます。その解説が折々に補足されているのだけれど、その「さも当然」感がじわじわ来る。例えばこんな感じ。
母は、竈の灰を分けて、その上に大きなラコス(甘い実のなる木)の葉を広げた。
「おかあさんが、おとうさんと出会ったのは、サモックの岩場だったの。岩場に咲くチャチモ(紫色の花を咲かせる植物。胃腸の薬になる)を探していて、崖の中腹に倒れている若者を見つけたのよ」
あー、はいはい、あれね、ラコスにチャチモね!…なんてつい知ったかぶりそうになるぐらい、しれっとサクッと書かれているので、未知の存在が混ざってきても、ストーリーを邪魔せずに読み進めやすかったです。
それに、登場人物たちの名前や役職名も、無国籍感(多国籍感?)があります。エリン、ソヨン、ヤントク、ヨジェ、辺りは韓国語っぽいし。アサンとかアッソンとかなってくると、ちょっと中東っぽい。かと思えばハルミヤ、セィミヤ、トムラ、なんて来たらどうにも日本ぽさが醸し出されるし。
こんな感じなので、人々の見た目や服装や生活様式も、どういう風に想像していったらいいかなぁ?と、一から頭の中で構成していくのはなかなか面白い経験でした。
ものすごい賞を授与されていた
この『獣の奏者』シリーズも含めた作品群を代表作とされている上橋菜穂子さんは、何と、児童文学のノーベル賞とも言われる「国際アンデルセン賞」という大変名誉ある賞の作家賞を2014年に受賞されたそうです。
なるほど児童文学だったのか!(←だからここで気づくんかい!)
でも、こういう独特の世界観に没入したい人には、老若男女問わず大きなお友達にも楽しめるシリーズだと思いました。また遊びに行ってみようっと!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
