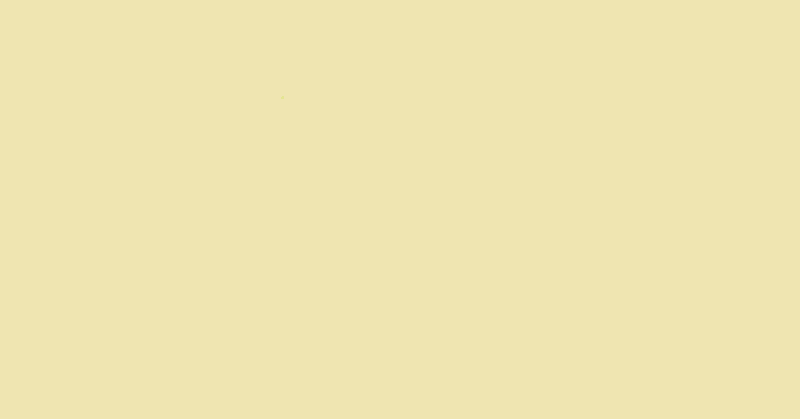
非対等性に対する単なる増減操作から、自由概念も、理想現実関係も解放しようという話(政治権力が負う責任対象の捉え直しにも触れつつ)
2023-1-001
政治家に求めるべきは、大小様々な主体の具体化精度確保(行動原理への改善フィードバック)を可能にする環境の確保である、と捉え直す事をもって、
不当な不利益回避や利得をも命じられてたり期待されてるかのように彼らが振る舞う余地を(政治家本人にも自身をそう規定してもらう事で内外共に)潰し、
対政治家の方向から奪い合い世界に加担する形となるのを防ぎましょう。(ちなみに、受容条件が論点でない単なる均衡志向は、泣き寝入りありきな平和と大差ないので、奪い合い世界の外に出てない、
もっと言うと、国際秩序に関する均衡発想が、ここ一年の国際状況を悪化させたのだろうし、
理想と現実の排安易な関係を受容に値する地点と見て、その点を紡いでく政治でやっと奪い合い世界の外に出られるだろうに、
その脱出を、非対等性に対する単なる増減操作で良しとする発想が妨げてると見なしましょう。)
また、生命と社会秩序の対立構図の類をこしらえて、一方を内実不問肯定する上下論(非対等性に対する増減操作の一種)をもって何らかの受容を強いる主張を過去の遺物とする事も、
限定作用(我々は自由平等を気にする一方で、理解限界等をもって対象や世界に限定を与える身でもある)に対する論点ズレを解けば
(被限定自体は不可避で、限定前後での確からしさ保存が論点である為、内在が外在によって発現阻害を受ける点は問題でない、との捉え直しをもって)可能でないか
(ひいては、非対等性の増減操作の域を出ない問題意識が内容の自由観や理想現実関係観からの、関連する概念や議論の解放も可能でないか)と期待します。
なのでまず、あらゆる現象は内在性質と外在性質の統合(内在性質だけ取り出す場合も、取り出しが要請されてる局面という外在性質を含んでる)であり、
限定作用は外在性質の取り込みに相当し、両性質の確からしさの上限化だけが問題としてある、
その問題は、抽象化具体化の不十分さ解消と言い換える事ができ、
抽象化具体化に際する捨象が同種の他との差異要素捨象であれば理系、同種の他との共通要素捨象であれば文系、個別性への帰属の余地をそう分別した上で、
抽象化具体化の交互反復(による具体化条件差異の取り込み)と捉えた展開(歴史や論理)についての論点ともなる(注1)、
つまり、同種の他との共通要素捨象を用いたその解消が論点化してない対文系は疑似問題や疑似解決である
(対教育などで、代替不可能な内外事情にしか応じない主体像と自身における獲得喪失とを整合させてない時点でその人の対文系は形骸であり、この構造が国や人類といった規模でも言える)、
フェア志向(フェアを越えて自身をも助けない生の規準化込み)は文系的な具体化精度確保(改悪フィードバックの阻止込み)を意味する為、
フェアを越えた問題設定や解決認定は、文系事象に関する解釈や論点などの選抜精度なり、アンフェア場での敗退などの場とそこに置かれてるものとの間の責任分別なりに、難のある判断力の産物である、
こう捉え直しましょう。
また、絶対主義や相対主義、あるいは、その二択に価値があるとの感覚(非対等性に対する、
受容に値する状態へと持ってく過不足除去ではない、単なる増減操作は、フェア志向、ひいては上の論点化とバッティングする)は、
被限定を前提にしてない(有限の与件性と向き合えてない)か、
被限定は前提で、受容に値するしないの二択が余地として、あるいは、有限者の責任範囲として(注3)あるだけと認めてはいるけれど、
受容条件が、内外境界意味する有限の与件性、より確からしいものが取って代わる運動性、これらから現象が成ってるという、帰属の修正余地のなさではないか、
いずれにせよ、帰属操作的な(何らかにとっての都合の良さという論点が、先の論点化を埋没させるという意味での、論点の疑似化な)生の産物でしょうから、
割り引かれ忌避を内容とする類の、自由観(内在不問外在軽視な典型自由観も当然含まれる)や実存観(秩序が生命を阻害する的な主張の類)や尊重観(改悪フィードバックを防いでいるいないによらず閉じる井の中の蛙化な純度追求)も、
私情を代替不可能化させる事で修正に対するいらぬ限定を抑えるのを怠った結果の、知性や倫理の機能不全の産物と見なせます。
内実不問(観点が受容に値するものかを問わない)な自我の始点化(感情なり解釈なりの選抜精度不問を結果的にでも齎した以上、フェア志向、
ひいては、対文系の実力向上にとっての直接的ネックとしてある近代始点)も、
典型自由観(非対等性を受容に値する状態へと持ってく話ではない)の徹底様態でしょうし(内実不問な欲望の始点化でも話は同じ)、
理想への到達は可能という前提に立ってる問題意識(認識は真理に至れる、認識は無理でも道徳は理想に至れる等の前提に加えて、
生の発現なり全面肯定なりを妨げてはいけないとの問題意識にも繋がる、道徳も無理だが現実を理想に代替させるのは可能との前提も込み)もその内容と言えますから、
対有限性の疑似化は、哲学史を通して哲学を矮小化させてきた(矮小化されてるものをむしろ哲学と称してきた哲学者は、
世界有り様の根本改善をも哲学は射程内であると考えると、その根本改善によって解放される存在にとって最も有害な敵である)とも疑えます(注4)。
ところで、先の論点化を対個人にも対社会にも持ち込むなら、
行動原理と状況把握に関するより確からしいものが取って代わる運動性にいらぬ阻害を持たない(向上限界を、代替不可能な内外事情にしか応じない主体像の反映にしてる)生、
その偶々の現れが、ある時空において罪とされ罰を受けた(その時空の性質と整合的なものへとポジションや具体的有り様が定まった)として、
時空固有性がその生の集積の反映に近いほど、先の論点を満足させるという、論点の三重構造が言えるように思います。
(勝負事のプロですら、敵の都合に合わせたり、味方全体が場に馴染んでなかったりを見せてきたわけで、
人と直接ではなく、場の深掘りされた性質に合わせた上で他者はもちろん、自分自身とすら関係を構築する方向に、我々は意識的であるべきだし、
そうであってやっと、場を荒らさない方向に行きがちな、つまりは、場の本質でなく場の表層に合わせる処理であり、泣き寝入りありきな平和の類と見なせる空気読む系への、妄信と反動反発を同時に防ぐ事も、
例えば、お金なり仕事なりを出す側受ける側関係などで、非対等性の増減綱引きの均衡点受容を、実態である事を理由に、
場の疑似でない固有性と整合的か非整合的かという内実について不問なまま強いる、奪い合い世界の外に出る事も、可能になるのだと考えます。)
通用領域の広狭と確からしさとの相関を踏まえ、先の論点における不十分さ解消を、限定前後での確からしさ保存と捉え、
より確からしいものが取って代わる運動性を無限性(有と無の差異、AがA以外でない事の担保、といったレベル有限性にすら先立つ)と捉えれば、その解釈は、
無限性と整合してない類の罪罰(善悪判定や許しも含めた問題設定なり解決認定なり)は形骸であるという内容になる為に、ある種の宗教観にも適ってる
(むしろ、無限者と有限者の関係改善としての信仰、あるいは、宗教的な概念や宗教的観点から捉え直された概念を、
逃れる事のできない有限性に無限性を取り込む方向で再構築する際の中身である)ようにも見えます。
ここで、受容に値する常識(形骸化してないので負わされても搾取でない常識)とは、
可能なだけ特定時空性を剥いだ抽象状態に遡った上で、引き受けざるを得ない特定時空性(具体化条件)を付し直した結果との内実を持つ類である
(したがって、対通念であれ対秩序であれ、検討や批判が過剰否定へと、ひいては、歪みの符号反転への加担へと堕すのを防ぐものである為、
文系概念に対する検討にせよ、何らかの場に見られる傾向に対する批判にせよ、先の論点化が必要条件)と解するとして、
そうした場の上に立ち上がってる秩序が、場の疑似でない固有性と整合的であるかどうかについて、
政治権力は自国社会に関しては管理者の立場からの、国際社会に関してはプレーヤーの立場からの責任を負ってる(そこの整合化能力が保有の肯定条件である)と捉えると、
国が負う保障の対象は、国民の生命や財産では(現実とのズレをリベラルやリバタリアンに、つまりは、非対等性の増減操作の域を出ない問題意識に、攻められてきたこの設定では)なく、
具体化精度が低いほど改悪フィードバックとなる点を踏まえた、国民の生の内実確からしさ(生の表層形がその反映となる事)であり
(先に見たように、場とそこに置かれるものとの責任分別の精度はフェア志向の程度と関わるので、
フェア志向でない者による管理過不足の主張と親しむのは、恐らく宗教系の不満含め、かえって過不足を許す上、奪い合い関係に閉じてしまう)、
同様に、政治家に求められてるのは、大小様々な主体の具体化精度確保(行動原理への改善フィードバック)を可能にする環境の確保である、と推測されます。
そして、その保障試みに際し中核となるイメージとして、
市場や民主制において、場での割り振りに直接反映される個々事情における、代替不可能な内外事情にしか応じない主体像
(私情をこの像のそれへと持っていった状態を実存的自由、持ってく以上の事を求めない対他者を実存的平等と解した場合、それら自由平等には同種の他との共通要素捨象が必要な事になる)、
それと整合的なものの割合を高める(市場や民主制を単なる実態主義に留めない)、
という像の、市場や民主制に話を限定しない拡張像を押さえるべきと考えます。
逆に言うと、政治家本人であれ政治家に注文つける側であれ、何らかの場において、場の疑似でない固有性が場全体に行き渡ってる状態と場に置かれてるものが実際に受ける整合との距離に鈍感な人(注2)が、
社会有り様について肯定否定するのは、影響力を持ってるほど有害であるわけで、この観点も押さえましょう。
注1
もちろん、アリストテレス時点で材料と設計者の関係のような枠組みはあるわけですが、
抽象化と具体化の不十分さ解消を論点とする内外性質統合が、プラトン提示の理想現実関係の解にも、世界からの主語の切り出しや主語からの述語の切り出し(修飾関係込み)に対する受容条件にもなってない以上、
個々の主題の連関から、展開の原理像にもなってないと、アリストテレス系については見るべきでしょうし、
理系ではガリレオ以降、数学で自然を説明するという形で、プラトンとアリストテレスの関係が事実上捉え直されつつ、内外性質統合な現象観が達成されてる件について、
説明作業も説明対象も、同種の他との差異要素捨象を用いた抽象化具体化の交互反復(による具体化条件差異の取り込み)を通して達成される、より確からしいものが取って代わる運動性となったと解するとして、
文系における説明作業も説明対象も、同種の他との共通要素捨象を用いた同運動性(抽象化具体化の不十分さ解消が論点)とするには、
A=Aに関して、前者後者で具体化条件が異なるとか、前者後者が抽象物と具体化条件付加物の関係であるとか、
そうした話が、理系的局面という外在事情下では、同種の他との差異要素捨象を通底文脈となる為に捨象されてると捉え直す、論理観の修正が必要であるように思われます。
注2
場で割り振り原理になってるものによって場に置かれてるもののポジションや具体的有り様が定まる、
という話(場で割り振り原理になってるものが疑似化してるほど、場に置かれてるものは負わされるに値しないものを負わされてるとの観点込み)の個々具体として、
局面と着目無視の合致という認識的な振り回されなさ(認識的な自由平等)もあるし、主体が何かを選ぶという現象もあると考えます。
もちろん、内在事情外在事情の統合場での、何らかの選抜(一位選抜的なものも順位関係選抜的なものもある)としての整合という選択像には、
個体や種の行動原理改善を付随させてる生命踏まえた歴史展開の産物である肉体なり、有限性が成り立つ為の個々整合でもあるだろう物理法則なりが、具体化条件の形で限定を与えてる、
実際、検証実験や短距離競走等のセットアップの抽象像でもある、何の差異に着目し何の差異を無視するか、という確からしさ判定に際する形式、
言わば、通用領域の広狭と確からしさとの相関という、否定も矛盾も通用領域の話をしてるわけなので認識に際し常にそれを認めてると見なせる、認識前提の落とし込み先は、
次元設定自在性という人間形式によって精度や維持強度を獲得してると言えて、
局面と着目無視が一致しているいないは、その人間形式に関する生かしてるか振り回されてるかの差異に相当しており、
したがって、そこの合致への志向は、何らかの事情で認知機能が万全でない場合のその影響を低減させるという、具体化条件の内実への介入でもあると思われます。
注3
有限の与件性を認めると、有限者の責任範囲は、受容に値する内外境界と値しない内外境界との選択余地に限られ、
認識(受容に値するしないの判定込み)は、通用領域の広狭と確からしさとの相関、
および、より確からしいものが取って代わる運動性(特に、通用の行き渡ってる状態な気がするものを選ぶ働き)を前提に機能してる為、
何に関してその相関を見るか、何の差異を確からしさ差とするか、という上の運動性に枠組み(限定)を与える働きである観点設定(着目無視設定)についての、
選抜原理部分へのその運動性の効き具合(種や個体に関するやむを得ない肉体事情を差し引いたそれ)しか、責任範囲を持たない
(そこの効き具合の上限化は、デカルトが内実不問の前提化を可能にした以上、必然ではない)と想像されます。
言わば、失敗は、代替不可能な内外事情にしか応じない主体像の、反映であるほど有限性の責任であり、反映でないほど個別性の責任である(有限性の責任にすると搾取になる)、
という構造が観点設定に関して言える上、
その主体像を可能にする同種の他との共通要素捨象が育成対象である(獲得はデフォルトでないけれど獲得可能な状況ではある)点に、自由の余地があり、
育成されるほど有限性が形骸でなくなる(負わされても搾取ではなく、受容に値する)という、本文で見た原罪等の内容再構築に、話が重なると疑えるように思います。
注4
分離処理に対する過大評価(割り引かれ忌避を強化する事で近代以降の問題解決を疑似化させてる)への対策は、特化の過不足抑制の論点化および能力によって、
つまりは、場の性質から疑似化部分を可能なだけ取り除き具体化精度を上限化する、代替不可能な内外事情にしか応じない主体像と獲得喪失とを整合させる、場を尊重すべくフェアを越えてまで自他に合わさない、
これらの生への取り込みによって、可能と推測できる為、近代病も結局は先の論点化不在の弊害であって、
例えば、加工や不確定について、局面から見た過不足、つまり、場との整合不整合の話ではなく、それら自体の許容拒絶の話にしてしまう論点ズレが、
侵略者の自覚ない領域侵犯な理系センスと不法占拠の自覚ない内実不問な個別性保障の二択へとさらにズレる、
このどちらであれいらぬ特化でしかない地平に縛られた文系空間の現状も、
言い換えるなら、存在と引き換えでない外在部分と縁を切ってる主観、切ってない主観、両者の差異も当然捨象する客観、このどれに立脚するかでいらぬ飛躍と見なすものが変わるのに、
個別性が根拠になる局面、つまりは、一つ目がいるべき場所での二つ目と三つ目による勢力争い、
どちらが優位であれ、いらぬ飛躍を取り違えた対象理解しかできない上、場に即してないので改悪フィードバックに至るそれが、近代性によって強まってる状況も、
古代以来の論点の疑似化問題が未だに修正されてない話(先の論点化自体がフェア志向を内包する為、論点の選抜精度の確保に相当してる)として捉え直しましょう。
ご支援の程よろしくお願い致します。
