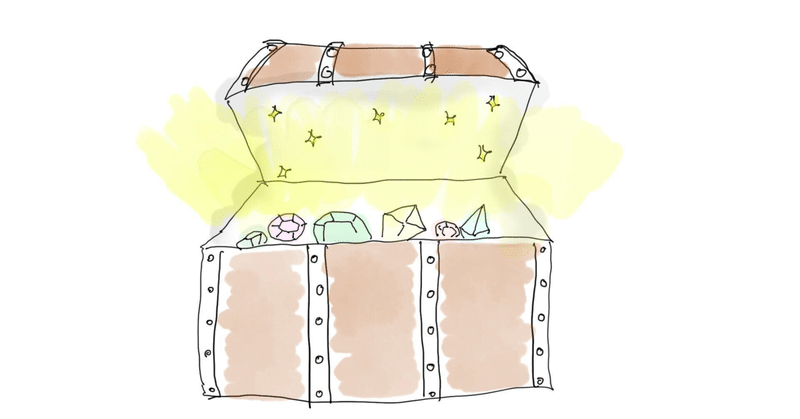
プラスのカケラが君を『タカラモノ』にする
「幸せな家庭」ってどんな家族?
高校二年の冬、車で去っていく母を裸足で追いかけた。走っても走っても止まってくれなくて、とうとう息が切れて、足がもつれて、道路にしゃがみこんだ。スカート越しに伝わるアスファルトの冷たさでお尻が痛い。お母さんがいなくなるのが、死んでしまいたくなるくらい悲しかった。
しばらく経って、高校へ行く途中のこと。電車の中で親戚のおばさんにバッタリ会って、言われた。「お母さん、出て行ったんだって?かわいそうに。」
母がいなくなって、父は私と弟の「いつも通り」を必死に守ろうとしてくれた。家事なんて、あまりしたことなかったと思う。慣れない手つきで、料理や掃除、洗濯をする。レシピ本から私たちの好みを聞いて、凝った料理を作ることもあった。何時間も玉ねぎを炒めて作ったオニオンスープ。味の薄いスープをすすりながら「おいしい」って何回も言った。
中学生だった弟に、父は毎日お弁当をつくるのだけど、あまりに忙しいと、コンビニ弁当を買ってくる。それを、家にある弁当箱に詰め替える。この「弁当箱に詰め替える」という行為は、父なりのこだわりのようだった。弟を「かわいそう」から守るためか。
母がいなくなったことが悲しくて、父に何度も当たった。リモコンを投げつけたこともある。だけど、父は決して叱らなかった。
買ったばかりのカメラで私たちをパシャパシャ撮り、私が家を出るまでクリスマスにはサンタを演じ続けた。
*
『タカラモノ』は「保美(ほのみ)」の目を通した、家族の物語だ。多くの人の「幸せな家庭」のイメージとはほど遠い。
彼女の母は、いつも朝帰りや昼帰り。保美が家に帰っても誰もおらず、ご飯はいつもレンジでチン。両親は一緒に住んでいるのに、憎しみあっているように見える。しかも、お互い別に恋人がいる。
でも、彼女は「かわいそう」を認めない。
「かわいそうに」
しばらくわたしを見たあと、柳川さんのお母さんはいった。まるで雨の日に捨てられた子猫を見つけたように。私は手にしていたレモンケーキをぽとんと皿に落とした。
帰りにおばさんはタッパーに入ったハンバーグとアジフライをくれた。
私は柳川さんの家を出ると、野良猫のエサ置き場に向かった。そこに、もらったタッパーをひっくり返して中身を全部置くと、三メートルくらい先に置かれたゴミ箱に向かって、えいっとタッパーを投げた。
「ナイスシュッ」
めずらしくストンと一回で入った。わたしは小さくガッツポーズをすると、バンバンと手を勢いよく払って、やっぱりママの店へ走った。
「喫茶&スナック シャレード」へ
*
破天荒に「ド」がつくような、保美の母だ。しかし、ことあるごとに「あんたはすごい」「あんたはえらい」「あんたは私のタカラモノ」と娘へ言って聞かせる。これだけは一貫している。
保美が思春期になって、大きなお尻をコンプレックスに感じていても、母はモノともしない。
「お尻が小さいほうがいいという人は、見栄っ張りが多いねん。ほのみのお尻は絶対にええから。」
ママは続ける。わたしがなにかいおうとすると、先回りするようにいった。
「長所なんやで。あんたが自信さえもてば、めっちゃすごい長所になるねん。」
私の父も、よく私を褒めてくれた。とくに私の「運」について。
母がいなくなって、数か月ほど登校拒否になったことがある。その間、数人の同級生が会いに来てくれた。友だちが来るたびに、父は「愛は友だちに恵まれているなぁ」と感心する。あとから、担任の先生が友達に頼んでいたらしいとわかったのだけど、今度は「愛は先生に恵まれているなぁ」と言った。
だからか「わたしは運がいい」と信じて疑わない。何かいいことがあると「ほらね」と思う。逆に悪いことがあると、反省はするが運のせいにはしない。
そう、ママは怒ったことがない。どんなことでも、どんなときでも、わずかなプラスのカケラを探して褒めてくれた。
わたしはそのカケラを寄せ集めて自分という形をつくってきた。
なんにも目立ったところのない、誰かの影のような子どもだったわたしが、自分をそんなに嫌いにならずにひょうひょうと生きてこられたのは、ママがカケラを見つけてくれたおかげだ。
泣きながら母を追いかけた、高校生のわたし。
あれからだって、辛くて挫けそうなことはいくつもあった。だけど、いつも立ち上がることができたのは「あなたはタカラモノ」と父が教えてくれたから。小さな「プラスのカケラ」集まって大きくなって、わたしの心を支えている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
