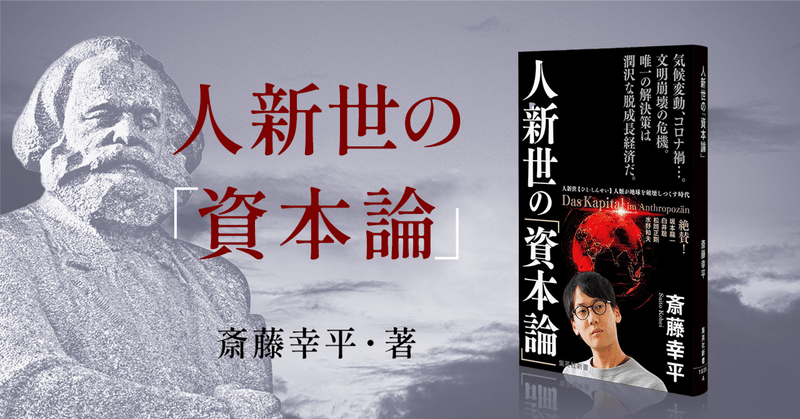
資本主義の黄昏
【書評】『人新世の「資本論」』斎藤幸平=著/集英社新書
𝑡𝑒𝑥𝑡. 養老まにあっくす
その湖の畔では、人々はよい暮らしを送っていた。日によって漁の成果は異なるものの、魚を採り自宅や近所の人々の食卓に供するには十分だった。漁師たちは、毎日売れるだけの量の魚を採っていた。しかし、やがて湖にも資本主義の波が押し寄せる。漁師たちは利益を上げるために、もっと大きな船を買い、さらに効果の高い漁法を採用した。冷凍倉庫が建てられ、採った魚はもっと遠くまで運搬できるようになった。漁師たちはより早く、より多く、より効率的に魚が採れるように、競って設備に投資した。船のローンを返すためにも、そうせざるを得なかった。とはいえ、湖の魚も無限ではない。今日では湖の魚が、文字通り最後の一匹まで採り尽くされてしまったという。
これは、ハンス=クリストフ・ビンスヴァンガーという経済学者が書いた本の中で紹介されているエピソードを、私がアレンジしたものである。このアレゴリーは、まさに現在世界で起こっている問題の縮図そのものである。
なぜこの寓話を紹介したかといえば、「人新世」という、人によっては聞き慣れない用語を説明するのに、ちょうどいいと思ったからである。これは、ヒトの経済活動が地球に与える影響があまりに大きいため、地球は地質学的に新たな年代に突入したとして、これを「人新世」(𝐴𝑛𝑡ℎ𝑟𝑜𝑝𝑜𝑐𝑒𝑛𝑒)と名付けたのである。この「経済活動が」という部分が重要だと私は考える。
環境と経済の問題は別々のもの。そう考えている方もおられるかもしれない。しかし、じつは経済こそ環境問題の真犯人、より正確にいえば、資本主義こそ環境破壊の張本人であると、私は思っている。それを端的に説明するために、冒頭の文章を書いた。
資本主義という経済システムは当たり前すぎて、他のやり方があるなどとは考えたことがないかもしれない。だから、われわれはまず資本主義の矛盾に気づかなければならない。その核心は、成長の強制である。資本主義は、経済がいまよりも必ず成長するという前提のもとに成り立っている。だが、少し考えてみればわかるように、永遠に成長し続けるということはありえない。それなら、今日のわれわれ先進国の豊かさは、いったいどこからきているのか。それはグローバル・サウス(地理的ではなくグローバルな意味における南部)からの労働力の搾取と自然資源の収奪によってである。そう著者は言う。
かつては、帝国が植民地の労働力と天然資源を搾り取ることによって先進諸国は経済的に発展してきたが、帝国主義の時代が終わった現代でもなお、われわれはグローバル・サウスからの搾取によって繁栄を誇っているのである。この帝国主義的生活様式は、われわれの日常の隅々まで行き渡っているのであって、たとえば洋服ひとつとってみても、中枢にいる人間たちの暮らしは、劣悪な条件下で働く辺縁の人々の労働や資源によって維持されている。
資本の力では、克服できない限界が存在する。資本は無限の価値増殖を目指すが、地球の資源は有限である。辺縁すなわちグローバル・サウスを使い尽くすと、今度は別な辺縁から搾取する。搾取するための辺縁がなくなれば、このシステムは立ち行かなくなる。それこそが、人類が「人新世」に突入したということなのである。
そこで、資本主義に対抗する新たな経済システムとして、著者が主張するのが「脱成長コミュニズム」である。コミュニズムとは、いわゆる共産主義である。共産主義というと、多くの人はかつてのソ連や中国を想像し、時代遅れで危険な思想だと思っているかもしれない。ところが、海外に目を向けると、近年マルクスの思想が再評価され、大きく注目を浴びているのだという。
『資本論』の第一巻はマルクス本人の手によって完成し、一八六七年に刊行された。しかし、第二巻、第三巻の執筆は未完のまま終わってしまい、今日読まれているものはエンゲルスがマルクスの没後に遺稿を編集し、出版したものである。したがって、意図せずしてかマルクスの見解が歪められ、見えにくくなっている部分があるらしい。そして、晩年のマルクスが残した研究ノートなどを読み解くことによって、まったく新しい『資本論』解釈が浮かび上がってくるという。その解釈がどのようなものか、詳細は本書をお読みいただくとして、ひとつだけ、資本主義に対抗するためのヒントとして、著者が述べている「コモン」というマルクスのアイディアを紹介したい。
たとえば、わが国でも水道事業が民営化されるのではないかといった動きがあるが、そうなるとその企業は利益を上げることが目的となるため、必要を超えて料金が値上げされる恐れがある。では、何がいちばんよい管理方法か。それは、水資源そのものを「コモン」(共有財産とでも呼んだらいいだろうか)として共有するのである。
冒頭の寓話でいえば、湖は誰のものでもないと考えるから、個々人が好き勝手に使い放題、取り放題になるのであって、これをみんなの共有財産として管理する。ここで大事なのは、コモン化するということは、国有化するということではない。それではかつてのソ連みたいになってしまう。そうではなくて、われわれ市民ひとりひとりが管理に参加するのである。水でも電気でも何でもよいが、市民ひとりひとりが民主主義を通じて政治に参加するように、資源もそれを拠り所としている人々が管理に参加するのである。
もっとも、民主主義の歴史が古いヨーロッパはそれでよい。しかし、借り物のデモクラシーしかない日本ではどうか。選挙の投票率はなかなか上がらず、何事もお上のお達しが出るまで「待ち」の姿勢を取りがちな日本人には、別なやり方が必要かもしれない。それがどんなものか、私にはまだわからない。いずれにせよ、危機はこれから訪れるのではない。もうすでに始まっているのである。落語の「花見酒」ではないが、いくら金勘定が合っていても、気づいたら樽の酒が底をついていた。このままではそんなオチになってしまいそうで恐い。
(2021.3 ブクログより転載)
𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑏𝑦 𝑦𝑜𝑟𝑜𝑚𝑎𝑛𝑖𝑎𝑥
養老先生に貢ぐので、面白いと思ったらサポートしてください!
