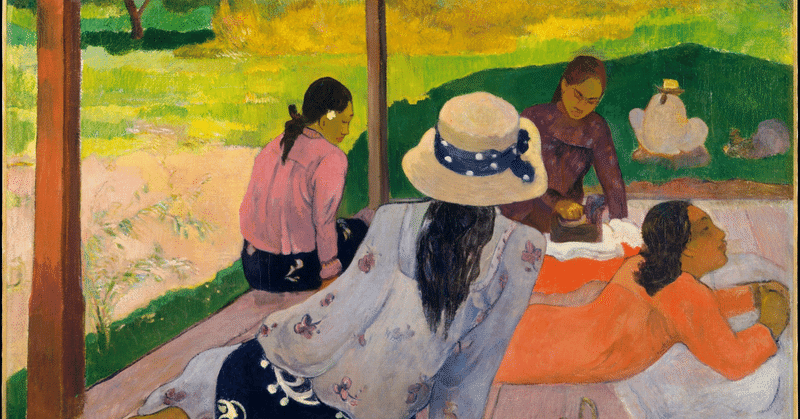
Vol.5_『計画順調なれど、業績悪し...』って、おいっ!
我社は、四半期に一度、経営陣から全社業績と各部の年度計画の進捗報告があり、全社員で状況を共有する機会があります。とても良い取り組みだと思います。
先日も第2四半期の報告会があったのですが、そこで今会社で起こっていることにふと気づいたので、今日はその話をしたいと思います。
※貼り付けた写真はドライブに行った先々で写したものですが、特に意味はなく、本文とはなんの関係もありません。

1.起こっていること
第2四半期の報告会では、まず社長から「全社業績が前年比・計画比とも、かなり厳しい」ということが実際の数値とともに報告されました。外部要因を中心にその原因についての説明もあり、現状についての共通理解が進んだと思います。しかし、挽回できるのかとかいった見通しや、明確な挽回策もなかなか見いだせず、なかなかしんどい状況…。
一方、業績報告に続いて行われた各部で展開している施策の進捗報告では、八割方順調に進んでいるとのこと…。報告を担当している役員からも、「◯◯は順調に進んでいます。ご協力ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。」なんてフレーズが何度も繰り返されます。
『 業績は悪いけど、計画は順調 』
そんなことってある??
恥ずかしながら、「今さら」ながら感じたのです。
ウチだけなんだろうか...?
よそもそうだといいな...。
なんて不謹慎なことを思いながら、なんでだろう、、、と考えてみました。

2.推定理由
推定① 木に登りて魚を求む的な理由
木に登っても魚は見つからない...。魚が欲しければ川や海にいかなければいけないのに、木に登ってどうする?!つまり、そもそも計画した施策が的外れで業績には関係のないものになっている。
推定② 運動すれど体重減らず的な理由
摂取カロリーが消費カロリーを上回ると太る...。つまり、計画は順調に進捗していて業績に寄与している(カロリーは消費している)けれど、それ以外のところで足を引っ張って(カロリーを摂取して)全体として業績を下げている(体重を増加させている)。
推定③ 及ばぬ鯉の滝登り的な理由
自分たちの力ではどうしようもない事情である...。つまり、業績悪化は「新型コロナ感染拡大による市況の悪化」「ウッドショックによる原材料の高騰」など特殊事情によるものであり、計画やその進捗のせいではない。
推定④ 君子危うきに近寄らず的な理由
そっとしておこう...。つまり、計画の遅れや不十分さを業績悪化の原因にすると、社員の仕事ぶりが原因だと取られて反発を招くので、それを理由には出来ない。
推定⑤ ローマは一日にして成らず的な理由
そんな簡単なものじゃないよ...。つまり、実行し続けることでやがて業績に繋がるのであって、すぐさま効果が現れるほど甘くはないので、業績と計画進捗にはタイムラグがある。

3.推定することに意義がある
いろいろ考えた上でこんな事を言うのもなんなのですが、理由はどれか一つではないし、全てでもないのだろうと思うし、他の何かかもしれない。
そして、徹底的に究明したところで確たる正解が得られるとも思えず、あまり意味のないことなのかも知れない...ということを思うのです。
でも、正解を求めることは無意味でも、推定することはとても大事なことと思います。なぜなら、今後の計画立案、進捗管理、目標設定、情報共有など事業運営に欠かせない活動を行うにあたり、推定した理由に留意することで、より良く活動することが出来るからです。
例えば、今後、経営計画を立案するにあたっては、先に推定したことを踏まえて、次のようなチェックポイントや対策を採ることが可能になり、随分とレベルアップした経営計画になるのではないでしょうか...。(ま、言うは易しですが...)
a.業績への影響度を慎重に考え、明確にする(推定①)
b.他に漏らしてはいけない重要な活動はないかをチェックする(推定②)
c.不測の事態に備え、緊急対策を考える仕組みを作っておく(推定③)
d.社員に対して『経営の責任』を明確に意思表示する(推定④)
e.短期的施策と中長期的施策を明確に分ける(推定⑤)
4.スケジュール管理から進捗管理へ
もう一つ気になっている点があります。
それは、当月に予定されていた活動が実施できていれば、『その計画は順調である』と評価してしまうという点です。
進捗管理とは、スケジュール通りに動いているかどうかをチェックすることだけが目的ではなく、日々状況が変化する中で、ゴールに向かって今どのくらいまで進んでいて、それは順調なのかどうか。その後はどのようなプロセスが予定されているのか。期待された成果が残せそうなのかどうか。ということを確認することだと思います。
しかし、当初計画していた活動が出来ているかどうかに固執しがちで、例えば「◯月度の定例◯◯会議は予定通り開催しました」などという進捗報告があったりするのです。
本来、経営としては、会議を開いたかどうかなんて全く関心はないと思いますが、それでも「よしよし、順調だね」なんて思いがち。すなわち、『手段の目的化』が起こりがちだと思うのです。

5.これらの問題・課題への対応
ここまでお話した問題・課題は、なかなか対応が難しいとも思います。日々起こっている事業に関する様々な出来事に対処するだけでも強烈に忙しい経営陣が、こういった問題・課題を考察し、対策を練り、仕組みを構築し、実際に運営する...少なくとも当社では想像できません。
なので、人員に余裕のないギリギリの経営をしている中小企業においても、やはりこういった『経営計画に基づいた事業活動を、仕組みでチェックしながら推進していく』そういう役割のチームを持つべきだと思います。チームが難しければ、そういう役割を担う人材の明確なポジションを設けるべきだと思います。
経営計画の実効性が損なわれる(社員の仕事が無駄になる)くらいならば、大いに検討の余地ありと思うのですが、いかがでしょう?

6.まとめ
今回は、私の頭の中を整理するような記事になりました。
中小企業において、経営計画をうまく機能させるにはどのような注意が必要なのか、といったことが少し整理されてスッキリしました。(笑)
マーケティングやファイナンスといったビジネスに欠かせない高度な専門分野に関わる内容ではありませんでしたが、少しでも効果のある事業計画を立て、地道な進捗管理を行うことだけでも、限りある資源を集中させることに繋がり、中小企業経営を助けるものになるのではないかと思います。
まだまだ勉強不足ですが、企業経営についてもっと深く、もっと広く学んでいきたいと思います。
本日はここまで。
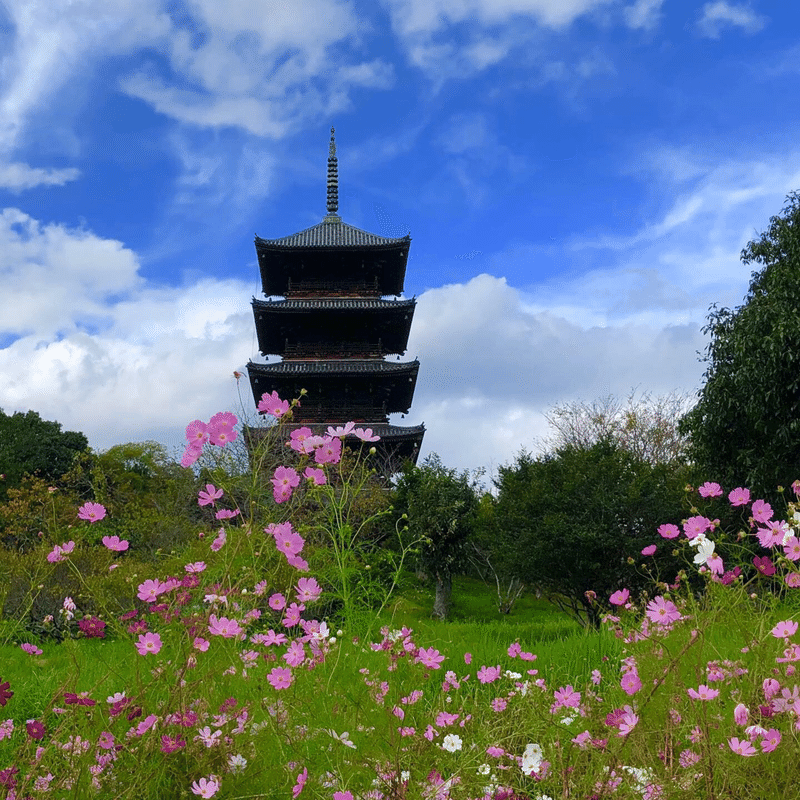
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
