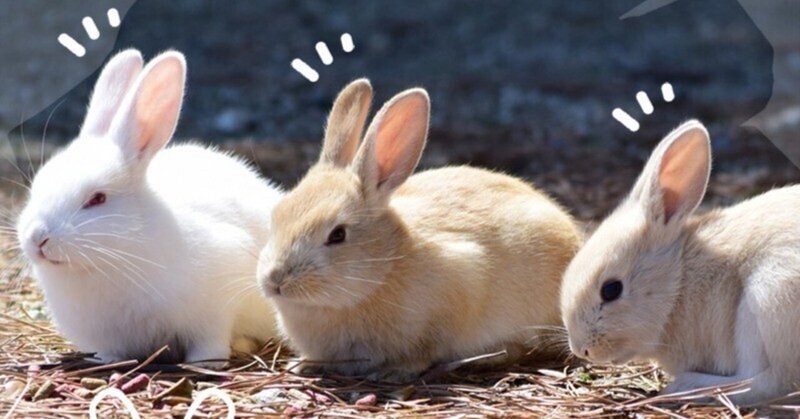
聞き手が対話をコントロールする
―やっぱり人の話を聞かないですよね。
会議終了後にメンバーが発した一言目でした。ここから「聞く」について私の頭は巡り始めます。
"話を聞いてもらえた"という満足感はどうすれば生まれるのでしょうか。一方で、話を聞かれなかったことでどういった心理状態になるのでしょうか。
聞かれないことによる思考は次のように流れることが多いと思います。
聞かれていない→「自分の言っていることは大切ではないらしい」→それでも聞かれない→「自分はここで役に立っていない」→聞かれない→「自分はここにいてもいいのか」→意見される→「ここにいない方がいい」→孤立する、、、
ちょうどこんな会話かもしれません。
上司「今取り組んでいる開発の進捗は?結果はいつわかるの?」
※この時の上司は、自分が把握できていないことから、不安になり、詰問をしてしまいます。それをされる部下はどうしても自分を守りたくなります。すると、上司にとっては求める答えが余計手に入らなくなるため、「なぜ」と強く発してしまいます。
上司「なぜ、もっと早く行動しなかったのか。」
「なぜ、早い段階で相談しなかったのか。」
※この「なぜ」は使い方によっては非常に効果の高い質問ではありますが、一方で今回のケースでは、部下は何かまずいことをしたのか、、、自分の話は聞いてもらえるのか、、、といった不安が大きくなります。
部下「今は他のタスクもあり進んでいません」
上司「いつまでに何かしら着手して答えを頂戴」
部下はこう思います。「自分の話は聞かれていないな」
聞かれないということは、焦りや不安が生まれます。その結果自分自身の価値を下げることになります。
また、聞かれないことにより、未完了が生まれます。最初から最後まで話を聞いて完了させているでしょうか?
◎聞き手がいない
コミュニケーションは、「話す」「書く」「聞く」という3つの要素から成り立っています。生まれてから、親や周りが使う言葉を聞き、理解し、話すこと、書くことで学んでいきます。つまり、「話す」「書く」は教わる環境にあります。
一方で、「聞く」についてはどうでしょうか?何か機会があれば学ぶ方がいるでしょう。しかし、それは必要に迫られた場合がほとんどのような気がします。例えば、職業との出会い(カウンセリング、コーチ、介護・看護職、営業など)、人間関係に悩み改善したいという思い、立場の変化(リーダー、マネージャーになる)など。
いずれも、研修などの1回きりで終わることが多いようにも思います。学んでいるときは、その重要性を認識し自身にインストールしますが、その場を離れるとまたこれまでと同じ日常となります。
病院、カフェ、レストラン、会社、学校など人と人が向かい合い話をしている場面は多くあります。よくよく観察していますと、話しは盛り上がっていますが、聞き手は話を聞いているようで、次は何を話そうかと考えているように思います。
そのため、相槌は適切にあるのですが、その次に出てくる言葉や内容は、相手の事ではなく自分の事であることが多いように思います。
―コミュニケーションが上手な人は?
と聞くと、話し手のスキル(伝わる、わかりやすい、相手が納得するなど)は上げられますが、聞くのが上手というのはあまり耳にしません。
つまり、話し手が沢山いることになり、聞き手が少ないのです。
◎じっくりと聞く
あなたは誰かに「話をじっくりと聞いてもらった」という経験はありますか?これまでのことを思い出してみてください。家族や友人、同僚が相手など。
あなたが十分に話を聞いてもらい、理解してもらったと感じたとします。あなたの話が大切に扱われたという状態です。
―さて、どうでしょうか?
◎聞くスタンスは?
今のあなたの聞くスタンスはどうでしょうか?次のチェックに取り組み、チェックが付いていないことについて向き合ってみてはいかがでしょうか。
▢ 相手の話を聞くときは、自分が次に何を話すか考えず、相手の話をじっくり聞いている。
▢ 相手が話している途中に口は挟まず、最後まで聞く。
▢ 相手の話を聞くときは、相槌を打っている。
※この「聞く」については次回以降もテーマとして取り上げ、継続していきます。
◇内容について気になる、お話してみたいなど、お気軽にご連絡ください。 ◇ コーチングって何?どんなもの?教えてほしい!ちょっと気になるので お試しで受けてみたい!という方大歓迎です。
―問い合わせはこちらから―
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
